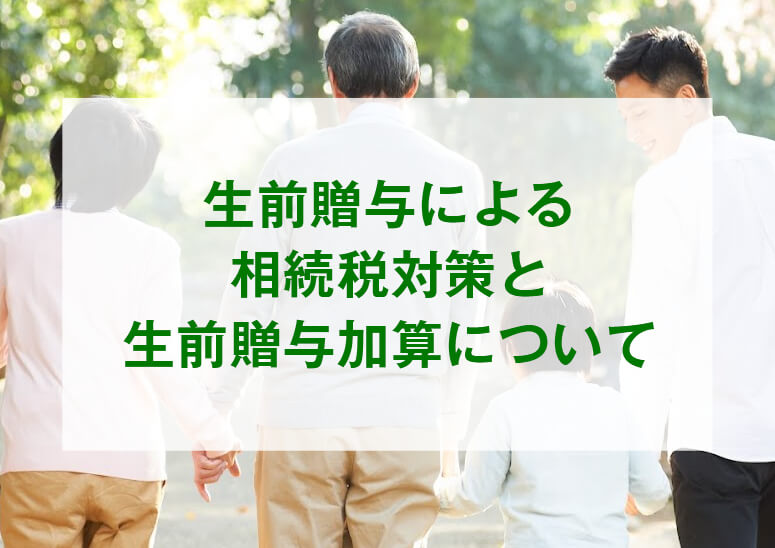
生前贈与による相続税対策と生前贈与加算について
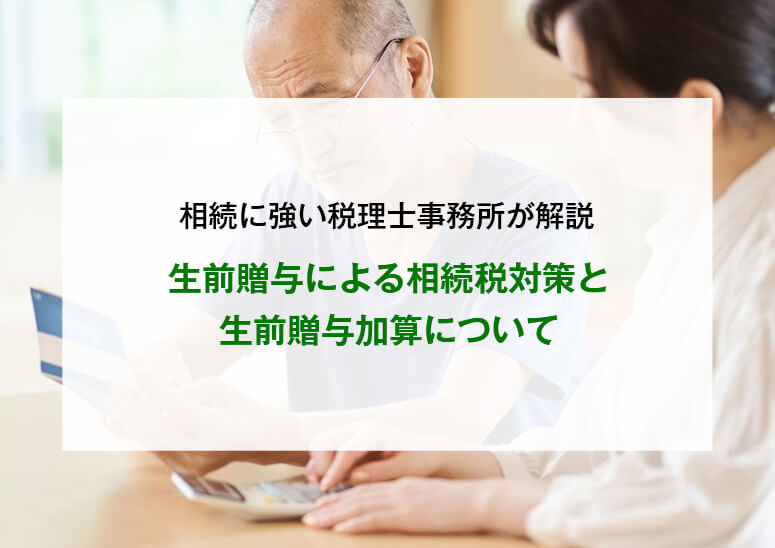
目次
相続対策としての贈与について
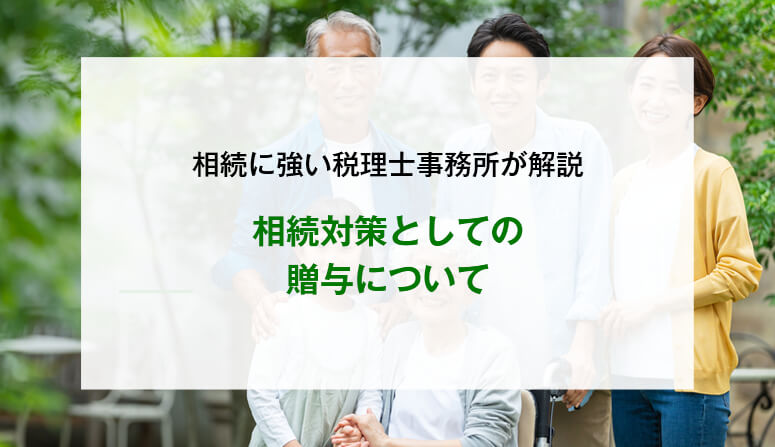
相続税は、相続が発生した場合に常に課されるわけではなく、相続財産が基礎控除額を超える場合にのみ課税されます。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば、法定相続人が2人であれば、基礎控除額は4,200万円となり、それ以下の財産には相続税がかかりません。
相続税は超過累進課税が適用されるため、相続財産が多いほど税率が高くなり、負担も大きくなります。そのため、将来的な相続税の負担を減らすには、生前に財産を減少させることが有効です。この方法の代表例が「生前贈与」です。
生前贈与とは
生前贈与とは、自身の財産を生前に、相続人や遺贈を受ける人に譲渡する行為です。生前贈与を活用すれば、相続財産を減らして相続税負担を軽減できるだけでなく、財産を希望する人に確実に承継させ、将来の相続争いを回避する効果もあります。
また、自身の意思で財産を処分できるため、贈与の内容や時期を自由に設定できる点も大きなメリットです。
生前贈与における贈与税の問題
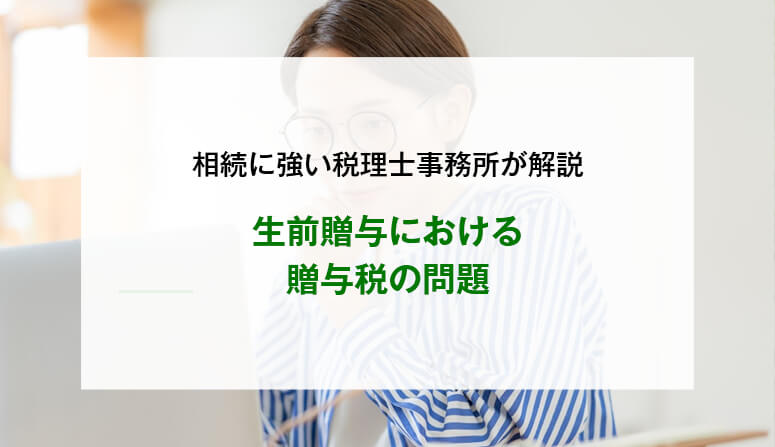
生前贈与には、暦年課税方式と相続時精算課税制度の2種類があります。それぞれ詳しく解説していきます。
暦年課税方式を選んだ場合
暦年課税方式では、贈与を受けた人が1年間に受けた合計額が110万円まで非課税となり、それを超える部分に贈与税が課せられます。
例えば、ある年に父から100万円、母から50万円を受けた場合、合計150万円となり、110万円を超える40万円に対して贈与税が課税されます。
相続時精算課税制度を選んだ場合
一方、相続時精算課税制度を選択した場合、贈与額は相続財産に加算されるため、相続財産を減少させる効果は限定的です。例外として、贈与時より相続開始時の評価額が高騰していた場合には、贈与時評価で相続税を計算できるメリットがありますが、基本的には暦年課税方式が相続税対策として適しているとされています。
贈与税の注意点
贈与税は相続税よりも高率に設定されているため、安易に多額の贈与を行うと、逆に生前贈与による節税効果が損なわれることがあります。
したがって、贈与は年間110万円までを目安に複数年に分けて行うことが有力な選択肢になってきます。
複数回に分ける場合は、各贈与ごとに贈与契約書を作成し、単なる分割履行ではないことを明確にしておく必要があります。
生前贈与加算について
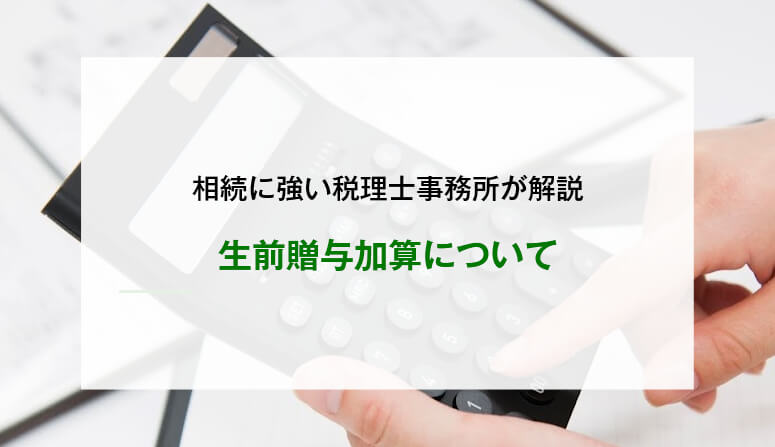
生前贈与加算とは
暦年贈与で相続対策を行う際に注意しなければならないのが「生前贈与加算」です。生前贈与加算とは、相続開始前の一定期間に行われた贈与を相続財産に持ち戻し、相続税を計算する制度です。この「一定期間」を「持ち戻し期間」と呼び、この期間内の贈与財産は相続財産に加算されます。
これは、生前贈与を無制限に認めると、相続直前に贈与を繰り返すことで相続税を回避できてしまうため、その防止を目的として設けられています。
この持ち戻し期間が2024年1月1日に発生した相続については、加算対象期間は相続開始前7年以内に延長されました。(従来は3年以内)
関連サイト「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」
特に、相続開始前4年超7年以内の贈与については、合計額から100万円を控除した残額が相続財産に加算されます。
生前贈与加算が適用される要件
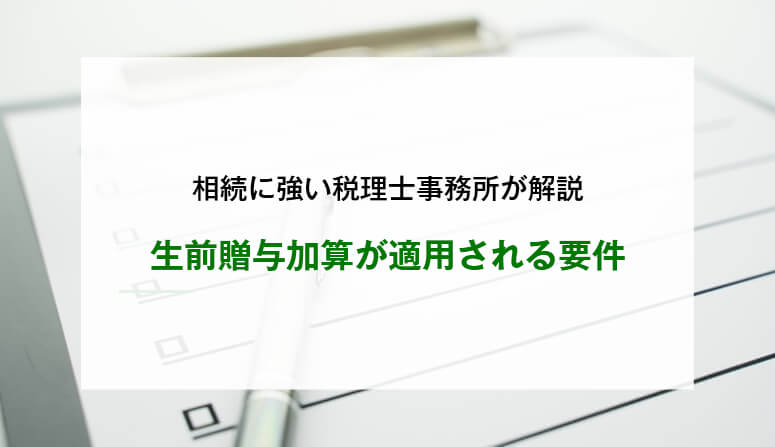
相続開始前7年以内に行われた贈与であること
相続開始前に行われた贈与のうち、7年以内の贈与は生前贈与加算の対象となります(従来は3年以内)。
ただし、相続開始前4年超7年以内の贈与については、合計額から100万円を控除した残額のみが加算対象となります。この7年の起算点は相続開始の日、すなわち被相続人が亡くなった日です。
例
2028年2月20日に被相続人が亡くなった場合、相続開始前7年間、すなわち2021年2月20日から2028年2月20日までの間に行われた贈与が生前贈与加算の対象となります。
なお、このうち2024年2月20日以前(4年超7年以内)の贈与については、合計額から100万円を控除した残額が加算されます。
また、贈与日については、実際に財産が移転した日ではなく、民法549条に基づき「贈与契約が成立した日(=贈与の合意が成立した日)」が起算日となります。
贈与を受けた者が相続人または遺贈を受けた人であること
生前贈与加算の対象となるのは、被相続人の相続人、または遺言により遺贈を受けた人です。したがって、相続開始前7年以内に贈与を受けていたとしても、その受贈者が相続人や遺贈受遺者でない場合は加算の対象になりません。
なお「遺贈」とは、被相続人が遺言によって自己の財産を特定の人に与える処分行為をいいます。遺贈は相続人に対しても、第三者に対しても行うことが可能です。
暦年課税方式による贈与であること
生前贈与加算の対象となるのは、暦年課税方式による贈与です。相続時精算課税方式による贈与は、その制度自体が贈与額を相続財産に加算して相続税を計算する仕組みになっているため、別途「生前贈与加算」の対象とする必要はありません。
一方、暦年課税方式で行われた贈与は、年間110万円以下の少額であっても、生前贈与加算の対象となる場合があります。つまり、贈与時には贈与税が課されなかった財産であっても、被相続人の死亡前7年以内の贈与であれば相続税計算上は加算される点に注意が必要です。
このように、暦年課税方式による贈与については、従来「非課税」と考えられていた少額贈与も含めて加算対象に含まれるため、相続対策として贈与を活用する際には、加算期間の拡大(3年 → 7年)と併せて十分な理解が求められます。
生前贈与加算は相続人以外にも影響がある
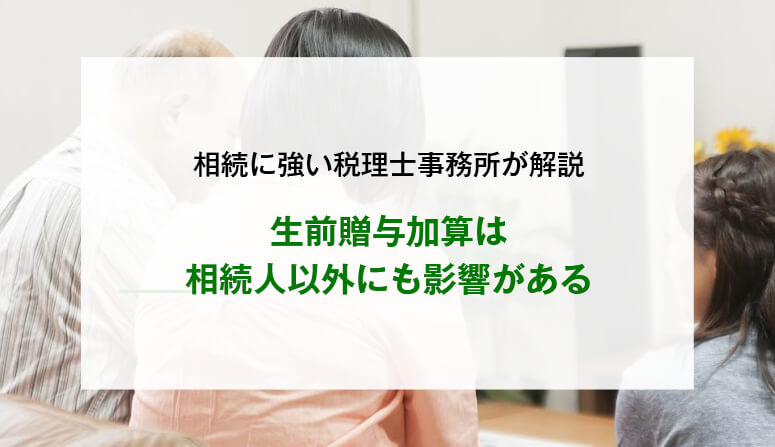
生前贈与加算は、相続人や遺贈を受けた人だけに限られる制度ではありません。相続人でなく、遺言により遺贈を受けたわけでもない人であっても、被相続人の死亡により生命保険金や死亡退職金を受け取った人が対象となる場合があります。
生命保険金や死亡退職金は、形式的には被相続人が生前に所有していた財産ではないため、本来の「相続財産」には含まれません。しかし、被相続人の死亡を原因として取得する財産であるため、相続税法上の「みなし相続財産」と位置づけられ、相続税の課税対象となります。
そのため、みなし相続財産の受取人が、相続開始前7年以内に被相続人から暦年課税方式による贈与を受けていた場合には、その贈与財産も生前贈与加算の対象となり、相続税額の計算に反映されます。
生前贈与加算が適用されないケースとは?
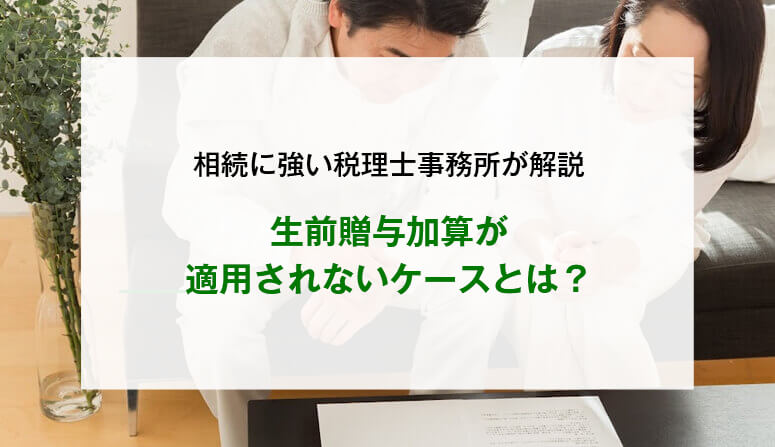
生前贈与加算の適用には例外があります。代表的なものは以下のケースです。
贈与税の配偶者控除が適用される場合
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与したときには、最大2,000万円までが非課税となります。この配偶者控除が適用された贈与は、たとえ相続開始前7年以内に行われたものであっても、生前贈与加算の対象外となります。
住宅取得等資金の贈与の特例が適用される場合
直系尊属から住宅取得のための資金を受ける場合、一定の要件を満たすと一定金額まで贈与税が非課税となる特例で、この住宅取得等資金の贈与を使った場合は生前贈与加算の対象外となります。
非課税となる枠は、住宅性能によって2つに分かれています。
| 省エネ等住宅 | 1,000万円まで(受贈者ごと) |
|---|---|
| それ以外の住宅 | 500万円まで(受贈者ごと) |
この特例は令和6年度の税制改正により、適用期限が延長され、令和8年(西暦2026年)まで適用できることになっています
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置が適用される場合
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置は30歳未満の子や孫が直系尊属から教育資金を一括贈与される場合、1,500万円まで非課税(学校以外は500万円)。相続開始前7年以内でも、既に教育資金として使った金額には加算されません。
ただし、贈与者が契約期間中に死亡したときは、その時点における管理残額に対して相続税・贈与税の対象となる可能性があります。
また、令和5年度の税制改正で、契約終了時に残額があり、改めて贈与税が課される場合は、年齢に関係なく「一般税率(通常の暦年贈与の税率)」が適用されることになったほか、贈与者の死亡時における「相続税の課税価格の合計額」が5億円を超える場合にも、管理残額は相続税の課税価格に含められることになりました。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が適用される場合
20歳以上50歳未満の子や孫が直系尊属から結婚・子育て資金を一括贈与された場合、最大1,000万円まで非課税となります(うち結婚資金は300万円まで)。
このうち既に結婚資金・子育て資金として支出済みの金額については7年以内であっても生前贈与加算は適用されません。(相続発生時に専用口座に残っている未使用分は、相続税の課税対象となることがあります。)
本制度の運用期間は当初2019年3月末まででしたが、その後延長が繰り返され、現在は2027年3月31日までの贈与が対象となっています。
生前贈与のお悩みは
当サポートセンターへご相談ください

生前贈与加算の制度とその例外を理解し、効果的に相続税対策を行うには専門的な知識が不可欠です。中途半端な理解で進めると、思わぬ税負担や手続き上のトラブルが発生する可能性があります。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ