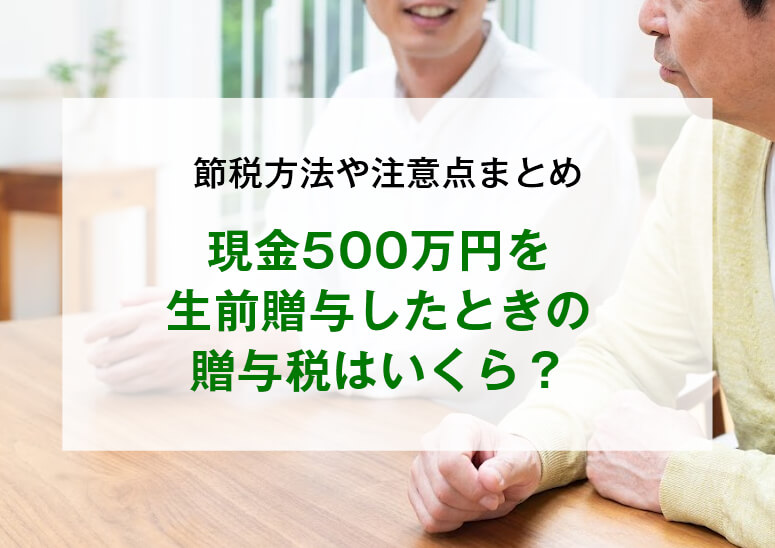
現金500万円を生前贈与したときの贈与税はいくら?節税方法や注意点まとめ
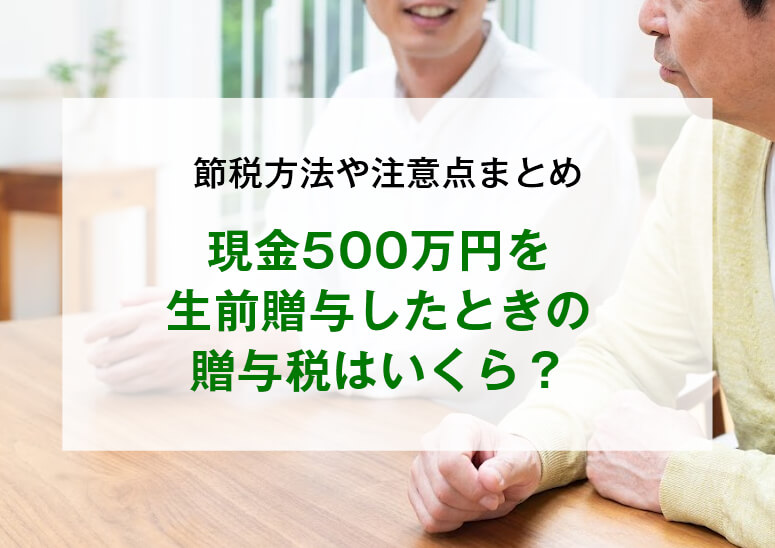
年間で110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与税がかかります。贈与税率は贈与された金額によって異なり、金額が多ければ多いほど税率も高くなってしまいます。
ただし、贈与税には様々な控除や特例制度が用意されているので、利用すれば贈与税を大幅に節税可能です。
本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが現金500万円を生前贈与したときにかかる贈与税や節税方法を紹介していきます。
目次
現金500万円を生前贈与したときに
かかる贈与税
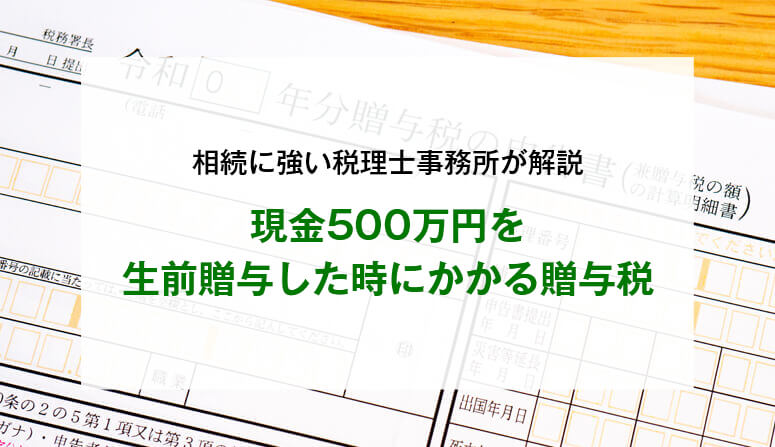
贈与税には年間110万円の基礎控除が用意されており、基礎控除を超えた部分に対しては、贈与税がかかります。
関連サイト国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
そのため、現金500万円を生前贈与したときには、贈与を受けた側(受贈者)が贈与税の申告および納税を行わなければなりません。
贈与税の税率は、以下の通りです。
特例贈与税率
贈与については、多くの場合、基礎控除額である110万円以下の範囲内で行われ、贈与税が発生しないようにすることが一般的です。
しかし、将来の相続税を見積もり、予測される相続税率よりも低い税率で贈与を実施することで、たとえ贈与税を支払ったとしても、総合的に見て節税効果を得られることがあります。
平成27年以降、直系尊属(両親や祖父母など)から贈与を受けた場合、受贈者がその年の1月1日時点で20歳以上であれば、特例税率という低めの税率が適用されるようになりました。このため、生前贈与を活用する機会が広がっています。
特例贈与税率の算出方法
| 贈与額(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
一般贈与税率
| 贈与額(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超え | 55% | 400万円 |
引用元国税庁「No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)」
特例贈与税率は、直系尊属(両親や祖父母)から成人した直系卑属(子供や孫)に贈与した場合に適用される税率で、一般贈与税率を用いた場合よりも納税額が低くなります。例えば、成人している孫に祖父母が現金500万円を贈与した際の計算方法は、以下の通りです。
| 基礎控除を差し引く | 500万円-110万円=390万円 |
|---|---|
| 贈与税を計算する | 390万円×15%-10万円=48.5万円 |
このように、祖父母から孫に生前贈与した場合でも、数十万円の贈与税がかかってしまいます。
関連サイト国税庁「Q28 贈与税の申告をする必要がある人は、どのような人ですか。」
また、特例税率を適用する場合は贈与税の申告書とともに受贈者(贈与を受けた方)の戸籍の謄本等の添付書類を添付する必要があります。
次の章では、贈与税の節税方法を詳しく解説していきます。
500万円を生前贈与するときの節税方法4つ
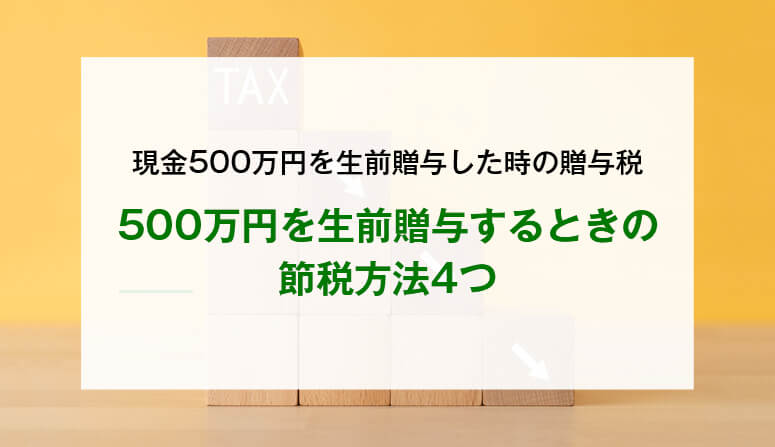
贈与税には控除や特例が用意されており、上手に利用すれば税負担を軽減しながら資産を移転することができます。500万円を生前贈与するときに活用できる節税方法を4つ紹介していきます。
暦年贈与を活用する
贈与税には年間110万円の基礎控除が用意されています。基礎控除を利用して複数年にわたり、生前贈与を行えば贈与税を節税可能です。
基礎控除枠を利用して行う生前贈与は、暦年贈与と呼ばれています。
暦年贈与とは、この110万円の非課税枠を活用して、相続税の負担を軽減する方法です。手軽に利用できることから、暦年贈与は多くの人にとって基本的な相続税対策とされています。
例えば、現金500万円を1年間で一括贈与した場合には、48.5万円の贈与税がかかってしまいます。一方で、以下のように複数年で贈与を行えば、同じ500万円を贈与した場合であっても贈与税はかかりません。
| 1年目 | 110万円贈与 |
|---|---|
| 2年目 | 110万円贈与 |
| 3年目 | 110万円贈与 |
| 4年目 | 110万円贈与 |
| 5年目 | 60万円贈与 |
暦年贈与は、要件も設定されておらず、贈与者・受贈者が誰であっても利用できるメリットがありますが、生前贈与の金額が多くなればなるほど、時間がかかってしまうのがデメリットです。
また贈与契約書がない場合など、税務署から「贈与税を回避するためにただ5年に分けただけ」と暦年贈与が否認され、贈与の最初の年に一括贈与契約があったとして贈与総額の500万円に贈与税が課される可能性もあります。
贈与契約書とは
財産移転の際に作成される重要な文書に、贈与契約書があります。この書類は、財産の無償譲渡に関して、譲渡者と受領者の間で合意された内容を明確に示すものです。
個人間での財産の無償譲渡は「贈与」と呼ばれ、実は口頭での約束だけでも法的には成立します。しかし、このような形式での合意には潜在的なリスクがあります。
例えば、当事者の一方が亡くなった場合、贈与の事実を証明することが困難になる可能性があります。また、後日、贈与者や受贈者が気持ちを変え、贈与を撤回したいと思うケースも想定されます。
こうしたリスクを回避し、贈与の確実性を高めるために、生前贈与の際には贈与契約書の作成が強く推奨されます。この文書は、贈与の取り消しを防ぐとともに、将来的な紛争や疑義が生じた際の有力な証拠となります。
つまり、贈与契約書は単なる形式的な書類ではなく、関係者全ての利益を守り、円滑な財産移転を実現するための重要なツールと言えるでしょう。
贈与税の控除や特例を活用する
贈与税には以下のような様々な控除や特例制度が用意されています。資金の使途目的や贈与時期などを決めた上で一括贈与する場合などに有効な方法です。
それぞれの控除や特例では、適用要件が設定されているので、資金の使途や贈与時期を踏まえて、利用できる控除や特例がないか確認してみるのが良いでしょう。
生活費や教育費として贈与をする
直径血族および兄弟姉妹は扶養義務者であり、生活費や教育費目的の贈与であれば、原則として贈与税はかかりません。生活費や教育費目的で贈与を行う際には、以下の点に注意をしておきましょう。
- 非課税になるのは一般的な金額の範囲内のみ
- 贈与は生活費や教育費が必要になったときに都度行う
なお、「教育資金贈与の非課税措置」はこれまでの税制改正で何度か延長されています。そして、2023年度の税制改正により期間が2026年3月31日までになりました。このように税制は改正が重ねられています。ご自身の状況を照らし合わせながら、検討していきましょう。
教育資金贈与の非課税措置とは
教育費用の世代間移転を促進する目的で設けられた特別措置として、「教育資金贈与の非課税制度」があります。この制度は、子や孫の教育を支援したい親や祖父母の方々にとって、大変有意義なものです。
本制度の下では、直系尊属(親や祖父母など)から直系卑属(子や孫など)への教育目的の資金贈与について、一定額まで贈与税が免除されます。
なお、この制度は各省庁によって呼び名が若干異なります。文部科学省では「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」、国税庁では「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」と呼ばれています。
通常、年間110万円を超える贈与には贈与税が課されますが、この特別措置を利用することで、最大1,500万円までの教育資金贈与が非課税となります。これにより、子や孫の将来に向けた大規模な教育投資が、税制面でのサポートを受けながら可能となります。
この制度は、教育の機会均等と世代間の資産移転の促進という二つの社会的目標に寄与する、重要な政策ツールと言えるでしょう。
そもそも基礎控除内であれば相続税はかからない
生前贈与を行うことで相続財産を圧縮し、相続税対策をしたいと考えている人も多いはずです。将来の相続財産を減らすために、生前贈与を行うのは確かに有効です。
その一方で、相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が用意されています。相続財産が基礎控除内に収まる範囲であれば、相続税の申告および納税は必要ありません。
相続税対策として生前贈与を行うのであれば、まずは将来かかる相続税を計算してみるのが大切です。
計算の結果、相続税がかからないと予想されるのであれば、無理して今の段階で500万円の生前贈与をおこなう必要性は薄いかもしれません。
現金を生前贈与するときの注意点
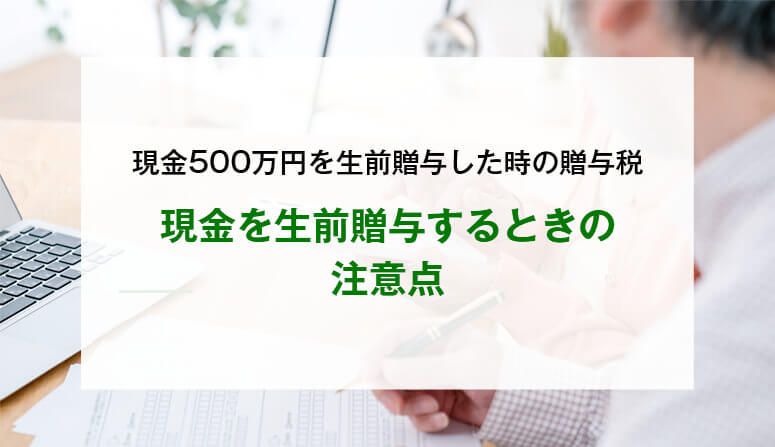
生前贈与は預貯金や不動産、株式だけでなく、現金で行うことも可能です。ただし、現金で生前贈与するときには、いくつか注意すべきことがあります。詳しく確認していきましょう。
現金の贈与でも必ず申告・納税する
ごくたまに現金手渡しの贈与であれば、税務署にはバレない」と考える人がいますが、税務署はかなりの確率で贈与税の無申告や申告漏れに気付きます。税務調査によって贈与税の申告漏れがバレてしまえば、追徴課税などのペナルティが発生してしまいます。
現金で生前贈与を行うとしても、贈与金額が基礎控除額を上回るのであれば、必ず贈与税の申告および納税をしましょう。
贈与契約書を作成する
現金で生前贈与を行う場合でも、必ず贈与契約書を作成しておきましょう。贈与は贈与者と受贈者の間に合意があれば、贈与契約書がなくても法律的には成立します。
しかし、贈与契約書があれば第三者にも確実に贈与があったと証明可能です。例えば、贈与者が亡くなったときに「生前贈与は無効だ」と他の相続人に主張されたときも、贈与契約書があれば生前贈与があったことを証明できます。
また、税務署から調査があった場合などにも贈与の事実を主張することが可能です。贈与契約書には以下の1~5の内容を記載した上で、記名・押印のうえ受贈者・贈与者それぞれが保管することが望ましいとされています。
- 誰があげるのか(贈与者の氏名・住所)
- 誰にあげるのか(受贈者の氏名・住所)
- いつあげるのか(贈与契約締結の日付、実際に贈与を実行する日付)
- 何をあげるのか(贈与財産の種目・内容・金額・住所、その他財産に関する情報)
- どうやってあげるのか(贈与の方法)
亡くなる3年以内に行われた贈与は相続税の課税対象財産に含まれる
亡くなる3年以内に行われた生前贈与は、相続税の課税対象財産に含まれます。相続開始直前に駆け込みで贈与することによる相続財産の圧縮を防ぐために設けられているルールです。
暦年贈与で複数年にわたり生前贈与を行う計画を立てている場合には、贈与者の体調や寿命なども考慮する必要があります。
また、相続税の課税対象財産に含まれた生前贈与は、贈与税の基礎控除が適用されないのでご注意ください。
贈与税の節税や申告は
当サポートセンターにお任せください

年間で110万円を超える贈与を受け取った場合には、贈与税がかかります。ただ、贈与税には様々な控除や特例が用意されているので、有効に活用することで贈与税を節税することも可能です。
一方で、贈与税は相続税法にその根拠を持つことから、相続税を補完するものとされており、令和3年度以降の税制改正大綱の中でも「相続・贈与一体課税」が論議されています。
今後は、相続まで見通した対策が必要になることが予想されますので、相続税対策全般に強みを持つ税理士に依頼をするのが良いでしょう。
杉並・中野相続サポートセンターでも、相続税対策や生前贈与の計画から実行まで一括でサポートを行っています。相続や生前贈与に関する疑問やお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
当サポートセンター・対応エリア
初回利用者向けの無料相談会も開催しておりますので、まずは一度お気軽にお問い合わせくださいませ。
関連サービス無料・相続相談のご案内
現金500万円を生前贈与した時の贈与税まとめ
預貯金や不動産だけでなく、現金を生前贈与したときにも贈与税はかかります。贈与税には、年間110万円の基礎控除が用意されており、基礎控除を超えた分にのみ贈与税が課税されます。
例えば、祖父母から成人している孫に対して、現金500万円を生前贈与したときにかかる贈与税は48.5万円です。なお、贈与税は贈与をした側でなく、贈与を受けた側が支払います。
贈与税は相続税よりも税率が高いですが、様々な控除や特例制度が用意されており、活用できれば贈与税を大幅に節税可能です。どの控除や特例が適用できるか、どのように生前贈与を行えば節税効果が高いのかは贈与者と受贈者の関係や贈与の目的によっても異なります。
生前贈与の節税対策にお悩みの人は、相続や生前贈与に詳しい税理士に相談することもご検討ください。もちろん、私たち杉並・中野相続サポートセンターでもご相談を承ります。経験豊富な税理士が直接お話を伺います。まずは無料相談をぜひご利用ください。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ