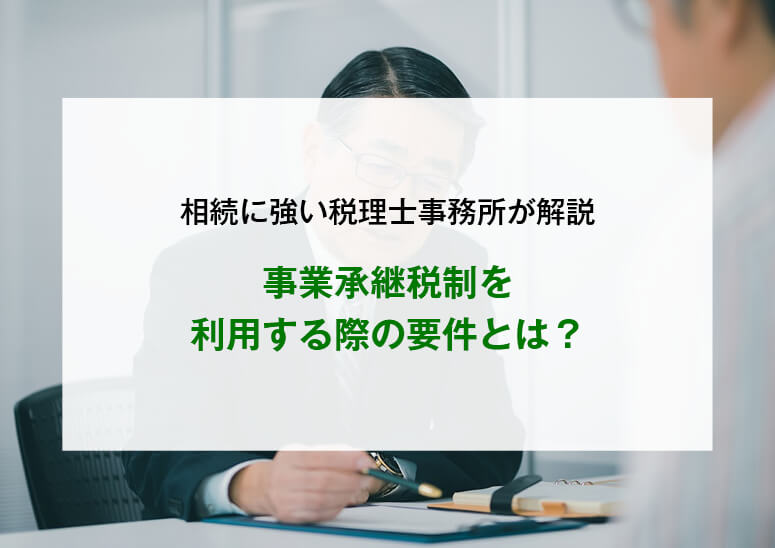
事業承継税制を利用する際の要件とは?税理士事務所が解説
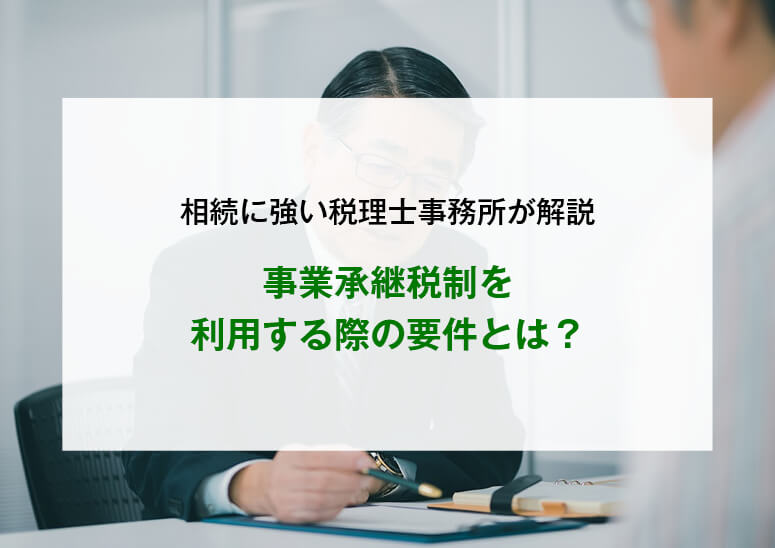
中小企業の経営者にとって、事業承継は避けて通れない重要な課題です。特に、自社株の相続や贈与には多額の税負担が生じることもあり、後継者へのスムーズな引き継ぎを阻む要因となり得ます。
こうした問題を解消するために設けられたのが「事業承継税制」です。事業承継税制を活用すれば、自社株を相続、贈与した際の税負担を抑えられます。
本記事では、事業承継税制の要件や手続きする流れについて詳しく解説します。
目次
事業承継税制とは
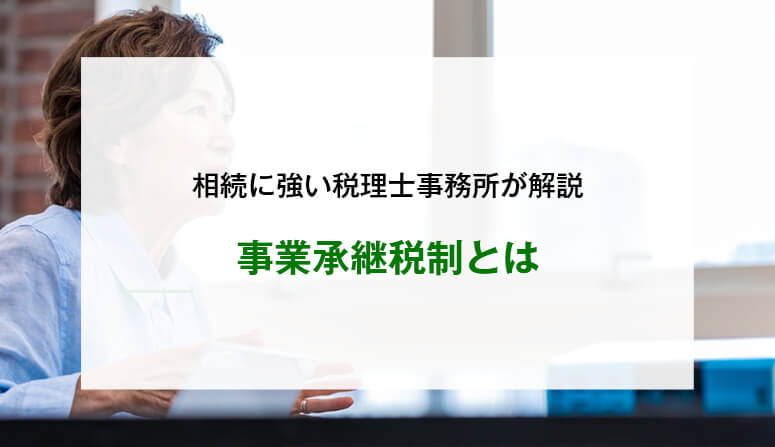
事業承継税制とは、中小企業の経営者が後継者に事業を受け継ぐ際に税負担を軽減できる制度です。事業承継税制を活用すれば、自社株を相続または贈与する際にかかる相続税・贈与税の納税猶予を受けられます。
関連サイト国税庁「法人版事業承継税制」
加えて、一定の要件を満たせば猶予されていた相続税や贈与税の納税義務が免除される場合もあります。
事業承継税制が設立された理由
日本の中小企業の多くが、経営者の高齢化に直面しつつも後継者問題を抱えています。
特に、中小企業では親族内承継が主流であり、後継者が自社株を相続する際の税負担の重さが事業承継の妨げとなっているケースも多くあります。
このような事態に対応するために、2009年に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が施行され、その一環として事業承継税制が導入されました。
特例措置と一般措置とは
事業承継税制には(1)一般措置と(2)特例措置の2つの枠組みがあり、それぞれ適用要件や対象期間に違いがあります。
| 一般措置 | 特例措置 | |
|---|---|---|
| 事前の計画策定 | 不要 | 5年以内の特例承継計画を提出する |
| 適用期限 | なし | 10年以内の贈与・相続等 (2018年1月1日から2027年12月31日まで) |
| 対象株数 | 総株式数の3分の2まで | 全株式 |
| 納税猶予割合 |
|
100% |
| 承継パターン | 複数の株主から1人の後継者 | 複数の株式から最大3人の後継者 |
| 雇用確保要件 | 承継後5年間にわたり平均8割の雇用維持が必要 | 弾力化 |
| 経営環境変化に 対応した免除 |
なし | あり |
特例措置は2018年の税制改正で創設された、より柔軟かつ手厚い制度です。特例措置では、相続税・贈与税ともに100%の納税猶予が認められ、雇用確保要件など一部の要件が緩和されています。
さらに、2024年度の税制改正により、事業承継税制の特例措置を適用するために必要な「特例承継計画」の提出期限が、従来の2024年3月31日から2026年3月31日までの2年間延長されるなど、政府としてもより多くの中小企業が計画的に事業承継を進めることができるよう後押しをする姿勢がうかがえます。
関連サイト中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」
事業承継税制の要件(対象企業)
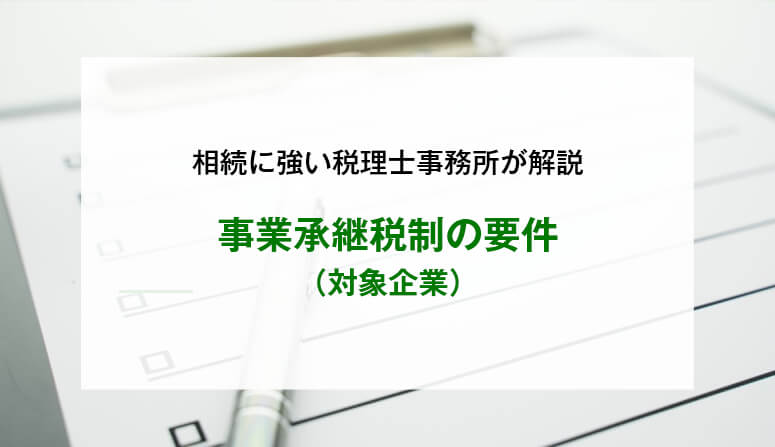
事業承継税制を活用するためには、制度の対象となる法人が下記の要件を満たしている必要があります。
- 非上場の中小企業である
- 風俗営業会社に該当しない
- 資産管理会社に該当しない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
制度の対象となる企業であることが大前提です。たとえ後継者の選定や計画が整っていても、企業自体が制度の適用対象外である場合には、納税猶予の恩恵を受けることができません。
以下では、制度上「対象企業」として求められる主な要件について解説します。
非上場の中小企業である
事業承継税制の対象となるのは、非上場の中小企業であり、資本金または従業員数の要件を満たす必要があります。
| 業種 | 資本金額もしくは出資金総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業や建設業、 運輸業、その他 |
3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
また、「非上場」であることも条件のひとつです。上場企業は原則として制度の対象外となります。
風俗営業会社に該当しない
事業承継税制は、中小企業の「健全な事業活動」を支援するための制度であることから、風俗営業を営む会社は制度の対象外とされています。
具体的には、下記の事業を行っている場合には、事業承継税制を活用することはできません。
- キャバレー、ナイトクラブ、バーなどの接待を伴う飲食業
- ライブハウスやカラオケ店など演者やサービスが提供される業態
- パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどの遊技業
- 無店舗型性風俗特殊営業などの性風俗営業
資産管理会社に該当しない
もうひとつの重要な要件が、資産管理会社に該当しないことです。資産管理会社とは、主たる業務が不動産賃貸や株式・預金の保有などであり、実態として事業活動を行っていない会社です。
事業承継税制では、収入割合や資産割合に基づいて、資産管理会社かどうかが判断されます。事業承継に精通した税理士に相談し、資産管理会社に該当しないかどうかを確認しておくと良いでしょう。
事業承継税制の要件(先代経営者・後継者)
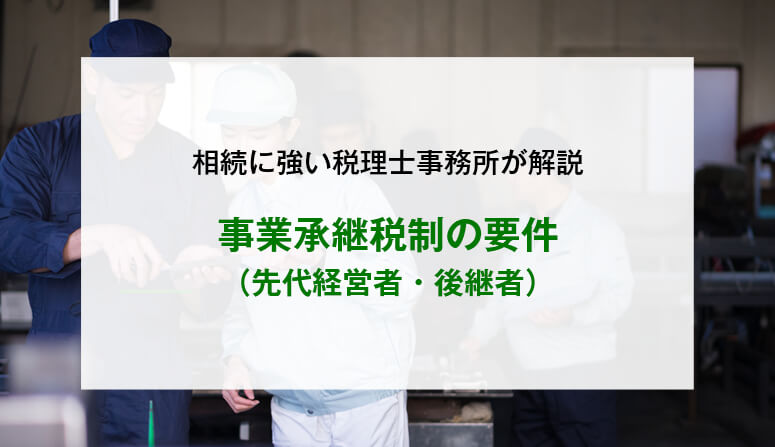
事業承継税制を活用するためには、対象企業だけでなく、株式を譲渡する先代経営者と、それを受け取る後継者が制度上の要件を満たしている必要があります。
なお、適用できる税金は贈与と相続に分けられますが、それぞれ要件が異なるのでご注意ください。それぞれ詳しく解説していきます。
先代経営者の要件
事業承継税制における「先代経営者」とは、対象会社の代表権を有していた人物であり、承継時点ですでに代表権を後継者に引き継いでいることが求められます。
具体的には、先代経営者は下記の要件を満たさなければなりません。
- 会社の代表者だった
- 相続開始・贈与直前に現経営者親族などで総議決権数の過半数を保有しており、筆頭株主だった
- 贈与時点で代表者を退任している(有給役員として残ることは認められている)
後継者の要件
制度を利用する「後継者」も、複数の要件を満たす必要があり、相続・贈与で共通する要件と、それぞれの方式に特有の要件に分けられます。
相続・贈与で共通している要件
相続と贈与で共通している要件として、後継者は承継時点で会社の代表者となっていることが求められます。
具体的には、下記の要件を満たす必要があります。
- 相続開始または贈与時、後継者と後継者親族などで総議決権数の過半数を保有する
- 後継者が1人なら、最も多くの議決権数を保有することになる。後継者が2人または3人なら、総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権数を保有する
贈与時の要件
贈与により事業承継税制の適用を受けるためには、後継者が20歳以上(2022年以降は18歳以上)である必要があります。
加えて、贈与の直前で3年以上の役員経験があり、贈与時点で会社の代表取締役に就任していなければなりません。
この3年以上の役員経験の要件は令和7年度税制改正大綱で緩和される方向性が示されました。具体的には、これまで後継者に贈与前3年の役員就任期間が必要でしたが、改正後は事業承継実施の直前までに役員就任すれば要件を満たすこととなります。
この改正により、後継者の役員就任のタイミングに柔軟性が生まれ、事業承継の準備をより計画的に行うことが可能になる効果が期待されます。
相続時の要件
相続により事業承継税制の適用を受ける場合には、下記の要件を満たさなければなりません。
- 相続開始直前に役員だった
- 相続開始から5ヶ月以内に会社の代表者となった
事業承継税制の要件(事業継続)
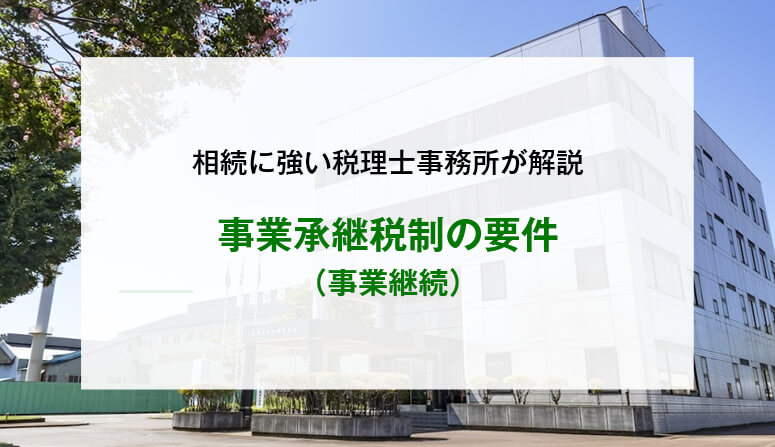
事業承継税制を適用するためには、株式の承継後も一定期間、事業を継続しなければなりません。事業承継制度の本来の目的は、中小企業の円滑な事業承継を支援し、経営と雇用を守ることだからです。
そのため、一時的な株式移転だけでなく、実際に会社が継続的に経営されているかどうかが重要視されます。具体的には、承継後に下記の要件を満たす必要があります。
5年間
- 後継者が会社の代表者かつ筆頭株主である
- 後継者が承継された株式を継続して保有している
- 5年間平均で雇用の8割以上を維持している
5年経過後
- 後継者が承継された株式を継続して保有している
上記の要件を満たしていない場合には、納税猶予は打ち切られ、相続税や贈与税の一括納付が求められる恐れがあります。
事業承継税制を適用する流れ
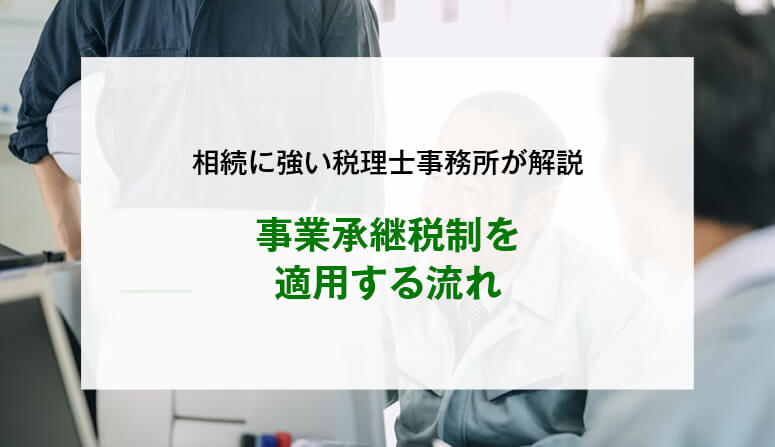
事業承継税制は自動で適用されるわけではなく、下記の流れで申請をしなければなりません。
- 事前準備をする
- 申請手続きをする
- 事業承継後の継続要件を満たす
事業承継税制は適用要件も複雑であり、承継後も継続して要件を満たす必要があります。
加えて、適用要件を満たせなかった場合の税負担は重いため、自己判断で手続きしないことが重要です。事業承継税制の適用を考えた段階で、税理士に相談しておくことを強くおすすめします。
事業承継税制の適用が取り消されるケース
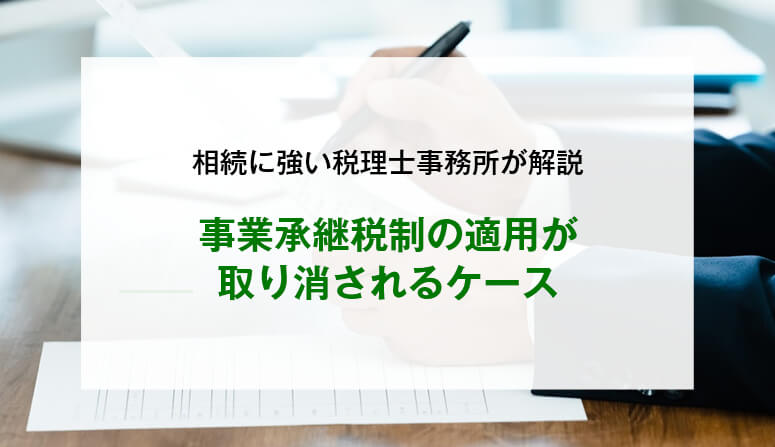
事業承継税制は節税効果が大きい一方で、要件を満たせていないと、制度の活用途中であっても適用が取り消される恐れがあります。
事業承継税制の適用が取り消されるケースは、主に下記の通りです。
- 5年間の経営継続要件・雇用継続要件を満たさなかった
- 株式を売却・贈与・譲渡してしまった
- 事業を廃業・解散した
- 代表者が死亡し、後継者が不在になった
- 適用要件を満たさなくなった
特に注意すべきは、5年間の雇用継続要件や承継された株式の継続保有です。経営不振によりリストラを行った結果、事業承継税制の適用が取り消される恐れもあるのでご注意ください。
事業承継税制を適用する場合、承継者は先代経営者から受け継いだ株式を保有し続けなければなりません。株式の譲渡や売却をする際には、専門家に相談した上で判断することをおすすめします。
事業承継は
当サポートセンターにお任せください

事業承継税制は、贈与税や相続税の節税効果が大きいため、後継者に経営権の引き継ぎを考えているのであればぜひとも活用したい制度です。
また、事業承継税制は法人のみならず個人事業においても同様の制度が始まっており、個人事業主が事業継続に必要な資産を後継者に継承する際などにはぜひ使いたい制度です。
しかし、事業承継税制は適用要件が複雑であり、承継後も要件を満たさなければなりません。自分たちで申請準備をすることや、適用後の継続要件を確認し続けるのは、あまり現実的ではないでしょう。
事業承継税制の利用を考えている方は、相続に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
事業承継税制を利用する場合、利用を検討し始めた段階や後継者選びについて考え出した段階で、税理士などの専門家に相談しておくことが大切です。
というのも、事業承継税制の要件の中には、後継者が会社役員であるといった要件も含まれているからです。
例えば、先代経営者が急死した場合、後継者が役員でなければ事業承継税制を適用することはできません。
このような不測の事態を防ぐためにも、事業承継は早い段階から準備を進めていきましょう。事業承継に精通した税理士などの専門家に相談すれば、準備を進めてもらえますし、必要に応じてアドバイスも受けられます。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ