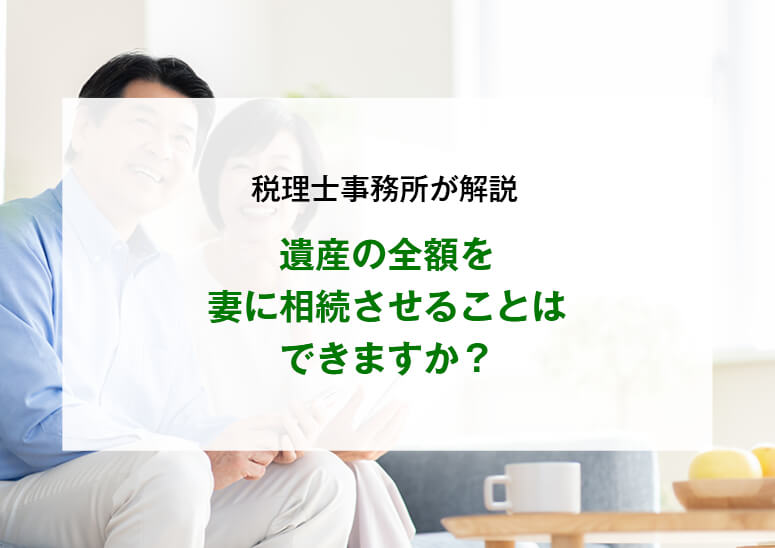
遺産の全額を妻に相続させることはできますか?税理士事務所が解説
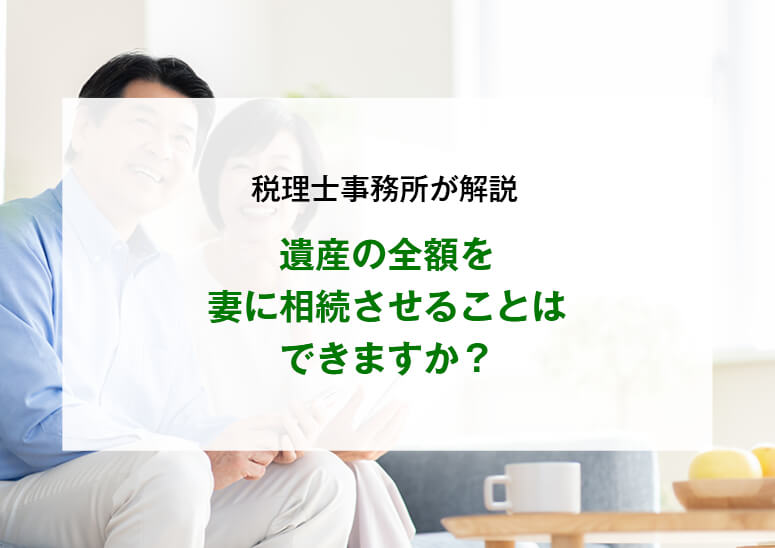
自分が亡くなった後、妻の生活はどうなるんだろう、経済的に困ることがないようにしてあげたいと考える方も多いのではないでしょうか。
遺産を受け継ぐ人物や順位は民法によって決められており、相続人の状況によっては妻がすべての遺産を相続できるとは限りません。
そのため、妻に遺産を全額相続させたいのであれば、遺言書などで相続対策をしておくことをおすすめします。
本記事では、遺産を全額妻に相続させることはできるのか、相続税の節税対策について解説します。
目次
妻の法定相続分とは
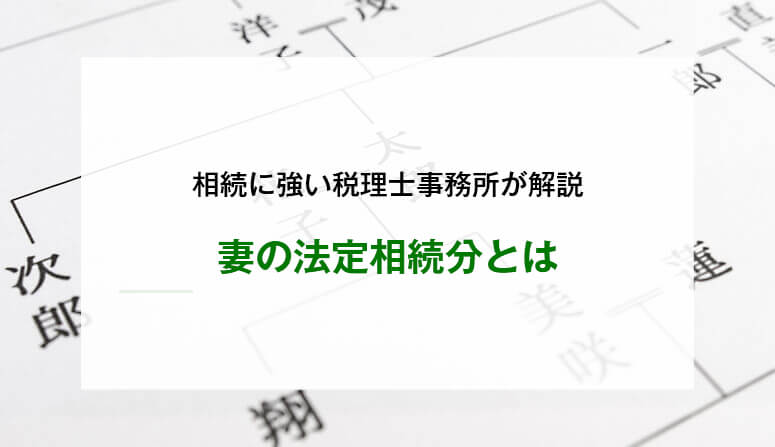
遺産を相続する人物および優先順位は、民法によって決められており、下記の通りです。
| 常に相続人になる | 配偶者 |
|---|---|
| 第一順位 | 子供や孫 |
| 第二順位 | 両親や祖父母 |
| 第三順位 | 兄弟姉妹や甥姪 |
上記のように、配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の相続人は優先順位の高い人物が1人でもいる限り、相続権を持つことはありません。
このように、民法上は被相続人に子供がいれば配偶者と子供が相続人となりますし、子供がいない場合は配偶者と両親(祖父母)や兄弟姉妹(甥姪)が相続人となります。
そして、民法では相続人になる人物や優先順位だけでなく、それぞれの相続人が相続する割合についても下記のように決めています。
| 相続人 | 相続割合 |
|---|---|
| 配偶者と子供 |
|
| 配偶者と両親(祖父母) |
|
| 配偶者と兄弟姉妹 |
|
このように、妻が必ずしも遺産を全額相続できるわけではなく、他の相続人の有無によって取り分が決まります。
そのため、妻に全額相続させたい場合は、適切な手続きを行う必要があります。次の章では、妻に遺産を全額相続させる方法を詳しく解説していきます。
妻に遺産を全額相続させる方法
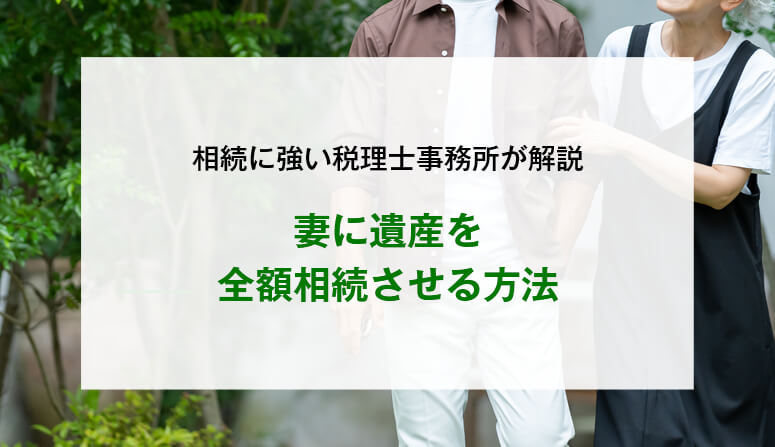
先ほど解説したように、民法では法定相続分が決められているため、妻が全額遺産を相続できないケースもあります。
相続人にかかわらず妻に全額遺産を相続させたい場合は、遺言書の作成など相続対策をしておきましょう。詳しく解説していきます。
遺言書を作成しておく
妻に全額相続させるための最も確実な方法のひとつが、遺言書の作成です。遺言書に「妻にすべての財産を相続させる」と明記すれば、原則としてその内容に従って遺産が分配されます。
ただし、他の相続人(被相続人の子供や両親)がいる場合、遺留分を侵害してしまう恐れがある点には注意しなければなりません。
遺留分トラブルを防ぐためにも、妻に全額遺産を相続させる遺言書を作成する場合は、相続の専門家に相談しておくことをおすすめします。
遺産分割協議にて決定する
被相続人が遺言書を用意せず亡くなった場合でも、遺産分割協議にて相続人全員が合意すれば、妻に全額遺産を相続させられます。
遺産分割協議は、遺産の取り分について相続人全員で行う話し合いです。
例えば、被相続人に子供がいたとしても「母親の生活を安定させるために、自分たちは遺産を相続しなくて良い」と考えれば、妻に遺産を全額相続させられます。
妻に遺産を全額相続させるときに
発生する相続税
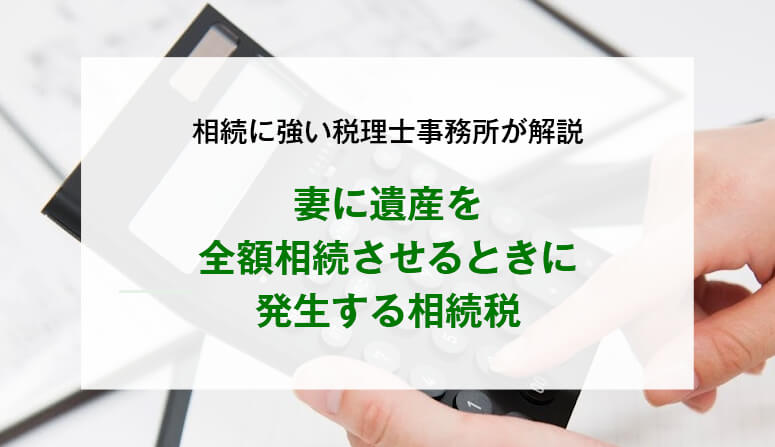
遺産を相続すると相続税がかかる場合があります。しかし、被相続人の配偶者は「配偶者控除」を利用できるため、1億6,000万円までの相続財産であれば相続税が発生することはありません。
そのため一般的な家庭の場合、被相続人の配偶者がすべての遺産を相続したとしても、相続税がかかるケースはほぼないといえるでしょう。
相続税を計算する流れは、下記の通りです。
- 遺産総額を計算する
- 基礎控除を適用し課税対象額を計算する
- 法定相続分で分けたとして相続税率を掛ける
- 実際の相続分で相続税を分配する
- 相続税の控除・加算を適用する(相続税の配偶者控除はこの部分で適用する)
なお、配偶者控除を適用し、相続税額が0円になったとしても、相続税申告書を期限内に申告しなければなりません。
相続税の計算や申告書作成に不安がある場合は、相続税に精通した税理士に依頼することをおすすめします。
相続税の節税に使える制度
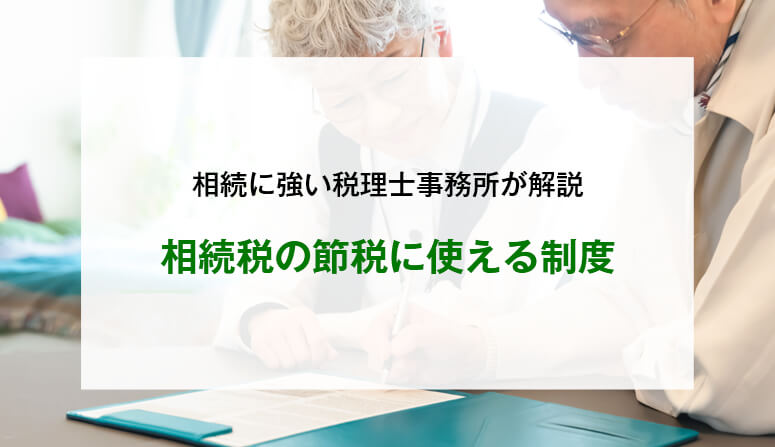
相続税には控除や特例が用意されており、活用すれば相続税の負担を大幅に軽減可能です。被相続人の配偶者が適用できる相続税の控除・特例には、主に下記のものがあります。
- 配偶者控除
- 小規模宅地等の特例
- 生命保険の非課税枠
- 配偶者居住権
それぞれ詳しく解説していきます。
配偶者控除
配偶者は、相続税の計算において特別な控除を受けることができます。この控除を配偶者特別控除と言い、以下のどちらか低い金額まで相続税が非課税になる制度です。
- 1億6,000万円まで
- 法定相続分相当額まで
この配偶者控除の節税効果は非常に大きいため、仮に配偶者が遺産をすべて相続したとしても、相続税がかかる可能性はとても低くなります。
関連サイト国税庁「No.4158配偶者の税額の軽減」
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、夫が住んでいた自宅を妻が相続する場合、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
被相続人の自宅に対して小規模宅地等の特例を適用する際の要件は、下記の通りです。
- 被相続人が住んでいた土地であること
- 配偶者または同居親族が相続すること
- 申告期限までに売却せずに保有していること
小規模宅地等の特例を適用し、相続税額が0円になったとしても、期限内申告が求められるので、確実に特例を適用するためにも税理士に相談することをおすすめします。
生命保険の非課税枠
生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象として扱われますが、法定相続人が相続した場合は非課税枠を適用できます。
非課税枠の計算式は下記の通りです。
500万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が妻と子供1人(計2人)の場合、500万円×2人=1,000万円まで生命保険金は非課税となります。
配偶者居住権
配偶者居住権とは、夫が亡くなった後も妻が自宅に住み続ける「居住権」と自宅不動産の「所有権」を分ける制度です。
夫の遺産のほとんどが自宅不動産だった場合、配偶者居住権を利用すれば、妻が預貯金と自宅に住み続ける居住権を相続し、生活を安定させられます。
配偶者居住権のメリットは、下記の通りです。
- 相続発生後も妻が自宅に住み続けられる
- 二次相続対策につながる
- 妻が他の財産を多く相続しやすくなる
妻に遺産を全額相続させるときの注意点
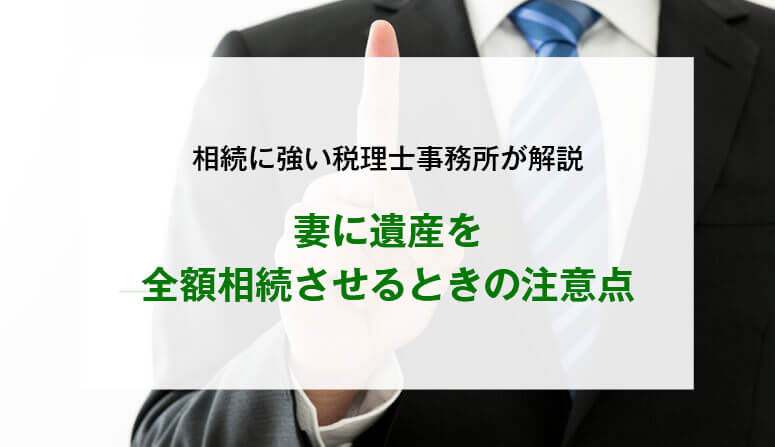
妻に遺産を全額相続させる際には、遺言書が遺留分を侵害する恐れがある点や二次相続の負担が重くなる点に注意しなければなりません。
それぞれ詳しく解説していきます。
遺言書が遺留分を侵害する恐れがある
遺言書を作成して妻に全額相続させる場合、他の相続人(子供や両親)がいると、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
遺留分とは、被相続人の配偶者や子供、両親が最低限度の遺産を受け取れる権利であり、遺留分は遺言内容より優先されます。
したがって、遺留分を侵害している遺言書を作成してしまうと、相続トラブルが発生するリスクが高まるため、注意しなければなりません。
- 遺留分侵害額相当分の金銭を用意しておく
- 子供たちに遺言内容を話しておき、理解してもらう
自分で遺言内容を考えてしまうと、トラブルに発展するリスクがあるので、相続に詳しい専門家に相談した上で遺言書を作成しましょう。
二次相続の税負担が重くなる可能性がある
妻に全額相続させることで、一次相続(夫の相続)では相続税の負担を軽減できます。
しかし、二次相続(妻が亡くなった際の相続)まで含めると、トータルでみた相続税は増加する可能性があります。
二次相続で税負担が重くなる理由は、主に下記の通りです。
- 子が相続する場合、配偶者控除が使えず相続税が高くなる
- 二次相続では法定相続人の数が減るため、基礎控除の金額が減る
- 配偶者より子供の方が小規模宅地等の特例の適用要件が厳しくなるため、適用が難しくなる
配偶者に全額遺産を相続させたい場合は、二次相続対策についても税理士に相談しておくと安心です。
相続税対策は
当サポートセンターにお任せください

妻に全額遺産を相続させるには、遺言書の作成など相続対策を行っておくと良いでしょう。
ただし、妻にすべて遺産を相続させると、二次相続でかかる相続税が高くなる可能性があるので、慎重に判断しなければなりません。
二次相続まで見据えた相続税対策をしたい場合は、相続に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
法定相続人になれる人物は、被相続人の配偶者だけでなく子供や両親、兄弟姉妹などもいます。したがって、妻に全額遺産を相続させたい場合は、元気なうちに遺言書の作成などを行っておきましょう。
ただし、遺言内容によっては遺留分を侵害する恐れもあるので、トラブルを避けるために専門家に相談した上で、遺言書の作成を行うと良いでしょう。
妻に遺産を相続させる場合は、相続対策と節税対策両方からアプローチしてく必要があります。そのため、複数の専門家と協力体制を取りつつ、対策を進めていくことをおすすめします。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ