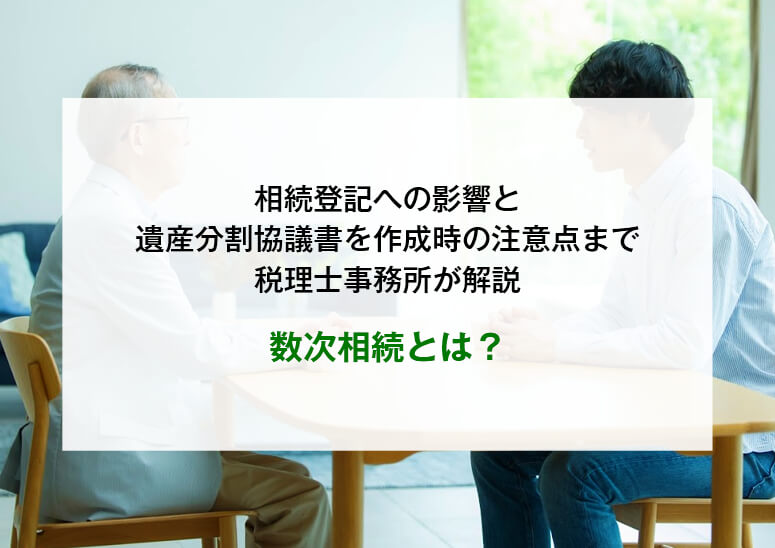
数次相続とは?相続登記への影響・遺産分割協議書を作成する際の注意点まで解説
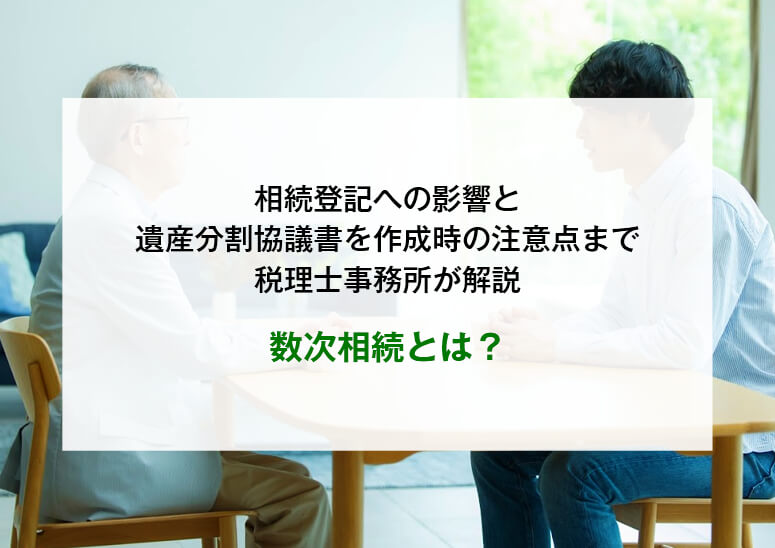
数次相続は、被相続人が亡くなった後、遺産分割など相続手続きが完了する前に相続人がさらに亡くなり、その相続人の相続人が引き継ぐことになるケースを指します。
例えば、父から母へ、さらに母から子供へと財産が移転するような場合には、相続人調査や遺産分割協議が複雑になり、相続税の申告や控除の適用判断にも注意が必要です。
本記事では、数次相続の仕組みや代襲相続・再転相続との違い、実際の手続きのポイントについて解説します。
目次
数次相続とは
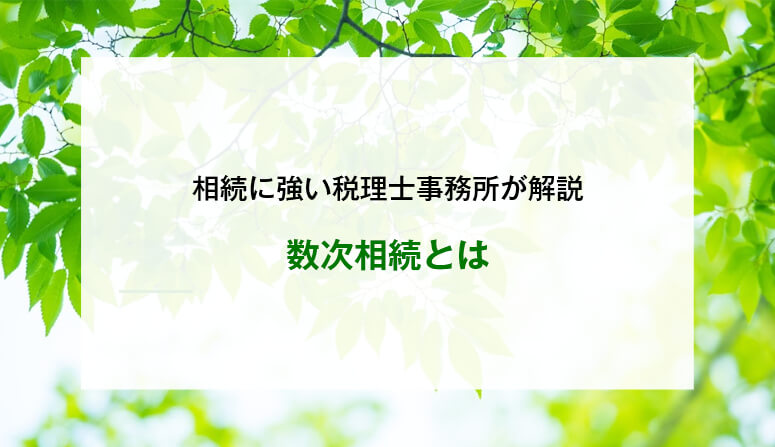
数次相続とは被相続人が亡くなった後、遺産分割など相続手続きが完了する前に相続人がさらに亡くなり、その相続人の相続人が引き継ぐことになる相続です。
例えば、父親が亡くなり、相続人である母親が遺産を取得する前に亡くなった場合、母親の相続人(子供など)が父親の遺産を「数次相続」として引き継ぐことになります。
数次相続が起こると、相続関係が複雑化しやすくなるため、相続人調査や相続財産調査を念入りに行う必要があります。
相続税の申告においても複数の相続が絡み合うため、計算・申告作業が煩雑になるので、必要に応じて専門家に相談することも検討しましょう。
数次相続と代襲相続の違い
代襲相続とは、相続人となるはずの子供や兄弟姉妹が被相続人の死亡以前にすでに亡くなっていた場合、その子供など直系の血族が代わりに相続することです。
例えば、父親が亡くなったときに長男がすでに死亡していた場合、長男の子供(被相続人にとっての孫)が代襲相続人となります。
一方で、数次相続は、被相続人の死亡後に相続人が亡くなることで発生します。
数次相続と再転相続の違い
再転相続とは、一次相続の相続人が相続するか放棄するか意志を示す前に亡くなってしまい、次の相続が発生することです。
数次相続と非常に似ていますが、二次相続が発生するタイミングが異なります。
| 再転相続 | 一次相続の相続人が相続する意思を示す前に亡くなる |
|---|---|
| 数次相続 | 一次相続の相続人が相続する意思を示したものの、遺産分割協議が完了する前に亡くなる |
再転相続が発生した場合、二次相続の相続人は一次相続について相続するか放棄するかを判断しなければなりません。
数次相続が発生したときの
相続手続きのポイント
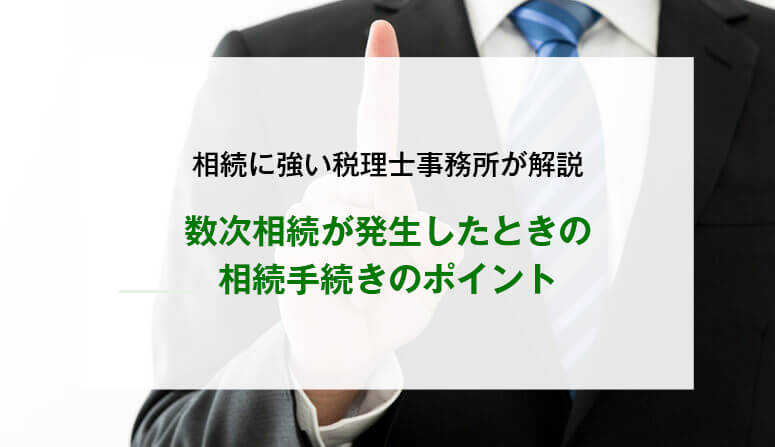
数次相続が発生すると、遺産分割の対象者が増えるため、通常の相続手続き以上に複雑になります。相続税の申告や相続登記など、期限が定められている手続きも複数回発生するため、早めに全体像を整理し、適切に進めることが重要です。
数次相続が発生したときは、相続手続きの際に、以下のようなことを意識しておきましょう。
- 相続人調査を念入りに行う
- 遺産分割協議書はそれぞれの相続で作成する
- 相続登記は中間省略登記が認められる場合がある
それぞれ詳しく解説していきます。
相続人調査を念入りに行う
数次相続では、被相続人の死亡後に一次相続人が死亡しているため、相続人の範囲が広がる点が特徴です。
例えば、父の相続人である母が相続開始後に死亡した場合、母の相続人である子供や孫が「父の相続人」として新たに関与することになります。
このため、一次相続だけでなく二次相続の戸籍もさかのぼって調査し、関与すべき全員を確定させなければなりません。相続人の一部が漏れていると、後から遺産分割協議をやり直さなければならないのでご注意ください。
また、二次相続により疎遠な親族が相続人に加わることも珍しくないので、早めに調査を進め遺産分割協議を進めていくことが大切です。
遺産分割協議書はそれぞれの相続で作成する
数次相続が発生した場合、被相続人ごとに遺産分割協議書を作成することをおすすめします。法律では、数次相続の遺産分割協議書を1枚でまとめて作成しても問題ないとはされています。
しかし、後々のトラブルを避け、相続手続き時の混乱を防ぐためにも、一次相続と二次相続で遺産分割協議書を分けて作成するのが良いでしょう。
複数の遺産分割協議書を作成することが難しい場合には、相続に精通した専門家に協議書の作成や相続手続きを依頼することもご検討ください。
相続登記は中間省略登記が認められる場合がある
数次相続が発生すると、不動産の名義変更(相続登記)を複数回行わなければならないように思えます。
しかし、実務上は「中間省略登記」が認められる場合があり、手続きを簡略化できます。数次相続が発生した場合に中間省略登記が認められるケースは、主に以下の通りです。
- 中間の相続人が1人だけのケース
- 中間の相続人が複数人いるがそのうちの1人だけが相続するケース
中間省略登記できるか判断できない場合や、相続登記を自分でするのが不安な場合には、相続登記について司法書士に依頼することをおすすめします。
数次相続が発生したときの注意点
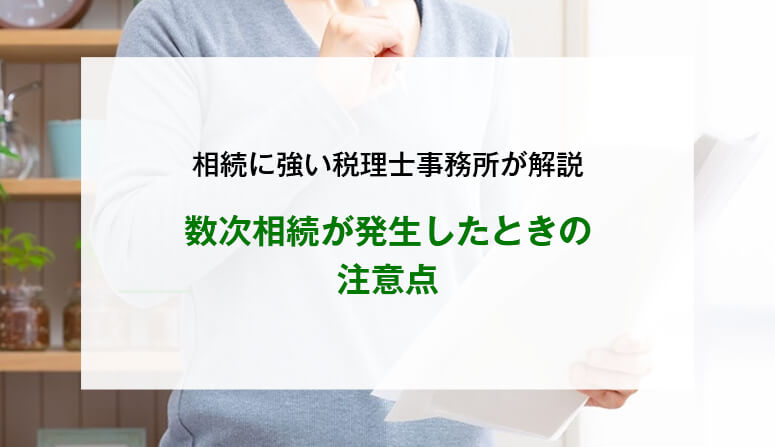
数次相続は相続関係が複雑になるだけでなく、税務上・法律上の取り扱いにも注意が必要です。具体的には、以下のような点に注意しましょう。
- 二次相続の相続人は相続税申告・納付義務を受け継ぐ
- 一次相続の相続税の申告期限が延長される
- 一次相続の相続税の基礎控除が増えることはない
- 相次相続控除を受けられる場合がある
- 相続トラブルが起きる場合がある
それぞれ詳しく解説していきます。
二次相続の相続人は相続税申告・納付義務を受け継ぐ
数次相続が起きると、一次相続の相続人が死亡した時点で、その相続人に課されていた相続税の申告・納付義務は、二次相続人が引き継ぐことになります。
例えば、父の相続税を母が申告・納付する前に母が亡くなった場合、母の相続人である子供が父の相続税の申告・納付義務を負うのです。
一次相続の相続税の申告期限が延長される場合がある
相続税の申告期限は原則として相続開始から10ヶ月以内です。
しかし、一次相続の申告期限内に相続人が死亡して数次相続が発生した場合には、二次相続の相続人が一次相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の期限が延長されます
ただし、延長が認められるのは、一次相続と二次相続の両方の相続人となる人物のみが対象となるためご注意ください。
一次相続の相続税の基礎控除が増えることはない
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
数次相続が発生すると相続人が増えることがありますが、一次相続の基礎控除の計算は「相続開始時点の相続人の数」で確定します。
したがって、二次相続の発生により、後から一次相続の相続人が増えても、一次相続の基礎控除額が増えることはありません。
相次相続控除を受けられる場合がある
数次相続では、相次相続控除を活用できる場合があります。相次相続控除とは、10年以内に同じ財産について相続が連続して発生したとき、二重課税を調整するために相続税額の一部を控除できる制度です。
例えば、父の遺産を相続した母が数年後に亡くなり、子供が母から相続するケースでは、父の相続税と母の相続税が重なる可能性があります。
この場合、母の相続税の計算において相次相続控除を適用することで、税負担の軽減が可能です。
ただし、相次相続控除の計算は非常に複雑なので、相続に精通した税理士に相談して計算してもらうことをおすすめします。
相続トラブルが起きる場合がある
数次相続では、遺産分割協議に関与する相続人の範囲が拡大するため、トラブルに発展しやすくなります。
特に、一次相続人の配偶者や子供といった二次相続人が加わることで、利害関係が複雑化します。
例えば、父の相続において、母が財産を取得する前に亡くなった場合、母の兄弟姉妹などが母の相続人として父の遺産分割に関与することもあり得ます。
このような場合、血縁関係の薄い相続人が加わることで協議がまとまりにくくなることがあるのでご注意ください。
トラブルを回避したい場合には、相続に精通した専門家に相談するのもおすすめです。
数次相続の相続税申告は
当サポートセンターにお任せください

数次相続では、相続人の範囲が広がり、相続税の計算も複雑になります。また、数次相続が発生したタイミングでは、相次相続控除を適用できる可能性があるので、相続税に精通した税理士に相談してミスなく申告をしてもらうことを強くおすすめします。
数次相続の相続税申告を税理士に依頼した場合には、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
数次相続は相続人が増えやすく、申告期限や相続税控除の扱いも通常と異なる場合があるため、慎重に相続手続きをしなければなりません。
具体的には、相続財産調査や相続人調査を念入りに進め、漏れがないように手続きを進めていく必要があります。
特に、相続税申告については、相続税の申告期限の延長や相次相続控除の活用などの点で複雑となるので、相続に詳しい税理士に相談するのが良いでしょう。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ