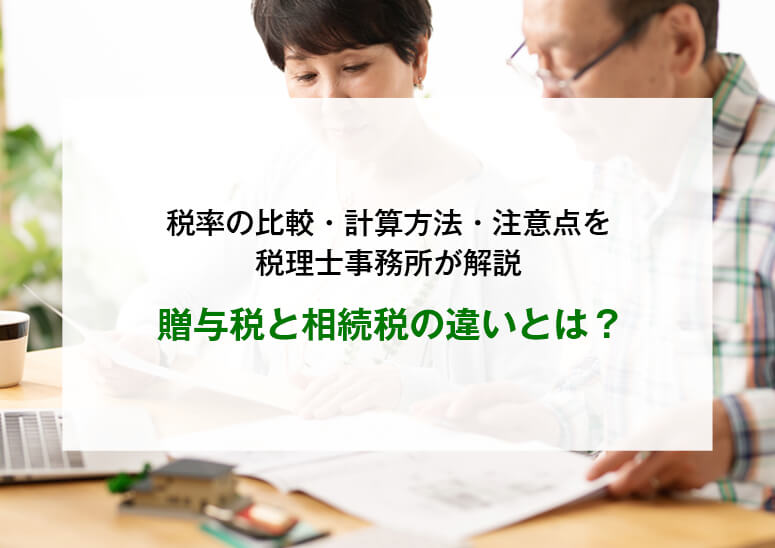
贈与税と相続税の違いとは?税率の比較・計算方法・注意点を税理士事務所が解説
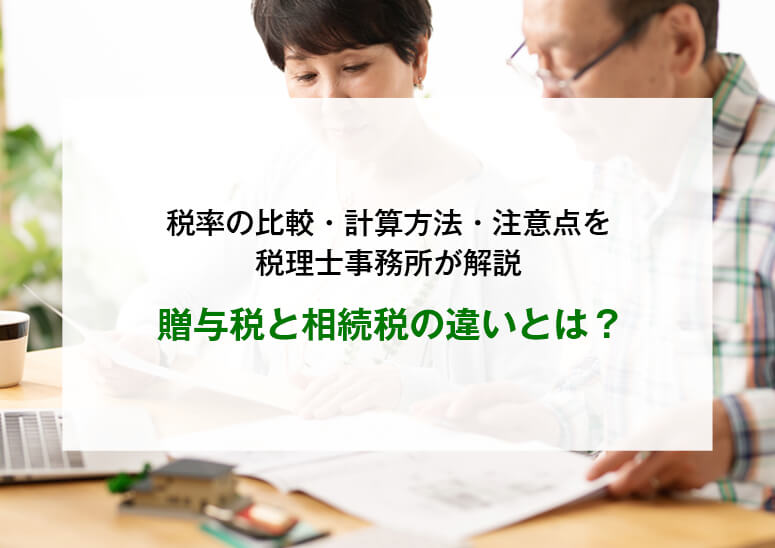
生前贈与と相続は、いずれも大切な財産を家族へ引き継ぐ手段ですが、それぞれに適したタイミングや状況があります。贈与税と相続税は、税率や課税対象の範囲、申告・納税義務者などに違いがあります。
生前贈与と相続どちらを選択すべきかを悩んだ場合は、税理士に相談するのも良いでしょう。
本記事では、生前贈与と相続の基本的な違いと、それぞれが向いているケースについてわかりやすく解説します。
目次
贈与税と相続税の4つの違い
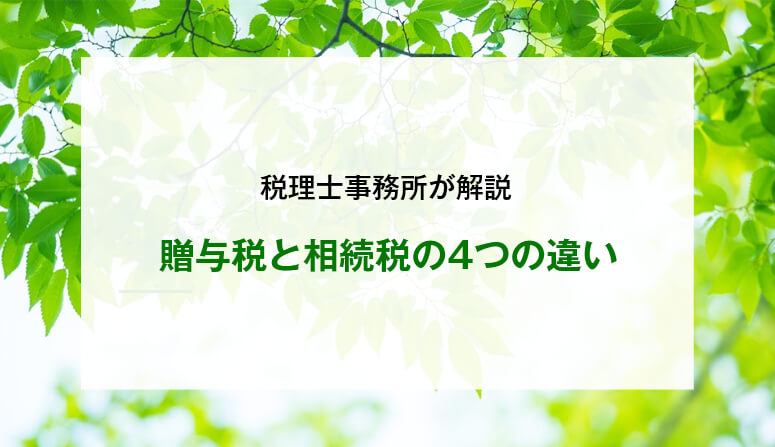
贈与税と相続税は、どちらも財産を譲り受けた際に発生する税金ですが、課税の仕組みや対象、手続きの流れには大きな違いがあります。
主な違いは、下記の通りです。
- 税率
- 課税対象の範囲
- 申告・納税義務者
- 申告・納税時期
税率
贈与税と相続税では、まず税率の仕組みに違いがあります。贈与税は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があります。
「暦年課税」は、1年間に受けた贈与額に応じて課税される制度で、「相続時精算課税」は一定額までの贈与を将来の相続時にまとめて精算する制度です。
暦年贈与の税率は下記の通りです。
一般贈与税率
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
特例贈与税率
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
特例贈与税率は、親や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子供や孫などの直系卑属に行われた贈与に対して適用される税率です。
一方、相続税の税率は、下記の通りです。
相続税の税率
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
関連サイト国税庁「No.4155相続税の税率」
課税対象の範囲
贈与税と相続税では、課税対象となる財産の範囲も異なります。
贈与税は、生前に贈与された財産が対象となる一方で、相続税は、被相続人が死亡時に保有していた財産のほか、死亡前3年以内に相続人に贈与された財産、生命保険金、死亡退職金なども含まれます。
また、国内に住所がある相続人の場合は、海外財産も原則課税対象になります。
申告・納税義務者
贈与税と相続税では、納税義務者が異なります。贈与税は、贈与を受けた受贈者が申告・納税を行います。例えば、親から子供に財産を贈与した場合、子供が贈与税の申告をすることになります。
関連サイト国税庁「贈与税の申告等」
これに対して、相続税は、相続または遺贈によって財産を受け取った各相続人が、それぞれの取得額に応じて申告・納税する義務があります。相続人の人数や取得割合に応じて税額が変わるため、相続人ごとの申告が必要です。
関連サイト国税庁「No.4205相続税の申告と納税」
申告・納税時期
贈与税と相続税では、申告・納税の期限にも違いがあります。贈与税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告・納税を行う必要があります。
関連サイト国税庁「No.4429贈与税の申告と納税」
一方、相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税を行わなければなりません。
どちらの申告も、期限を過ぎると、延滞税や加算税の対象となる場合があるため注意しましょう。
贈与税を計算する流れ
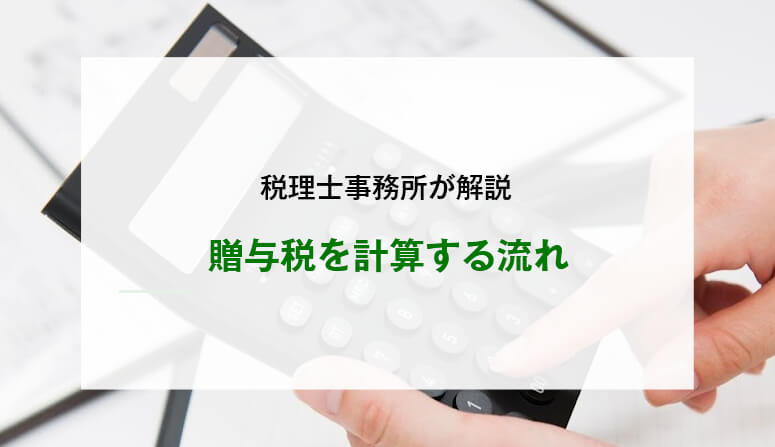
贈与税は、生前に個人から財産をもらった場合に発生する税金であり、計算する流れは、下記の通りです。
- 贈与財産を計算する
- 基礎控除を引き課税対象額を計算する
- 贈与税率を掛けて税額を計算する
それぞれ詳しく解説していきます。
贈与財産を計算する
まずは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額を把握します。贈与税の課税対象となるのは、下記などのように様々なものがあります。
- 預貯金・現金
- 不動産
- 株式
基礎控除を引き課税対象額を計算する
贈与税には、年110万円の「基礎控除」が設けられているため、贈与財産から基礎控除を引き、課税対象額を計算しましょう。
例えば、1年間で父親から50万円、母親から70万円の合計120万円の贈与を受けた場合、合計金額から110万円の基礎控除を引いた「10万円」が課税対象となります。
贈与税率を掛ける
課税対象額が確定したら、最後に税率をかけて税額を計算します。暦年贈与を適用する場合、贈与税の税率には(1)一般贈与税率と(2)特例贈与税率があります。
特例贈与税率は、18歳以上の子供や孫など、直系尊属から贈与を受けた場合に適用される税率です。例えば、先ほどの例であれば受贈者である子供が18歳以上であれば、特例贈与税率が適用され「10万円×10%=1万円」が贈与税として課税されます。
相続税を計算する流れ
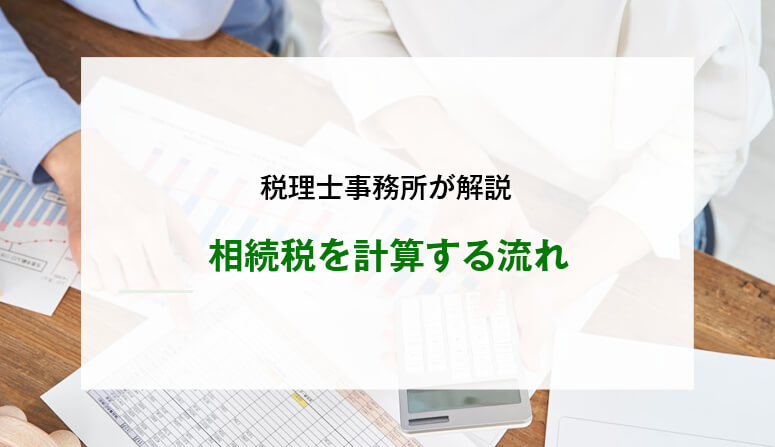
相続税は、被相続人の財産を相続したときに発生する税金であり、計算の流れは下記の通りです。
- 遺産総額を計算する
- 基礎控除を引き課税対象額を計算する
- 相続税率を掛ける
- 加算や減算を行う
それぞれ詳しく解説していきます。
遺産総額を計算する
まずは、相続の対象となる財産の総額を算出します。相続財産には、下記などの財産が含まれます。
- 預貯金
- 有価証券
- 不動産(自宅・土地など)
- 自動車
- 貴金属
- 被相続人名義の貸付金や未収金
- 生命保険金や死亡退職金
- 借金や葬式費用などの債務(債務控除として遺産から差し引くことができる)
基礎控除を引き課税対象額を計算する
遺産総額が出たら、次に「基礎控除額」を差し引きます。相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算可能です。
例えば、配偶者と子供2人が法定相続人の場合、基礎控除は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。この基礎控除を遺産総額から引いた残額が、課税対象額になります。
相続税率を掛ける
課税対象額が確定したら、相続税率を掛けて税額を求めます。ただし、相続税は「法定相続分課税方式」を取っており、まず遺産を法定相続分に分けたうえで仮の相続税額を計算し、最終的に相続人ごとに按分するという流れなのでご注意ください。
法定相続人が誰か判断することや、それぞれの法定相続分を計算することが難しい場合には、相続に精通した税理士に相談することをおすすめします。
加算や減算を行う
最後に、実際の相続税額を算出するために相続人ごとの加算・減算を行いましょう。例えば、被相続人の配偶者や子供、両親以外が遺産を受け取った場合、相続税は2割加算されます。
生前贈与と相続はどちらがおすすめ?
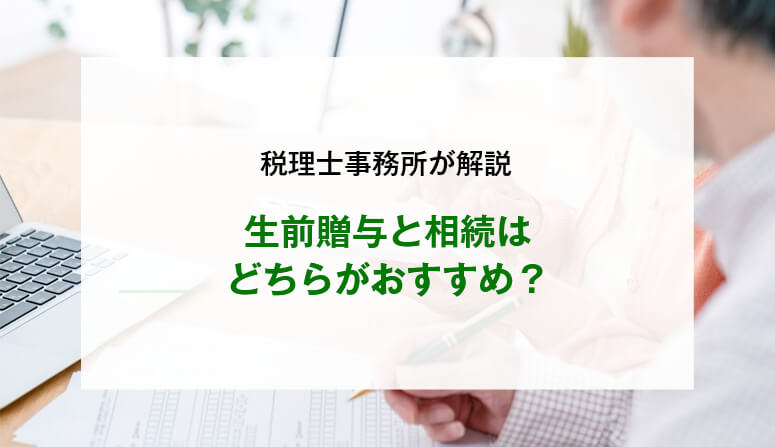
資産承継を考える際、「生前贈与」と「相続」のどちらを選ぶべきかどうかは、多くの方が悩むポイントではないでしょうか。
本記事で解説してきたように、贈与税と相続税にはいくつかの違いがあります。本章では、生前贈与と相続それぞれおすすめできる方の特徴を解説していきます。
生前贈与がおすすめなケース
生前贈与は、生きている間に財産を贈る方法であり、下記のような方におすすめできます。
- 自分が希望する人物に確実に資産を譲りたい場合
- できるだけ早いタイミングで贈与をしたい場合
- 将来値上がりしそうな財産を譲りたい場合
- 贈与税の控除・特例を利用したい場合
相続がおすすめなケース
贈与税と相続税の税率を単純に比較した場合、相続税の方が低い税率が適用されます。そのため、下記に該当する方は生前贈与ではなく相続による資産承継を検討しましょう。
- 配偶者控除や小規模宅地等の特例など相続税の控除・特例を適用したい場合
- 自分の老後資金を確保しておきたい場合
- 家族・親族の関係が良好であり、相続トラブルは起きなさそうな場合
- 子供や孫、配偶者などがいない場合
- 遺産総額が相続税の基礎控除内に収まる場合
相続税対策は
杉並・中野サポートセンターにお任せください

生前贈与と相続のどちらの方法で資産承継を行うべきかについては、ケースバイケースです。そのため、自分で判断することが難しい場合には、相続や贈与に精通した税理士に相談することを強くおすすめします。
相続税対策や生前贈与すべきかの判断は、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは、弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続税対策をワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
生前贈与は、計画的な相続税対策や資産承継として適している一方で、贈与税がかかる可能性があります。
贈与税率と相続税率を単純に比較した場合、贈与税の方が税率は高いため、本当に生前贈与すべきか慎重に判断しなければなりません。
どちらが適しているかは家庭ごとの事情や資産状況によって異なるため、早めに方針を立て、必要に応じて専門家の助言を得ることが安心につながるでしょう。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ