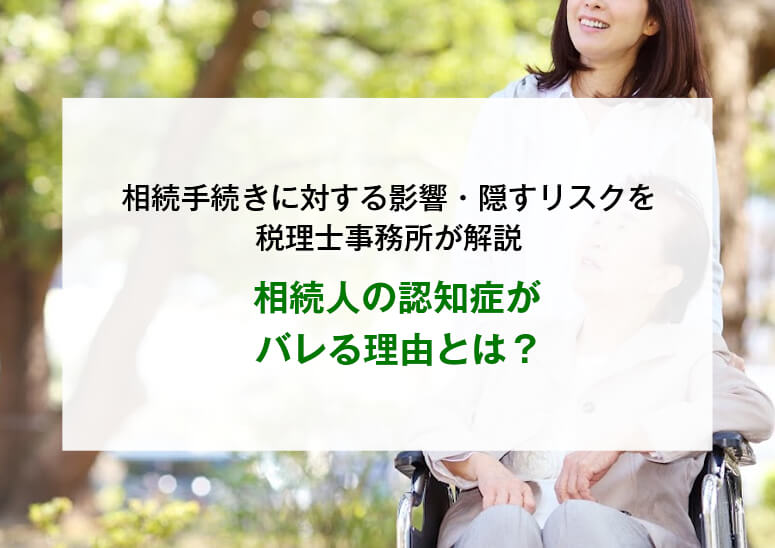
相続人の認知症がバレる理由とは?相続手続きに対する影響・隠すリスクを解説
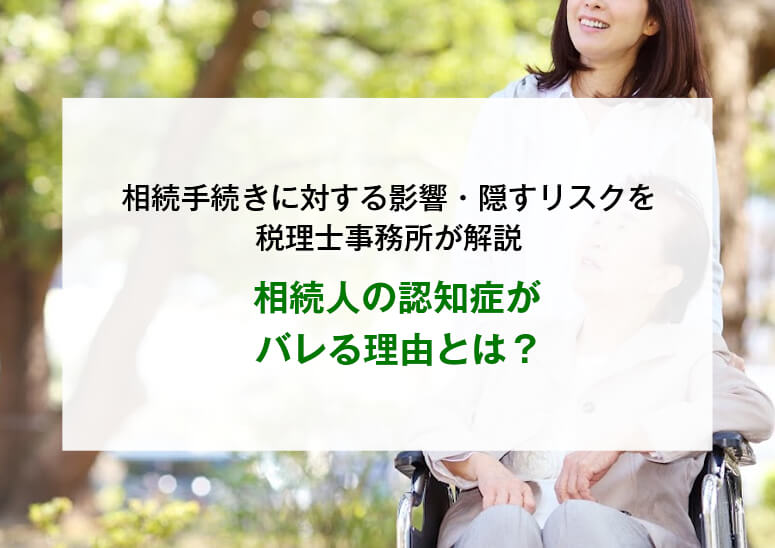
相続人の1人が認知症の場合、相続手続きを進めることができなくなってしまいます。
認知症の人は判断能力が失われており、遺産分割協議への参加や遺産の名義変更手続き、相続放棄の手続きなどを行えないからです。
「相続人が認知症であることを隠して手続きを進めよう」と考えるかもしれませんが、遺産分割協議や遺産の名義変更手続きの際にバレてしまう可能性が高いのでご注意ください。
本記事では、相続人の1人が認知症だとバレてしまう理由・タイミングや認知症の相続人がいるとどうなるかを解説します。
目次
相続人が認知症だと
バレる理由・タイミング

認知症の相続人がいる場合、隠して相続手続きを進めることは難しく、下記のタイミングでバレやすいのでご注意ください。
- 遺産分割協議時にバレる
- 遺産の名義変更手続き時にバレる
- 相続手続き完了後にバレる
それぞれ詳しく紹介していきます。
遺産分割協議時にバレる
遺産分割協議の際に、相続人の1人が認知症であることが判明するケースは多いです。
具体的には、下記のシーンで認知症の症状が出ていることや判断能力が失われていることがバレてしまいやすいです。
- 本人が意思を表明できない
- 他の相続人が医師の診断書を確認してしまう
- 遺産分割協議をしても話し合いが成立しない
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要なため、認知症によって判断能力が欠けている場合、その相続人は自分の意思を示すことができません。
相続人の1人が認知症であることを隠して遺産分割協議書を作成してしまうと、有印私文書偽造の罪に問われる可能性もありますし、遺産分割協議書が無効になってしまいます。
遺産の名義変更手続き時にバレる
遺産分割協議が終わった後、遺産の名義変更手続き中に認知症がバレてしまう場合もあります。
遺産の名義変更や登記手続きは、金融機関や法務局などで手続きを行う必要があるため、担当者とのやり取りで認知症であるとバレる可能性があります。
相続手続き完了後にバレる
相続手続きが完了してから、相続人が認知症だったことが発覚し、遺産分割協議時の判断能力が問題になるケースもあります。
かかりつけ医の記録やカルテ、認知症の診断書などが見つかると、遺産分割協議時も判断能力がなかったことが証明され、協議そのものが無効になってしまう恐れもあるのでご注意ください。
認知症の相続人がいると
相続手続きを進められない
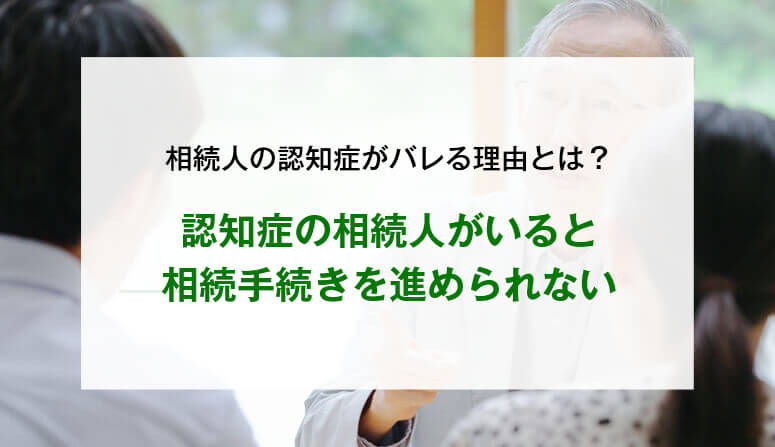
被相続人が遺言書を用意していない場合、相続人全員で遺産分割協議などの手続きを行わなければなりません。
そして、相続人の中に1人でも認知症の人がいると、遺産分割協議が完了せず他の相続人も遺産を受け取れなくなってしまいます。
相続人の1人が認知症だと、どんな問題が起きるのか詳しく見ていきましょう。
認知症の相続人は遺産分割協議に参加できない
認知症になった相続人は、遺産分割協議に参加できないため、いつまでも話し合いがまとまらなくなってしまいます。
遺産分割協議とは、誰が遺産を受け継ぐかについて話し合うもので、相続人全員が参加し合意しなければ成立しません。
認知症の相続人がいる場合、成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加する必要があります。
認知症の相続人は相続放棄・限定承認を行えない
認知症になった相続人は、相続放棄や限定承認の申立ても行うことができません。相続放棄や限定承認を行う際には、本人の意思表示が必要とされているからです。
認知症の相続人の場合、意思表示ができないため相続放棄や限定承認を行えず、いつまでも手続きを進められなくなってしまいます。
特に、限定承認は相続人全員で手続きする必要があるため、認知症の相続人がいると他の相続人への影響も大きくなってしまいます。
認知症の相続人がいると残りの相続人も遺産を受け取れない
認知症の相続人がいる場合、その相続人が遺産を受け取れないだけでなく、残りの相続人も遺産を受け取ることができない恐れがあります。
先ほど解説したように、遺産分割協議は相続人全員が参加しなければならないからです。そして、遺産分割協議が完了しないと、遺産の名義変更手続きを行うこともできません。
結果として、いつまでも遺産を受け取れない、遺産を受け取るのに数ヶ月から1年以上かかってしまう恐れもあります。
相続人が認知症の場合の対処法
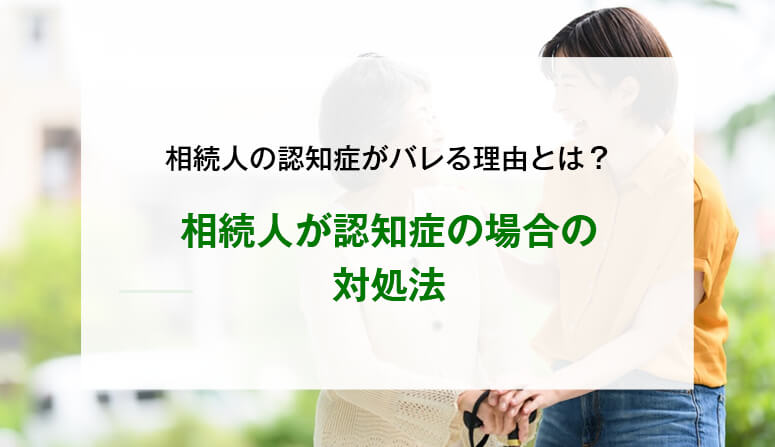
相続人の中に認知症の人がいる場合、成年後見人や特別代理人を選任し、代わりに遺産分割協議への参加や相続手続きを進めてもらう必要があります。
それぞれの制度について、詳しく解説していきます。
成年後見制度を活用する
認知症になった相続人がいて遺産分割協議に参加できない場合、成年後見制度を活用しなければなりません。
成年後見制度とは、認知症などで意思能力を失った人に代わって法的な意思決定を行う制度です。利用するには、家庭裁判所に申立てを行い成年後見人を選任してもらう必要があります。
成年後見人として選ばれた人物は、認知症の相続人の代わりに遺産分割協議への参加や遺産の受け取り、管理などを行います。
なお、成年後見人は被後見人(認知症の相続人)の利益を最優先にすると決められているため、場合によっては遺産分割協議がまとまらず手続きが難航する恐れもあるのでご注意ください。
特別代理人を選任する
認知症の相続人がすでに成年後見制度を利用しているものの成年後見人も相続人となっているケースでは、相続人間で利益相反が生まれるため特別代理人を選ばなければなりません。
例えば、下記のケースでは特別代理人の選任が必要です。
具体例
- 父親が亡くなり相続が発生した
- 相続人は母親および長男、次男
- 母親は相続発生前から認知症であり、長男が成年後見人となっている
上記のケースでは、長男が相続人でありながら母親の成年後見人としての地位にもついており、利益相反となってしまいます。
長男が自分に有利な行動をすることを防ぐために、特別代理人を選任し母親の代わりに遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
特別代理人になれる人物に決まりはなく、利益相反とならなければ問題ありません。頼れる親族や知人、司法書士や弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。
特別代理人の選任も家庭裁判所にて手続きが必要です。手続きには数ヶ月から半年以上かかることも多いので、相続発生後はできるだけ早く申立ての準備をすると良いでしょう。
高齢の相続人がいるときの対処法
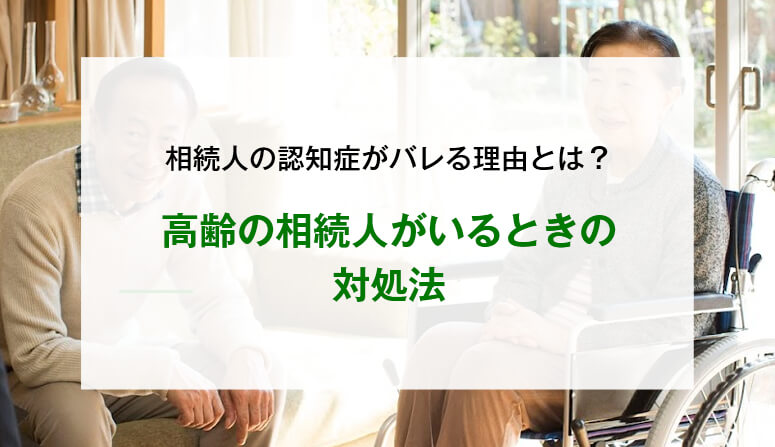
相続人になるであろう人物が高齢の場合や最近物忘れが激しくなってきたなど認知症症状が見られる場合は、遺言書の作成など相続対策をしておくと安心です。
遺言書を用意しておけば、遺言内容通りに遺産分割が行われるため、遺産分割協議を行う必要がないからです。
したがって、認知症の相続人がいたとしても成年後見制度を利用する必要もなくなりますし、残りの相続人もスムーズに遺産を受け取れます。
相続手続きは
当サポートセンターにお任せください

認知症の相続人がいると、その人だけでなく残りの相続人も手続きを進められず遺産を受け取るのに時間がかかってしまう恐れがあります。
また、相続税の申告・納税期限は相続開始から10ヶ月以内とされており、認知症の相続人がいても期限が延長されることはありません。
遺産の名義変更手続きを速やかに完了させ、相続税の納税資金を用意するには、成年後見人や特別代理人選任の準備を進める必要があります。
また、まだ相続が発生していないものの、相続人が認知症であることがわかっている場合は、遺言書の作成など相続対策をしておくのが良いでしょう。
相続対策は「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
相続人に認知症の人がいると、残りの相続人も手続きを進められなくなってしまいます。
認知症であることを隠して手続きしたとしても、遺産分割協議や遺産の名義変更手続き時にバレてしまう可能性が高いのでご注意ください。
また、手続き完了後に相続人が認知症であるとバレた場合、遺産分割協議や手続きが無効になる恐れもあるのでご注意ください。
相続人に認知症の人がいる場合、成年後見人や特別代理人を選任し、代わりに手続きを行ってもらわなければなりません。
選任申立て完了までには数ヶ月以上かかることが多いので、できるだけ早めに準備を始めておきましょう。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ