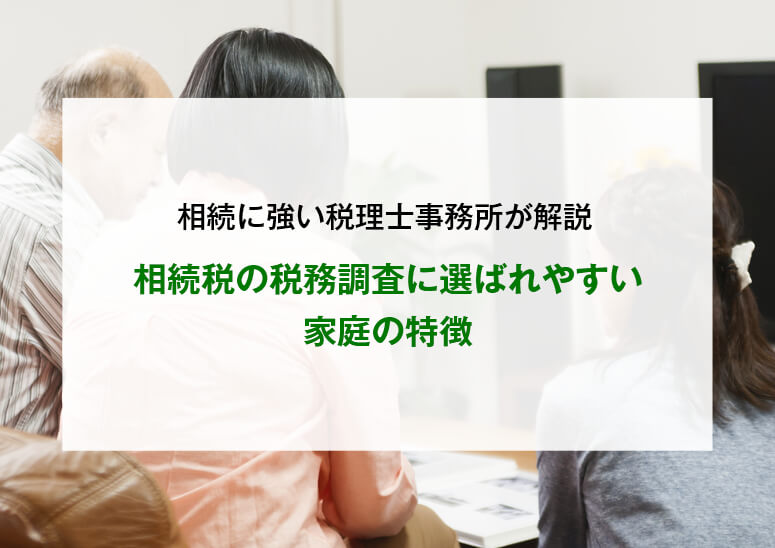
相続税の税務調査に選ばれやすい家庭の特徴を税理士事務所が解説
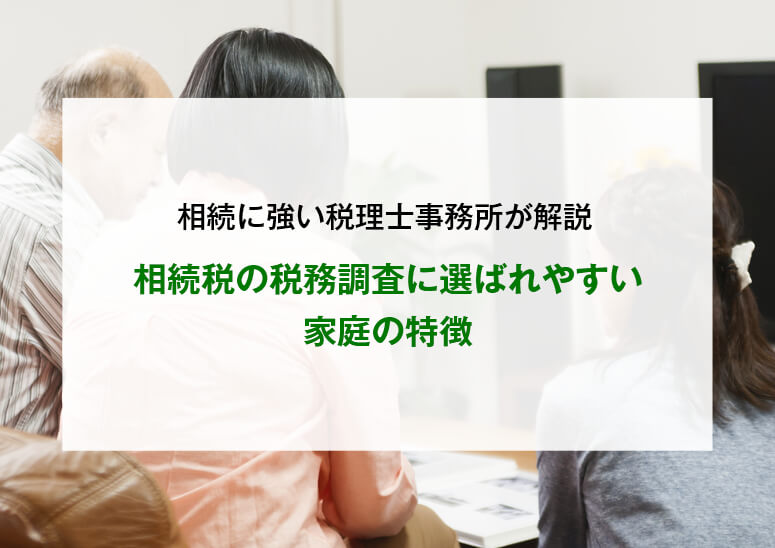
相続税の申告を終えても安心はできず、場合によっては、税務調査が入ることがあります。
国税庁の統計によれば、相続税の申告のうち約1割程度は税務調査の対象となり、多くのケースで申告漏れが指摘されています。
税務署は個人の収入や資産状況、資産の流れを把握しているので、贈与を受けたときや介護費・医療費を立て替えたときには証拠を残しておくことが何より大切です。
本記事では、相続税の税務調査に選ばれやすい家庭の特徴や調査を回避するための準備について詳しく解説します。
目次
相続税の税務調査とは
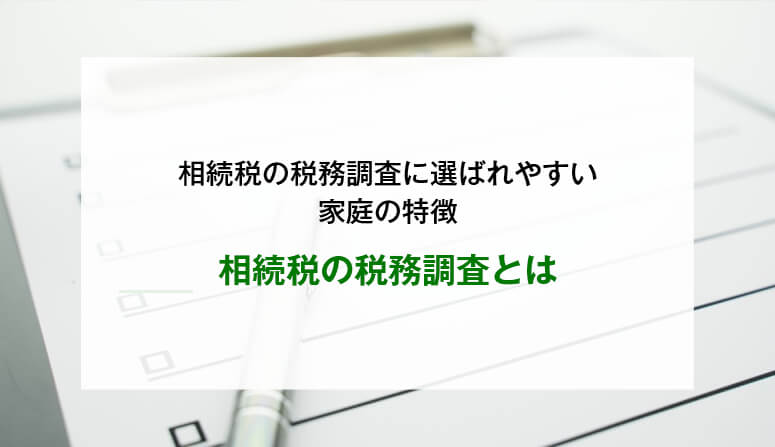
相続税は、申告をした納税者が納税を済ませたとしてもそのすべてがそのまま受理されるわけではなく、税務署による「調査」が行われる場合があります。
税務調査の目的は、申告内容に誤りや申告漏れがないかを確認することです。
特に、相続税は金額が大きくなりやすく、財産の把握が難しいため、税務署も重点的にチェックを行います。
税務調査が行われる割合と件数の実態
国税庁が公表している統計によると、相続税の申告件数のうち、実地調査が行われる割合はおおむね5〜10%程度とされており、近年増加傾向にあります。また、実地調査には及ばないいわゆる「簡易な接触」も増加傾向にあります。
関連サイト国税庁「令和5年事務年度における相続税の調査等の状況」
なお、税務調査が行われた場合、申告漏れを指摘される可能性は非常に高く、実地調査があったうち約8割あまりの案件で申告漏れ等による修正が必要になると言われています。
申告漏れとして多いのは、やはり「現金や預貯金」「名義預金」「土地の評価誤り」など、相続人が見落としやすい財産や判断が難しい財産です。
相続税の税務調査に選ばれやすい家庭の
5つの特徴
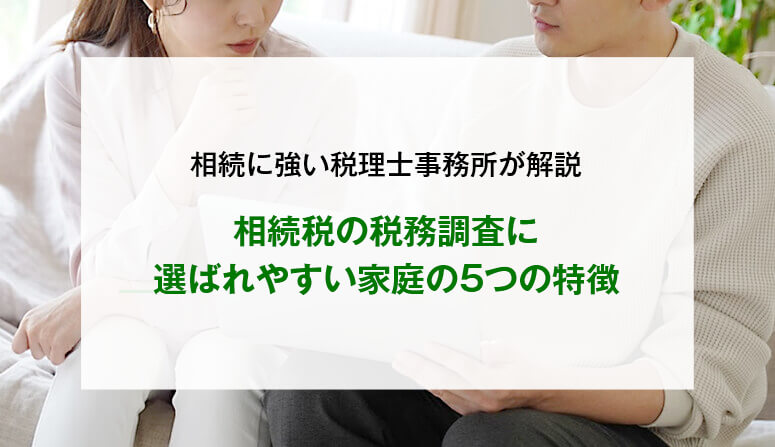
相続税の税務調査は、すべての家庭に行われるわけではなく、対象となるのは申告内容に不自然さや不明確な点があるケースが中心です。
税務署は、被相続人の財産や生活状況、過去の税務情報などを分析し、リスクが高いと判断した家庭に重点的に調査を行います。
具体的には、以下のようなケースでは税務調査の対象として選ばれやすいのでご注意ください。
- 現金や預貯金が多くタンス預金の可能性がある家庭
- 被相続人の生前出金が多く使途不明金がある家庭
- 生前贈与を繰り返していたが贈与契約書などの証拠がない家庭
- 不動産の評価額が実勢価格に比べて著しく低い家庭
- 生命保険金・名義預金・貸金庫などの扱いが曖昧な家庭
それぞれ詳しく解説していきます。
現金や預貯金が多くタンス預金の可能性がある家庭
現金や預貯金の比率が高い家庭は、税務調査に選ばれやすい傾向があります。特に「タンス預金」と呼ばれる自宅での現金保管が疑われるケースは要注意です。
被相続人が高齢で現金主義だった場合や、口座に多額の引き出しがあるのに使途が説明できない場合、調査官から「隠された現金があるのでは」と疑われる可能性が高くなります。
現金は不動産や株式と違って足跡が残りにくいため、申告漏れの典型的な対象とされているのです。
被相続人の生前出金が多く使途不明金がある家庭
被相続人の口座から生前に多額の現金が引き出されているにもかかわらず、その使い道が明確でない場合も、税務調査の対象となりやすいポイントです。
例えば、介護や生活費として引き出されたと説明しても、領収書や記録が残っていなければ、相続人が引き出して預かっている「名義預金」とみなされる可能性があります。
特に相続開始前の数年間の大きな出金は、重点的に調査される傾向があるため、記録を残しておくことが重要です。
生前贈与を繰り返していたが贈与契約書などの証拠がない家庭
相続税対策として生前贈与を活用する家庭も多いですが、贈与契約書や振込記録といった証拠がない場合、調査で指摘を受けやすくなります。
特に「毎年110万円の基礎控除枠を利用したつもり」の贈与は、契約書や受贈者による管理がないと税務署に過去の贈与を否認される恐れがあります。
贈与を継続的に行う際は、必ず契約書を作成し、受贈者本人が管理・使用していることを明確にしておくことが大切です。
不動産の評価額が実勢価格に比べて著しく低い家庭
不動産は評価方法が複雑で、相続税評価額と市場価格(実勢価格)が大きく乖離することがあります。
例えば、市街地にある土地を「貸家建付地」として評価し大幅に減額している場合や、路線価を基にした評価額が実勢価格より極端に低い場合、税務署は「過少申告の可能性がある」と疑います。
不動産の評価は専門家でも判断が難しいため、申告時に適正な評価方法を採用していないと、調査対象となるリスクが高まるのでご注意ください。
生命保険金・名義預金・貸金庫などの扱いが曖昧な家庭
生命保険金や名義預金、貸金庫の中身といった「見落とされやすい財産」の取扱いが不明確な家庭も、税務署が注目するポイントのひとつです。
例えば、生命保険金は受取人が誰であるかによって課税関係が変わりますし、名義預金は形式的に子供孫の名義であっても、実際の管理者が被相続人であれば相続財産に含まれます。
また、貸金庫に何が保管されているかを申告で明示していないと、調査時に「隠し財産」と疑われることもあります。
いくら以上で税務調査に入るの?
金額の目安はある?
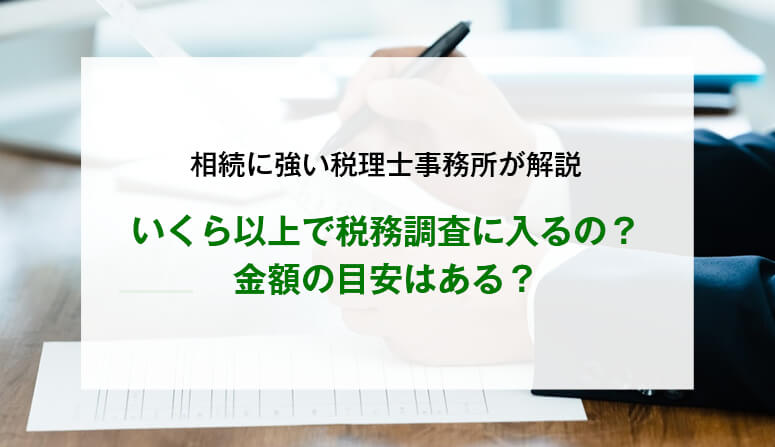
相続税の税務調査について「相続財産がいくら以上なら調査に入られるのか」というご相談を受けることは少なくありません。
しかし実際のところ、税務署が調査対象を決める際に「金額のライン」が明確に定められているわけではありません。
確かに、相続財産の総額が高額であるほど調査対象になりやすい傾向はありますが、それだけで一律に判断されるわけではなく、財産の種類や申告内容の整合性、不明点の有無など、さまざまな要素が加味されます。
税務署が注目しやすい相続財産
税務調査において、税務署が特に注目する財産にはいくつかの典型的なものがあります。これらは申告漏れが発生しやすく、また相続人が誤解しやすい性質を持っているため、重点的に確認されるのです。
税務署が注目しやすい財産は、主に以下の通りです。
| 現金・預貯金 | 被相続人の生前の口座からの出金履歴は入念にチェックされる |
|---|---|
| 不動産 | 実勢価格と申告した相続税評価額との乖離が大きいとチェックされやすい |
| 生命保険金 | 形式的な名義人のみでなく、保険料を負担していたのは実質誰だったかまで確認される |
| 貸金庫の中身やゴルフ会員権、美術品 | 相続人が相続税の課税対象と認識していない場合もあるため、入念に調査される |
相続税の税務調査で指摘されやすい
ミス・申告漏れ
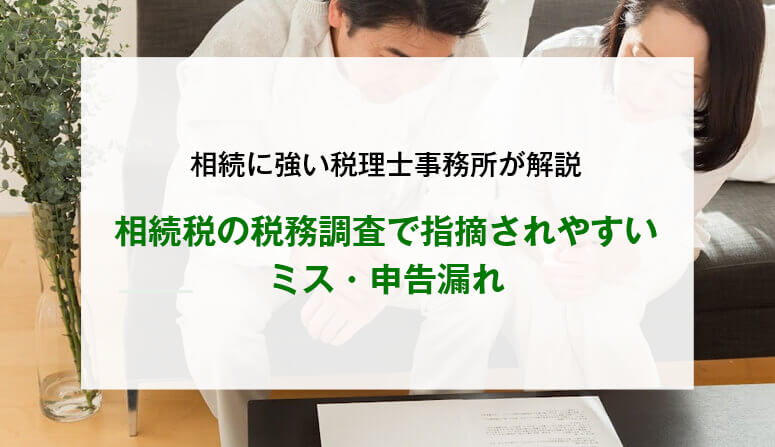
相続税の税務調査では、意図的に隠した財産だけでなく、「相続人が知らず知らずのうちに見落としていた」ミスや不備も数多く指摘されます。
以下のようなミスや申告漏れには特に注意しておきましょう。
- 名義預金を「贈与」と勘違いしていた
- 評価額の計算ミス・計算根拠の不備
- 贈与契約書の未作成・日付不備
- 税理士に依頼せず自分で作成した申告書の不備
- 書類添付の漏れや説明資料の不足
名義預金とは、口座名義人とその口座を管理していた人物が異なる預金であり、子供や孫の名義で預金口座を作り、被相続人が資金を移していた場合などが該当します。
「毎年110万円の贈与をしたつもり」であっても、贈与契約書がなかったり、通帳や印鑑を被相続人が管理していたりすれば、名義預金とされ税務調査で否認される可能性が高いので注意しましょう。
他にも、相続財産の内容によっては個別に相続税評価額の算出が必要なものもあります。相続税評価額の計算時には専門的な知識や経験が求められるため、自分で相続税申告をしていると税務調査で指摘を受けやすい傾向があります。
税務調査を回避・対策するために
家庭でできる準備
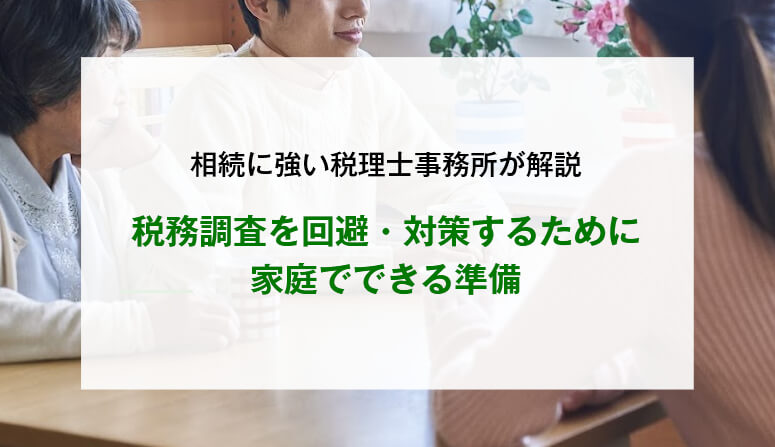
相続税の税務調査のリスクを少しでも軽減したいのであれば、以下のような準備をしておきましょう。
- 相続発生前の生前贈与の記録を残す
- 通帳・領収書などの資金の流れを可視化する
- 贈与契約書・生命保険の控えを整理しておく
- 家族間の現金の移動には必ず証拠を残す
それぞれ詳しく解説していきます。
相続発生前の生前贈与の記録を残す
相続税の対策として生前贈与を行う家庭は多いですが、税務署から見れば「贈与か、それとも名義預金か」は厳しくチェックする対象となります。
税務署から調査されたときに備えて、贈与契約書を必ず作成し、受贈者本人が管理・使用していることを明確にしておきましょう。
通帳・領収書などの資金の流れを可視化する
税務調査では被相続人の口座からの出入金記録も細かく確認されます。相続開始前の数年間に多額の出金があると、「その資金はどこへ行ったのか」と疑われてしまいます。
介護費用や医療費に充てたとしても、領収書や請求書を残していなければ、相続人が預かっている「隠し財産」と見なされる可能性もあるのでご注意ください。
このような事態を防ぐためにも、日頃から通帳のコピーや出金に関する領収書を保管しておくことが大切です。
贈与契約書・生命保険の控えを整理しておく
贈与契約書や生命保険の契約控えは、相続税の申告時に非常に重要な資料となるので、大切に保管しておきましょう。
特に、生命保険は、契約者・被保険者・受取人の関係性によって課税関係が異なるため、契約書類をしっかりと整理しておく必要があります。
家族間の現金の移動には必ず証拠を残す
相続税の調査で特に注目されることのひとつが、家族間のお金のやり取りです。
例えば、親が子供の生活費を支援していた場合や、子供が親の医療費を立て替えていた場合などは、実態が「贈与」なのか「預り金」なのかが問題となることもあります。
そのため、家族間で現金を移動させる場合は、できる限り銀行振込を利用し、証拠を残しておきましょう。また、振込明細とあわせて、支払い時の領収書などを残しておくことも大切です。
相続税申告や税務調査対応は
当サポートセンターにお任せください

相続税の税務調査を絶対に回避する方法は、残念ながら存在しません。しかし、相続税申告を税理士に依頼することで、申告ミスも発生しにくくなりますし、税務調査が来る確率自体も下げられます。
相続税申告や税務調査対応は、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
相続税の税務調査は「高額な相続だから必ず入る」というものではなく、申告内容の整合性や証拠の有無が大きく影響します。
現金や預金の出入り、名義預金、生前贈与、不動産評価など、調査官が注目するポイントを把握し、そこで不備や説明不足がないように準備することが大切です。
税務調査を回避するためには、家族同士の資金移動や贈与であっても、証拠や記録を残しておくことが大切です。
また、税務調査をできるだけ回避したいのであれば、自分で相続税申告をするのではなく、税理士に依頼することも検討しましょう。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ