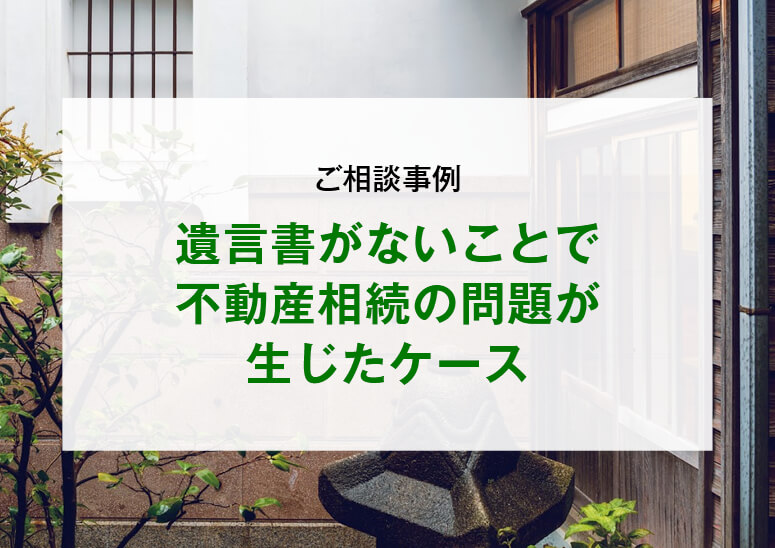
相続税の試算シミュレーション
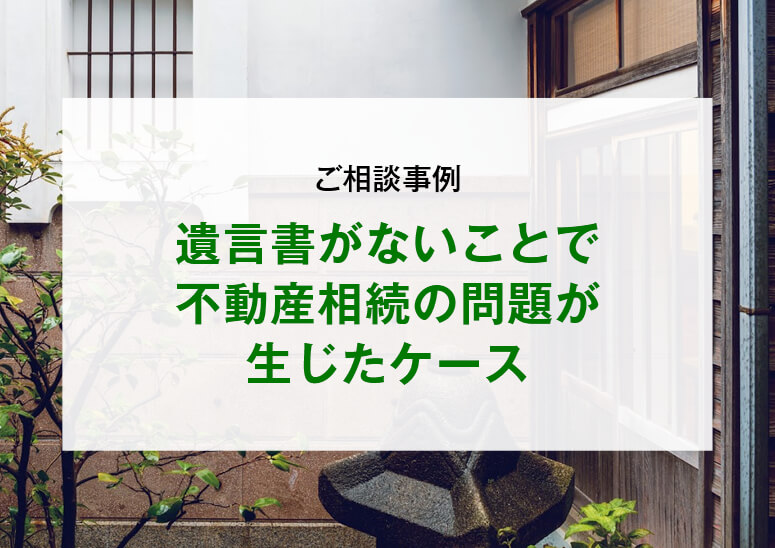
目次
お客様のお悩み

- 被相続人である父の相続財産の総額が分からない
- 相続税申告が必要か否かを教えてほしい
- 妻は高齢で認知症のため、二次相続も検討している
- 争うことなく兄弟で平等に遺産分割をしたい
対象となる財産
- 不動産(土地・建物)
- 預金
- 株式
- 外貨建外債等債券
- 投信
- 現金など
サポート内容

相続財産の総額について下記書類の調査、ご提供をお願いします。これらの書類を基に財産評価を致します。
相続財産の調査評価をします
不動産に関連する書類の確認
不動産が御有りになれば固定資産税の課税明細書をお持ちいただきます。権利書等が御有りになればお持ちいただきます。
預貯金の確認
預貯金などは通帳をお探しいただきます。
株式の確認
株式などは証券会社からの残高取引報告書や株主配当金通知書をご持参いただきます。
生命保険の確認
保険証券などもお持ちいただきます。
遺言書の確認
遺言書が御有りになるかの確認を致します。
相続人と相続内容のヒアリング
どなたが何を相続させるのか聞き取りをさせていただきます。これにより相続税の申告が必要かのアドバイスを致します。
遺産分割協議書の作成
分割がお決まりになれば、遺産分割協議書を作成いたします
相続税・申告書の作成
相続税の申告が必要な場合には申告書の作成を致します
不動産の相続登記
不動産の相続登記をします
銀行預金の解約
銀行預金の解約払い戻しをします
有価証券の名義変更
有価証券の名義変更をします
二次相続時の相続税のシュミレーション
二次相続の場合の相続税のシュミレーションも致します。
遺言書作成サポート
遺言書の作成のお手伝いもいたします。
解決のポイント
土地の評価に関する手続きを検討する
その土地の接道状態や整形、不整形の具合、利用区分や地積によって、大きく評価を下げることができます。また、その不動産をどなたが相続するかによって小規模宅地の特例を適用することができます。
- 特定居住用の土地等ですと面積が330平米まで80%減額できます
- 家業(不動産業を除く)を継ぐ相続人が相続されると400平米まで80%減額できます
- アパート、マンションなど賃貸している土地を相続される場合は200平米まで50%減額できます(但し上記と併用する場合には面積制限があります)
- 利用されている土地が500平米以上の普通住宅地等ですと21%からの減額ができます
このようにどなたが相続をされるのかよって減額ができますので、ご依頼者のご事情を丁寧にヒアリングして適切なアドバイスを致します。
二次相続に関連する手続きを検討する
二次相続では、残された配偶者のご年齢により相続税額を試算し、一次相続の配分をアドバイスいたします。また、納税資金の捻出や納税方法についてもアドバイスいたします。
ご家族のご事情をふまえた手続きを検討する
たとえば、認知症の場合には家族信託をご提言することもあります。
争うことなく御兄弟で平等に遺産分割をされたい場合には、全体の財産を算出して、土地など分けられない場合には他の金融資産や生命保険金があればこれを他の相続人に割り振るあるいは相続人ご自身が金銭の拠出の余力が御なりになれば代償分割という方法もあります。
不動産を兄弟間で共有にされると、後々そのお子様や配偶者が相続され全員の合意がなければ、修理や売却もできません。固定資産税などの維持費もみなさんでご負担しなくてはなりません。将来売却をすることでご了解を得ている場合には共有でもよいかもしれません。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ