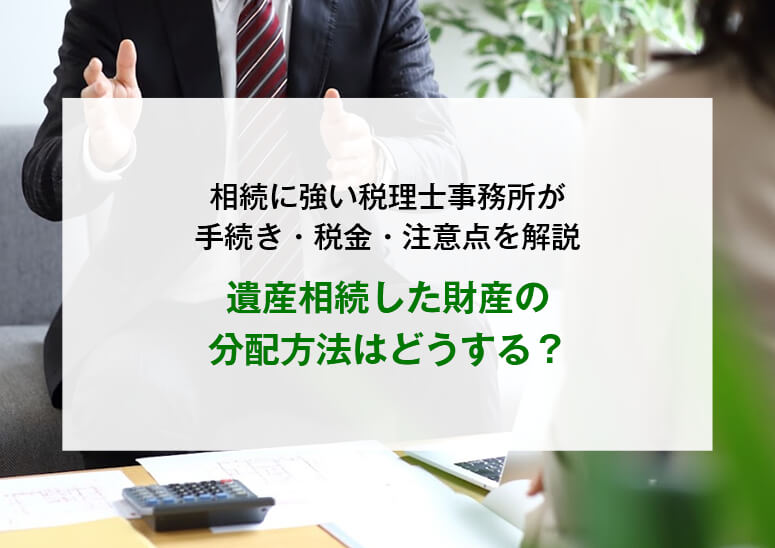
遺産相続した財産の分配方法はどうする?手続き・税金・注意点を解説
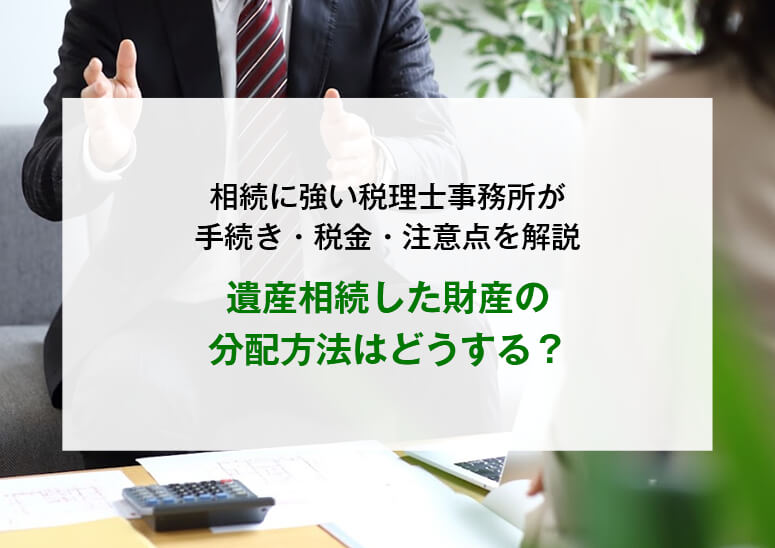
遺産相続は、誰にでも起こりうる身近な問題ですが、実際には「何をどう分ければいいのか分からない」「トラブルになりそうで不安」と感じる方も多いのではないでしょうか。
相続の方法や財産の分け方には、法律で定められたルールがある一方で、柔軟に対応できる部分もあります。
本記事では、遺産相続の基本的な仕組みから、分配方法の種類、協議の進め方、よくあるトラブルや疑問点までを網羅的に解説します。
相続に関する不安を解消し、スムーズな手続きの第一歩を踏み出すための参考にしていただければ幸いです。
目次
遺産相続とは
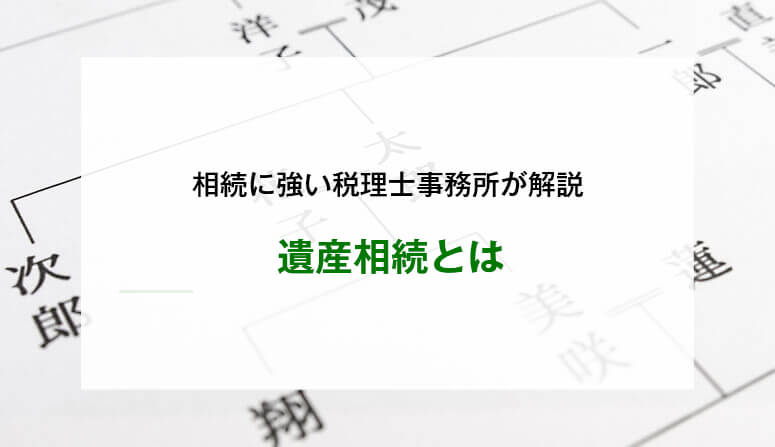
遺産相続とは、被相続人が遺した財産を、残された家族や親族(相続人)が引き継ぐことです。
財産には、現金や預貯金、不動産、有価証券といったプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。
相続財産の分配方法にはいくつかの選択肢があり、相続人の間でトラブルになるケースも少なくありません。円満な相続を行うためには、相続の基本的な仕組みや手続きを理解しておきましょう。
相続財産の分割方法は3種類
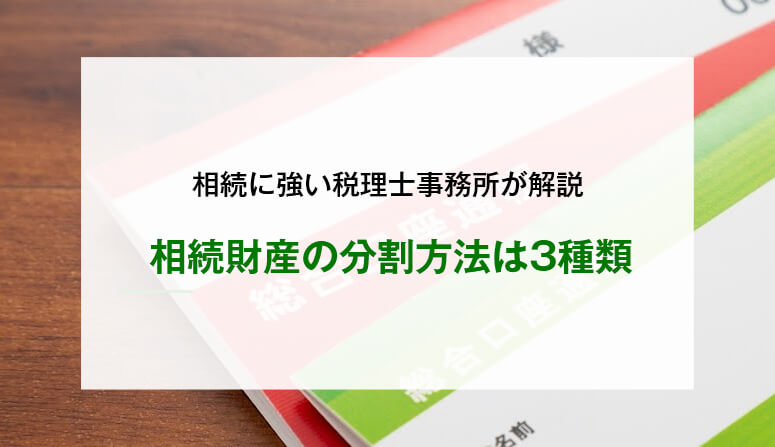
相続財産をどのように分けるかについては、大きく分けて3つの方法があります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
法定相続による分割
法定相続とは、民法で定められた割合に従って相続人が財産を取得する方法です。例えば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、子ども全員で残りの2分の1を均等に分けるのが原則です。
法定相続による分割は、被相続人が遺言を残していない場合や、相続人間で協議が整わない場合に用いられます。
遺言による分割
被相続人が遺言書を作成していた場合、その内容が原則として優先されます。遺言書には、財産を誰にどれだけ分け与えるかを明記することができます。
ただし、遺留分は遺言より優先されるため、遺言の内容によっては、相続人や受遺者同士でトラブルが起きる恐れもあるのでご注意ください。
遺産分割協議による分割
遺産分割協議とは、法定相続人全員が集まり、相続財産の分け方を話し合うことです。
被相続人が遺言書を用意していなかった場合や、相続人全員が遺産分割協議を行うことに合意している場合には、話し合いによって遺産の分割方法を決められます。
遺産分割協議を行えば法定相続分以外の割合で遺産分割を行うことも認められます。例えば「長男が不動産5,000万円を相続し、次男と三男は預貯金3,000万円ずつを相続する」などといった柔軟な対応も可能です。
遺産相続の分配方法は4種類
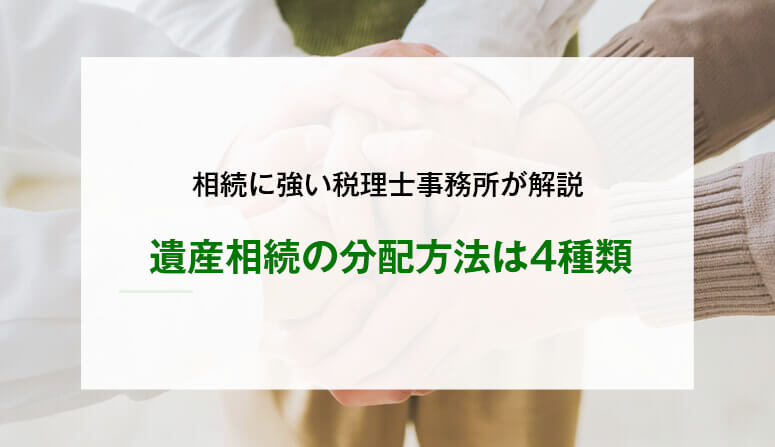
先ほど解説した「遺産分割協議による分割」では、遺産の分け方として4つの分配方法があります。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
- 共有分割
それぞれ詳しく解説していきます。
現物分割
現物分割とは、遺産を現物のまま分け合う方法です。例えば、不動産は長男が相続し、長女が預貯金を相続するといった方法は現物分割に該当します。現物分割は、個別の財産をそのままの形で割り振るため、最もシンプルで費用もかかりません。
一方で、不公平な遺産分割となることもあるため、相続人の1人が納得せず話し合いが長引く恐れもあります・
換価分割
換価分割とは、遺産を一旦売却し、売却代金を相続人で分ける方法です。例えば、実家不動産を売却し、売却代金を子供たちで分けるのは換価分割に該当します。
換価分割は公平に遺産分割できるメリットがありますが、遺産を現金化しなければならないデメリットがあります。
また、相続不動産を売却し利益が発生した場合には、譲渡所得税や住民税がかかるのでご注意ください。
代償分割
代償分割とは、遺産を多く取得した相続人が他の相続人に代償金を支払う方法です。例えば、長男が実家の土地建物を相続し、次男と三男には代償金としてそれぞれ500万円ずつ支払うといった形です。
代償分割では、公平な遺産分割ができるのがメリットですが、遺産を多く取得した相続人が代償金を用意しなければなりません。
共有分割
共有分割とは、相続人全員で特定の財産を共有名義で受け継ぐ方法です。例えば、兄弟3人で1つの不動産を持ち分3分の1ずつ相続するケースが該当します。
共有分割では、相続人が法定相続分で受け継ぐことができ、早期に登記手続きなどを完了できるなど短期的にはメリットがあります。
しかし、不動産を活用・売却するときには共有名義人の合意が必要であることや、共有のまま次世代に相続されることで「持ち分が細分化」していき、権利関係が複雑になるなどのデメリットがあります。
そのため、共有分割で相続する際には、慎重に判断しなければなりません。
関連サイト国税庁「共有物の分割」
遺産分割協議を行う流れ
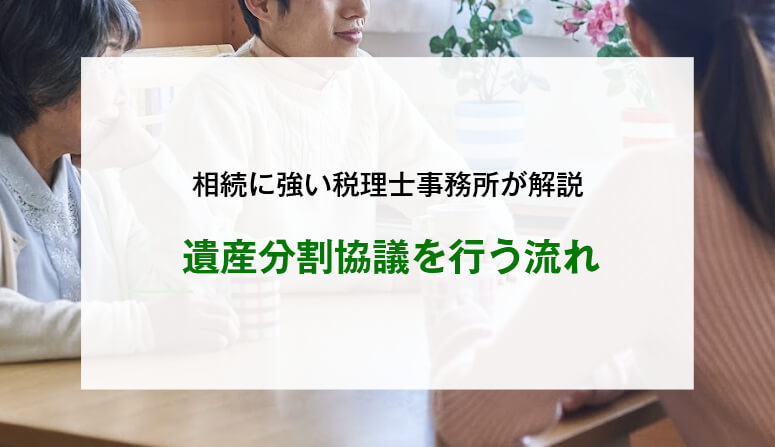
遺産分割協議は、相続人全員が参加して財産の分け方を話し合う重要な手続きであり、下記の流れで行うことが一般的です。
- 相続人調査を行う
- 相続財産調査を行う
- 遺産分割協議を行う
- 決定した内容を遺産分割協議書にまとめる
遺産分割協議書を作成した後は、遺産ごとに名義変更手続きを進めていきます。
遺産相続の際に起きやすいトラブル例
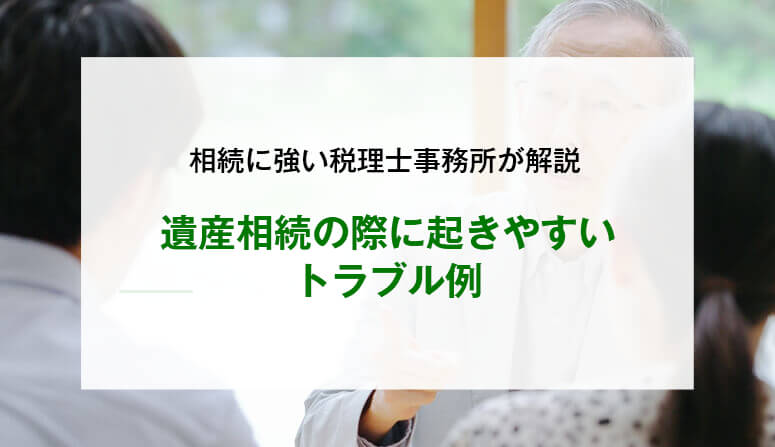
相続発生時には、過去の経緯やそれぞれの感情が絡み合い、トラブルに発展することも珍しくありません。
遺産相続時に起きやすいトラブルは、主に下記の通りです。
- 偏った内容の遺言書が発見される
- 介護をした人が寄与分を主張する
- 関係の悪い人物や疎遠な人物同士が相続人となる
- 過去に生前贈与を受けた相続人がいる
それぞれ詳しく解説していきます。
偏った内容の遺言書が発見される
被相続人が遺言書を作成していたものの、内容が偏っていた場合には、一部の相続人が不満を持つ恐れがあります。
例えば「全財産を長男に相続させる」といった遺言書が発見された場合、次男や長女といった他の兄弟姉妹は不満を持つ可能性が高いでしょう。
このようなケースでは、遺留分侵害額請求や遺言無効確認訴訟などに発展することもあり、相続手続きが完了するまでに時間がかかることもあります。
介護をした人が寄与分を主張する
相続人の1人が被相続人の介護を長年にわたりしていた場合、寄与分を主張することがあります。
寄与分とは、介護や事業の手伝いなどで被相続人の財産の維持や増加に貢献した人物が他の相続人より遺産を多く受け取ることです。
しかし、寄与分が認められるケースはあまり多くないため、介護をしてきた相続人とそれ以外の相続人で対立してしまう場合も多くあります。
関係の悪い人物や疎遠な人物同士が相続人となる
仲の悪い人物や疎遠だった人物同士が相続人となり、遺産分割協議がまとまらないことも多くあります。
遺産分割協議が完了しない場合には、裁判所で遺産分割調停や審判などの手続きを行う必要があり、相続手続き完了までに時間がかかってしまいます。
過去に生前贈与を受けた相続人がいる
被相続人が生前のうちに特定の人物に多額の贈与をしていた場合、特別受益に該当する恐れがあります。
過去の贈与が特別受益に該当すると、贈与財産を遺産分割に反映させる必要があります。結果として、贈与を受けた相続人とそれ以外の相続人で意見が対立し、調停や審判をしなければ解決できないケースも多いのでご注意ください。
遺産相続や分配についてよくある質問
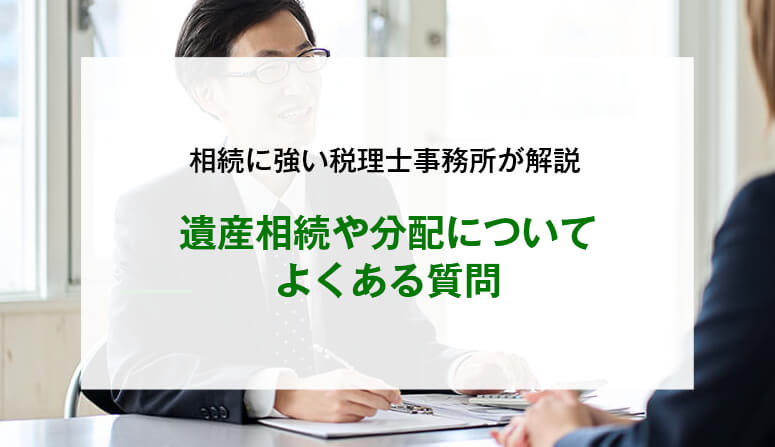
最後に、遺産相続や分配方法についてよくある質問を回答と共に紹介していきます。
独身者が亡くなったら誰が遺産を相続する?
独身者が亡くなった場合、養子や前の配偶者との間に生まれた子供などがいない場合には、被相続人の両親や祖父母が遺産を相続します。両親や祖父母が他界している場合には、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪が遺産を相続します。
孫が遺産を相続することはできる?
原則として、孫は法定相続人にはなりません。孫が法定相続人となるのは、本来相続人であるはずの子供が死亡しており、代襲相続が発生するケースのみです。
被相続人に養子がいた場合の相続はどうなる?
被相続人に養子がいた場合、養子は実子と同様の相続権を持ちます。法定相続分も実子と同じ割合ですし、遺留分に関する権利も実子と同様となります。
前妻の子は相続人になる?
前妻との間に生まれた子供も親子であることにかわりはないため、相続人となります。前妻と離婚した後に再婚している場合は、現在の妻と、子供、前妻の子が法定相続人となることもあります。
相続手続きは
当サポートセンターにお任せください

被相続人が遺言書を用意していなかった場合は、法定相続による分割か遺産分割協議による分割をする必要があります。相続人全員で意見をまとめられそうであれば、柔軟な遺産分割を行える遺産分割協議による分割を選択するのが良いでしょう。
遺産分割協議がまとまらない場合は、相続について詳しい専門家に相談することもご検討ください。相続税申告や相続手続きは、相続に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
相続発生時にどのように遺産を分割するかは、相続人同士の話し合いによって決定できます。遺産をそのまま分ける現物分割や現金化して代金を分配する換価分割など、いくつか方法があるので、自分に合ったものを選択しましょう。
万が一、トラブルに発展してしまった場合や、遺産分割協議がまとまらない場合には、相続に精通した専門家に相談してみることをおすすめします。
専門家であれば、これまで培った経験を活かして、資産や家族の状況に合った遺産分割を提案可能です。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ