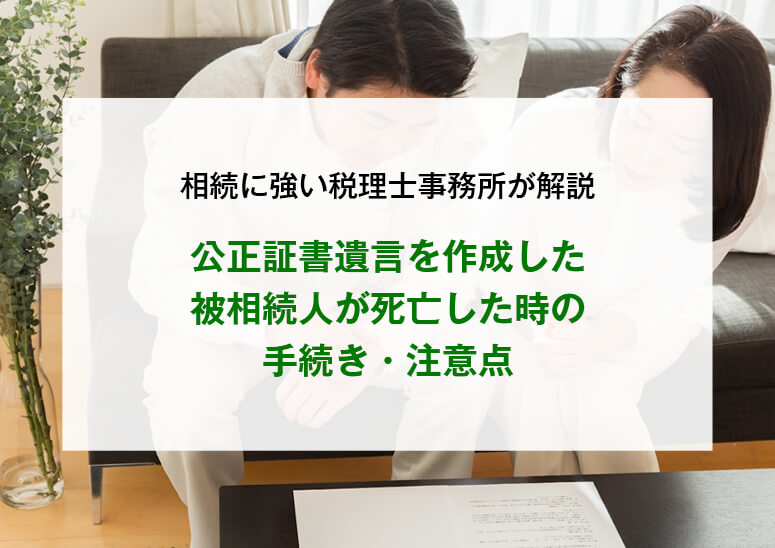
公正証書遺言を作成した被相続人が死亡した時の手続き・注意点を解説
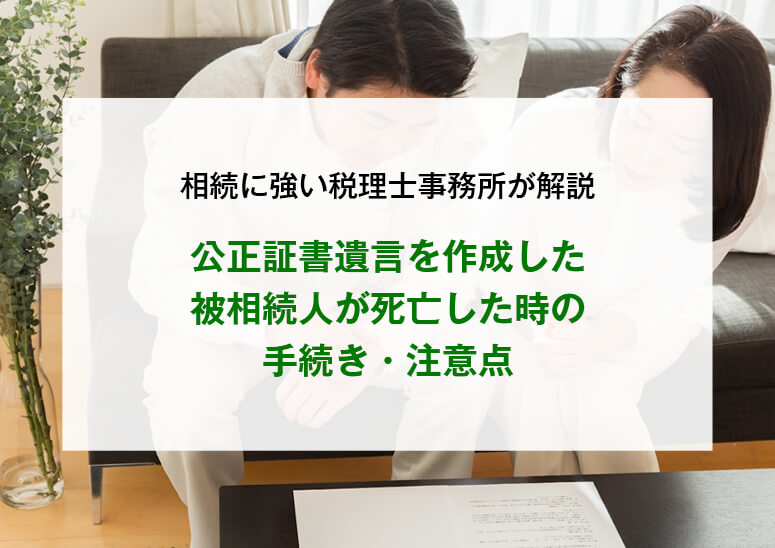
親や配偶者が生前に「遺言を残してある」と話していた場合、その遺言がどこにあるのか、どう活用できるのかは相続手続きに大きく関わります。
特に、公正証書遺言は信頼性が高く、家庭裁判所の検認も不要なためスムーズに手続きを進められます。
しかし、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されており、どこに遺言があるのかわからず困ってしまうこともあるでしょう。
本記事では、公正証書遺言とは何か、遺言者が死亡したら連絡が来るのかなどを解説していきます。
目次
公正証書遺言とは?
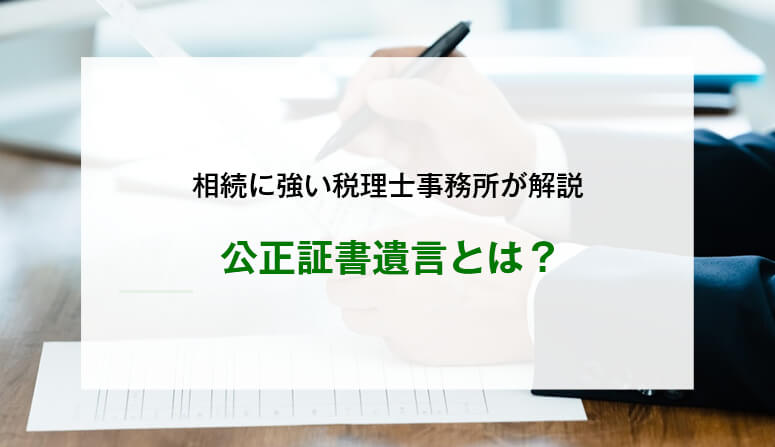
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。遺言者が口頭で伝えた内容をもとに、公証人が文章を作成し、遺言者と証人2名が署名・押印することで成立します。
遺言書の原本は、公証役場に保管され、正本と謄本が遺言者に渡されます。自筆証書遺言と異なり、公正証書遺言は形式不備によって無効になるリスクが低く、紛失や改ざんの心配がないため、確実に遺言の内容を実現したい場合に適しています。
関連サイト法務局「自筆証書遺言と公正証書遺言の違い」
公正証書遺言を作成した人が
死亡したら連絡が来る?
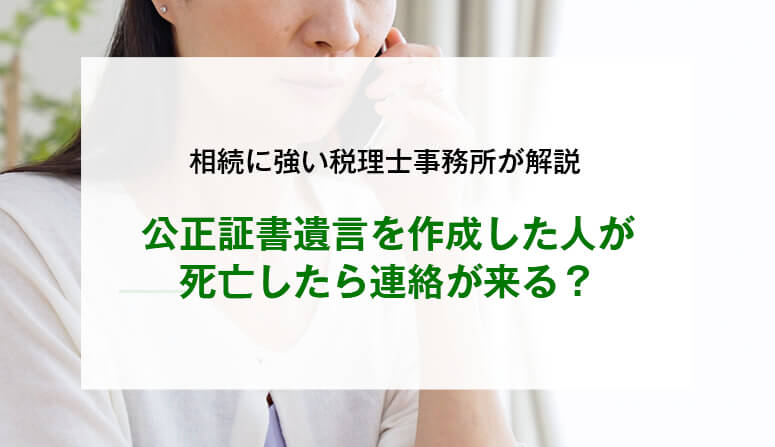
結論から言うと、公正証書遺言を作成したからといって、作成時に指定された相続人や受遺者に自動的に連絡が届くわけではありません。
公証役場や公証人が、遺言者の死亡を把握した時点で通知を行う制度は、2025年3月時点では存在しないからです。
そのため、公正証書遺言が存在していても、相続人が遺言の存在を知らなければ手続きに活用できない恐れがあります。
遺言者が死亡した際に
公正証書遺言を探す方法
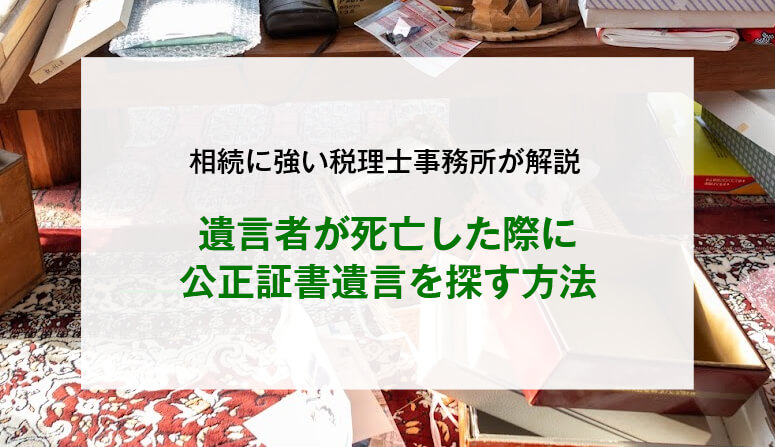
遺言者が亡くなり相続が発生した際には、公証役場で遺言書が保管されていないかを確認する必要があります。
被相続人が作成していた公正証書遺言を探す方法は、下記の通りです。
- 故人の自宅などを整理し遺言書を探す
- 公証役場の遺言検索システムを利用する
- 故人の家族・友人などに聞いてみる
- 信託銀行などに問い合わせる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
故人の自宅などを整理し遺言書を探す
まずは、故人の自宅や入院先の病室などを整理し、遺言書がないか探してみましょう。
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるものの、遺言者は写しである「正本」や「謄本」を保管していることも多いからです。
以下のような場所に遺言書がないか、確認してみましょう。
- 自宅の引き出し
- 金庫
- 重要書類を保管しているファイル
公証役場の遺言検索システムを利用する
公正証書遺言が作成されたかどうかを公的に調べるには「遺言検索システム」を利用する方法があります。
遺言検索システムでは、相続発生後に相続人や代理人が全国の公証役場を通じて遺言の有無を調査できます。遺言検索システムを利用するにあたり、必要な書類は、主に下記の通りです。
- 遺言者の死亡を証明する書類(死亡診断書または除籍謄本など)
- 依頼者の本人確認書類(運転免許証など)
- 依頼者が相続人であることを示す戸籍謄本等
- 委任状(代理人)
検索の結果、公正証書遺言が見つかった場合には、その作成日や保管場所、公証人の氏名などの情報が提供されます。必要に応じて謄本の交付を行ってもらえるので、遺言内容も確認可能です。
関連サイト日本公証人連合会「亡くなった方について、公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることができますか?」
故人の家族・友人などに聞いてみる
遺言の存在を把握するもうひとつの手段は、被相続人の家族や親しい友人、信頼できる知人に尋ねてみることです。
公正証書遺言の作成時には、証人2名の立ち会いが必要なため、証人を務めた人物やその場に居合わせた家族が遺言の存在を知っている可能性があるからです。
信託銀行などに問い合わせる
被相続人が信託銀行と取引していた場合には、信託銀行の遺言信託を利用していないかも確認しておきましょう。
遺言信託とは、信託銀行が遺言の保管および執行までを担うサービスです。被相続人の自宅を整理していて、遺言信託のパンフレットや信託銀行との契約書類があれば、遺言信託を活用している可能性が高いでしょう。
関連サイト一般社団法人信託協会「遺言信託」
公正証書遺言が発見された後の
相続手続きの流れ
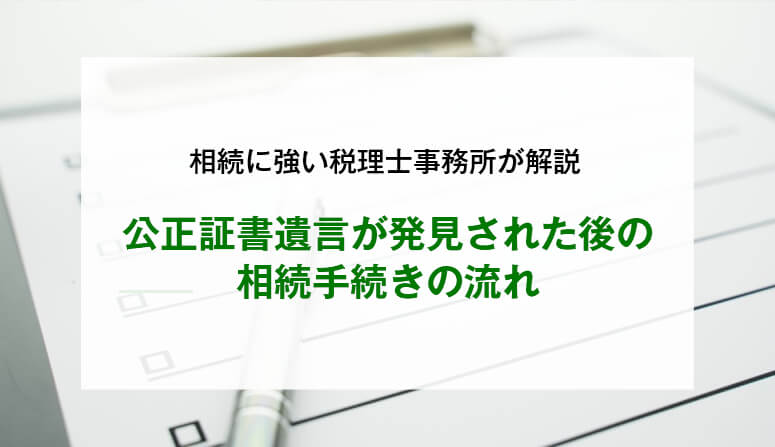
公正証書遺言が発見された場合、原則として遺言内容にしたがって相続手続きを進める必要があります。
相続手続きは、下記のように進める形が一般的です。
- 遺言執行者の有無を確認する
- いる場合は、遺言執行者に手続きを任せる
- いない場合は、相続人と受遺者で協力して相続手続きを進める
被相続人が公正証書遺言を作成していた場合、遺言執行者を選任していることがあります。
遺言執行者とは、遺言内容の実現のために相続手続きなどを行う人物です。遺言執行者が選任されている場合には、相続財産調査から遺産の名義変更手続きまで執行者が単独で行えます。
公正証書遺言が発見された後の注意点
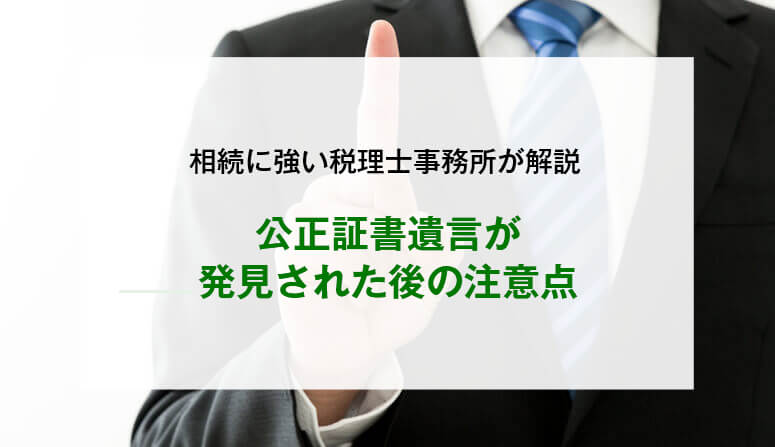
公正証書遺言が見つかった後は、原則として遺言書の内容にしたがって相続手続きを進めていく必要があります。
公正証書遺言発見後には、下記に注意しながら相続手続きを進めましょう。
- 公正証書遺言は検認手続きが不要である
- 遺留分は遺言より優先される
- 公正証書遺言でも無効になることがある
それぞれ詳しく解説していきます。
公正証書遺言は検認手続きが不要である
公正証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きが不要であり、すぐに相続手続きに移れます。
関連サイト裁判所「遺言書の検認」
一方、法務局による保管制度を利用していない自筆証書遺言や、秘密証書遺言の場合は、発見後に家庭裁判所で検認手続きをしなければなりません。
このように、遺言書の種類によっては、検認手続きが必要となるので注意しなければなりません。
遺留分は遺言より優先される
公正証書遺言が見つかっても、すべての内容がそのまま実行されるとは限りません。遺留分は遺言より優先されるため、遺言内容が遺留分を侵害している場合、トラブルが起きる恐れもあります。
遺留分とは、被相続人の配偶者や子供、両親が最低限度の遺産を受け取れる権利です。例えば「全財産を長男Aに相続させる」といった公正証書遺言が見つかった場合、次男や長女が遺留分侵害額請求をすることが可能です。
遺留分侵害額請求を行った場合、遺言によって遺産を多く相続した長男は次男や長女に遺留分侵害額相当分の金銭を支払わなければなりません。
公正証書遺言でも無効になることがある
公正証書遺言は形式的な不備が生じにくいメリットがありますが、すべての公正証書遺言が有効なわけではありません。
例えば、遺言者が遺言を作成した時点で意思能力(判断能力)を欠いていた場合、その遺言は無効となる可能性があります。
遺言者の認知症症状が進行している状態で作成されたとみなされた場合には、公正証書遺言でも無効になる恐れがあるのでご注意ください。
他にも、証人2名が欠格事由に該当していた場合も、公正証書遺言が無効になってしまいます。
このように、公正証書遺言でも無効になってしまうリスクはあります。無効リスクをできるだけ軽減したい場合には、遺言書を作成する時点で、相続に精通した専門家に相談しておくと良いでしょう。
相続手続き・相続税申告は
当サポートセンターにお任せください

被相続人が公正証書遺言を用意していた場合、原則として遺言書の内容にしたがって相続手続きを進めていきます。
そのため、相続発生後は被相続人が作成した公正証書遺言を確認しなければなりません。
公正証書遺言を探すのが難しい場合や、その後の手続きに不安がある場合は、相続に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
被相続人が公正証書遺言を用意していた場合、相続発生後に遺言書を探す必要があります。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているものの、正本や謄本などの写しは被相続人が保管していることも多いからです。
相続発生後は自宅や病室、入所していた施設の部屋などを整理して、遺言書がないか探してみましょう。
遺言書が見つからない場合には、公証役場の遺言検索システムを利用すれば全国の公証役場に遺言書が保管されていないか調べられます。遺言書が見つかった後の相続手続きに不安がある場合や、ミスなく相続税申告したい場合は、相続に精通した専門家に相談することも検討しましょう。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ