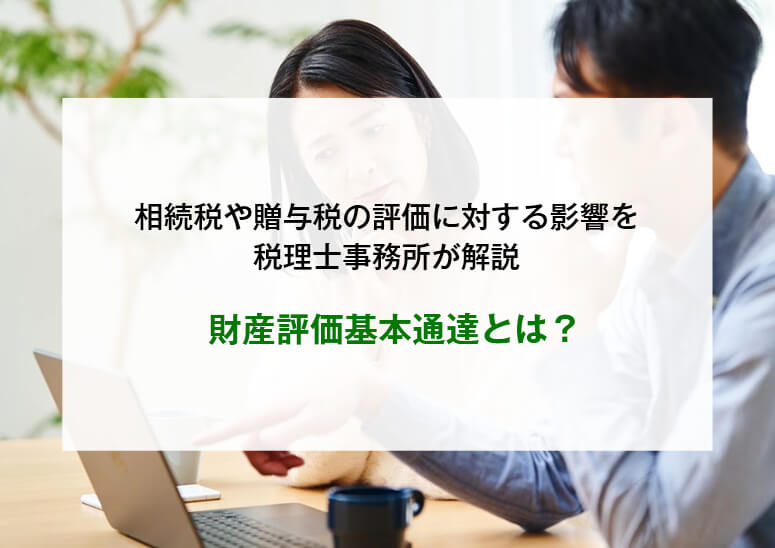
財産評価基本通達とは?相続税や贈与税の評価に対する影響を解説
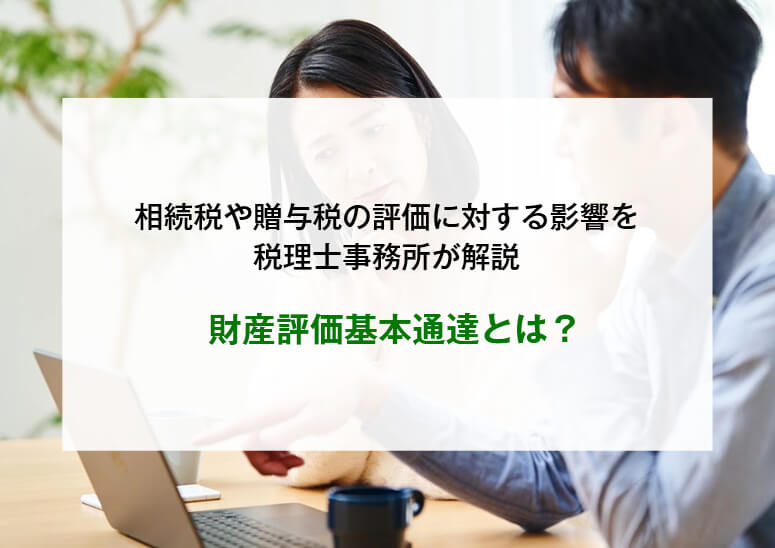
相続税の計算に欠かせないものが財産評価基本通達です。相続財産は原則として時価で評価されますが、その基準があいまいでは申告の公平性が保てません。
そこで国税庁が示す財産評価基本通達を参考に、土地や建物、株式、預貯金といった財産の評価方法を統一しています。
本記事では、財産評価基本通達の基本的な考え方や具体的な評価方法、相続税申告における実務上の注意点を解説します。
目次
財産評価基本通達とは
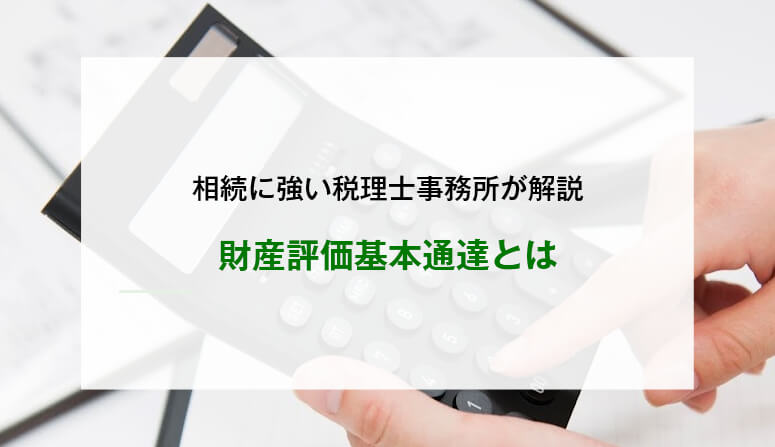
財産評価基本通達とは、相続税や贈与税を計算する際に必要となる財産の「時価」を合理的に評価するための基準を定めた国税庁の指針です。
土地・建物・株式・預貯金など財産の種類ごとに具体的な評価方法が示されており、全国一律で公平な課税を実現する役割を担っています。
財産評価基本通達は法律そのものではなく行政通達ではあるものの、実務では申告や税務調査において基準として扱われています。
財産評価基本通達は時価で評価する方法を定めている
財産評価基本通達の根底にある考え方は、時価評価です。ただし、ここでいう「時価」とは必ずしも実際の売買価格を指すものではなく、合理的に算出された「相続税評価額」を意味します。
例えば、宅地であれば路線価や倍率方式を用いて評価し、非上場の株式であれば純資産価額や類似業種比準価額を基準に計算します。
財産評価基本通達の主要条文
財産評価基本通達には、数多くの条文が設けられており、財産の種類ごとに詳細な評価方法が定められています。相続税や贈与税の計算時に特に確認されることが多いものは、以下の通りです。
| 条文 | 概要 |
|---|---|
| 第24条(宅地評価) | 路線価方式に基づき、道路付け・間口・奥行などを補正。都市計画道路予定地(24-7)の場合、利用制限があるため評価減を考慮 |
| 第165条~(建物・設備) | 固定資産税評価額を基準に算定。老朽化や特殊構造などに応じて調整を行う |
| 第178条~189条(取引相場のない株式) | 中小企業株式の評価を定める条文。類似業種比準価額方式と純資産価額方式を使い分ける |
| 第185条(純資産価額方式) | 会社の貸借対照表に基づき資産・負債を時価評価し、株式価額を算出する |
| 第188条(会社規模による区分) | 大会社・中会社・小会社に区分し、評価方法を調整。規模に応じて比準価額方式の計算式が変わる |
| 第203条(預貯金の評価方法) | 残高証明書等に基づき相続開始日時点の残高を評価額とする |
| 第204条(債権の評価) | 貸付金などの債権を原則額面で評価。回収不能の恐れがある場合は減額も認められる |
これらの規定に基づくことで、実際に市場で取引しなくても公平かつ一貫性のある財産評価が可能になります。
特に、相続税申告では評価額の僅かな差が税額に大きく影響するため、通達の理解と活用は実務上きわめて重要です。
財産評価基本通達の対象財産と
主な評価方法
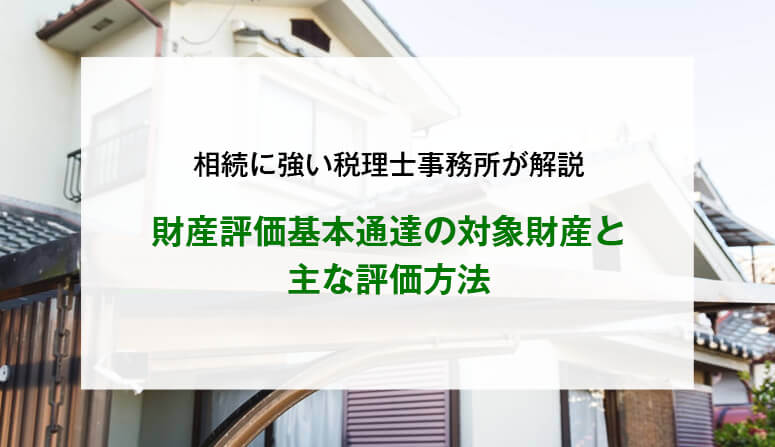
相続財産には、現金や預貯金だけでなく、土地などの不動産や株式など様々な財産が含まれます。本章では、財産評価基本通達に記載されている対象財産と主な評価方法について解説していきます。
土地・宅地の評価
土地・宅地の評価は、財産評価基本通達において最も重要な部分のひとつです。宅地の場合、主に(1)路線価方式と(2)倍率方式の2つの方法が採用されます。
建物・家屋の評価
建物や家屋については、原則として固定資産税評価額を基準に評価します。固定資産税評価額は、市町村が課税のために算定している評価額で、耐用年数や構造、築年数などを反映した現実的な金額です
農地・山林・原野の評価
農地については、その利用状況や立地に応じて倍率方式や路線価方式などの方法で評価されます。同じ農地であっても市街化区域内の農地は宅地並み評価となり、実質的に宅地と同様の方法で算定される場合もあります。
山林や原野については、近隣の取引事例や固定資産税評価額に基づき倍率をかけて評価するのが一般的です。
預貯金・有価証券
預貯金は、被相続人が亡くなった時点の残高証明に基づいて評価されます。普通預金や定期預金ともに額面通りで評価するのが原則です。
有価証券は、上場株式であれば相続開始日の終値、あるいは一定期間の平均値を基準に評価します。
関連記事株の相続方法と必要書類について
非上場株式の評価
中小企業などの非上場株式は、財産評価基本通達の中でも特に複雑な分野のひとつです。
評価方法としては(1)類似業種比準価額方式と(2)純資産価額方式が規定されており、会社の規模や業種、財務内容に応じて使い分けます。
動産・その他の財産
最後に、動産やその他の財産についても評価基準が定められています。例えば、自動車は中古車市場での取引価格、貴金属や宝石は鑑定評価額を参考に算定します。
書画・骨董品は専門家の鑑定を要するケースも多く、相続財産の中で見落とされやすいので注意しなければなりません。
財産評価基本通達を参考にして
相続税申告をする流れ
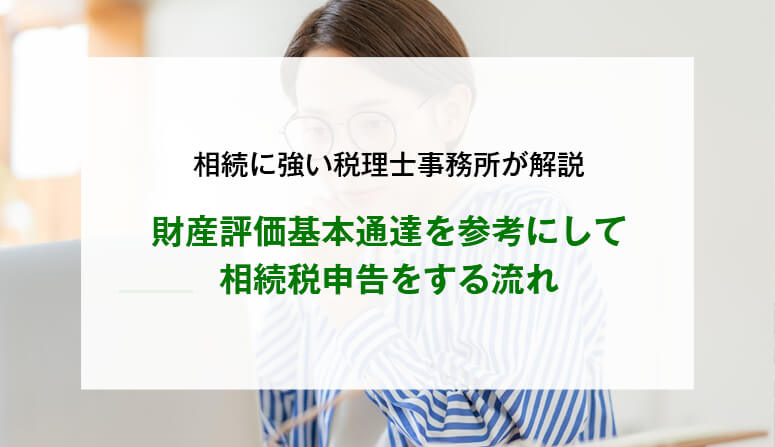
財産評価基本通達を確認すれば、相続財産の評価額を算出できます。相続税は相続財産の合計額をもとに計算する必要があります。具体的には以下のような流れで計算します。
- 相続財産の洗い出し(不動産・金融資産・株式・動産)
- 通達に基づく評価方法の判定
- 評価額計算・補正率適用
- 課税価格の合計額を計算する
- 相続税を計算する
それぞれ詳しく解説していきます。
相続財産の洗い出し(不動産・金融資産・株式・動産)
まずは、被相続人が残した財産を漏れなく洗い出しましょう。財産のリストアップ段階で漏れがあると、後の評価や税額計算に誤差が生じ、誤申告や税務調査の対象となるリスクが高まるのでご注意ください。
通達に基づく評価方法の判定
続いて、財産の種類ごとに、財産評価基本通達で定められた評価方法を選択します。不動産や非上場株式の相続税評価額を計算する際には、専門的な知識や経験が必要となるので、税理士に相談することをおすすめします。
評価額計算・補正率適用
評価方法を決定した後は、実際に金額を算定します。宅地であれば、路線価を基準に「間口狭小補正」「奥行長大補正」「不整形地補正」などの補正率を適用します
株式や債権についても、通達に基づいた具体的な計算式を適用しなければなりません。
課税価格の合計額を計算する
すべての財産を評価したら、債務控除や葬式費用の控除を行い、課税価格を算定します。
また、相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除や生命保険金・死亡退職金の非課税枠が用意されているので、こちらも漏れなく計算しましょう。
相続税を計算する
課税対象額の計算が完了したら、下記の流れで相続税の計算を行います。
- 法定相続分で遺産を分けたとして各相続人の相続税額を計算する
- 相続税額を合計し、実際の相続割合で按分する
- 各相続人に適用される控除・加算を加える(配偶者控除や相続税の2割加算など)
このように、相続税の計算は非常に複雑であり、計算をする前には相続財産調査や相続税評価額の算出が必要となります。
自分で計算することが難しい場合には、相続に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
相続税申告時に
財産評価基本通達を参考にするときの注意点
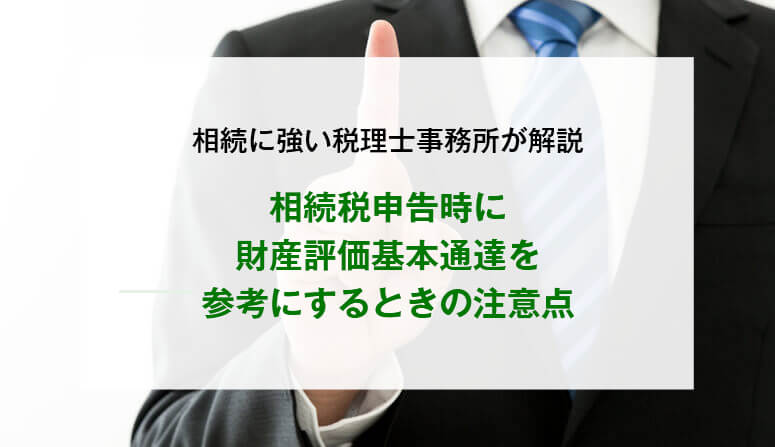
財産評価基本通達は、相続税や贈与税を計算するときの基準となるものですが、通達に従った場合でも過度な節税対策とされると税務署に否認される恐れがあるのでご注意ください。
他にも、相続や遺産の状況によっては、個別の鑑定評価が必要となるケースもあります。財産評価基本通達を参考にする際の注意点を詳しく見ていきましょう。
通達に従っても否認される可能性がある
財産評価基本通達は、相続税や贈与税の課税において全国一律の基準を示す重要な指針ですが、あくまで「一般的な評価方法」を定めた行政通達にすぎません。
そのため、通達に従って算定した評価額であっても、必ずしも税務署がそのまま認めるとは限らない点に注意が必要です。
相続や遺産の状況が特殊な場合には鑑定評価が必要になることがある
財産評価基本通達に定められている評価方法は、通常のケースを想定した標準的なルールです。
そのため、遺産や財産の状況が特殊な場合には、通達だけでは正確な評価が困難となり、専門家による鑑定評価を活用することが推奨されます。
ミスなく相続税を申告したい場合や、できるだけ相続税を節税したい場合には、相続に精通した税理士に相続税の申告や計算を依頼しましょう。
相続税申告は
当サポートセンターにお任せください

相続税や贈与税の計算は財産評価基本通達を確認すれば、自分でもできると考えているかもしれません。
しかし、実際には宅地や非上場株式の評価は財産評価基本通達を見ても複雑ですし、ケースによっては個別の判断が必要となることもあります。
相続税申告や対策に不安がある場合には、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
財産評価基本通達は、相続税や贈与税の実務を円滑に進めるための基準であり、相続財産を公平に評価するうえで欠かせません。
ただし、通達に従えば必ず認められるわけではなく、特殊なケースでは鑑定評価が必要になることもあります。
相続税申告を正確かつ安全に行うためには、通達を理解した上で、専門家の助言を得ながら評価方法を検討することが重要です。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ