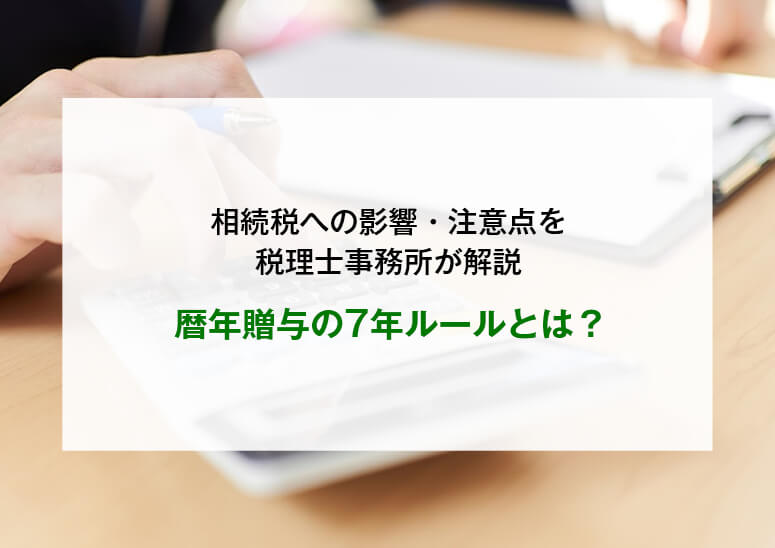
暦年贈与の7年ルールとは?相続税への影響・注意点を税理士事務所が解説
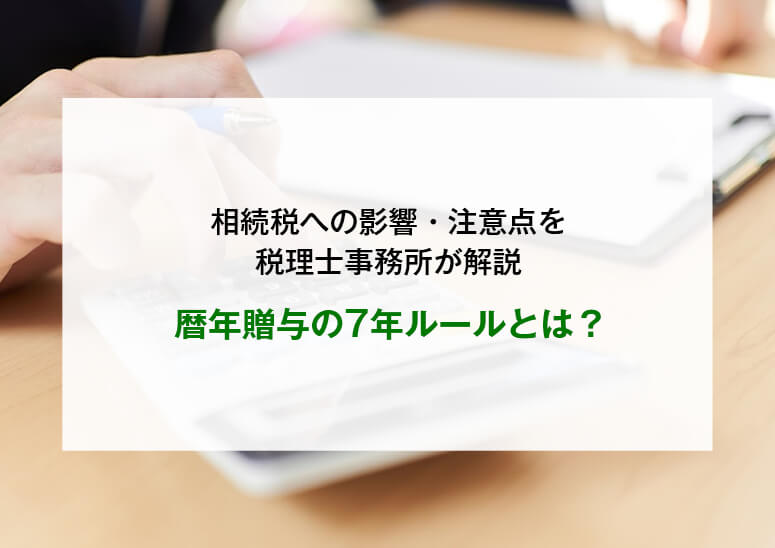
2024年から、暦年贈与に関する生前贈与加算の対象期間が従来の3年から7年に拡大されました。これにより、暦年贈与を利用した相続税対策が従来より難しくなった点に注意が必要です。
本記事では、暦年贈与の7年ルールとは何か、贈与税・相続税の計算方法、注意すべきポイントについて解説します。
目次
暦年贈与の7年ルール(生前贈与加算とは)

暦年贈与とは、贈与税の基礎控除である年間110万円を活用し、毎年少しずつ財産を贈与することで、相続財産を減らしながら贈与税・相続税を軽減する方法です。
2024年までは、贈与から3年以内に被相続人が亡くなった場合、その贈与分を相続財産に加算するというルール(生前贈与加算)が適用されていました。
しかし、2024年1月1日以降の贈与については、この加算される期間が「3年から7年」に延長されました。この加算期間の延長は相続税対策に大きな影響を及ぼすこととなりました。
なお、2024年以降の暦年贈与では、相続発生前7年の贈与すべてが相続税の課税対象となるわけでなく、4年目以降については合計100万円の控除が認められます。
関連サイト国税庁「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」
これまでの3年ルールとの違い
これまでの生前贈与加算では、被相続人が亡くなる直前の3年間の贈与のみが対象でした。しかし、2024年から適用される新ルールでは、死亡前最長7年間の贈与額が加算対象となるため、結果として加算額が大きくなる可能性があります。。
仮に、毎年100万円ずつ贈与していた場合、相続直前の7年間で合計700万円を贈与したことになります。
このうち、相続開始前3年分(300万円)は全額が加算対象となり、残りの4年分(400万円)は100万円の控除後の300万円が加算対象となります。したがって、合計600万円が相続財産に加算されてしまいます。
従来の3年ルールでは300万円のみが加算対象だったところ、ルール変更後は相続税の課税対象となる財産額が600万円に増え、結果的に相続税が高額になる可能性があるので注意しなければなりません。
相続時精算課税制度との違い
相続時精算課税制度は、60歳以上の直系尊属から18歳以上の直系卑属への贈与を行う場合に選択できる制度で、累計2,500万円までの財産を贈与税の負担なく贈与することが可能な制度です。
ただし、贈与時に贈与税がかからない代わりに、相続時にその贈与財産を相続財産に合算して相続税を計算しなければなりません。
暦年贈与と相続時精算課税制度の最大の違いは、贈与した財産が最終的に相続財産に加算されるか否かどうかです。暦年贈与の場合、相続発生から7年を超えた贈与については相続財産に加算されません。
一方、相続時精算課税制度では、贈与した財産は基礎控除を除き、全額が相続財産として扱われるため、相続税の節税にはつながらない可能性もあります。
このように相続にまつわる税制は複雑であるため、適切に相続税対策を行いたい場合は税理士への相談も検討しましょう。
暦年贈与の7年ルールの
対象になるケース・ならないケース
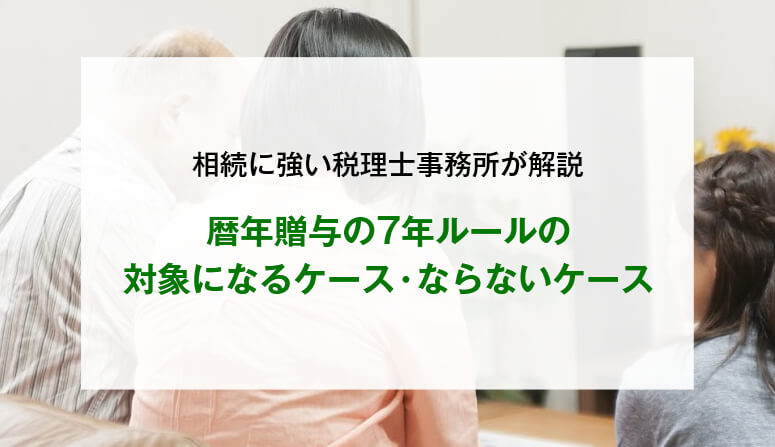
2024年以降、相続税における生前贈与加算が3年から7年に延長されたことにより、暦年贈与による相続対策に大きな影響が出ています。ただし、この「暦年贈与の7年ルール」はすべての贈与に適用されるわけではありません。
本章では、ここでは、暦年贈与の7年ルールがどのような贈与に適用されるのか、具体的に解説します。
対象になるケース
暦年贈与の7年ルールの対象となるのは、次の3つの要件をすべて満たす贈与です。
- 贈与者が相続開始前7年以内に贈与したものである
- 相続または遺贈によって財産を取得した者(相続人・包括受遺者など)に対する贈与である
- 暦年課税による贈与である
対象にならないケース
一方で、先ほどの要件を満たさない贈与は、贈与者が亡くなる直前に行われたとしても、暦年贈与の7年ルールの対象外となります。
- 贈与を受けた人が相続人ではない場合(養子縁組していない孫や甥・姪への贈与)
- 贈与者の死亡時点で、受贈者が生存していない場合
- 相続時精算課税制度によって贈与された場合
暦年贈与の7年ルールが適用される場合の
相続税・贈与税の計算例
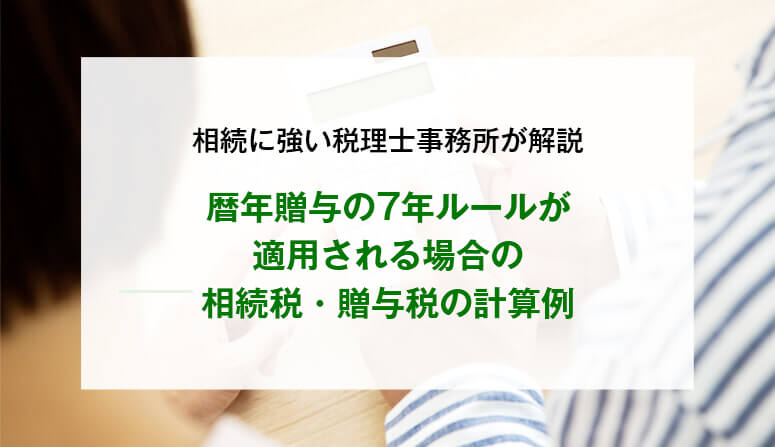
2024年以降に始まった暦年贈与の7年ルールにより、贈与税と相続税の計算が複雑になりました。本章では、7年ルールが適用された場合の贈与税や相続税の計算方法を具体例と共に解説します。
贈与税の計算例
まずは、暦年贈与における贈与税の計算例を見てみましょう。
子供が2024年に父から200万円を贈与された場合
贈与税は暦年課税方式を選んでいる場合、1年間の合計贈与額から基礎控除110万円を差し引き、残りの金額に税率を適用して算出します。
贈与税は「(200万円-110万円)×10%=9万円」と計算できます。
この時点では、贈与者が生きているため、暦年贈与の7年ルールなどを考慮せず、贈与税を計算します。
相続税の計算例
次に、上記の贈与が相続開始前7年以内に行われたと仮定し、相続税においてどのように加算されるかを見てみましょう。
被相続人(父)が2030年に死亡し、相続人である子供が過去7年間に合計1,400万円(200万円×7年)の暦年贈与を受けていた場合
なお、7年ルールでは4年目以降(3年超)の贈与分については合計100万円の控除が適用されます。
この場合、最初の3年間(2027~2029年)の600万円はそのまま全額加算、残りの4年分は100万円の控除が適用され「800万円−100万円=700万円」となります。
したがって、生前贈与加算の合計額は「600万円+700万円=1,300万円」です。この加算額1,300万円を、相続税の課税遺産総額に上乗せして、法定相続分に応じた課税が行われます。
なお、贈与を受けた際に贈与税を申告・納税している場合には、相続税申告時に贈与税額控除を適用可能です。
暦年贈与の7年ルールが
適用される場合の注意点
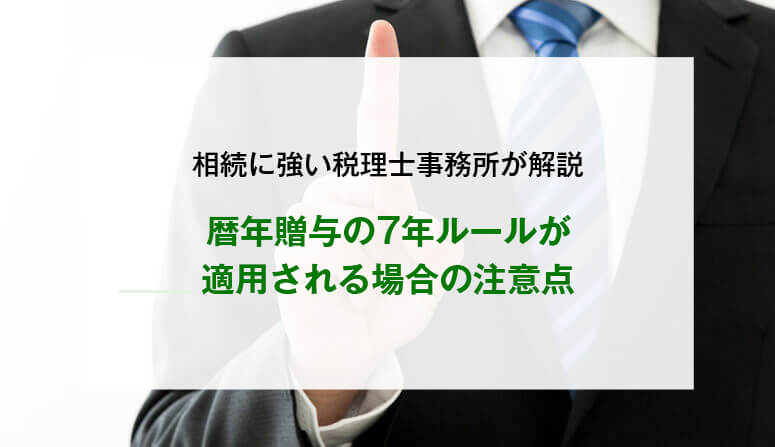
2024年以降に暦年贈与にて、贈与税や相続税を節税しようとしている場合には、以下のような点に注意しなければなりません。
- 贈与税・相続税の申告漏れや二重課税に注意する
- 贈与契約書を作成し贈与の証拠を残しておく
- 名義預金とされないように注意する
それぞれ詳しく解説していきます。
贈与税・相続税の申告漏れや二重課税に注意する
基礎控除である年間110万円を超える贈与を受けた際には、贈与税を申告しなければなりません。贈与税の申告を怠ると、税務調査の対象となり、加算税や延滞税が課されるリスクがあります。
また、2024年以降は7年ルールにより、生前の贈与が相続税の課税対象として相続財産に加算されることがあります。
贈与財産を相続財産に加算する際に、すでに贈与税を納めた金額がある場合には、相続税計算時にその分を控除可能です。
贈与契約書を作成し贈与の証拠を残しておく
暦年贈与を行う場合、税務署に対して贈与の事実を証明するために、贈与契約書を作成しておきましょう。
贈与契約書に決まった書式はありませんが、贈与者・受贈者の氏名・住所や贈与財産などに記載しておくと良いでしょう。
名義預金とされないように注意する
暦年贈与で毎年贈与を繰り返す場合には、贈与税が名義預金と判断されないように注意しましょう。名義預金とは、口座名義人が贈与財産を管理するのではなく、贈与者が管理しているものを指します。
名義預金とされると、贈与者が亡くなったときに贈与が無効とされ相続財産として扱われる恐れがあるのでご注意ください。
名義預金と判断されないようにするには、贈与後は口座名義人(受贈者)が預貯金を管理することが大切です。
相続対策は
当サポートセンターにお任せください

2024年からは暦年贈与の生前贈与加算が3年から7年に延長されることとなりました。そのため、従来検討・実施した節税スキームが使えなくなったケースも出ています。
相続税対策や贈与税の節税方法には様々なものがあり、資産や家族の状況によって最適な対策方法が変わってきます。自己判断で生前贈与を行うのではなく、相続や贈与に詳しい税理士に相談しながら手続きを進めていくと良いでしょう。
相続税対策や贈与税の節税対策は、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
暦年贈与の7年ルールが適用されることにより、相続税の税負担が重くなり、相続税対策をしにくくなったことは否めません。
しかし、7年ルール適用後も暦年贈与は有効な相続税対策のひとつであることには変わりません。贈与者の年齢が若い場合や、受贈者となる人物が多くいる場合には、暦年贈与にて節税対策をするのも良いでしょう。
相続税対策にはいくつか方法があるため、税理士に相談した上で、自分に合う方法を選択することが大切です。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ