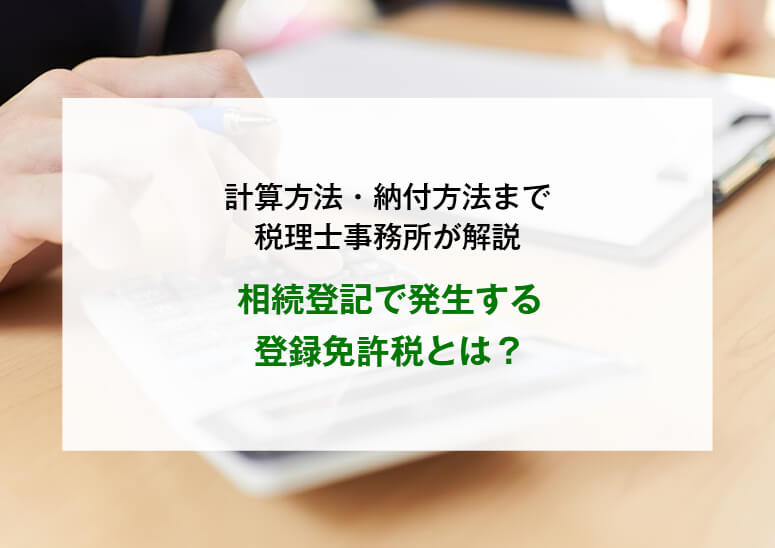
相続登記で発生する登録免許税とは?計算方法・納付方法まで解説
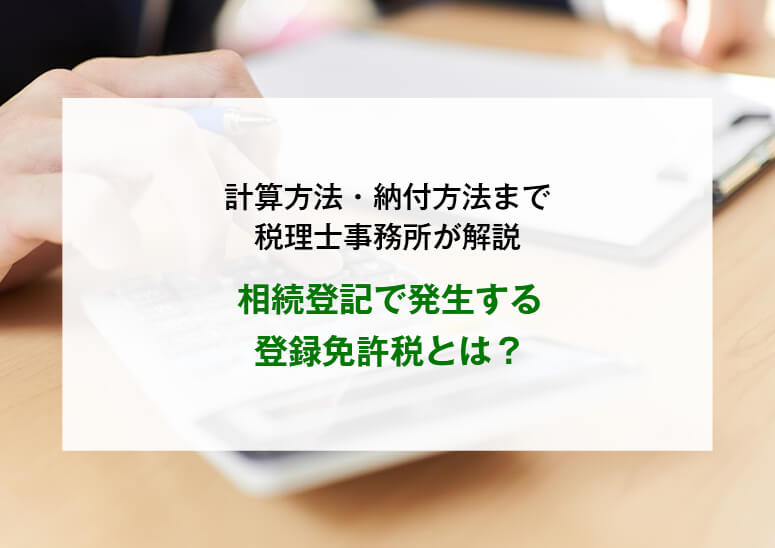
相続登記を行う際に避けて通れないのが「登録免許税」です。登録免許税は単なる手数料ではなく、登記手続に伴って国に納める税金であり、不動産の固定資産税評価額を基準に算定されます。
関連サイト国税庁「No.7190登録免許税のあらまし」
相続不動産の数が多い場合や評価額が高額である場合には、登録免許税の負担もそれだけ重くなるのでご注意ください。
また、登録免許税は登記申請時に自分で計算して収入印紙などで納付する必要があるので、ミスなく計算することが非常に重要です。
本記事では、相続登記における登録免許税の計算方法や登録免許税の計算時によくある質問を紹介していきます。
目次
登録免許税とは
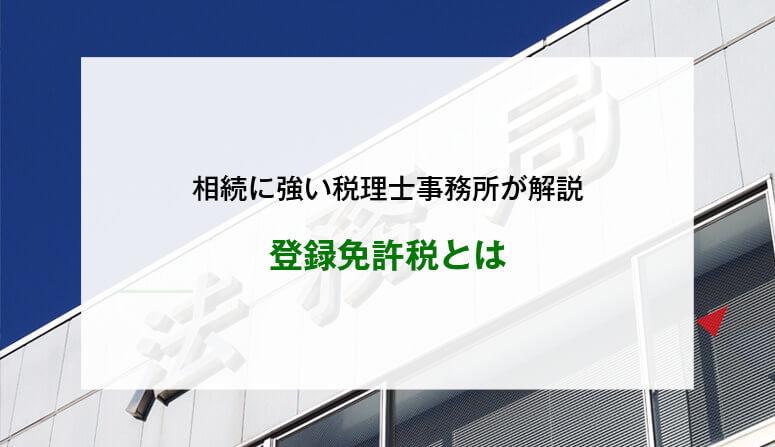
登録免許税とは、不動産の権利に関する登記や会社設立の登記など、法務局で登記を行う際に国に納める税金です。
関連サイト国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
不動産の登記においては、所有権移転登記や抵当権設定登記など登記の種類ごとに課税基準や税率が定められています。特に、相続による所有権移転登記は、売買や贈与とは異なり、比較的低い税率が適用される点が特徴です。
関連サイト法務局「不動産登記申請手続」
登録免許税は通常、不動産の固定資産税評価額をもとに計算されます。固定資産税評価額は市区町村が毎年作成する「固定資産課税台帳」に記載されており、登記の際には必要な「固定資産評価証明書」を取得して確認します。
関連サイト国税庁「固定資産税評価額」
次の章では、相続登記における登録免許税の計算方法を詳しく解説していきます。
相続登記における登録免許税の計算方法
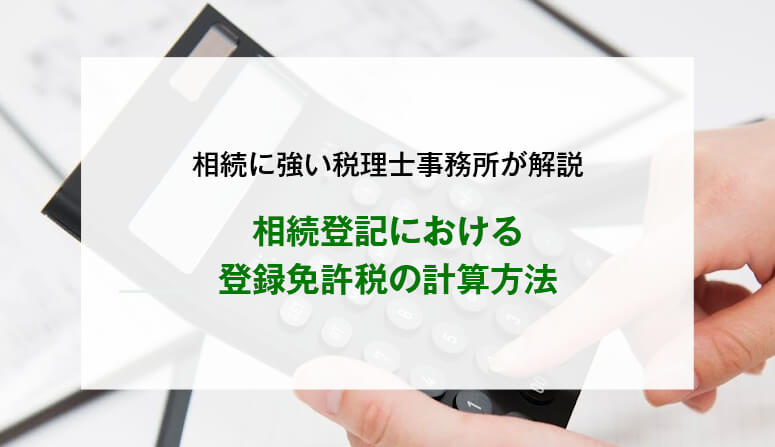
相続登記の際に課せられる登録免許税は「不動産の固定資産税評価額×0.4%」で計算されます。例えば、固定資産税評価額が2,000万円の土地を相続登記する場合、登録免許税は「2,000万円×0.4%=8万円」となります。
ただし、法定相続人以外の人が特定遺贈によって不動産を取得した場合には「不動産の固定資産税評価額×2%」と税率が上がるのでご注意ください。
相続登記にかかる登録免許税を計算する際に注意すべきことのひとつは、相続登記は不動産ごとに課税されるという点です。
例えば、土地と建物を併せて相続する場合、それぞれの評価額に0.4%を掛けて計算し、合算した金額が納付額となります。
被相続人が複数の不動産を所有していた場合には、それぞれの登録免許税を計算しなければなりません。なお、登録免許税には1件あたり1,000円の最低税額が定められています。
つまり、山林や農地などのいった評価額が極端に低い不動産であっても、税額は最低1,000円となることも理解しておきましょう。
登録免許税の計算に不安がある場合や、相続登記の申請に不安がある場合には、手続きを司法書士に依頼することもご検討ください。
登録免許税の納付方法
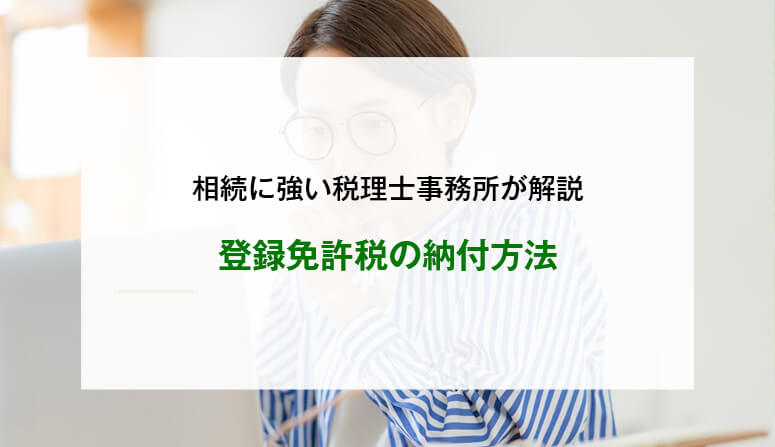
相続登記を含む不動産登記の手続きでは、申請時に必ず登録免許税を納める必要があり、納付方法は、以下の3種類が用意されています。
- 収入印紙による納付
- 現金納付
- オンライン納付
それぞれ詳しく解説していきます。
収入印紙による納付
最も一般的なのが収入印紙による納付です。郵便局や法務局内の印紙売りさばき所で購入した収入印紙を、登記申請書の所定欄に貼付して納めます。相続登記に限らず、多くの登記申請で利用されており、全国どの法務局でも対応しています。
ただし、収入印紙は一度貼付すると再利用ができず、訂正時に貼り直す場合には新たに購入が必要となる点には注意が必要です。また、金額が大きくなると高額の印紙が必要となるため、取り扱いに慎重さが求められます。
関連サイト国税庁「印紙税額」
現金納付
登録免許税は金融機関を通じて現金で納付することも可能です。現金納付では、所定の納付書を用いて金融機関にて登録免許税を納付します。
納付手続きが終わったあとに受け取る領収書を登記申請書に貼り付けて法務局に提出します。相続不動産の評価額が高額であり、収入印紙による納付やオンライン納付が難しい場合に、現金納付を検討すると良いでしょう。
オンライン納付
近年普及しているのがオンライン納付です。あらかじめオンラインで申請すると、ネットバンキングによる納付ができるため、自宅などで申請から納付までの手続きを完了させられます。
しかし、相続登記のオンライン申請自体の難易度が高いこととマイナンバーカードやICカードリーダーの準備や事前登録などが必要となることがデメリットとしてあげられます。
登録免許税を計算するときに
よくある質問
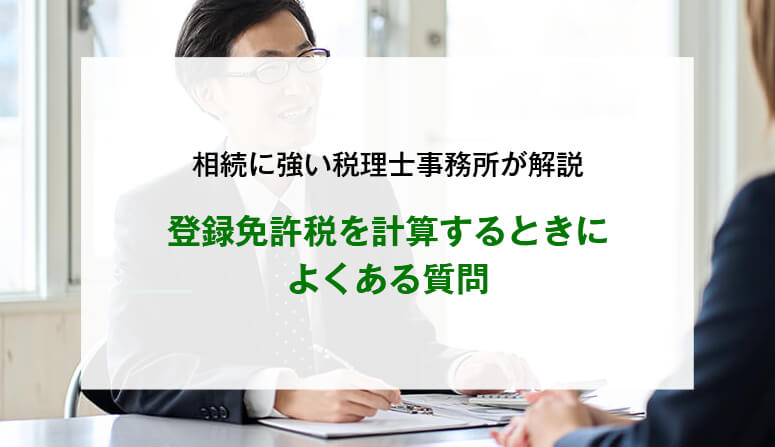
人生において相続は何度も発生するものではなく、相続登記の際に登録免許税の計算や納付方法で迷ってしまうこともあるでしょう。
本章では、登録免許税を計算するときによくある質問を回答と共に紹介していきます。
登録免許税は誰が支払うべきですか?
登録免許税は、登記申請を行う人が納付義務を負います。例えば、相続登記の場合、申請者は相続人であり、通常は不動産を取得する相続人がその費用を負担します。
ただし、遺産分割協議により「相続人全員で費用を分担する」と定めることも可能です。
例えば、遺された配偶者が被相続人の自宅を相続する場合、母親の負担を軽減するために子供たちが登録免許税を負担することも認められます。
登録免許税は遺産分割協議が未了でも課税されますか?
登録免許税の納付と遺産分割協議の完了には直接的な関係はありません。というのも、相続登記自体は遺産分割協議が完了していない状態でも行うことができるからです。
そして、相続登記を行う際には、相続不動産の評価額に応じた登録免許税がかかります。
相続登記を行わなければ登録免許税の納付は必要ないと考える方もいるかもしれませんが、2024年4月より相続登記が義務化され3年以内に登記申請をしないと過料が科される恐れもあるのでご注意ください。
登録免許税は経費として計上できますか?
個人の相続登記にかかる登録免許税は、原則として経費にはできません。相続登記は私的な財産の承継に伴う費用であり、事業所得や不動産所得を得るための必要経費には該当しないからです。
ただし、法人が事業用不動産を相続し、その所有権移転登記を行った場合には、法人税法上の損金として計上できるケースがあります。
共有名義の持分相続時の登録免許税の計算はどのようにすれば良いですか?
共有不動産を相続する場合には、持分ごとに評価額を按分して計算します。
例えば、固定資産税評価額が2,000万円の土地を兄弟2人で2分の1ずつ相続する場合、それぞれの持分評価額は1,000万円となり、各自が支払う登録免許税は「1,000万円 × 0.4% = 4万円」となります。
なお、申請をまとめて行う場合には、登記簿上の移転登記に必要な登録免許税を合算して納付します。
登録免許税の納付漏れやミスに気付いたらどうすれば良いですか?
納付漏れや計算ミスがあった場合、法務局から補正を求められることがあります。例えば、金額が不足している場合には追加で納付し、不足分に延滞税等が課される可能性もあります。
逆に多く納めすぎてしまった場合には、還付請求を行うことで返金を受けることができます。いずれの場合も、早めに法務局へ相談し、適切な対応を取ることが大切です。
仮登記や根抵当権の移転登記でも登録免許税は発生しますか?
仮登記や根抵当権の移転登記であっても、登録免許税法上の「登記」に該当するため、所定の税率が課されます。例えば、仮登記の所有権移転登記には、不動産の評価額に対して1%の税率が適用されます。
相続手続きは
当サポートセンターにおまかせください

相続登記をする際には、登録免許税を自分で計算しなければなりません。
登録免許税の計算式は「固定資産税評価額 × 0.4%」とそれほど難しくありませんが、相続不動産の固定資産税評価額を正確に把握することや複数不動産にまたがる計算は難しい場合もあるのでご注意ください。
相続登記をはじめとする様々な手続きは自分で行うだけでなく、専門家に依頼することも可能です。相続手続きは、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
相続登記における登録免許税は、「固定資産税評価額 × 0.4%」という計算式で算定されます。ただし、法定相続人以外が特定遺贈によって不動産を受け継いだ場合には、登録免許税が高額になるのでご注意ください。
登録免許税の納付方法は複数ありますが、収入印紙による納付が一般的です。また、相続登記は自分たちで行うだけでなく、司法書士に依頼することも可能です。
相続不動産が遠方にある場合や、手続きに不安がある場合には、相続に精通した司法書士に依頼しても良いでしょう。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ