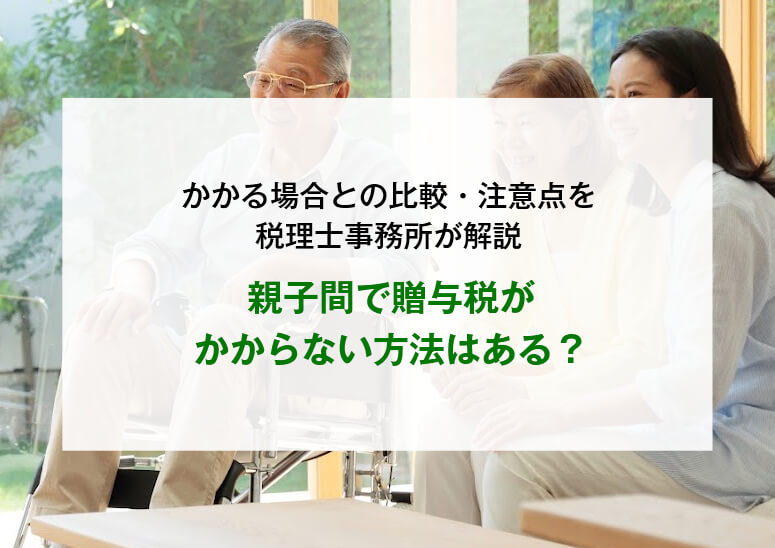
親子間で贈与税がかからない方法はある?かかる場合との比較・注意点を解説
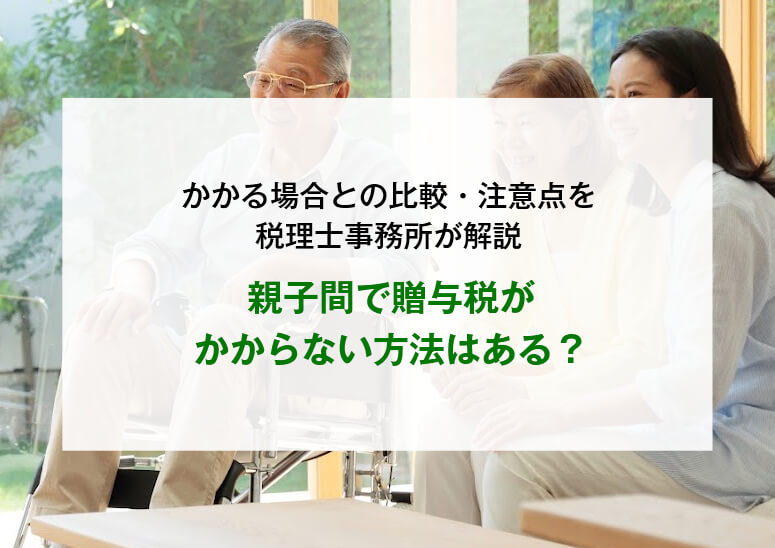
親子間での財産の受け渡しは、相続対策や生活支援の一環として多くの家庭で行われています。
しかし、贈与の方法やタイミングを誤ると、思わぬ贈与税が発生するリスクや、後々の税務調査で指摘されるリスクもあるので注意しなければなりません。
贈与税は年110万円の基礎控除(非課税枠)がある一方で、住宅取得資金や教育資金の贈与に使える特例制度も充実しているので、上手に活用していきましょう。
本記事では、贈与税がかからない方法や、かかるケース、控除・特例について解説していきます。
目次
親子間で贈与税がかからない方法

親子間で財産を移転する際、「贈与税がかかるのでは」と不安に感じる方は多いでしょう。確かに、年間110万円を超える贈与を受けると、贈与税が課せられる可能性があります。
関連サイト国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
一方で、下記のケースに該当する場合、贈与税はかかりません。
- 生活費・教育費目的の贈与
- 年間110万円以内の贈与
- 贈与税の控除・特例を利用した贈与
それぞれ詳しく解説していきます。
生活費・教育費目的の贈与
親子など扶養義務者間で生活費や教育費として贈与した財産には、税金がかかりません。
国税庁は、日常的に必要な生活費や教育費の贈与については、「通常必要と認められる範囲」であれば贈与税の課税対象としないと明示しています。
具体的には、下記などの贈与には、贈与税がかからないと判断しても良いでしょう。
- 仕送り
- 家賃
- 医療費
- 学費
- 教材費
一方で、生活費や教育費を贈与する場合でも、下記に該当すると贈与税の課税対象となる場合があります。
- 生活費や教育費として、一括で贈与を受けている
- 贈与財産が実際には、生活費や教育費として支出されていない
- 生活費や教育費として贈与された金額が高額すぎる
生活費や教育費を贈与する際に、贈与税がかけられることを防ぐには、必要な金額を都度贈与するようにしましょう。
年間110万円以内の贈与
親子間の贈与に限らず、年間110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。贈与税には、年間110万円の基礎控除が用意されているからです。
そのため、毎年110万円以内の範囲で贈与を繰り返せば、贈与税や将来発生するであろう相続税を節税できる可能性があります。
贈与税の控除・特例を利用した贈与
贈与税には、いくつか控除や特例が用意されており、利用すれば贈与税を大幅に節税可能です。
贈与税の控除や特例はそれぞれ適用要件が定められているので、利用したい場合には、税理士に相談してみることをおすすめします。
関連サイト国税庁「No.4405贈与税がかからない場合 」
親子間で贈与税がかかるケース
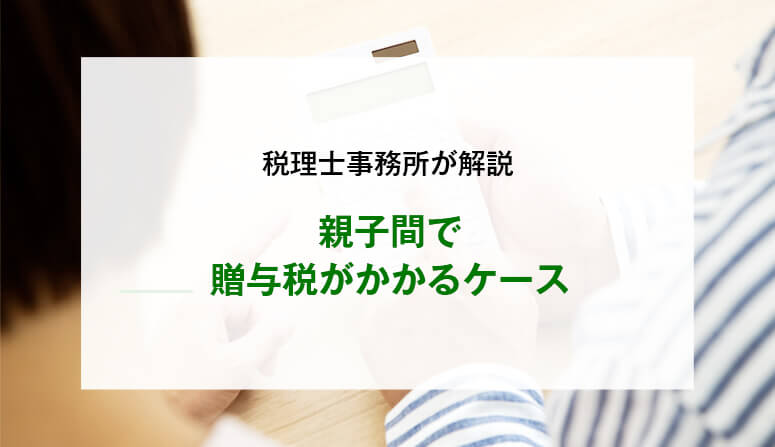
親子間でのお金や財産のやりとりは、家族内のこととして軽視されがちですが、贈与税がかかる場合もあるので注意しなければなりません。
また、資産を無償で譲渡していない場合でも、贈与税の課税対象となる場合もあります。親子間で贈与税がかかるケースは、主に下記の通りです。
- 年間110万円超えの贈与
- 借金を帳消しにしてもらう
- 住宅ローンなどの肩代わりを借金してもらう
- 親名義の不動産を子供名義に変更する
- 不動産・車などを安価で譲り受ける
それぞれ詳しく解説していきます。
年間110万円超えの贈与
年間110万円を超えると、贈与税がかかります。なお、贈与税は贈与をする側ではなく受ける側にかかる税金である点にも注意しなければなりません。
例えば、父親と母親の双方から100万円ずつ贈与を受けた場合、一人当たりの贈与額は110万円以下ですが、贈与財産の合計額は200万円となり、贈与税がかかる可能性があります。
借金を帳消しにしてもらう
親から子供がお金を借りていたものの、返済義務を免除してもらった場合にも、贈与税がかかる可能性があります。
借金の帳消しは資産こそ譲り受けていないものの、実質的には贈与として扱われるからです。
親子間の借金に対して贈与税がかからないようにするには、借用書を作成しておいたり、期日までに返済をしたりといった対策が必要となります。
関連サイト国税庁「No.4420 親から金銭を借りた場合 」
住宅ローンなどの肩代わりをしてもらう
子供が組んだ住宅ローンを、親が代わりに返済する行為も、贈与税の対象になります。親が支払った金額分の経済的利益を子供が受け取ったと考えられるからです。
よくあるケースが、住宅ローンの返済資金を親が定期的に子供の口座に振り込み、それを子供がローン返済に充てているパターンです。この場合も、贈与と見なされ、振り込み額が年間110万円を超えれば贈与税がかかる可能性があります。
なお、親が子供の住宅購入資金を援助したい場合、住宅取得等資金の贈与を利用できる場合があります。適用要件や贈与の手続きについては、贈与に精通した税理士に相談してみると良いでしょう。
関連サイト国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
親名義の不動産を子供名義に変更する
預貯金や現金などを親から子供に譲るだけでなく、不動産などの資産を譲ることも贈与税の課税対象となるのでご注意ください。
また、不動産を贈与する場合には、贈与税だけでなく、不動産取得税や登録免許税もかかります。
さらに、贈与による所有権移転登記では登録免許税の税率が高く、不動産取得税の軽減も受けられないケースが多いため注意が必要です。
不動産・車などを安価で譲り受ける
親が所有する不動産や自動車などを、著しく安い価格で譲り受けた場合、その差額部分が「みなし贈与」として課税される可能性があります。
例えば、時価1,000万円の不動産を100万円で譲り受けた場合、差額の900万円が贈与と評価される可能性があるので注意しなければなりません。
贈与税の節税目的で資産を安く子供に譲る場合、贈与税がかからないかどうかについて、一度税理士に相談しておくことを強くおすすめします。
関連サイト国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
親子で利用できる贈与税の控除・特例
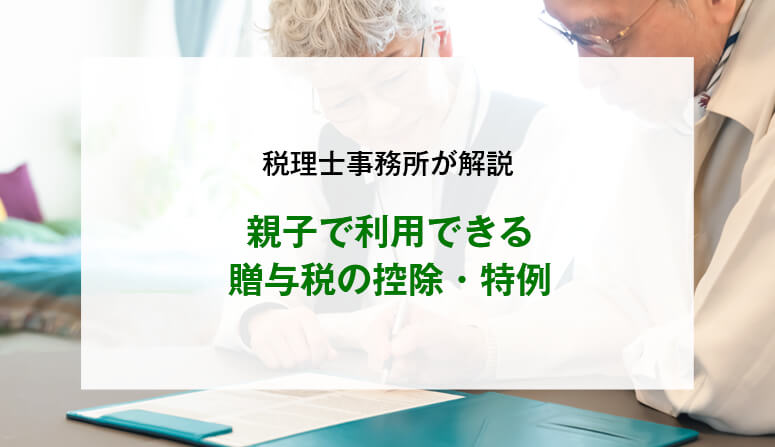
贈与税には控除や特例があり、利用すれば贈与税を大幅に節税できる可能性があります。代表的な控除や特例は、主に下記の通りです。
- 相続時精算課税制度
- 住宅取得等資金の贈与
- 教育資金の一括贈与
- 結婚・子育て資金の一括贈与
それぞれ詳しく解説していきます。
相続時精算課税制度とは
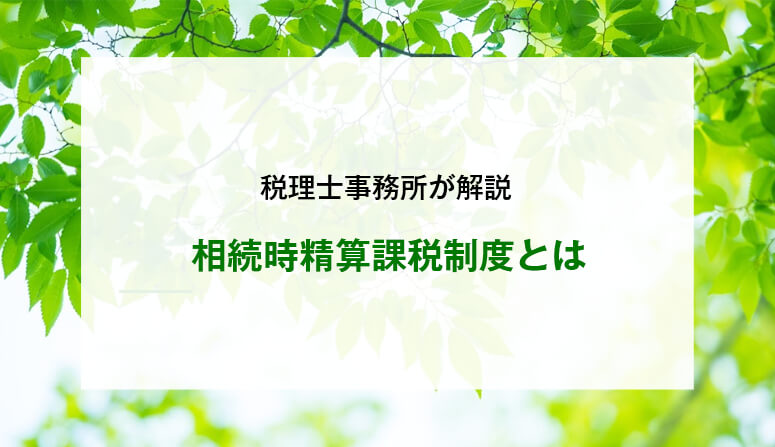
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親から18歳以上の子供(または孫)への贈与について、最大2,500万円まで非課税にできる制度です。2,500万円を超えた贈与については、贈与税が一律20%かかります。
ただし、相続時精算課税制度を利用して贈与をした場合、贈与者が亡くなると相続税の課税対象となります。2024年からは相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が追加され、課税対象から除外(申告不要)となり、より利用しやすくなったともいえるでしょう。
まとまった金額を贈与したい場合には、相続時精算課税制度の利用をご検討ください。
住宅取得等資金の贈与
マイホーム購入を支援する目的で設けられているのが「住宅取得等資金の贈与に係る非課税制度」です。
直系尊属(親や祖父母)からの住宅取得資金の贈与について、一定額まで贈与税が非課税となります。令和7年時点では、以下の非課税枠が設定されています。
| 省エネ等住宅 | 最大1,000万円 |
|---|---|
| 一般の住宅 | 最大500万円 |
制度を利用するには、受贈者の年齢や購入する住宅、住宅への入居日などの要件を満たす必要があるほか、期限内に贈与税の申告書を提出する必要があります。
利用したい場合には、不動産会社やハウスメーカー、税理士などに相談してみましょう。
教育資金の一括贈与
「教育資金の一括贈与」とは、子供や孫の教育にかかる費用を一括で贈与する場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。主に祖父母が資金提供者となることが多い制度ですが、親が提供者でも利用可能です。
対象となる教育費には、授業料や入学金といった学費だけでなく、塾や習い事費用なども含まれます。
ただし、教育資金の一括贈与を利用するには、銀行など金融機関にて専用口座を開設する必要があるなど手間がかかります。
親子間であれば、生活費や教育費の贈与については、そもそも非課税ですので、都度贈与では難しいのかを検討し、「金融機関の手続きや管理の手間」と「金額や目的」を踏まえて制度を利用すべきか判断するのが良いでしょう。
なお、この制度は期限付きの特例となっており、2026年3月31日までの贈与が対象となっています。
結婚・子育て資金の一括贈与
結婚・子育て資金の一括贈与は、結婚や出産、育児にかかる費用の援助を目的とした制度で、あり最大1,000万円までが非課税となります。
ただし、結婚費用の非課税枠は最大300万円となるので注意しましょう。
また、結婚・子育て資金の一括贈与についても、教育資金の一括贈与と同様に、金融機関にて専用口座を作成しなければなりません。
親子で贈与するときの注意点
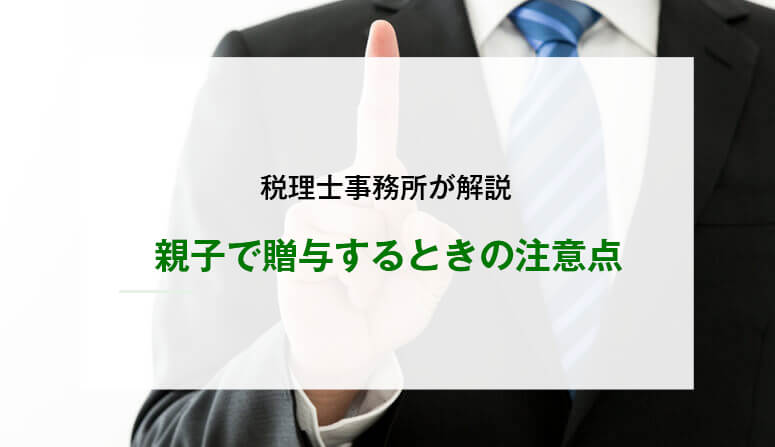
親子間での贈与は、相続対策や生活支援として非常に有効な手段ですが、税務上のリスクを理解せずに行うと、思わぬ税金やペナルティが発生することがあります。
特に、贈与をするときには、下記に注意しておきましょう。
- 贈与契約書を作成する
- 名義預金にならないようにする
- 定期贈与にならないようにする
- 贈与税の無申告・申告漏れは高確率でバレる
それぞれ詳しく解説していきます。
贈与契約書を作成する
親子間であっても、贈与契約書を必ず作成しましょう。贈与契約は口頭でも成立するものの、後々のトラブルを減らすためには、書面にて契約を交わすことが大切だからです。
名義預金にならないようにする
親名義の口座から子供の名義口座へお金を移すだけでは、税務署は「名義預金」として判断する可能性があります。これは、形式上は子供の口座でも、実際には親の資産として扱われてしまいます。
そのため、贈与税や相続税の節税目的で預貯金を贈与するのであれば、名義預金とならないようにしなければなりません。
定期贈与にならないようにする
「毎年100万円ずつ10年間あげるからね」といった約束をしてしまうと、それはあらかじめ贈与の総額や期間が決まっている契約である「定期贈与」と見なされ、初年度に10年分(1,000万円)を一括贈与したと判断されるリスクがあります。
贈与税の基礎控除を利用して、贈与税や相続税を節税しようと考えている場合、定期贈与にならないように税理士に相談した上で、贈与をすると良いでしょう。
贈与税の無申告・申告漏れは高確率でバレる
「親子間ならバレないだろう」「税務署は調べないだろう」と安易に考え、贈与を行うのは非常に危険です。
税務署は、個人の資産状況や収入状況をある程度把握しているため、親子であっても贈与を行うと税務署に知られてしまう可能性が高いからです。
特に以下のようなケースでは、贈与税の無申告・申告漏れが発覚しやすくなっています。
- 相続発生時に過去の資金移動が洗い出される
- 不動産購入時に名義と資金出所が異なることが発覚する
- 親名義の預金口座から子供の口座に不定期に高額入金されている
- 子供が収入に見合わない買い物をしている
贈与税の無申告が発覚すると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが科せられるので絶対にやめましょう。
生前贈与は
杉並・中野サポートセンターにお任せください

親子間であっても、贈与の方法によっては、贈与税がかかる場合があります。贈与税や相続税を節税したいのであれば、相続や生前贈与に詳しい税理士に相談するのがおすすめです。
相続税対策や贈与税の計算、申告は、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは、弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の生前贈与をワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
親子間の贈与は、正しく行えば贈与税を抑えつつ、資産をスムーズに移転できる有効な手段です。生活費や教育費などの非課税贈与、110万円以内の暦年贈与、各種特例の活用など、制度を理解して適切に利用することが重要です。
その一方で、名義預金や定期贈与など、形式を整えない贈与は後々トラブルの元になりかねません。
贈与契約書の作成や贈与税の正しい申告を徹底し、必要に応じて税理士などの専門家に相談しながら、将来を見据えた贈与を進めていきましょう。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ