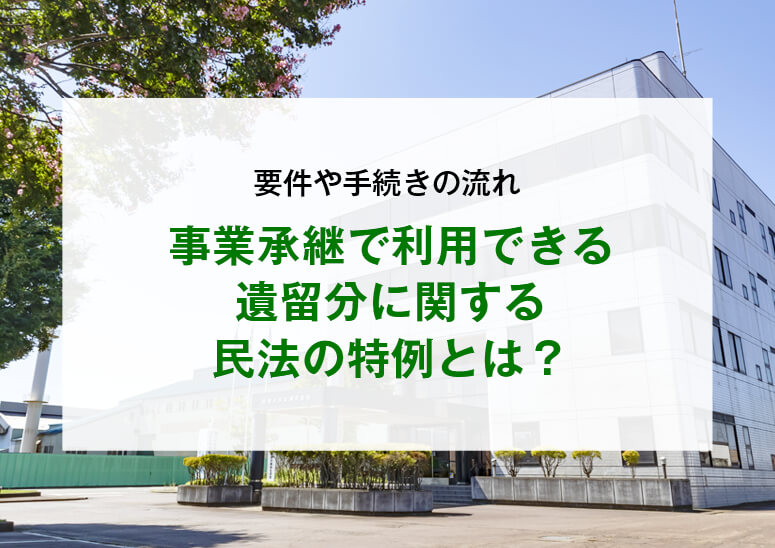
事業承継で利用できる遺留分に関する民法の特例とは?要件や手続きの流れ
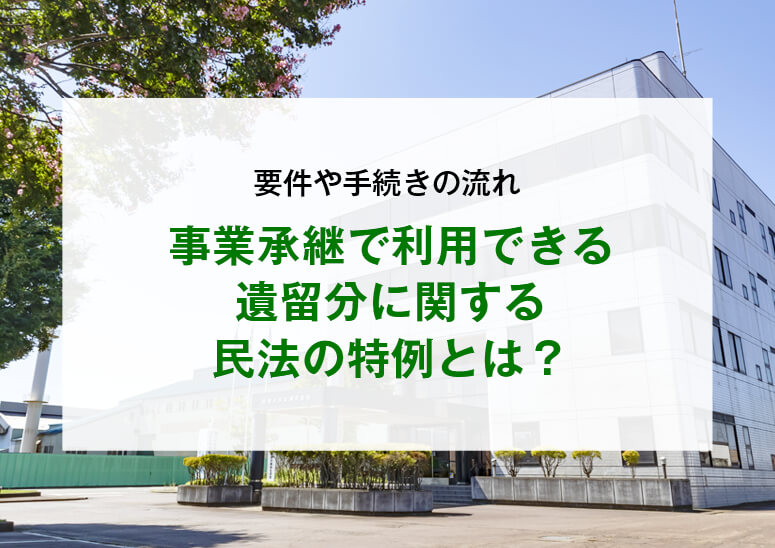
事業承継を行う場合、特定の相続人に自社株のほとんどを相続させるケースが多いです。そのため後継者の他に相続人がいる場合には、相続に偏りが生じてしまう場合もあるでしょう。
亡くなった方の配偶者や子供、両親には遺留分という相続を最低限度受けとれる権利があります。
しかし事業承継で遺留分を主張されると、事業を継続させるための十分な財産を後継者に遺せないかもしれません。
そのため事業承継を行うときには、他の相続人の理解を得ると同時に遺留分対策も進めておくのがおすすめです。
本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが事業承継とあわせて行う遺留分対策についてわかりやすく解説していきます。
目次
事業承継で遺留分トラブルが起きやすい理由

事業承継では遺留分トラブルが起きやすく注意が必要です。
「子供たちはそれぞれ仲が良いから大丈夫」「後継者選びに関して他の親戚も理解している」と安易に考えてしまうのは禁物です。
相続財産は自社株も含まれることに注意
被相続人が会社を経営している場合、相続財産の中には自社株も含まれます。会社の規模や事業内容にもよりますが、相続財産のほとんどを自社株が占めるケースもあるでしょう。
事業承継を行うときには、自社株をほとんど後継者に相続もしくは生前贈与するのが一般的です。
相続人が後継者1人だけの場合は良いですが、被相続人に子供が複数いる場合には「後継者だけ多額の相続をするのはずるい」と相続トラブルに発展しかねません。
兄弟姉妹以外の相続人は最低限度、遺産を受け取ることができる権利「遺留分」を持っています。自社株を相続した後継者に対し遺留分を主張されると、事業承継が計画通りに進まなくなってしまいます。
後継者の納税資金の確保も課題のひとつ
また相続の不公平感を減らすために、自社株を後継者に相続、預貯金や不動産を残りの相続人に相続させる場合も注意が必要です。
| 後継者 | 自社株 |
|---|---|
| 後継者以外の相続人 | 不動産や預貯金 |
不公平感は拭えるかもしれませんが、今度は後継者の納税資金確保が難しくなってしまいます。
自社株を相続した後継者が納税資金を用意できず、結果として自分の財産や事業に使用すべき財産の一部を手放さなければならないケースもあるからです。
このように事業承継を円滑に行うためには、他の相続人の遺留分に関しても考慮しながら計画、実行していかなければなりません。
事業承継で使える
遺留分に関する民法の特例とは

中小企業経営承継円滑化法では、事業承継時の遺留分に関しても定めています。中小企業経営承継円滑化法とは名前の通り、中小企業の事業承継を円滑に進めるために定めた法律です。
関連サイト中小企業庁「経営承継円滑化法による支援」
この法律の中で事業承継に関する相続の場合、他の法定相続人が同意していれば遺留分を減らせると定めています。
遺留分に関する民法の特例は除外合意と固定合意の2つの選択肢があります。それぞれ解説していきます。
除外合意
除外合意とは、後継者が相続もしくは生前贈与した自社株を相続財産から除外できる制度です。
後継者が相続した自社株に関しては他の相続人が遺留分を主張できなくなるので、後継者に自社株を集中させやすく事業承継を進めやすくなります。
固定合意
固定合意とは自社株を後継者に生前贈与させたときに使われる制度です。
原則として後継者に生前贈与させた自社株は、被相続人(先代経営者)が亡くなった時点で評価され相続財産に加えられます。
しかし、原則通りに自社株を評価すると以下の問題が浮上します。
- 後継者の経営努力によって自社株の評価額が上がってしまう
- 自社株の評価額が上がったことにより遺留分を主張されてしまう
- 生前贈与時にしていた遺留分対策が無駄になってしまう
固定合意を適用させれば、自社株は生前贈与されたタイミングで評価額が固定されます。
後継者の経営努力で自社株の評価額が相続時に高くなったとしても、遺留分対策に影響は出ないメリットがあります。
遺留分に関する民法の特例の適用要件

遺留分に関する民法の特例には様々な適用要件があります。それぞれ確認していきましょう。
会社の要件
遺留分に関する民法の特例を適用させる会社は「特例中小企業者」のみとなっています。特例中小企業者の条件は以下の通りです。
- 3年以上継続して事業を行っている
- 金融商品取引所に上場している株式を発行していない
- 店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行していない
先代経営者の要件
先代経営者は過去もしくは贈与時において会社の代表者であることが要件として定められています。
後継者が所有する株式に関する要件
先代経営者から自社株を譲り受ける前に、後継者が総株主の議決権の過半数を有していた場合には遺留分に関する民法の特例は適用できません。
特例を適用せず最終的に先代経営者から後継者に自社株が渡らなかったとしても、後継者が議決権の過半数を有しているので事業の継続に影響は出ないと考えられるからです。
遺留分に民法の特例を適用するための
流れ・必要書類

遺留分に民法の特例を適用する際には、所定の手続きを行う必要があります。それぞれ確認していきましょう。
推定相続人全員と後継者の合意を得る
まずは先代経営者の推定相続人全員で合意書を作成します。推定相続人全員というのは、遺留分の権利を持つ人物に限ります。合意書に決まったフォーマットはありませんが、以下の内容を記載しましょう。
- 会社の経営承継の円滑化のために合意すること
- 後継者が先代経営者から贈与された自社株式は遺留分の計算から除外する、もしくは遺留分の計算に算入する金額を固定する
- 後継者が代表者でなくなった場合に後継者以外が取れる措置
- 推定相続人間の公平をはかる措置
経済産業大臣に申請書を提出
合意をしてから1ヶ月以内に後継者は遺留分に関する民法の特例にかかる確認申請書と必要書類を経済産業大臣に提出します。主な必要書類は以下の通りです。
- 定款と株主名簿の写し
- 登記事項証明書
- 従業員数証明書
- 貸借対照表と損益計算書
- 上場会社でない旨の誓約書
- 印鑑証明書
- 現在の経営者と推定相続人全員と後継者の戸籍謄本
- 税理士などの証明書
税理士の証明書は贈与した自社株式を遺留分の計算算入時に固定してしまう「固定合意」の場合にのみ必要です。
家庭裁判所の許可を得る
経済産業大臣から確認所の交付を受けた後に、確認を受けた日から1ヶ月以内に家庭裁判所に申立書を提出し、許可を得ます。
家庭裁判所では推定相続人と後継者が遺留分に関する民法の特例に同意しているのかを主に判断します。
遺留分に関する民法の特例を
適用できないときの対処法

本記事ですでに解説したように、遺留分に関する民法の特例は推定相続人と後継者全員の合意が必要です。誰か1人でも合意しない場合には特例を適用することはできません。
遺留分に関する民法の特例を適用できないときには、別の方法による遺留分対策を考えておきましょう。
遺留分に配慮した遺言書を作成する
遺言書がある場合の相続は、原則として遺言書に書かれた内容に基づき行われます。
しかし遺言書の内容が遺留分を侵害している場合には、相続人が遺留分侵害額請求権を行使可能です。
遺留分侵害額請求権を行使されてしまうと、せっかく相続トラブルを回避するために遺言書を作成したとしても別の問題が発生してしまいます。
遺言書を作成するときには、相続人の遺留分を侵害しない内容で作成しておくのが良いでしょう。
自社株の評価額引き下げ後に生前贈与をする
後継者と先代経営者の関係が円滑であれば、自社株の評価額引き下げをした後に生前贈与してしまうのも有効です。
- 評価引き下げ後の自社株なので評価額が低く税負担が軽い
- 非上場企業の自社株の評価は比較的操作しやすい
上記が理由です。後継者と先代経営者の関係が円滑であれば、後継者が自社株を受け継いだ後も実質的な経営権はこれまで通り先代経営者が握り続けることも可能です。
受取人を後継者にした生命保険をかける
相続人に遺留分侵害額請求権を行使されることを見越して、後継者のために現金を用意しておくのも遺留分対策として有効です。生命保険金は遺産分割協議の対象になりません。
- 生命保険金の受取人を後継者にする
- 自社株を後継者に相続させる
- 他の相続人が遺留分侵害額請求権を行使したら保険金を使って遺留分を支払う
上記の流れで自社株を後継者に受け継ぎつつ遺留分トラブルも回避できます。
遺留分の権利を持つ方と相談しておく
具体的な対策とは少し異なりますが、先代経営者が何度も推定相続人と話をしておくのも遺留分対策に繋がります。
繊細経営者と後継者、推定相続人の関係が円滑であればあるほど、将来の遺留分トラブルも回避しやすいです。関係が円滑であれば相続人が自分の意思で相続発生時に遺留分を放棄してくれるかもしれません。
事業承継や相続対策は
当サポートセンターにお任せください

遺留分に関する民法の特例は、事業承継における遺留分対策に有効な手段のひとつです。
しかし適用要件を満たしているか、相続人の合意を得られるかなど適用までのハードルが高い特例でもあります。
更に事業承継を行うのであれば、遺留分対策だけでなく事業承継税制などを含め様々な対策を取る必要があるでしょう。
事業承継にお悩みの方は、事業承継を専門に取り扱う税理士や弁護士などの専門家にご相談ください。
杉並・中野相続サポートセンターでも事業承継に関する相談を受け付けております。当サポートセンターの対応エリアは下記の通りです。
当サポートセンター・対応エリア
初回利用者向けの無料相談も行っておりますので、まずは一度、お気軽にお問い合わせくださいませ。
まとめ
中小企業の経営者の相続財産は自社株が占める割合が非常に高いです。後継者に自社株のほとんどを相続させようとすると、相続人間で遺産分割に偏りが生じてしまいます。
それにより相続人が遺留分侵害額請求権を行使するケースがあります。事業承継の遺留分対策には、遺留分に関する民法の特例を適用するのがおすすめです。
適用要件の確認や書類の準備に手間がかかるので、特例を適用する際には弁護士や税理士などの専門家に相談することもご検討ください。











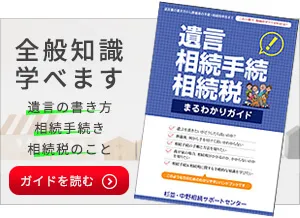
 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ