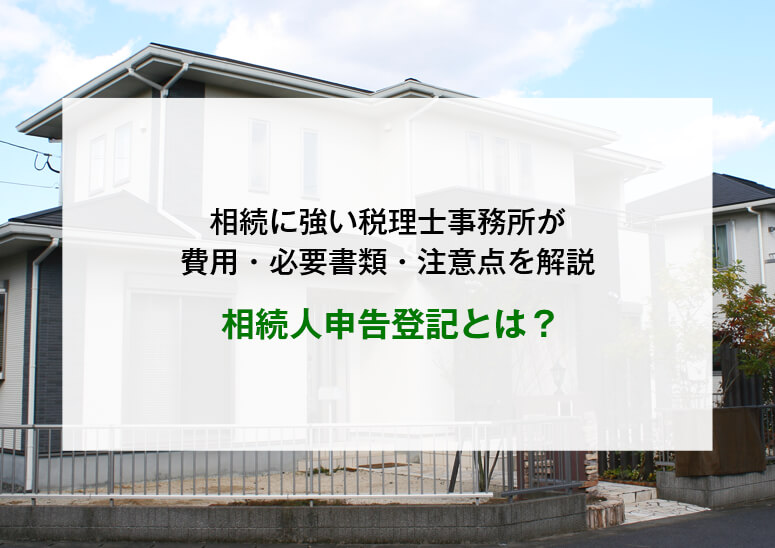
相続人申告登記とは?費用・必要書類・注意点を解説
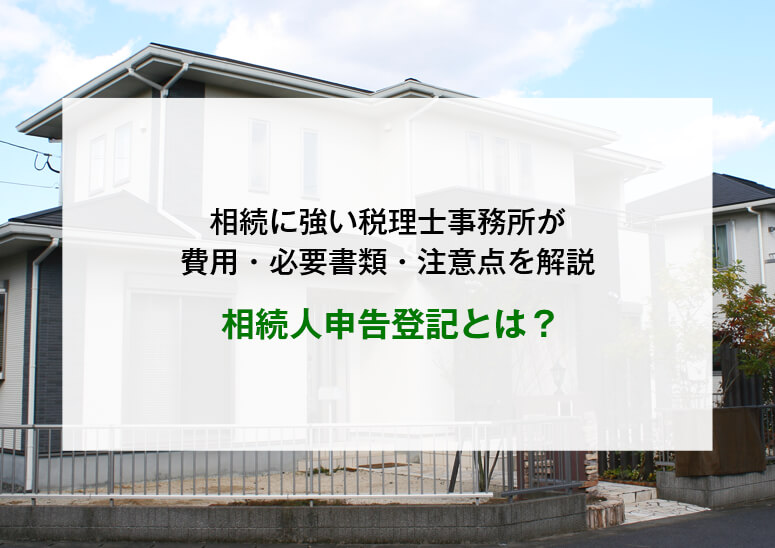
2024年4月の法改正により導入された相続人申告登記は、相続不動産をめぐる登記義務を簡便に果たせる新しい制度です。
関連サイト法務省「相続人申告登記について」
従来の相続登記とは異なり、所有権移転までは行わず、相続人である旨を申告するだけで義務履行とみなされます。遺産分割がまとまらず相続登記をすぐに行えない場合には、相続人申告登記を行っておきましょう。
本記事では、相続人申告登記とは何か、手続き方法について解説します。
目次
相続人申告登記とは
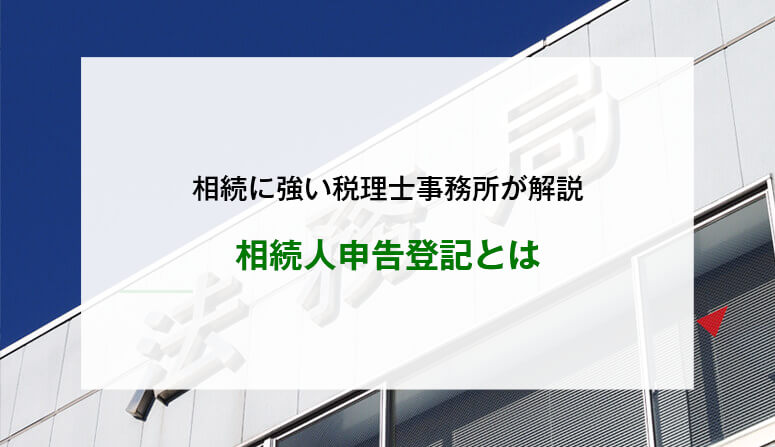
相続人申告登記とは、2024年4月から相続登記が義務化されたことにより新設された制度です。
被相続人から不動産を受け継いだ場合、相続登記をする必要がありますが、先祖代々にわたり名義変更されていない場合や遺産分割協議がまとまらない場合には、すぐに相続登記を行えないこともあります。
そのようなケースでは、相続人申告登記を行うことで、相続登記の義務違反による過料を避けることが可能です。相続人申告登記を行えば、自分が不動産を相続したことと自分が相続人であることを示せます。
ただし、相続人申告登記は正式な登記申請ではないので、相続人申告登記だけでは相続不動産の活用や売却をすることはできません。
相続人申告登記と相続登記の違い
相続登記は、相続人が被相続人から不動産の権利を正式に承継し、登記簿上の名義を変更する手続きです。遺産分割協議や遺言の内容に基づいて、具体的な相続人と持分割合が記録され、相続不動産の活用や売却、担保設定も可能になります。
一方、相続人申告登記は、あくまで「私はこの不動産の相続人です」と申告するだけの制度です。
自分が不動産を相続したことや自分が相続人であることの証明はできるものの、所有権の移転までは行われません。そのため、遺産分割が終わった段階で改めて相続登記を行わなければなりません。
つまり、相続人申告登記は、相続登記の義務の履行という観点では役割を果たせますが、権利関係を明確にするという本来の登記機能までは及びません。
相続人申告登記は、何らかの理由により期限までに相続登記を行えない方が行っておく手続きであると理解しておきましょう。
相続人申告登記の対象となる
人物・不動産
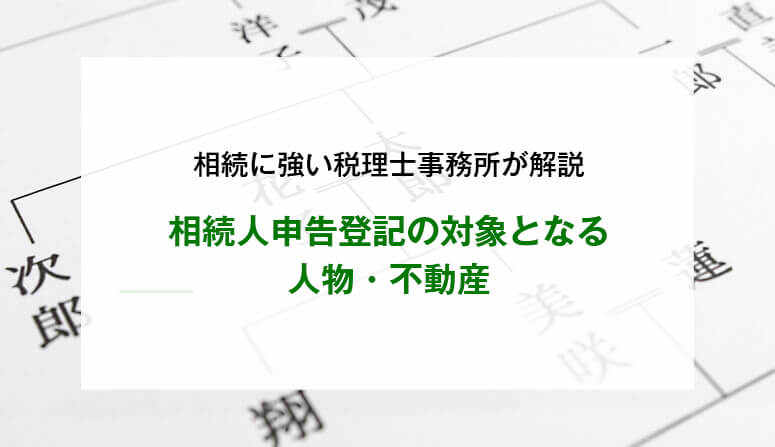
相続人申告登記は誰でも利用できるわけではなく、対象となる人物や不動産が定められています。それぞれ詳しく解説していきます。
相続人申告登記の対象となる人物
相続人申告登記の対象となるのは、被相続人の法定相続人または遺言により相続人となった人です。具体的には、配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹など民法で定められた相続人などが該当します。
一方で、被相続人から特定の財産を「遺贈」により取得する受遺者(法定相続人でない第三者)は、原則として相続人申告登記の対象とはなりません。
また、相続放棄が家庭裁判所で受理されている人はそもそも相続人ではないため、相続人申告登記の対象外です。
関連サイト法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」
なお、相続登記と異なり、相続人申告登記は相続人の1人が単独で手続き可能です。例えば、兄弟3人が相続人の場合、まず長男だけが相続人申告登記を済ませ、のちに次男・三男がそれぞれ追加で申告登記を行うことも可能です。
相続人申告登記の対象となる不動産
相続人申告登記の対象となる不動産は、不動産登記簿に記録されている土地や建物などの不動産であり、所在地の法務局に対して申告を行います。対象となる不動産は、宅地や建物だけでなく、山林や農地なども含まれます。
関連サイト一般財団法人民事法務協会「登記情報提供サービス」
ただし、被相続人が所有していない不動産や、すでに他人名義に移転済みの不動産については申告できません。
また、借地権や借家権などの権利関係は相続人申告登記制度の対象外であり、取り扱いできない点も理解しておきましょう。
相続人申告登記をする
メリット・デメリット
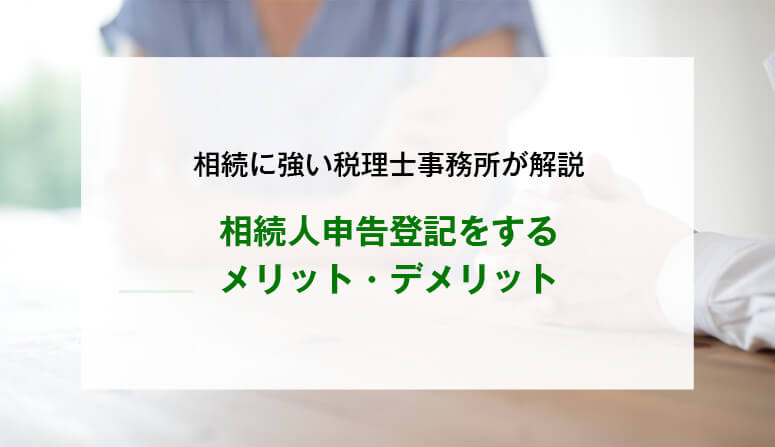
相続人申告登記をすれば、相続登記の義務を果たせるため、過料が課せられることはなくなります。一方で、相続人申告登記のみでは、相続不動産の活用や売却はできないのでご注意ください。
本章では、相続人申告登記のメリットやデメリットを解説します。
相続人申告登記をするメリット
相続人申告登記の最大のメリットは、相続登記の義務を簡易に果たせる点です。2024年4月以降、相続不動産については3年以内に登記を行う義務が課せられています。
しかし、遺産分割協議がまとまらなかったり、先祖代々にわたり相続登記が行われておらず権利関係が複雑だったりする場合もあるでしょう。
このようなケースでも、相続人申告登記を済ませれば、義務不履行による過料を回避できます。また、相続人申告登記は相続登記と比較して手続きがシンプルであり、費用もかかりません。
相続人申告登記をするデメリット
相続人申告登記は正式な登記申請ではないため、それ自体では所有権の移転は完了しません。
相続人申告登記は、あくまで「相続人である」という事実を登記簿に記載するだけであり、実際の名義変更は行われないのでご注意ください。
そのため、相続人申告登記のみでは、相続不動産を売却したり担保提供したりすることはできず、結局は相続登記を別途行わなければなりません。
また、相続人が複数いる場合は、それぞれの相続人が手続きしなければ、義務違反による過料を回避できない点にも注意する必要があります。
関連サイト法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
相続人申告登記の
手続き方法・必要書類
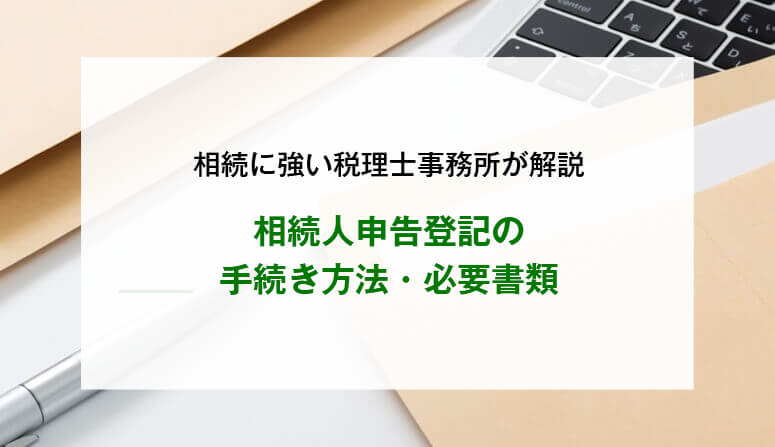
相続人申告登記の手続きは、相続不動産の所在地を管轄する法務局で行います。郵送でも申請可能ですが、不備があると補正を求められるため、事前に管轄法務局で相談するのが安心です。
手続きの大まかな流れは、以下の通りです。
- 戸籍の収集
- 申請書の作成
- 法務局へ提出
相続人申告登記をする際には、被相続人の除籍謄本や自分が相続人であると証明できる戸籍謄本類などが必要となります。
また、相続不動産に関する情報も必要となるので、登記事項証明書なども用意しておきましょう。
関連サイト法務局「各種証明書請求手続」
相続人申告登記にかかる費用
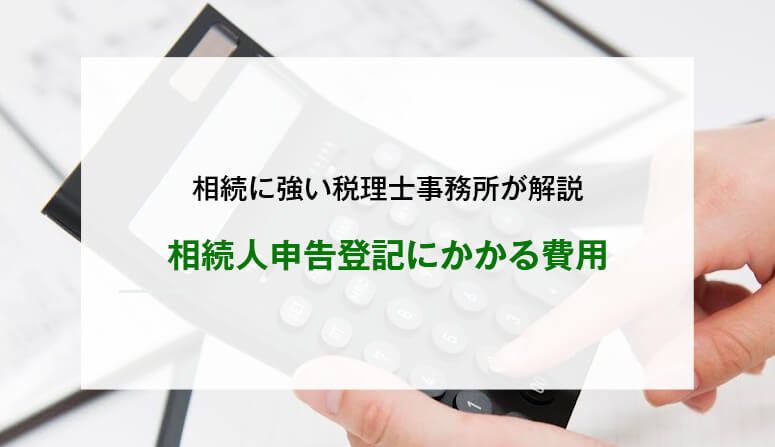
相続人申告登記は、相続登記の義務を簡便に果たすための制度として導入されたもので、手続き時に登録免許税はかかりません。
ただし、手続きの際に、戸籍謄本類を収集する必要があるため、それらの収集費用は数千円程度かかるでしょう。
また、相続人申告登記だけでは所有権が移転しないため、将来的に相続登記を行う際には登録免許税がかかります。
相続人申告登記についてよくある質問
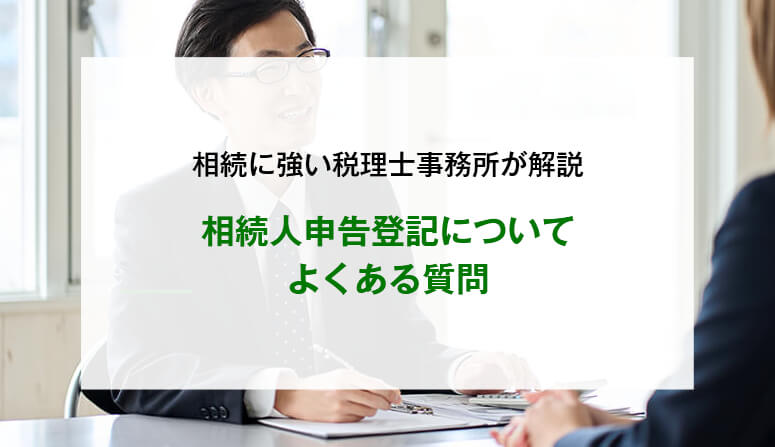
最後に、相続人申告登記についてよくある質問を回答と共に紹介していきます。
いつまでに相続人申告登記をすればよいですか?
相続人申告登記は、相続の開始から3年以内に行う必要があります。ただし、期限までに相続登記を済ませられるのであれば、相続人申告登記はする必要がありません。
相続人が複数いる場合にはまとめて申請できますか?
相続人が複数いる場合、全員が一度にまとめて申請することもできますし、それぞれ個別に申請することも可能です。また費用は掛かりますが、弁護士、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
ただし、1人の相続人が申告登記をしただけでは、残りの相続人は相続登記の義務を果たしたことにならないのでご注意ください。
相続登記をしないと不動産の売却はできませんか?
相続人申告登記をしていても、正式な相続登記をしなければ不動産の売却はできません。
申告登記はあくまで「相続人である」という事実を登記簿に記載するだけであり、所有権の移転は行われないからです。
相続放棄した人も相続人申告登記が必要ですか?
相続放棄をした方は家庭裁判所で相続放棄が受理されれば、最初から相続人ではなかったことになります。そのため、相続人申告登記を行う必要はありません。
相続手続きは
当サポートセンターにお任せください

相続人申告登記をすれば相続登記の義務化違反を回避できるので、何らかの理由で相続登記が難しい方は、申告登記だけでも行っておきましょう。
ただし、相続人申告登記のみでは相続不動産の所有権までは移転されないため、最終的には相続登記を完了させる必要があります。
相続手続きは複数あり、専門的な知識や経験が求められる場合もあるため、自分たちで行うことが難しい場合には、専門家に相談することも検討しましょう。
相続手続きは相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
相続人申告登記は、相続登記の義務を果たせる制度として注目されています。相続登記できない事情がある場合には、期限内に相続人申告登記だけでもしておきましょう。
ただし、相続人申告登記では、所有権の移転はされないため、相続不動産の売却や担保設定には相続登記をしなければなりません。
相続人申告登記は、あくまで暫定的な制度と理解し、最終的には遺産分割協議の成立を経て正式な相続登記を行うことが重要です。
遺産分割協議が整わない場合には、専門家に相談してみることも検討してみましょう。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ