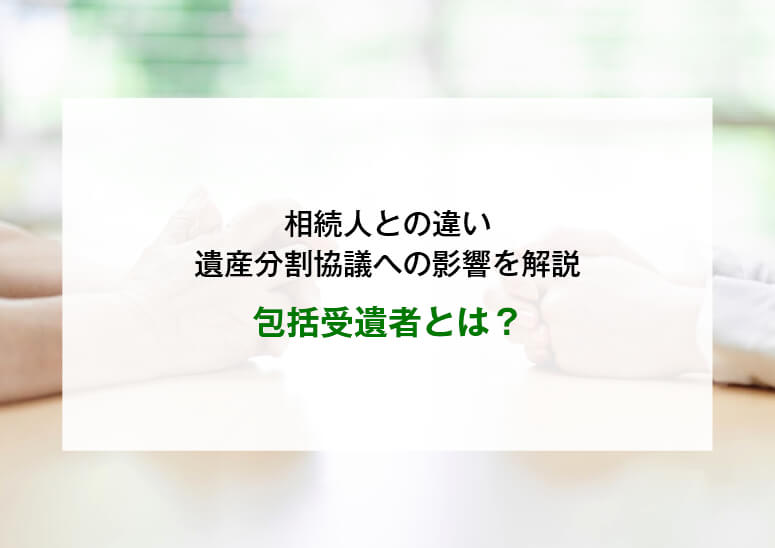
包括受遺者とは?相続人との違い・遺産分割協議への影響を解説
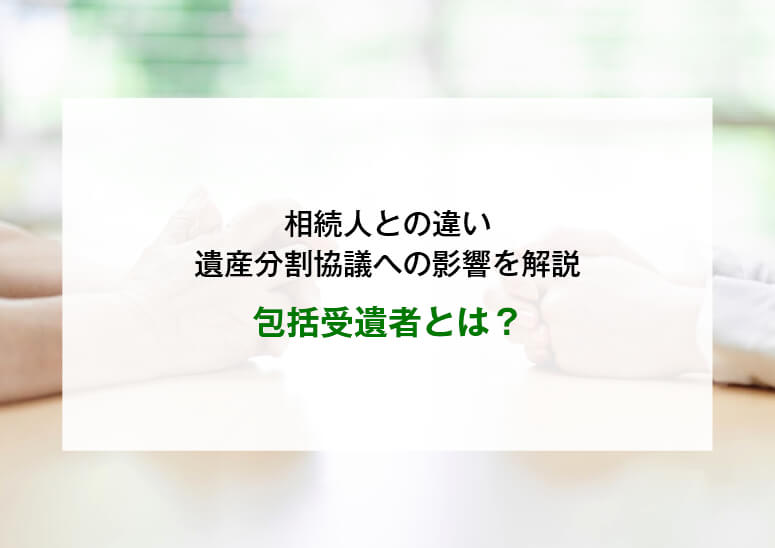
遺言によって財産を受け継ぐ「受遺者」の中でも、相続人に近い立場を持つのが「包括受遺者」です。包括受遺者は、財産全体や一定割合を承継できる一方で、借金などの債務も引き継ぐ可能性がある点が特徴です。
また、包括受遺者はどの遺産を受け継ぐかは指定されていないので、他の相続人と同様に遺産分割協議に参加しなければなりません。
本記事では、包括受遺者とは何か、メリット・デメリットや相続手続きの注意点を解説します。
目次
包括受遺者とは
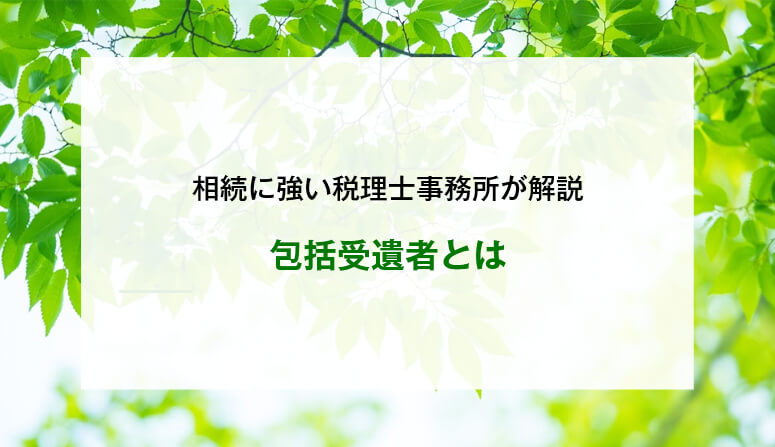
包括受遺者とは、遺言によって被相続人の財産全体、またはその一定の割合を包括的に承継する人です。例えば、「全財産の2分の1をAに遺贈する」と記載されていれば、Aさんは包括受遺者となります。
つまり、包括受遺者は「財産の割合」で指定される点が特徴です。包括受遺者は、相続人とほぼ同じ地位を持ち、借金のような相続債務も承継することになります。
なお、被相続人の借金の返済義務を受け継ぎたくない場合には、相続放棄のように家庭裁判所に対して「遺贈の放棄」の申述をすることができます。
包括受遺者と相続人の違い
包括受遺者と相続人は、どちらも「遺産を包括的に承継する」という点で共通しています。しかし、両者は、法的な根拠と承継の仕組みに違いがあります。
相続人は、民法で定められた法定相続人であり、被相続人の配偶者や子供、両親、兄弟姉妹などが順位に応じて相続権を持ちます。
一方、包括受遺者は、遺言によって指定された人であり、法定相続人でなくてもなることが可能です。例えば、親族以外の友人や団体が包括受遺者として遺言により遺贈を受けられます。
また、相続人だけでなく、包括受遺者も相続人と同等の権利義務を持つため、遺産分割協議に加わる立場になります。ただし、包括受遺者には「遺留分」は認められません。遺留分を主張できるのは法定相続人のみです。
包括受遺者と特定受遺者の違い
特定受遺者とは、遺言において「自宅の土地をBに与える」「預金口座の残高をCに遺贈する」といったように、特定の財産を個別に承継する人です。
包括受遺者が財産の「割合」を承継するのに対し、特定受遺者は財産の「個別の対象物」を承継する点が大きな違いといえるでしょう。
特定受遺者は、承継する財産を具体的に指定されるため、被相続人の借金の返済義務を負うことはありません。一方、包括受遺者は相続人と同じように債務も引き継ぐので注意しなければなりません。
相続手続きについて言えば、特定受遺者は遺産分割協議に参加する必要がないのに対し、包括受遺者は相続人と同様に遺産分割協議に参加する必要があります。
包括受遺者の種類
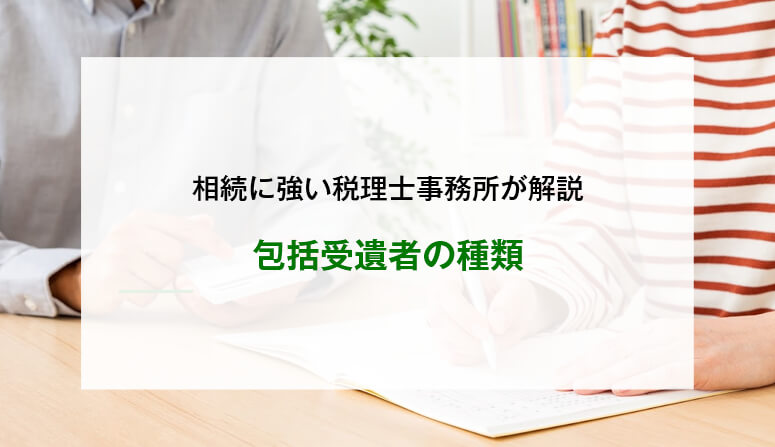
包括受遺者は、遺言の書き方によっていくつかの種類に分けられます。ここでは代表的な4つの類型をご紹介します。
全部包括受遺者
全部包括受遺者とは、被相続人が所有していた財産を一切合切すべて承継する立場の人を指します。遺言で「私の全財産を妻に遺贈する」と記載されていれば、妻は全部包括受遺者になります。
割合的包括受遺者
割合的包括受遺者とは、遺産の「一定の割合」を承継するように指定された受遺者です。例えば、「全財産の3分の1を長女に遺贈する」といった場合がこれに該当します。
特定財産を除いた財産についての包括受遺者
遺言の中には「自宅不動産を次男に与える。その他の財産はすべて長女に与える」といったように、特定の財産を誰かに個別に遺贈した上で、それ以外の財産を包括的に承継させる形が見られます。この場合の長女は「特定財産を除いた財産についての包括受遺者」となります。
清算型包括受遺者
清算型包括受遺者とは、被相続人の債務を弁済した上で、残余財産を承継する立場に置かれる受遺者です。例えば「私の全財産をもって債務を弁済し、その残りを甥に遺贈する」といった遺言が典型例です。
包括受遺者が承継する権利と義務とは?
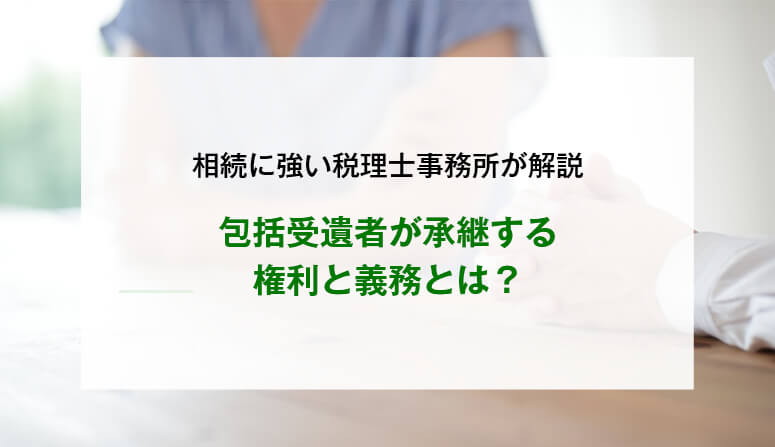
包括受遺者は、遺言によって被相続人の財産を包括的に承継する立場となります。そのため、相続人に近い立場で多くの権利を持つと共に、義務を負担しなければならないのでご注意ください。
包括受遺者が承継する権利と義務について詳しく見ていきましょう。
包括受遺者が承継する権利
以下のように、包括受遺者は、相続人と同様に被相続人の財産に対する様々な権利を承継します。
- 遺産全体または割合に応じた承継権
- 遺産分割協議への参加権
- 相続回復請求権や占有回収の権利
包括受遺者が承継する義務
一方で、包括受遺者は権利だけでなく、様々な義務も負担するので注意しなければなりません。包括受遺者が受け継ぐ主な義務は、以下の通りです。
- 債務の承継義務
- 遺産管理義務
- 相続税申告・納付義務
遺言で包括受遺者を指定する
メリット・デメリット
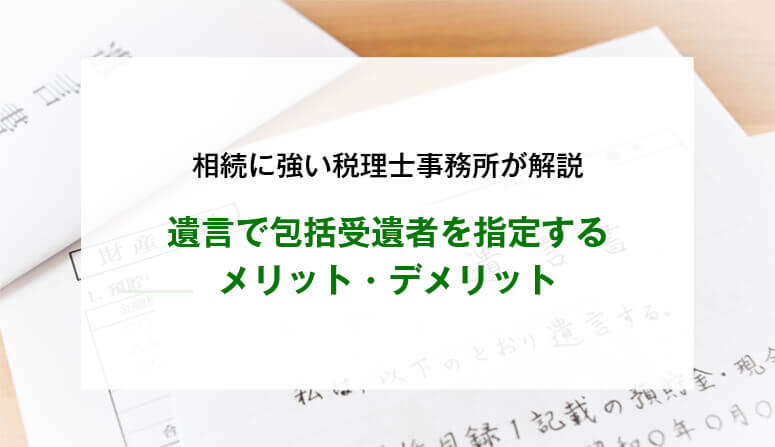
遺言にて、包括受遺者を指定すれば、相続人に近い権利義務を持たせることができます。ただし、包括受遺者を指定することにはメリットだけでなく、デメリットがあるので、理解しておくことが大切です。
包括受遺者を指定するメリット
遺言で包括受遺者を指定するメリットは、主に以下の通りです。
- 財産を包括的に承継できる
- 相続人以外にも承継させられる
- 遺産分割協議に参加できる
包括受遺者を指定するデメリット
遺言で包括受遺者を指定するデメリットは、主に以下の通りです。
- 債務も引き継ぐリスクがある
- 放棄の手続きが必要になることがある
- 遺産分割協議が複雑化する可能性がある
包括受遺者を指定すべきか迷った場合や、希望の人物に遺産を承継させたい場合には、相続に詳しい専門家に相談することも検討しましょう。
包括受遺者が遺産分割協議に参加できる?
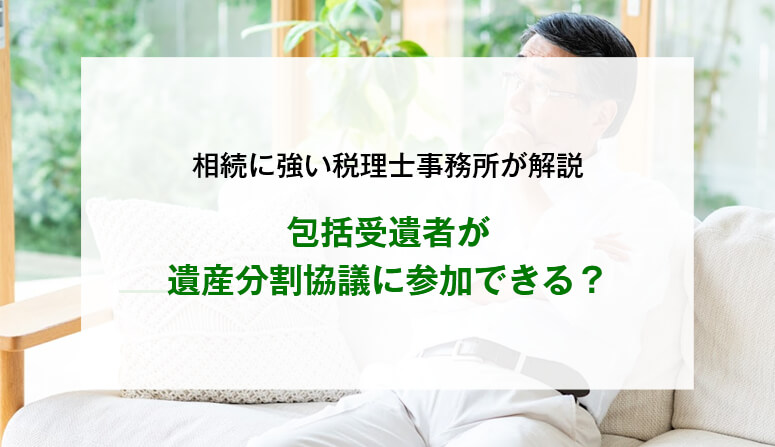
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の具体的な分配方法を決定する話し合いです。
相続人全員が参加する必要がありますが、遺言によって指定された包括受遺者も「相続人に準じた立場」として扱われるため、遺産分割協議に参加しなければならない場合があります。
包括受遺者が遺産分割協議に参加できるケース
遺言にて遺産の承継割合のみを指定されていた場合には、包括受遺者も遺産分割協議に参加する必要があります。
包括受遺者が遺産分割協議に参加できないケース
包括受遺者が遺贈の放棄をした場合や、「特定財産を除いた残余を承継する」といったように具体的かつ明確にに承継する財産が指定されている場合には、遺産分割協議に参加する必要はありません。
包括受遺者が遺産を受け継ぐときの注意点
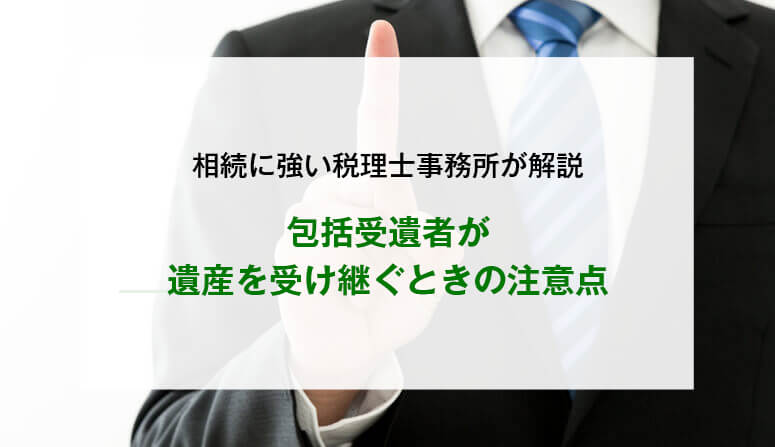
包括受遺者は、遺言によって財産を包括的に承継するという特徴を持ち、相続人に近い権利と義務を負います。そのため、遺産を受け継ぐ際には相続税の負担や借金の承継などに注意しなければなりません。
包括受遺者が遺産を受け継ぐときの注意点について、詳しく見ていきましょう。
相続税が2割加算される恐れがある
包括受遺者が相続税を申告する際、税額が通常より2割加算されるケースがあります。
被相続人の配偶者や子供、両親以外の人物が遺産を取得したときには、相続税額が2割加算されると決められているからです。
例えば、被相続人が長年世話になった友人を包括受遺者に指定した場合、その友人が受け取る遺産には相続税が課せられ、さらに算出された税額に2割が上乗せされます。
関連サイト国税庁「No.4157 相続税額の2割加算」
被相続人の借金を受け継ぐ恐れがある
包括受遺者は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も承継する点に注意が必要です。被相続人が生前に抱えていた借金、未払いの税金、連帯保証債務なども承継の対象に含まれます。
そのため、包括受遺者と指定されていた場合には、相続財産調査をしてプラスの遺産とマイナスの遺産がいくらあるかを確認した上で承継の可否を検討しなければなりません。
包括受遺者に遺留分は認められない
包括受遺者は相続人に準じた権利と義務を持つものの、遺留分は認められないのでご注意ください。遺留分とは、配偶者や子供など一定の法定相続人に保障されている最低限の取り分です。
また、包括受遺者が遺言で大きな割合を承継することになった場合、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性もあると理解しておきましょう。
相続税申告は
当サポートセンターにお任せください

包括受遺者は被相続人が指定した割合で遺産を相続できるものの、遺産管理義務や借金の返済義務も受け継いでしまいます。
また、被相続人と包括受遺者の関係によっては、相続税が2割加算され、相続税の負担が重くなってしまう点に注意しなければなりません。
相続税申告をミスなくこなしたい場合や、相続税の節税対策をしたい場合には、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
包括受遺者は、相続人に準じた強い権利を持ちながらも、同時に大きな義務やリスクを負う存在です。
特に、包括受遺者は被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も受け継いでしまう点に注意しなければなりません。
また遺言内容によっては、他の相続人の遺留分を侵害する恐れもあるので、遺言書を作成する段階で相続に精通した専門家に相談するのが良いでしょう。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ