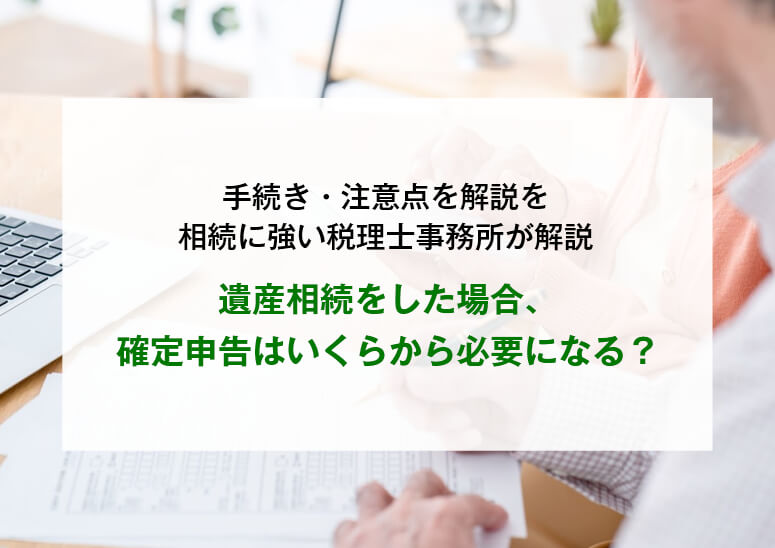
遺産相続をした場合、確定申告はいくらから必要になる?手続き・注意点を解説
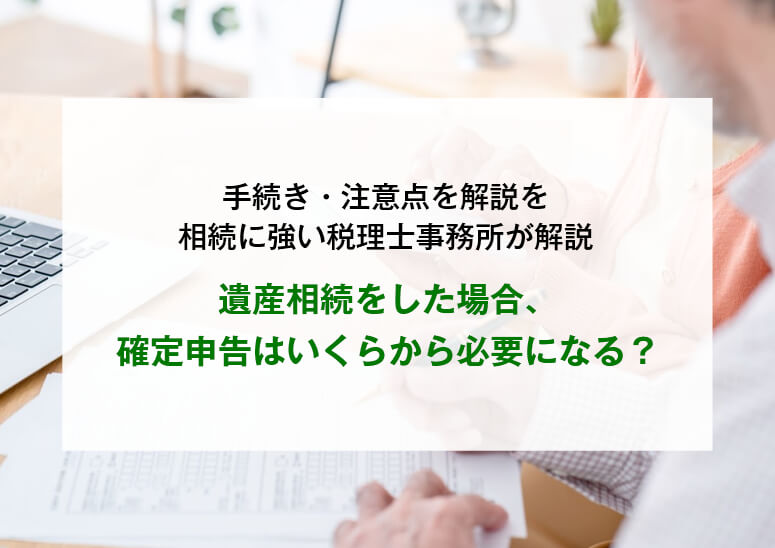
遺産相続に直面すると、「確定申告は必要なのか」「相続税の申告はいつまでに行うのか」など、税金に関する疑問が多く浮かぶはずです。
相続財産を受け取っただけでは、確定申告は不要ですが、相続後に不動産の売却や賃貸収入がある場合などは申告義務が発生することもあります。
また、遺産の金額によっては、相続税申告が必要になりますし、被相続人に事業所得や不動産所得がある場合には、準確定申告が必要となるのでご注意ください。
本記事では、遺産を相続すると確定申告が必要なのか、他にどんな申告が必要なのかをわかりやすく解説します。
目次
遺産相続では
確定申告は原則として必要ない
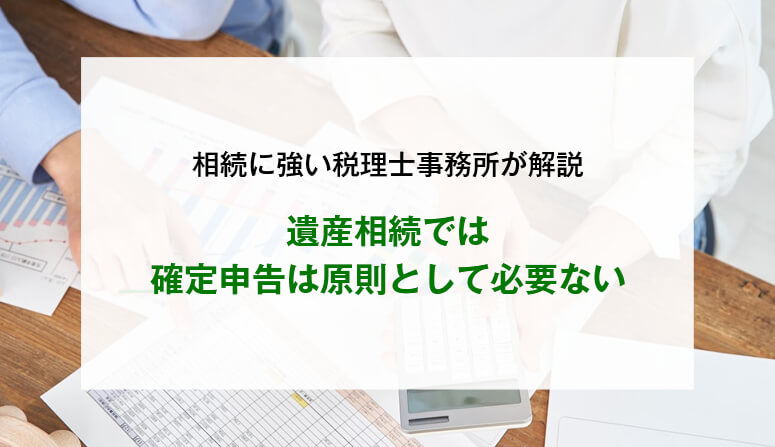
遺産としてまとまった資産を相続すると、確定申告が必要だろうかと不安になる方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、遺産相続そのものに対して確定申告は原則として必要ありません。なぜなら、遺産として相続する現金や預貯金、不動産、株式などは「所得」ではなく「相続財産」として扱われるためです。
本章では、遺産相続があったときの税金の申告について解説していきます。
確定申告で計算・申告するのは所得税
確定申告は、個人が1年間に得た所得を計算し、所得税を申告・納税するための手続きです。
会社員であれば年末調整によって所得税が精算されるため、医療費控除やふるさと納税などの還付申告を除き、原則として確定申告を行う必要はありません。
遺産相続の場合、相続人が受け取った遺産は「所得」とは異なるため、所得税の確定申告は不要です。たとえば、親から1,000万円の預金を相続したとしても、所得税の対象とはならず、確定申告書に記載する必要もありません。
関連サイト国税庁「所得税の確定申告」
遺産を相続したときにするのは相続税申告
遺産を相続しても、所得税に影響がない一方で、相続税は課税される可能性があります。
ただし、すべての遺産相続に対して相続税がかかるのではなく、遺産総額が基礎控除を上回った場合に相続税の申告や納税が必要となります。
故人の所得を申告するのは準確定申告
相続が発生すると、被相続人が生前に得ていた所得について、相続人が代わりに申告・納税する準確定申告が必要となる場合があります。
準確定申告とは、被相続人がその年に得た給与所得や事業所得、不動産所得などを1月1日から死亡日までの期間で計算し、相続人が代理で申告・納税する制度です。
関連サイト国税庁「No.2022納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
準確定申告の申告期限は、相続開始の翌日から4ヶ月以内と、相続税の申告よりも短い点に注意が必要です。
遺産相続をして
確定申告が必要になるケース
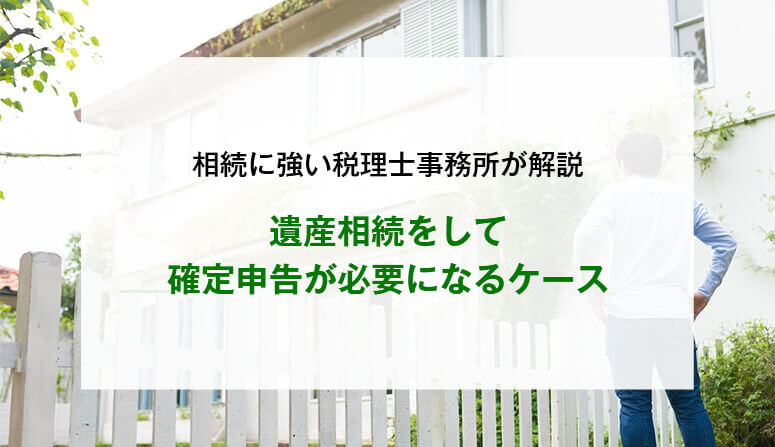
遺産相続そのものには確定申告は不要ですが、相続した財産を活用することで新たに所得が生じる場合には、確定申告が必要となることがあります。
本章では、遺産相続をした際に確定申告が必要になるケースを解説していきます。
相続不動産を売却したケース
相続した不動産などを相続し、売却益が発生した場合は譲渡所得として確定申告が必要です。譲渡所得は「売却価格-取得費-譲渡費用」で計算されます。
関連サイト国税庁「不動産等を売却した方へ」
なお、被相続人が住んでいて空き家になった不動産を売却した場合には、相続空き家の特別控除を適用できる可能性があります。
相続した空き家を売却する場合には、特例の適用要件を満たしているか確認してみましょう。
関連サイト国税庁「No.3306被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
収益不動産を相続したケース
相続によってマンションやアパートなどの収益物件を引き継いだ場合、家賃収入が不動産所得として課税対象になります。
また、被相続人が賃貸経営をしていた場合には、準確定申告が必要な可能性が高いことにも注意しなければなりません。
確定申告の方法・必要書類
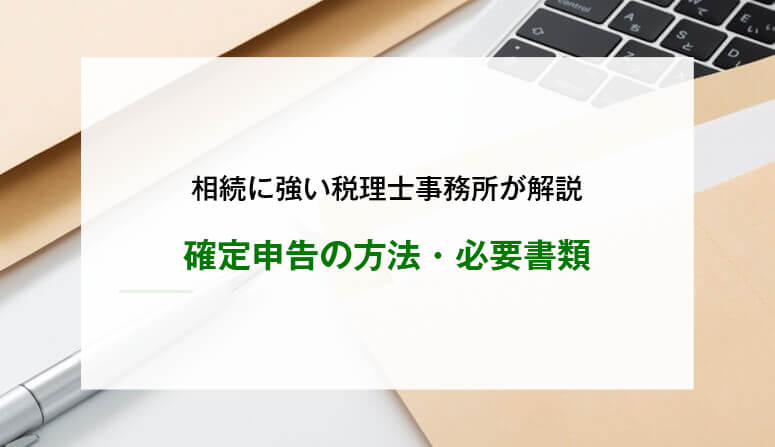
相続不動産の売却益が発生した場合や相続不動産によって賃貸収入を得た場合には、確定申告が必要です。
確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの期間に、所轄の税務署に書類を提出して行います。また、提出方法には、次の方法があります。
- 税務署に直接持参
- 郵送
- e-Tax(国税電子申告・納税システム)
特にe-Taxは自宅から24時間手続きでき、還付金の受取が早いというメリットがあります。
関連サイト国税庁「e-Tax」
必要書類としては、売却や収入に関する書類が中心であり、相続不動産を売却した場合には、以下のような書類が必要です。
- 譲渡所得の内訳書
- 売買契約書
- 仲介手数料などの領収書
- 登記事項証明書
- 固定資産税評価証明書
相続財産が基礎控除内に収まる場合は
相続税申告が必要ない
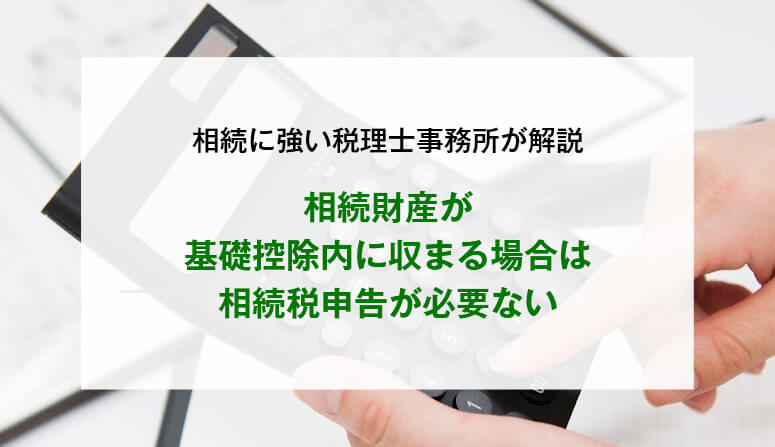
先程も解説しましたが、相続税申告は遺産総額が基礎控除額を超えた場合のみ必要です。相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算できます。
ただし、遺産総額が基礎控除額の範囲内であっても、「小規模宅地等の特例」や「非上場株式の評価減」など、各種の評価減制度を適用して課税対象を圧縮する場合には、相続税の申告が必要になります。
また、遺産総額を計算する際には、不動産や有価証券の相続税評価額を計算しなければならない場合もあります。
これらの計算は複雑であり、専門的な知識が必要となることも多くあるので、税理士に相談することもご検討ください。
相続税申告の方法・必要書類
相続税申告は、相続開始の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
相続税申告の方法や必要書類は、以下の通りです。
| 手続きする人 | 遺産を受け取った人 |
|---|---|
| 手続き先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する税務署 |
| 必要書類 |
|
準確定申告が必要なケース
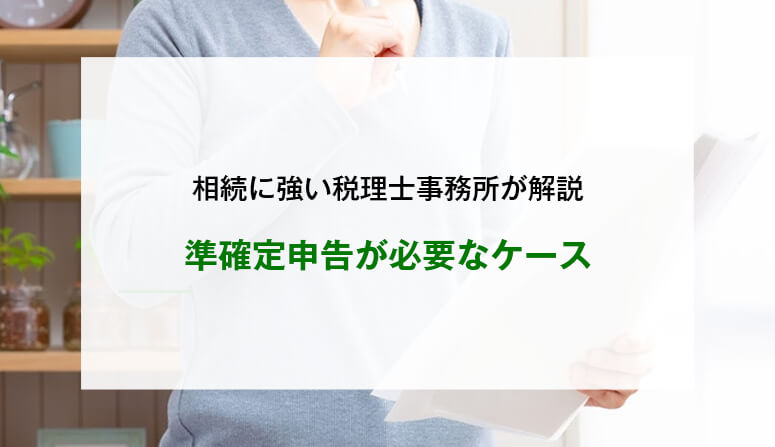
被相続人が個人事業を営んでいた場合や、賃貸収入などを得ていた場合には、原則として準確定申告が必要です。
一方、被相続人の収入が年金のみだった場合は、準確定申告が不要となる可能性が高いでしょう。
準確定申告の方法・必要書類
準確定申告の提出期限は、相続開始の翌日から4か月以内であり、申告方法や必要書類は以下の通りです。
| 手続きする人 | 遺産を受け取った人 |
|---|---|
| 手続き先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する税務署 |
| 必要書類 |
|
準確定申告は期限が短く設定されていますし、被相続人と相続人の関係によっては、必要書類を集めることや準確定申告が必要かどうかの判断が難しいことも有るでしょう。
自分で準確定申告できない場合や不安な場合には、相続に詳しい税理士に相談するのが良いでしょう。
相続税申告・確定申告は
当サポートセンターにお任せください

遺産相続をしても確定申告は原則として必要ありませんが、状況によっては相続税申告や準確定申告をしなければなりません。
相続税申告は相続開始の翌日から10ヶ月以内、準確定申告は相続開始の翌日から4ヶ月以内と期限が短いのでご注意ください。
自分でこれらの申告を行うことが難しい場合には、税理士に相談することも検討しましょう。
相続税申告や準確定申告は、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
遺産相続では原則として確定申告は不要ですが、相続不動産を売却した場合や、賃貸不動産を相続した場合には、確定申告が必要です。
また、基礎控除を上回る遺産を相続した場合には、相続税申告もしなければなりません。相続税の申告は、相続開始の翌日から10か月以内と期限が設定されているのでご注意ください。
他にも、被相続人に事業所得や不動産所得があれば、準確定申告もする必要があります。相続発生に伴い、どのような税金を申告すれば良いかわからない場合や、申告手続きに不安な場合は、できるだけ早めに税理士に相談することをおすすめします。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ