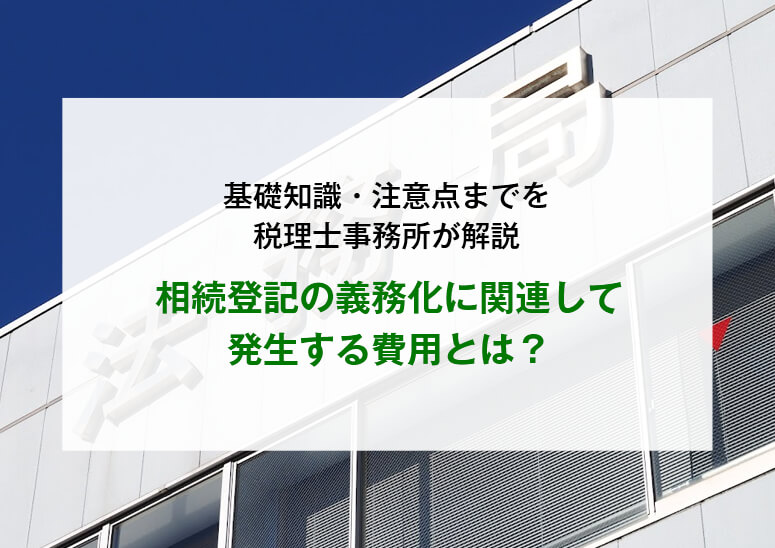
相続登記の義務化に関連して発生する費用とは?基礎知識・注意点まで解説
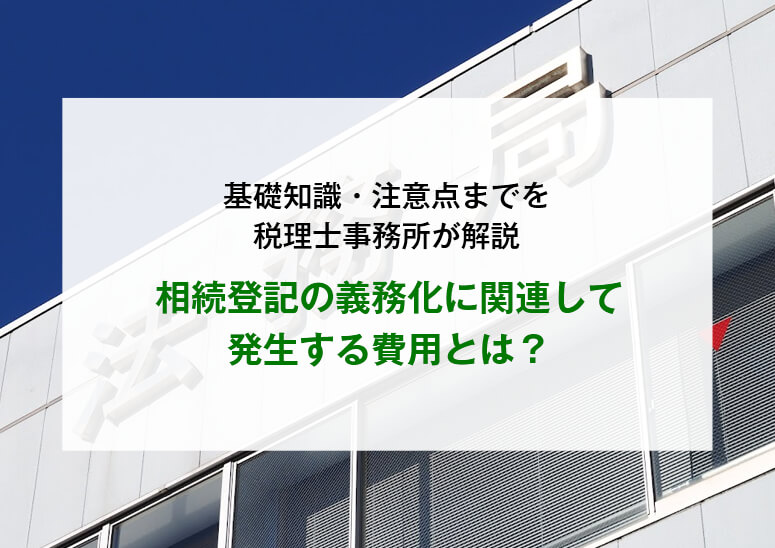
2024年4月から、相続登記が義務化され、登記を怠ると過料が科せられる恐れがあります。
相続登記をするにあたり、「費用が高そう」「どれくらいかかるのか分からない」といった不安を抱える方もいるのではないでしょうか。
相続登記では、登録免許税や書類収集費用、司法書士報酬などがかかります。本記事では、相続登記の費用内訳や相場、費用を負担する人物、費用を抑える方法を解説します。
目次
相続登記の義務化とは
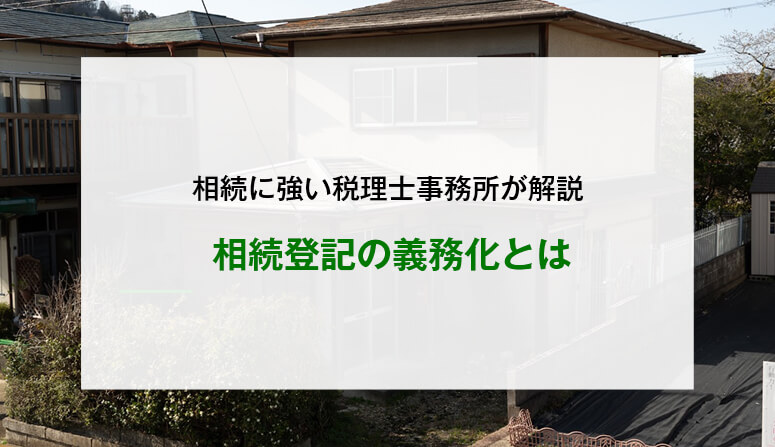
2024年4月から施行された改正法により、相続によって不動産を取得した人は、相続登記を義務的に行わなければならなくなりました。
関連サイト東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)」
これは、不動産の名義変更が長期間行われない「所有者不明土地問題」を解消するための制度改正の一環です。2024年4月以降は、相続発生から3年以内に相続登記を完了させないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、相続登記の義務化については、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。
相場付相続登記にかかる費用の内訳
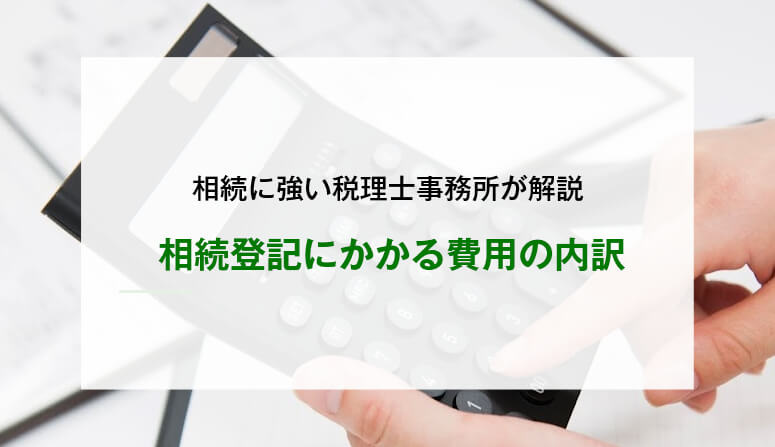
相続登記には、大きく分けて以下の3つの費用が発生します。
- 登録免許税
- 書類の収集費用
- 司法書士報酬
それぞれの費用目安を確認しておきましょう。
登録免許税
登録免許税は、不動産を相続した際に法務局へ支払う税金であり「固定資産評価額 × 0.4%」で計算できます。
例えば、固定資産評価額が2,000万円の土地の場合、登録免許税は8万円となります。
書類収集費用
相続登記には、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、固定資産評価証明書など、さまざまな書類を提出しなければなりません。
それぞれの書類発行手数料は、以下の通りです。
| 戸籍謄本 | 1通あたり450円 |
|---|---|
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 1通あたり750円程度 |
| 住民票の除票 | 1通あたり300円程度 |
| 固定資産評価証明書 | 1通あたり300〜400円程度 |
相続登記の必要書類を収集するにあたり、数千円程度かかることが一般的です。書類の通数が多い場合は、1万円以上かかることもあります。
収集する書類が多い場合や、先祖代々にわたり相続登記されていなかった場合には、さらに費用がかかる可能性があります。
司法書士報酬
相続登記は、自分で申請することもできますが、司法書士に依頼する方も多くいます。
司法書士へ依頼した場合には、物件数や相続人の数などによって異なりますが、おおよその相場は5万円~10万円程度です。
相続登記の費用を払うのは誰?
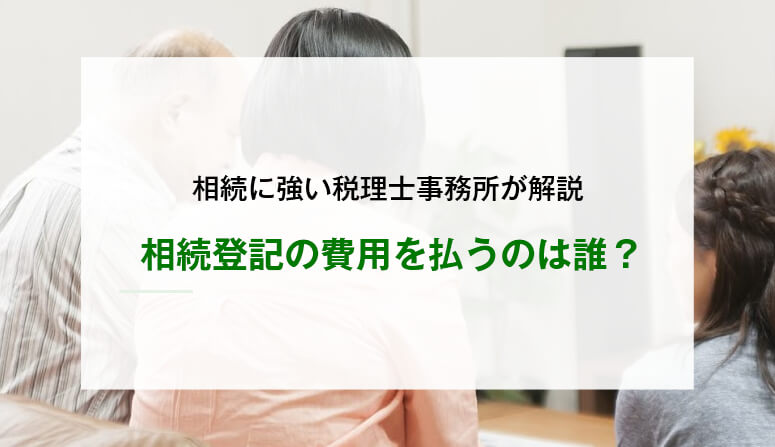
相続登記にかかる費用を負担する人物は、法律などで決められているわけではありませんが、不動産を受け継ぐ相続人が払うことが一般的です。
ただし、費用を負担する人物は自由に設定できるため、自宅を相続する配偶者の負担を減らすため、被相続人の子供が相続登記を負担するなども可能です。
相続登記の費用が高くなりやすいケース
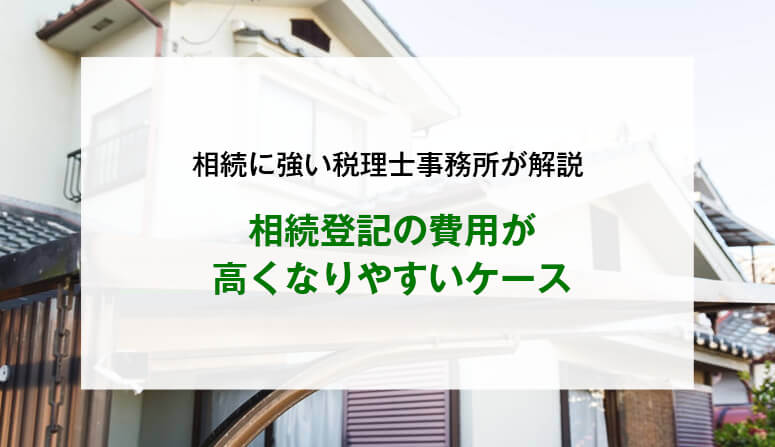
相続人や相続不動産の状況によっては、相続登記の費用が一般的なものよりも高くなる場合があります。相続登記にかかる費用が高額になりやすいケースは、主に以下の通りです。
- 先祖代々にわたり名義変更されていないケース
- 相続人の人数が多いケース
- 相続不動産の数が多いケース
それぞれ詳しく見ていきましょう。
先祖代々にわたり名義変更されていないケース
何世代にもわたり相続登記が放置されていた不動産の登記申請をする場合、相続登記にかかる費用が高額になりがちです。
というのも、相続登記は原則として中間省略登記が認められないため、過去の相続分も含めて登記申請が必要になるからです。
このようなケースでは、必要書類の数も増えるので書類収集費用も高額になりますし、登記申請の難易度も上がるため司法書士に支払う報酬も高くなるでしょう。
相続人の人数が多いケース
相続人が多いほど必要書類の枚数が増え、相続登記の費用が高くなりやすいです。
また、不動産を共有名義で相続する場合、登記申請書の作成にかかる手間も増えるため、司法書士に支払う報酬も高額になります。
相続不動産の数が多いケース
相続対象の不動産が複数ある場合も、費用は高額になります。不動産の数が増えると、それぞれに登記申請件が必要になるため、登録免許税も物件数分発生するからです。
また、司法書士の報酬も物件数に応じて加算されることが多く、1件ごとに1万〜2万円前後の追加料金がかかる場合もあります。
相続登記の費用を抑える方法
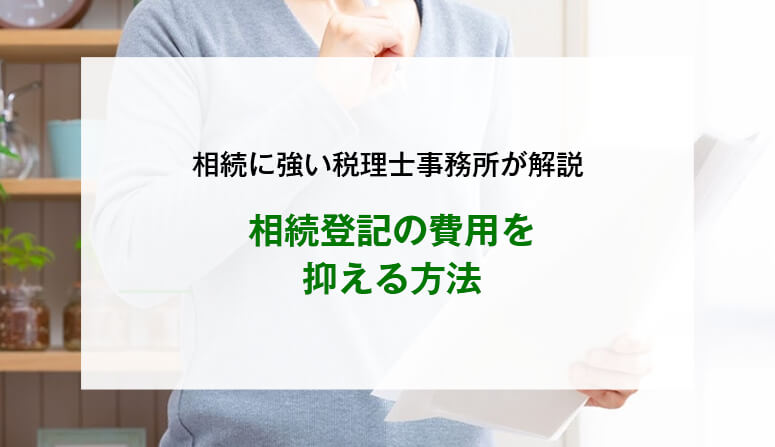
相続登記にかかる費用を抑えるには、以下の方法などを試しましょう。
- 自分で相続登記する
- 複数の司法書士に見積もり依頼を出す
- 相続発生から3年以内に登記する
それぞれ詳しく解説していきます。
自分で相続登記する
司法書士に依頼せず自分で相続登記を行えば、費用を節約できます。司法書士に依頼した場合は5万~10万円程度の報酬が必要になりますが、自分で手続きをすれば、登録免許税と書類収集にかかる実費のみで済みます。
ただし、相続登記では必要書類の収集や登記申請書の作成などを行う必要があり、相続の状況によっては専門的な知識や経験が必要な場合もあります。
そのようなケースでは、費用の安さにとらわれるのではなく、専門家に依頼した方が良いでしょう。
複数の司法書士に見積もり依頼を出す
司法書士に依頼する場合は、複数の事務所に見積もりを依頼しましょう。司法書士報酬は法律で定められているわけではなく、各事務所が自由に設定しているからです。
そのため、同じ条件でも報酬額が2〜3万円程度違うことも珍しくありません。見積もりを比較する際は、以下の点に注意しましょう。
- 見積金額に登録免許税・印紙代・郵送費などが含まれているか
- 不動産の数や相続人の人数によって追加費用が発生しないか
- 書類取得代行の有無と費用
相続発生から3年以内に登記する
相続登記に関する費用を抑えたいのであれば、相続発生から3年以内に登記申請をしましょう。
2024年4月からは、相続登記が義務化され、相続から3年以内に登記申請をしないと10万円の過料が科せられる恐れがあるからです。
また、相続発生から期間が空くと、戸籍の収集範囲が広がり、調査コストや時間が増加するため、早めの対応が金銭面でも有利です。
相続登記の期限に間に合わない場合には
相続人申告登記をしよう
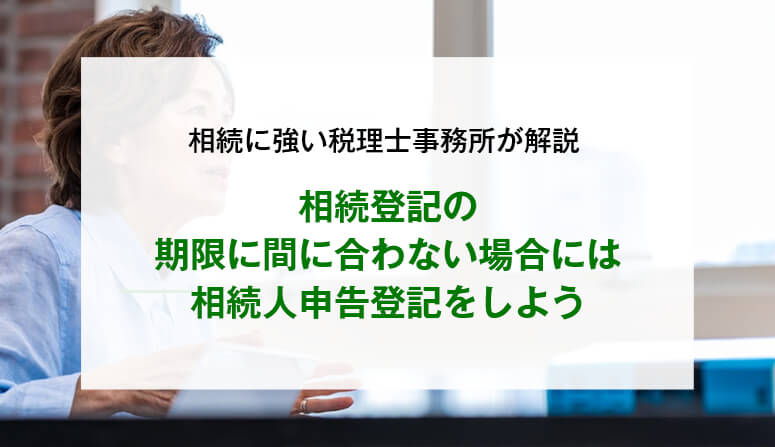
「相続人が多くて遺産分割協議がまとまらない」「忙しくて手続きに着手できなかった」などの事情で、3年以内の相続登記が間に合わないこともあるかもしれません。
そうした場合に有効なのが、「相続人申告登記」です。
相続人申告登記をしておけば、期限までに相続登記が完了しなくても過料が科せられることはありません。相続人申告登記の方法や必要書類は、以下の通りです。
| 手続きする人 |
|
|---|---|
| 手続き先 | 相続不動産の住所地を管轄する法務局 |
| 必要書類 |
|
| 費用 | 無料 |
関連サイト法務省「相続人申告登記について」
相続手続きは
当サポートセンターにお任せください

相続登記をする際には、登録免許税などの費用がかかります。費用を節約したいと考える方も多いですが、司法書士報酬を抑えようとして、自分で相続登記をすることは場合によってはおすすめできません。
相続の状況によっては、相続登記を自分で行うことが難しい場合もありますし、司法書士に相続登記を依頼すれば必要書類の収集や登記申請書の作成などをすべて任せられます。
相続手続きは、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
相続登記は法律で義務化された手続きであり、登録免許税や書類収集費、司法書士報酬などの費用がかかります。
費用を抑えたいのであれば、自分で相続登記することや、複数の司法書士に見積もり依頼を取ることをおすすめします。
万が一、期限内に相続登記が間に合わない場合には、相続人申告登記をし、過料が科せられるのを避けましょう。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ