
民法改正内容と相続税申告時のポイントを解説

40年振りに行われた民法改正によって、相続に関するいくつかの制度が変わるだけでなく、相続税申告にもさまざまな影響が考えられます。
ここでは、まだまだ皆様に浸透しておりませんので2018年に成立した民法改正のうち、相続に関する改正点や相続税申告時のポイントなどについて相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが解説していきます。
生前贈与や遺言の作成、配偶者や相続人以外の相続についても改正されていますので、現在相続が発生していない方も参考にしていただけます。
目次
民法改正で変更される内容
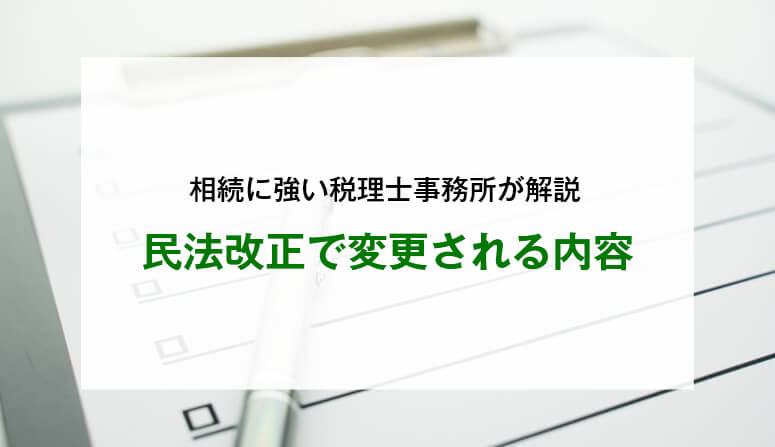
民法改正は2018年7月に成立しました、制度ごとに順次施行が始まっています。どのような改正が行われたのか、その内容について簡単に確認していきましょう。
故人の配偶者が居住する自宅に関する制度
2020年4月に新制度として「配偶者居住権」と「配偶者短期所有権」が創設されました。これは夫婦で住んでいた故人名義の自宅に、配偶者が引き続き居住できる権利です。
遺産の相続は配偶者と子との間で1:1となるため、居住している自宅についても子の相続対象となります。配偶者が自宅を相続して居住する場合、以前では自宅の評価額に相当する他の遺産(預貯金など)を子へ分配する必要がありました。
配偶者居住権では、自宅の名義人の死後にその配偶者が生涯(または一定期間)自宅へ住み続ける権利を保障するとともに、他の遺産についても子と等分できるようになります。
また、相続が発生した際に家賃等を支払うことなく自宅へ居住していた配偶者は、最大で6か月間無償で自宅を使用できる「配偶者短期居住権」も新設されました。
関連サイト法務省「残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。」
預貯金払戻し制度の創設
遺産分割の完了していない預貯金について、以前ではたとえ葬儀費用であっても払い戻しを受けることはできませんでした。また、遺産となる預貯金の払い戻しには、家庭裁判所から「仮分割の仮処分」を受ける必要もありました。
2019年7月1に施行された改正により、遺産の分割が終わっていない段階でも家庭裁判所の判断を経ることなく、一定額の払い戻しができるようになっています。
遺言や添付書類等に関する制度
生前に自筆証書遺言を作成する際、これまでの遺言書類では本文から財産目録に至るまで、すべてを自書で作成しなければなりませんでした。
この制度が2019年1月13日より、パソコンによる財産目録の作成が認められるようになっています。また、現行法で認められていなかった通帳のコピー添付も可能です。但し誰に相続させたいなどの意思については自筆でなければなりませんのでご注意ください。
自筆証書遺言の保管については、2020年7月10より法務大臣指定の法務局へ保管申請ができるようになりました。
関連サイト法務省「03遺言書の様式等についての注意事項」
法定相続人以外の相続に関する制度
以前では、生前に故人の看護や介護療養などのお世話をしていた人のうち、たとえば子の配偶者など、法定相続人以外の人は原則として相続の分配を受けることができませんでした。
2019年7月1日に新設された特別寄与制度では、生前に故人の介護などをしていた人が相続人に対して金銭の請求ができるようになりました。
関連サイト裁判所「特別の寄与に関する処分調停」
遺留分に関する制度
「遺留分」とは、遺言などで故人が遺産の配分を指定している場合に、法律で定められた相続額までは請求できる権利があり、その際に設定されている割合のことです。
以前でも、遺留分よりも少ない相続が指定された相続人は、その差額分を遺留分減殺請求として請求することができました。
しかし、これまでは不動産や会社などについて減殺請求を行った場合に共有状況が複雑となり、経営や所有に問題が生じるケースが多かったため、2019年7月1より遺留分減殺請求による請求は金銭債権となるよう見直しが行われました。また、名称も遺留分侵害額請求に変更されました。
この他にも、将来的に施行予定の民法改正により、相続手続きや相続税申告に大きな影響があると予想されています。
関連サイト裁判所「遺留分侵害額の請求調停」
民法改正による相続税申告のポイント
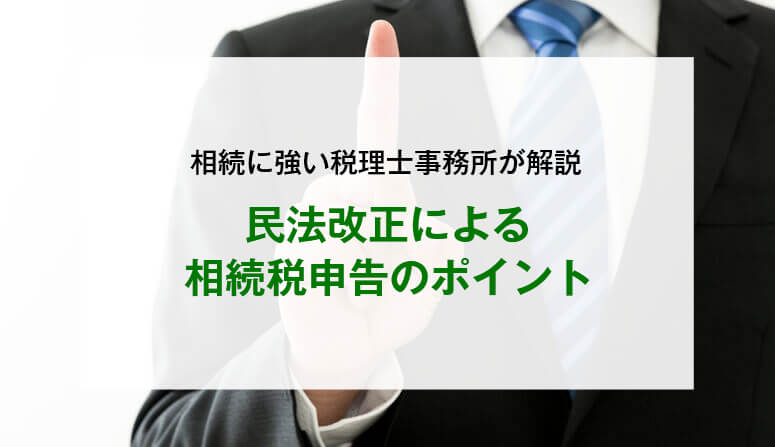
上記で挙げたような民法改正により、相続税申告時にはどのような点がポイントとなるのでしょうか。
配偶者居住権に関する相続税申告のポイント
配偶者居住権が新設されたことにより、相続対象となる故人の自宅について、遺産分割協議で設定できるようになりました。
具体的には、配偶者が自宅を相続して引き続き住もうとする際に「配偶者居住権」か「所有権」かの権利選択が可能となり、配偶者以外の親族が自宅を相続する場合には、配偶者居住権のある自宅は「負担付所有権」となります。
配偶者居住権付きの不動産は、相続税の課税対象となります。配偶者居住権付き不動産の評価額には時価を採用するため、所有権を設定した不動産よりも評価額が抑えられた場合には、相続税の申告額を軽減できます。
評価額の計算方法や相続税の比較をしたい場合は、一度税理士などの専門家へ確認してみましょう。
特別寄与者の相続に関する相続税申告のポイント
故人の介護などに関わった親族が特別寄与料を請求し金銭を得た場合、これも相続税の課税対象となるため、法定相続人の申告と同様、特別寄与の権利が発生した日から10か月以内に相続税申告をする必要があります。
特別寄与料がいくらになるかわからないまま申告期限を迎えそうな場合は、相続税申告の期限を延長できる制度もあるので、詳しくは税理士などへ相談してみるとよいでしょう。
遺留分侵害額請求に関する相続税申告のポイント
遺留分侵害額請求を受けた相続人は、不動産や会社を相続した場合であっても、請求された額について金銭化して支払う必要が出てきます。
預貯金が足りずに不動産を売却して支払う場合、特別控除内であれば相続税は発生しませんが、売却時の譲渡所得が課税対象となるため注意が必要です。
「多額の預貯金がなく、不動産を相続するだけだから相続税は発生しないだろう」と考えていても、不動産の評価額が予想よりも高く特別控除の範囲を超え、譲渡所得税が発生するケースもあります。
相続が発生した時点で、遺産や遺言の内容については親族間でしっかりとチェックするか、当事者同士での協議が難しい場合には専門家へ仲介に入ってもらうことになります。
成年年齢引き下げに関する相続税申告のポイント
施行日が2022年と少し先になりますが、成年年齢引き下げにともなう相続税の控除制度も改正となる予定です。
相続人が未成年の場合に、現行法で20才未満であれば未成年者控除の対象となりましたが、民法改正後は18才未満となります。また、相続時精算課税についても、現行20才以上が対象となっていますが、改正後は18才以上から対象となります。
現行(一部改正済み)の民法は、昭和55年に作られたため現代の事情にそぐわない法律も多く、遺言のPC作成や高齢化による配偶者の居住権、少子化による成年年齢の引き下げといった要素が盛り込まれた大幅な改正となります。
相続税についても、申告額の計算や課税対象など改正内容に応じて申告手続きをする必要があるため、相続に強い専門家のアドバイスを受けるか、無料相談などを利用するようにしましょう。











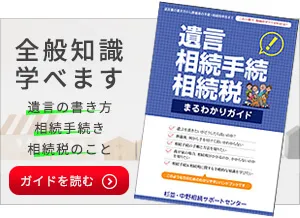
 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ