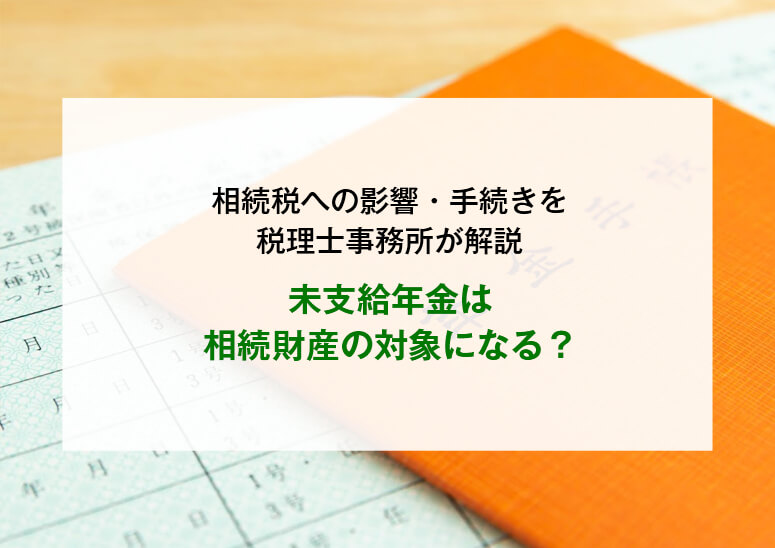
未支給年金は相続財産の対象になる?相続税への影響・手続きを解説
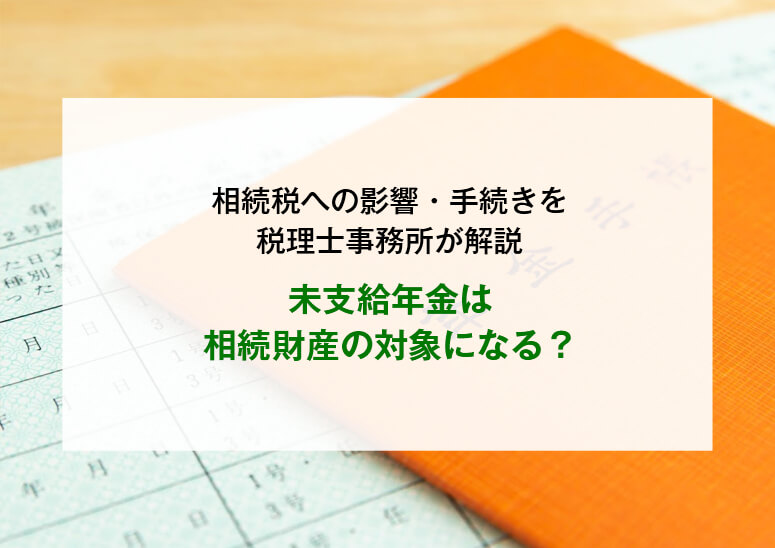
未支給年金とは、年金受給者が亡くなった際に、まだ支給日が到来していない分の年金を遺族が請求できる制度です。未支給年金は相続財産とは異なり、受取人固有の財産として扱われます。
加えて、未支給年金は公的年金と私的年金では税金のかかり方や請求方法が異なる点にも注意しなければなりません。
本記事では、未支給年金とは何か、請求できる人や税金の取り扱いを解説します。
目次
未支給年金とは
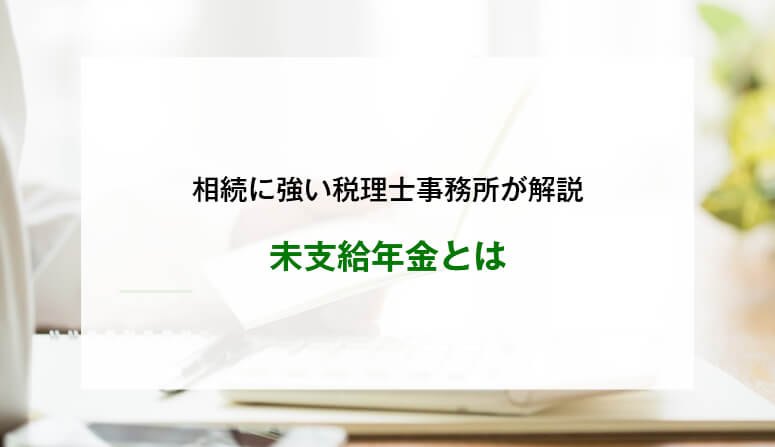
未支給年金とは、年金受給者が亡くなった際に、まだ受け取っていなかった年金を遺族などが請求できる制度です。
通常、年金は偶数月に前2か月分を支給する形を取っており、例えば、4月に支給されるのは2月・3月分です。
このため、年金受給者が3月中に亡くなった場合、本来であれば支払われるはずだった2月・3月分は未支給年金として取り扱われます。
関連サイト日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
未支給年金と
年金受給権の法的な位置づけ
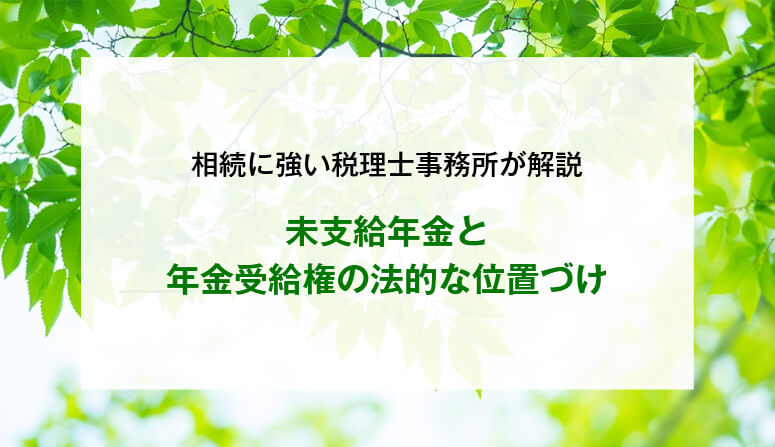
年金を受け取る権利(年金受給権)は、個人の身分に基づく権利であり、一般の財産権とは区別されます。このため、年金受給者が亡くなると、その人の受給権は消滅します。
ただし、死亡前に発生していた支給対象分(未支給分)については、例外的に「遺族の固有の権利」として支給されます。
つまり、未支給年金は被相続人の財産(相続財産)ではなく、受給者(相続人)自身の所得として扱われるのです。
関連サイト国税庁「No.1605遺族の方に支給される公的年金等」
未支給年金を請求できる人
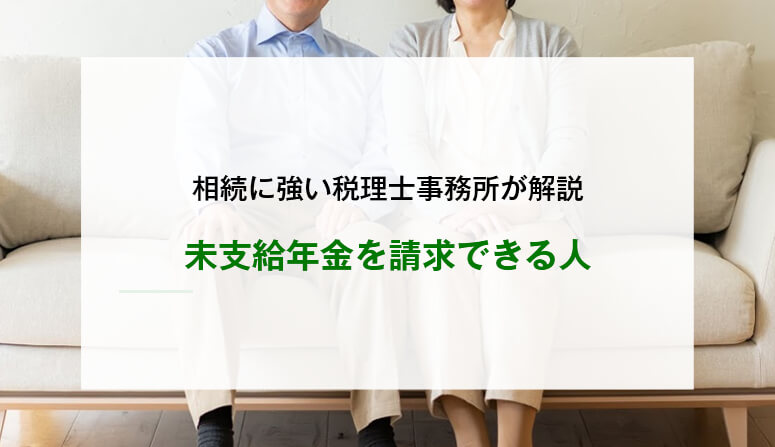
未支給年金を請求できる人は、民法上の相続人ではなく、年金法で受給順位が定められています。具体的には、以下の通りです。
- 配偶者
- 子供
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記以外の3親等以内の親族
先順位の人がいる場合は後順位の人は請求できません。例えば、配偶者が存命であれば、子供や兄弟姉妹が請求することはできません。
なお、請求には戸籍謄本・死亡届出受理証明書・振込口座などの提出が必要になります。
未支給年金を相続したときにかかる税金

未支給年金と一口に言っても、公的年金と私的年金では税務上の取り扱いが大きく異なります。相続税がかかるのか、所得税の確定申告が必要なのかといった点で誤解が生じやすいため、本章では整理して解説します。
公的年金の未支給年金を受け取っても相続税はかからない
まず、国民年金や厚生年金といった公的年金の未支給年金については、相続税の対象にはなりません。理由は、未支給年金は被相続人の財産ではなく、年金法に基づいて遺族に支払われるものとして扱われるからです。
関連サイト国税庁「No.4123相続税等の課税対象になる年金受給権」
私的年金の未支給年金を受け取ると相続税がかかる場合がある
一方、生命保険会社や金融機関が提供する個人年金保険など、私的年金に基づく未支給分は取り扱いが異なります。
契約者が亡くなった場合に、まだ受け取っていなかった年金部分は、契約者の財産とみなされ、相続財産として扱われるのが原則です。
そのため、私的年金の未支給年金を受け取ると、相続税がかかる恐れがあるのでご注意ください。なお、生命保険金と異なり、私的年金の未支給分には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は適用されないことも理解しておきましょう。
企業年金(確定給付企業年金など)
企業年金の場合も、制度設計や年金規約により取扱いが異なります。死亡時に「一時金」として支給される場合は退職手当金等として相続税の対象、単なる未支給分として支払われる場合は遺族固有の権利として所得税の対象になることもあります。具体的な扱いは企業年金の契約内容を確認する必要があります。
未支給年金の金額によっては相続人の確定申告が必要となる
未支給年金を受け取った場合には、相続税だけでなく所得税や住民税の申告義務が発生することもあります。
前述した通り、国民年金や厚生年金などの公的年金の未支給分を遺族が請求して受け取った場合は、相続税の課税対象にはなりません。しかし、公的年金の未支給分を一時所得として受け取った場合、その金額が50万円を超えると所得税の課税対象となり、確定申告が必要です。
一時所得は、「(一時所得の金額)=(総収入金額-必要経費-特別控除50万円)÷2」で計算できます。
関連サイト国税庁「No.1490一時所得」
また、私的年金の未支給分については、相続税の対象となるだけでなく、その後の運用益や受け取り方によっては所得税の対象になる場合もあります。確定申告の必要可否や相続税申告について不安がある場合には、税理士に相談してみると良いでしょう。
関連サイト国税庁「未支給の国民年金に係る相続税の課税関係」
未支給年金を相続するときの注意点
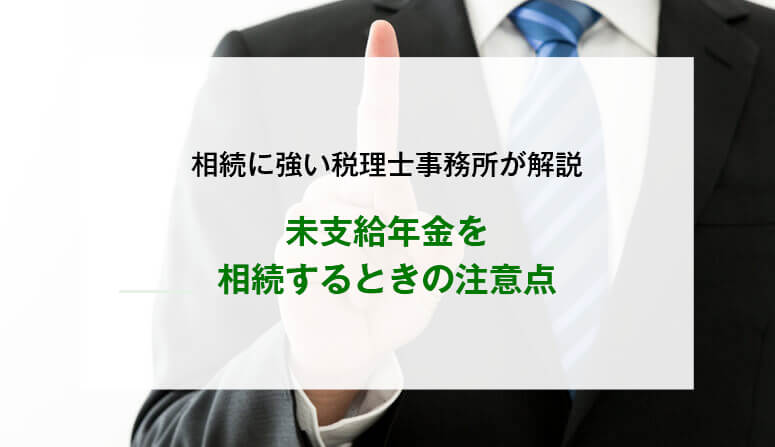
未支給年金は、被相続人が亡くなったときに受け取れる点では相続財産と共通していますが、実際にはいくつか異なる点があるので注意しなければなりません。
未支給年金を相続するときの注意点は、以下の通りです。
- 相続放棄をしても未支給年金を受け取れる
- 未支給年金の請求には5年の時効が設定されている
- 未支給年金の請求以外にも年金関連の相続手続きが必要である
- 未支給年金が被相続人の口座に振り込まれると引き出せない恐れがある
それぞれ詳しく解説していきます。
相続放棄をしても未支給年金を受け取れる
未支給年金は相続財産ではなく、遺族への給付として扱われるため、相続放棄をしても受け取り可能です。
ただし、未支給年金は遺族に対して自動で振り込まれるわけではなく、自分で請求する必要があるので、相続放棄したから受け取れないと誤解しないようにご注意ください。
未支給年金の請求には5年の時効が設定されている
未支給年金は、自動的に支給されるものではなく、遺族が所定の手続きを経て初めて受け取ることができます。
加えて、未支給年金の請求権には、5年の時効が設けられており、請求を怠るとその権利が消滅してしまいます。
葬儀や相続手続きに追われているうちに請求を失念してしまうこともありますが、5年を過ぎると取り戻すことはできないので必ず期限内に請求しましょう。
未支給年金の請求以外にも年金関連の相続手続きが必要である
未支給年金の請求が完了しても、それで年金関連の手続きがすべて終わるわけではありません。
例えば、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合、年金の停止手続きや遺族年金、寡婦年金の請求など、別の手続きが必要になることがあります。
未支給年金が被相続人の口座に振り込まれると引き出せない恐れがある
未支給年金は相続発生時期や請求時期によって、請求した遺族の口座ではなく、被相続人の口座に振り込まれてしまうことがあります。
被相続人の口座に振り込まれたとしても、受取人固有の財産として扱われることには変わりません。
ただし、銀行が被相続人の死亡を知ると、口座が凍結されてしまうため、受取人が引き出しをしたくてもできなくなる恐れがあります。
もし、凍結された被相続人の口座に入金されてしまった場合には、相続手続きを早めに完了させ、銀行口座の払い戻しを行いましょう。
相続税申告は
当サポートセンターにお任せください

未支給年金は相続財産ではなく、受取人固有の財産として扱われます。そのため、公的年金の未支給年金については、相続税が課税されることはありません。
一方で、被相続人が生命保険会社や金融機関で契約していた私的年金の未支給分については、相続税がかかるので注意しましょう。
このように、相続税申告では、財産ごとに相続税が課税されるかの判断や評価額の計算をしなければなりません。相続税申告や対策に不安がある場合には、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
未支給年金は、相続財産ではなく受取人固有の財産として扱われることを理解しておきましょう。
公的年金の未支給年金については、相続税は課税されないものの、金額によっては一時所得として確定申告が必要になるのでご注意ください。
また、未支給年金は自動で振り込まれるわけではなく、遺族が請求する必要がある点も注意しなければなりません。
このように、家族や親族が亡くなると、相続税申告をはじめとして様々な申請や手続きが必要となります。自分ですべてこなすのが不安な場合や、何から手続きすれば良いかわからない場合には、相続に詳しい専門家に相談してみるのも良いでしょう。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ