
生前贈与を受けていても相続放棄はできる?相続税への影響・注意点を解説

相続放棄において生前贈与と相続は区別して扱われるため、過去に生前贈与を受けていても相続放棄することは認められます。
原則として、過去の生前贈与に対して遺留分侵害額請求をされることもありませんし、過去の贈与財産を債権者に渡す義務もありません。
しかし、生前贈与時の状況や贈与の時期によっては、過去の贈与財産が遺留分の計算対象となったり、債権者に詐害行為取消権の対象となる可能性があります。
本記事では生前贈与と相続放棄の関係や相続放棄をする際の注意点について解説します。
目次
生前贈与を受けても相続放棄できる

相続放棄は、被相続人が亡くなった後に家庭裁判所で行う手続きであり、認められると相続人は相続権を失い、プラスの財産もマイナスの財産も相続しなくなります。被相続人が多額の借金を遺していた場合には、相続放棄を検討すると良いでしょう。
関連記事相続の放棄の申述
しかし、被相続人から過去に生前贈与を受けていると「相続放棄しても良いのか」と不安になる方もいるかもしれません。
結論から言えば、生前贈与を受けていても相続放棄は可能です。
生前贈与はあくまで被相続人が生前に行った財産移転であり、相続開始後に承継する相続財産とは区別して考えられるからです。相続放棄をしても生前贈与で受け取った財産を返還する義務は通常ありません。
ただし、贈与の時期や目的によっては、過去の贈与財産について遺留分請求されたり、詐害行為取消権を行使されたりする恐れがあるのでご注意ください。
生前贈与を受けていて
相続放棄を検討すべきケース

過去に被相続人から生前贈与を受けていた方が相続放棄を検討すべきケースは、主に下記の通りです。
- 被相続人に多額の借金がある場合
- 被相続人が連帯保証人となっている場合
- 生前贈与で十分な資産を受け取っており、遺産はいらない場合
- 相続人同士のトラブルを避けたい場合
相続放棄すべきか判断がつかない場合には、相続財産調査をしてプラスの財産やマイナスの財産がいくらあるのかを調べてみると良いでしょう。
相続放棄の手続き方法・必要書類
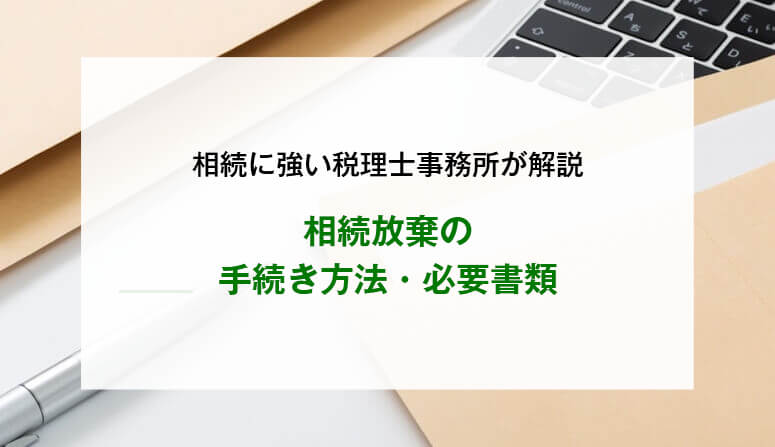
相続放棄を行うには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、受理してもらう必要があります。手続き方法や必要書類は、以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続きする人 | 相続放棄する本人または法定代理人 |
| 手続き先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 費用 |
|
| 必要書類 |
|
相続放棄をしても遺留分を請求される?
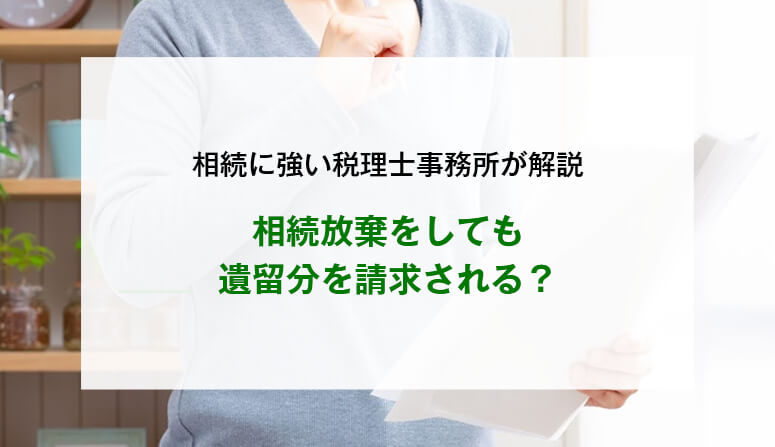
相続放棄をすると、相続に関する権利義務から完全に外れると考える方は少なくありません。しかし、実際には過去に受け取った生前贈与が遺留分の計算対象に含まれる場合もあるのでご注意ください。
本章では、生前贈与を受けていた方の相続放棄と遺留分侵害額請求の関係について解説します。
相続放棄をすると一般的には遺留分侵害額請求を受けることはない
原則として、相続放棄をした相続人は、最初から相続人でなかったものとみなされ、遺産を一切相続しない扱いになります。
相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったことになるため、相続財産を承継せず、当然に遺留分を主張・請求する立場にもなりません。
したがって、相続放棄をした方は遺留分を請求されることもありませんし、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けることもありません。
贈与の状況や時期によっては遺留分侵害額請求を受ける可能性がある
ただし、注意すべきなのは、「生前贈与を受けていた場合」です。相続放棄をしても、生前贈与を受けていた事実は消えません。法律上、被相続人から相続人に対して行われた贈与は「特別受益」として扱われることがあります。
特別受益は、遺産分割や遺留分の計算に反映されるため、贈与の状況や時期によっては他の相続人から調整を求められる可能性があるのです。
具体的には、以下のようなケースでは遺留分侵害額請求の対象となり得ます。
- 死亡前1年以内に行われた生前贈与
- 遺留分権利者に損害を与えると知っていたにもかかわらず行われた生前贈与
- 相続人への生前贈与(特別受益に含まれるもの)
過去の生前贈与が上記のケースに該当する場合には、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける恐れがあるのでご注意ください。
生前贈与を受けていて
相続放棄をするときの注意点
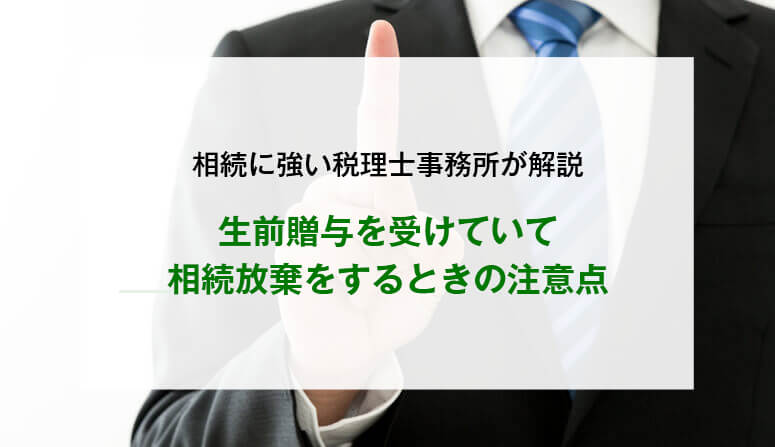
相続放棄は、被相続人に多額の負債がある場合などに有効な手段ですが、過去に生前贈与を受けているときには注意が必要です。
過去の贈与だから返還しなくて良いし、被相続人の借金も返済しなくて良いと安易に考えてしまわないようにしましょう。
生前贈与を受けていて相続放棄をする際には、以下のような点に注意しなければなりません。
- 過去の贈与に対して詐害行為取消権を行使される恐れがある
- 相続放棄には期限がある
- 相続放棄をしても過去の生前贈与について相続税の課税対象になることがある
それぞれ詳しく解説していきます。
過去の贈与に対して詐害行為取消権を行使される恐れがある
被相続人が多額の借金を抱えていた場合、過去の生前贈与が債権者から問題視されるケースがあります。
具体的には、過去の生前贈与が意図的な財産隠しであり、「債権者を害する目的で行われた」と判断されると、債権者が「詐害行為取消権」を行使して贈与を取り消し、財産を取り戻す可能性があるからです。
相続放棄をしても「生前贈与で得た財産は完全に守られる」とは限らず、贈与の背景や被相続人の債務状況によっては返還義務が生じる可能性があると理解しておきましょう。
相続放棄には期限がある
相続放棄は「自分が相続人であることを知ったときから3か月以内」に行わなければなりません。この期間を「熟慮期間」と呼び、期間内に家庭裁判所に申述して手続きをする必要があります。
相続放棄をする際には、被相続人や相続人の戸籍謄本類が必要となるため、相続発生後はできるだけ早く準備を進めることをおすすめします。
相続放棄をしても過去の生前贈与について相続税がかかる恐れがある
過去に生前贈与を受けていた人が相続放棄をした場合、過去の贈与について相続税がかかる恐れがあります。
相続開始前7年以内に相続人が贈与を受けた場合、贈与財産は相続税の課税対象となるからです。
「相続放棄したから相続税はかからないはず」と考えてしまうと、相続税の申告漏れにつながる恐れがあるのでご注意ください。
生前贈与を受けていて相続放棄する際に
専門家に相談すべきケース
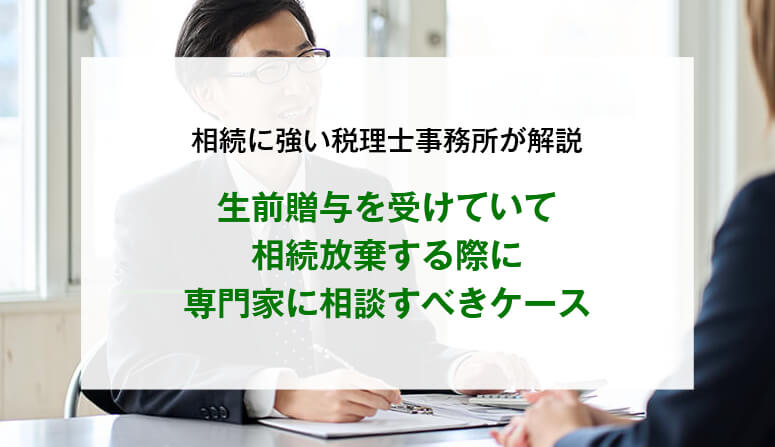
生前贈与を受けていて相続放棄をした場合でも、相続税がかかる恐れもありますし、場合によっては債権者とトラブルになることがあります。
トラブルや相続税の申告漏れを避けるために、以下のようなケースでは専門家に相談することを強くおすすめします。
- 被相続人が多額の借金を遺していた場合
- 生前贈与が複数年・高額にわたる場合
- 相続人同士で遺留分トラブルが起きそうな場合
また、相続放棄自体も家庭裁判所に申請しなければならない手続きであるため、ミスなく確実に行いたい場合には相続に精通した専門家に相談することもご検討ください。
相続税申告のご相談は
当サポートセンターにお任せください

生前贈与と相続放棄に直接的な関係はなく、過去に被相続人から生前贈与を受けていたとしても、相続放棄することができます。
ただし、相続開始3~7年以内に行われた贈与については、贈与財産を相続税の計算対象に含めなければなりません。
したがって、過去に生前贈与を受けていた方は、相続放棄をしたとしても相続税の申告義務が生じる場合があります。
相続税申告が必要か判断が難しい場合や、ミスなく申告手続きを完了したい場合には、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
生前贈与を受けていても相続放棄することは可能であり、原則として過去の贈与財産を返却する必要もありません。
しかし、贈与の時期や状況によっては、遺留分トラブルや債権者とのトラブルに発展する恐れもあるのでご注意ください。
確実に相続放棄したい場合や、放棄後にトラブルに巻き込まれたくない場合には、相続放棄に詳しい専門家に相談することをおすすめします。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ