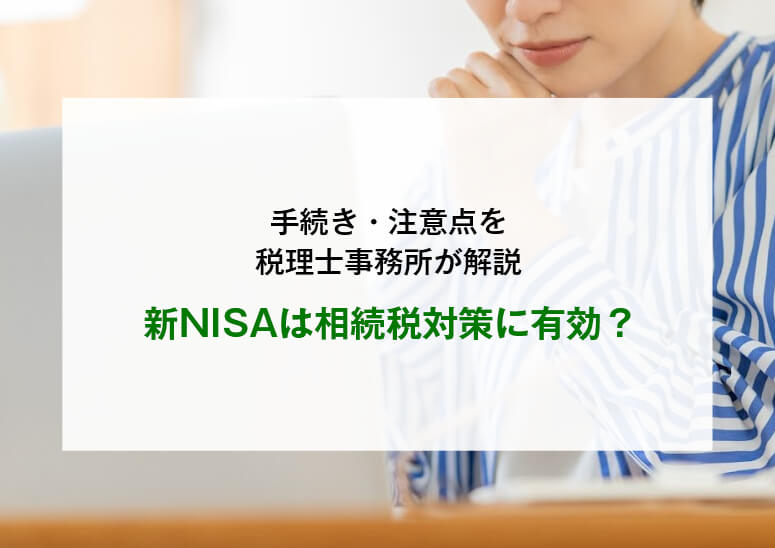
新NISAは相続税対策に有効?手続き・注意点を税理士事務所が解説
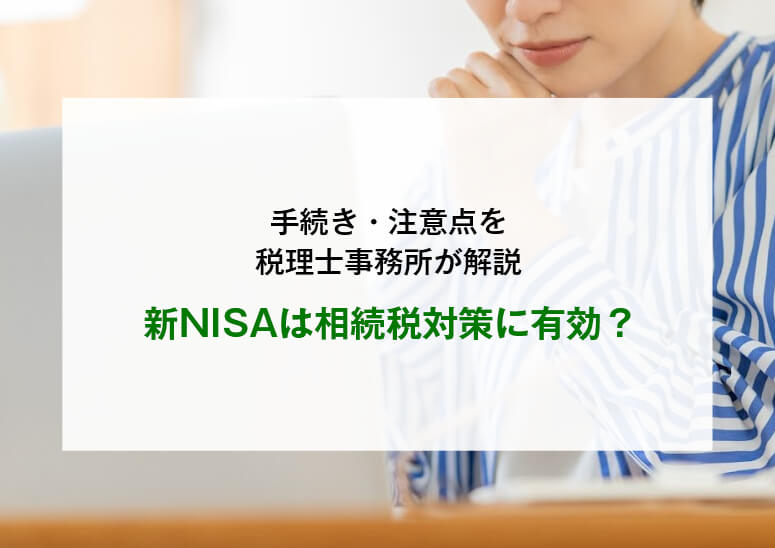
2024年からスタートした新NISA(少額投資非課税制度)は、従来の制度よりも非課税枠が拡充され、長期的な資産形成に適した仕組みとして注目されています。
投資初心者はもちろん、相続や資産承継を見据える高齢世代にとっても、新NISAは有効な選択肢のひとつです。
本記事では、新NISAの概要や相続税対策に活用するメリット・デメリットを解説していきます。
目次
新NISAとは

2024年からスタートした「新NISA(少額投資非課税制度)」は、個人の資産形成を後押しする目的で、従来のNISA制度を大幅に刷新したものです。最大の特徴は、非課税保有限度額の拡充と恒久化です。
関連サイトNISA特設ウェブサイト「NISAを知る」
旧制度では、制度ごとに利用期限が設けられていましたが、新NISAは恒久制度として位置づけられ、長期的な資産形成が可能となりました。
また、新NISAの非課税保有限度額は、合計1,800万円であり、この範囲内であれば何度でも売却と再投資が可能です。
新NISAと旧NISA・つみたてNISAの違い
新NISAと旧NISA(一般NISA・つみたてNISA)では、以下のような違いがあります。
- 利用可能期間と制度の恒久化
- 投資可能額と非課税限度額の大幅な拡充
- 投資可能商品の範囲
旧NISA制度にはそれぞれの制度に「制度の有効期間」が設けられておりました。それに対し、新NISAでは制度が恒久化され、継続的に利用できる点が大きなメリットといえるでしょう。
また、新NISAの非課税限度額は「つみたて投資枠」「成長投資枠」とあわせて年間360万円と大幅に拡大されており、より積極的な資産運用が可能です。また、トータルの非課税保有限度額1,800万円(生涯投資上限額)という枠内で、売却によって空いた枠を再利用できる点も大きな違いです。
関連サイト国税庁「No.1535NISA制度」
新NISAを活用して
相続税対策するメリット
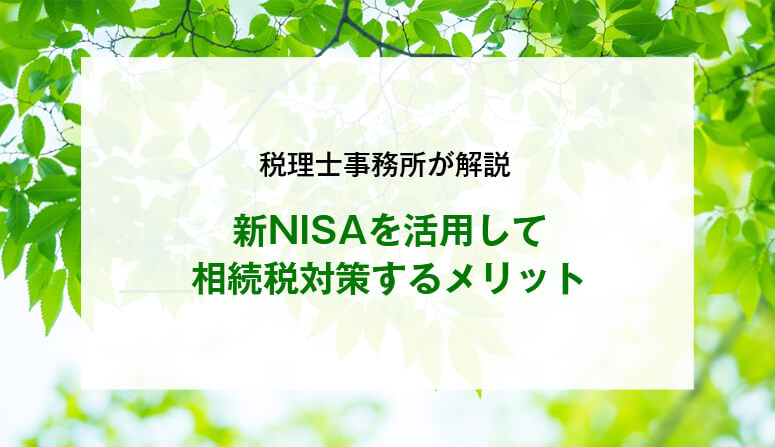
新NISAは、単なる資産形成ツールとしてだけでなく、生前贈与と組み合わせた相続税対策の一環としても注目されています。
新NISAを利用して相続税対策をするメリットは、主に以下の通りです。
- 非課税運用による効率的な資産増加
- 生前贈与と組み合わせて資産の移転を促進できる
- やるべきことが比較的シンプルでわかりやすい
新NISA口座内の金融商品は、売却益や配当金が非課税となるため、通常の課税口座と比べて効率的に資産を増やせます。
これにより、高齢の親が生前に新NISA口座を使って資産運用し、子や孫に引き継ぐ際に資産価値を最大化できる可能性もあるでしょう。
また、新NISAは、1人につき年間最大360万円までの投資が可能です。子供や孫が新NISA口座を開設し、親や祖父母が投資資金を贈与すれば贈与財産で資産運用を行えます。
ただし、贈与税の非課税枠には制限があることや、死亡前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻される場合があるため、専門家へ相談しながら進めていった方が良いでしょう。
新NISAを活用して
相続税対策するデメリット
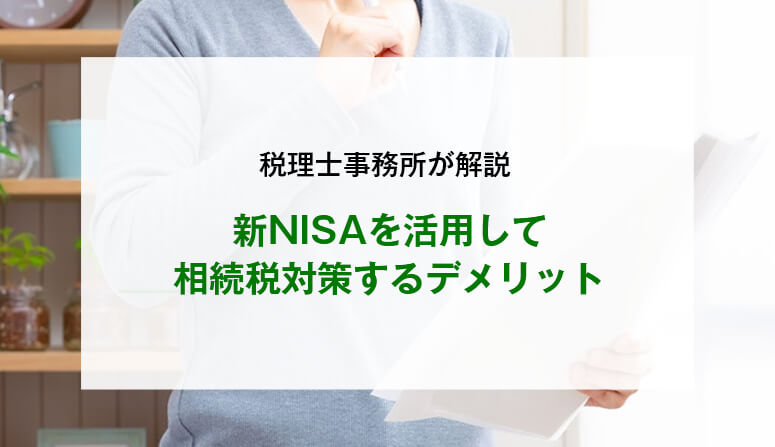
新NISAは便利な制度ではありますが、相続税対策として利用する際には、以下のようなデメリットもあります。
- 相続発生時に非課税措置は消失する
- 相続税評価額は相続開始時点の時価ベースで課税される
新NISA口座内の資産は、口座名義人が死亡した時点でNISA制度の非課税扱いが終了し、その時点の資産は相続人の課税口座へ払い出されます。
つまり、相続発生後はNISAの恩恵は引き継がれず、保有していた金融商品の取得価格は「死亡時の時価」とみなされ、その後の売却によって利益が出た場合は譲渡益課税の対象となることがあります。
関連サイト国税庁「No.1463株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
また、新NISA口座内の金融資産も相続税の課税対象であり、相続税評価時には時価で評価されます。相続開始時点の時価によっては、重くなる可能性も否定できません。
新NISAを活用して相続税対策をする方法
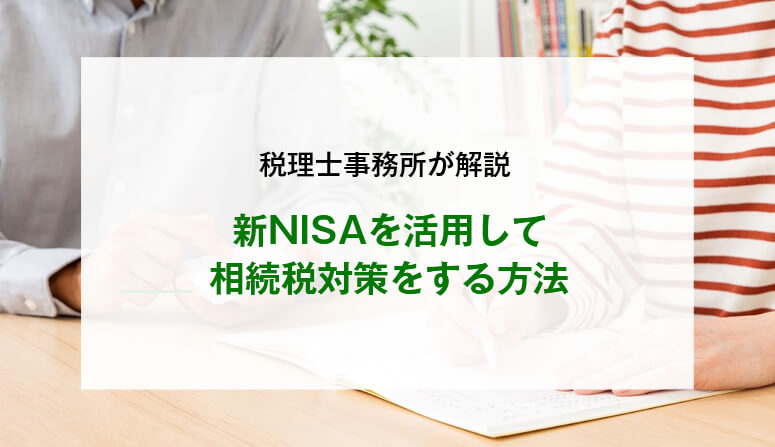
新NISAは、個人の資産形成支援を目的とした非課税制度ですが、使い方によっては相続税対策としても効果的に機能します。
本章では、新NISAを利用して相続税対策をする方法を解説していきます。
新NISAで長期運用して資産を増やしていく
新NISAの最大の特長は、年間360万円、累計1,800万円までの投資が非課税で可能な点です。非課税で運用益を積み上げることで、通常の課税口座よりも効率よく資産を増やせます。結果として、相続財産を増やし、子供や配偶者に受け継げる財産を増やせる可能性もあるでしょう。
生前贈与と新NISAでの運用を組み合わせる
相続税対策としてより効果的なのは、生前贈与と新NISAによる運用を組み合わせる方法です。具体的には、親や祖父母が子供や孫に投資資金を贈与し、そのお金で子供や孫が新NISA口座を利用して運用する流れになります。
贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、この範囲内で贈与を行えば、贈与税を節税しつつ資産を譲れます。
早い時期から贈与を繰り返し、子供や孫が新NISA口座で運用すれば長期運用により資産を増やしやすくなるはずです。
また、贈与財産によって資産運用すれば、運用益については受贈者の財産となるため、贈与者が自分で運用するより税負担を軽減できます。
新NISAで相続税対策するときの注意点
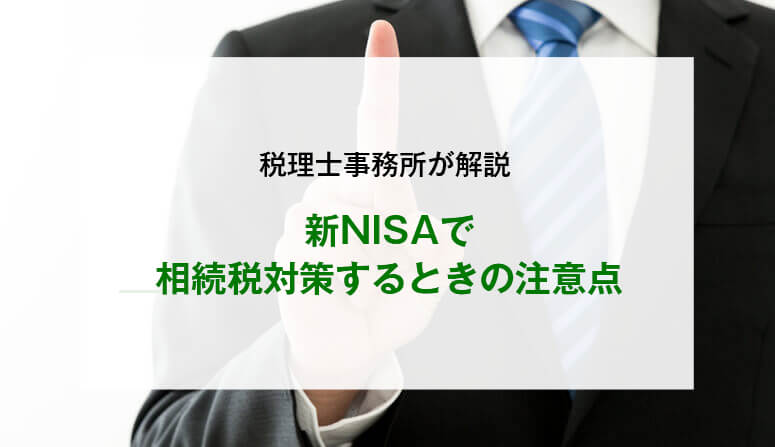
新NISAで相続税対策をする場合、以下のような点に注意しましょう。
- 配偶者・子供への資産移動には贈与税がかかる場合がある
- 新NISA口座を作成できるのは18歳以上のみである
- 新NISAの保有資産も相続税の課税対象である
- 被相続人の新NISA口座から相続人の新NISA口座には移管できない
- 相続税対策には他にも方法がある
それぞれ詳しく解説していきます。
配偶者・子供への資産移動には贈与税がかかる場合がある
新NISAで資産運用するための資金を生前贈与する場合、金額によっては贈与税がかかるのでご注意ください。贈与税には年間110万円の基礎控除が用意されており、贈与財産が基礎控除を上回ると贈与税がかかります。
例えば、新NISAの年間投資の上限額である360万円を生前贈与すると、贈与税がかかります。なお、配偶者には贈与税の配偶者控除が用意されていますが、こちらの制度は居住用不動産もしくは居住用不動産の取得費用を贈与した場合のみ適用できるものです。
関連サイト国税庁「No.4452夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
そのため、新NISAで運用するための資産を贈与する場合には、配偶者控除を利用することはできないのでご注意ください。
新NISA口座を作成できるのは18歳以上のみである
新NISA制度の対象年齢は、口座開設年の1月1日時点で18歳以上の日本居住者に限定されています。そのため、未成年の子供や孫に対して生前贈与と新NISAによる運用を組み合わせようとしても、すぐには行えないのでご注意ください。
未成年者向けの「ジュニアNISA」は2023年で新規受付を終了しており、現在は新たに開設できません。
関連サイト財務省「ジュニアNISA制度の概要」
そのため、未成年の子供や孫に資産を贈与したい場合は、預貯金などで贈与しておき、受贈者が18歳になったら新NISA口座を開設し運用していくプランが現実的です。
新NISAの保有資産も相続税の課税対象である
新NISAで保有している株式や投資信託は、非課税運用が可能ですが、相続が発生した場合は原則として時価評価で相続税の課税対象になります。
新NISAの非課税措置はあくまで所得税や住民税に関するものであり、相続税についてではないのでご注意ください。
被相続人の新NISA口座から相続人の新NISA口座には移管できない
新NISA口座は、個人ごとに開設される非課税口座であり、相続が発生するとその口座は閉鎖扱いとなります。被相続人の新NISA口座に残っていた資産を、相続人の新NISA口座にそのまま移すことはできません。
相続税対策には他にも方法がある
新NISAは相続税対策のひとつとして活用できますが、相続税の節税対策には以下のように様々な方法があります。
- 生命保険を利用する
- 不動産を購入し相続税評価額を圧縮する
- 生前贈与の控除や特例を利用する
自分に合った相続税対策をしたいのであれば、相続や生前贈与に精通した税理士に相談することもご検討ください。
相続税対策は
当サポートセンターにお任せください

新NISAは個人の資産運用方法として優れているだけでなく、相続税対策に活用することもできます。
ただし、新NISAによる相続税対策にもデメリットはありますし、相続税の節税対策には他の方法もあるので、自分に合った方法を選択することが大切です。
相続税対策は、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続税対策をワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
新NISAは、非課税で資産を運用しながら、将来的な資産移転にも活用できる制度です。生前贈与との組み合わせや長期運用により、相続税対策を行うこともできますが、一方で贈与税の課税リスクや相続時の取り扱いなどに注意しなければなりません。
特に、高齢の方が新NISAを活用する場合には、万が一に備え、相続税対策や資産の承継方法についても考えておくことが大切です。
相続税対策は自分に合った方法で行うことが大切なので、必要に応じて専門家に相談するのも良いでしょう。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ