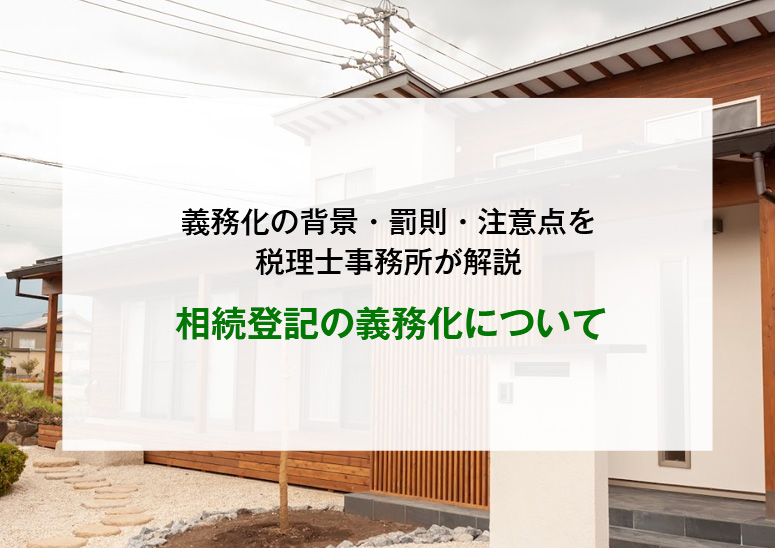
相続登記の義務化について|義務化の背景・罰則・注意点を解説
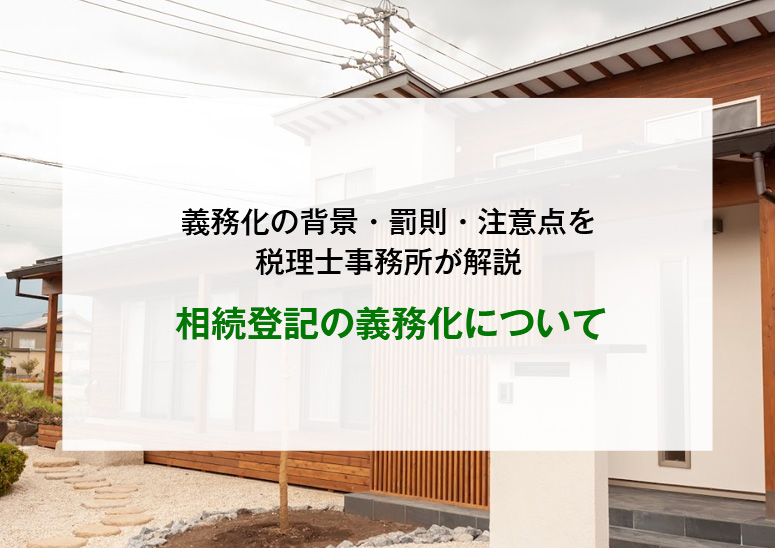
2024年4月に相続登記が義務化され、相続から3年以内に登記申請を済ませないと、10万円以下の過料が科せられる恐れがあります。
また、相続登記の義務化による過料が科せられないとしても、登記申請を済ませずにいると様々なリスクやデメリットがあるのでご注意ください。
本記事では、相続登記の義務化とは何か、義務化が決定した背景や手続きの流れ、期限までに対応できない場合の対処法などを解説します。
目次
相続登記の義務化とは
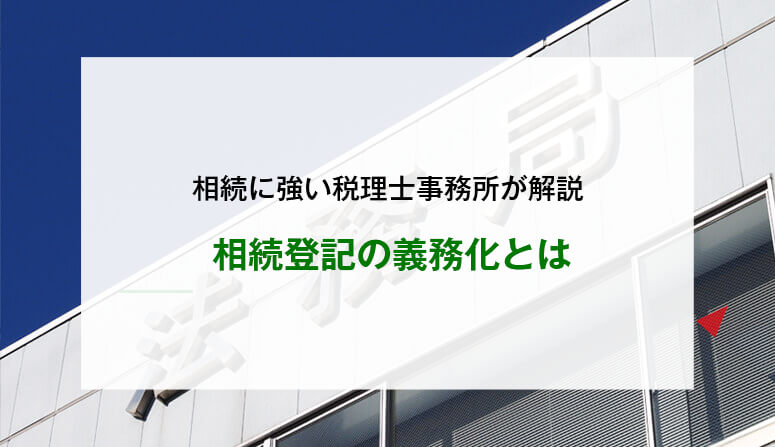
2024年4月から、不動産を相続した場合に登記を行うことが義務化されました。
関連サイト東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)」
これまでは、相続による所有権の移転登記は任意とされており、手続きせずにそのまま放置されている不動産も少なくありませんでした。
しかし、相続登記されない所有者不明の土地は年々増加し、大きな社会問題に発展していきました。こうした中、相続登記の義務化が決定し、相続から3年以内に登記申請をしないと10万円以下の過料が科せられるようになりました。
相続発生から3年以内に登記しなければ10万円以下の過料が科せられる
相続登記義務化により、相続発生から3年以内に登記しなければ10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
なお、被相続人が所有していた不動産は、相続発生後、遺産分割が済むまでは相続人全員の共有財産となります。そのため、被相続人が亡くなり相続が発生したら、速やかに登記申請の準備を始めることが大切です。
相続登記については以下の記事でも詳しくご紹介しています。ぜひ合わせてお役立てください。
過去に発生した相続も義務化の対象となる
相続登記の義務化が始まったのは2024年4月からですが、過去に発生した相続も義務化の対象となるのでご注意ください。
ただし、過去に発生した相続については経過措置期間が設けられており、2027年3月31日までに登記申請をすれば過料は発生しません。
とはいえ、過去に発生した相続の登記申請を放置している場合、新たな相続が発生し権利関係者が増えている可能性や必要書類の収集が難しい可能性もあるでしょう。
自分で手続きすることが難しい場合には、できるだけ早く相続に精通した司法書士などに依頼することをおすすめします。相続した不動産の相談先については以下の記事でも解説しています。ぜひご覧ください。
相続登記が義務化された
背景・理由とは?
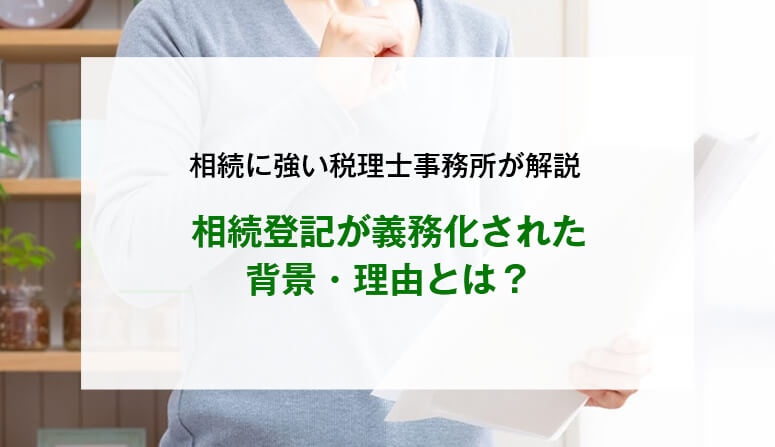
相続登記の義務化は、単なる制度改正ではなく、長年にわたり社会的に問題視されてきた「所有者不明土地問題」への対策として位置づけられています。
日本では、人口減少や都市部への人口集中などが理由となり、地方を中心として空き家・空き地が増加し、適切に管理されない土地が急増しました。
その一因となっていたのが、相続登記がなされないまま放置された所有者不明の不動産の存在です。相続登記されず放置されていて所有者不明となった土地は、国の推計によれば、全国で約410万ヘクタールにも及ぶとされています。
このような所有者不明の土地が増え続ける状況を改善し、自治体が所有者の管理を適切に行うために設定されたのが相続登記の義務化です。
関連サイト国土交通省「所有者不明土地を取り巻く 状況と課題について」
相続登記をせずに放置する
リスク・デメリット
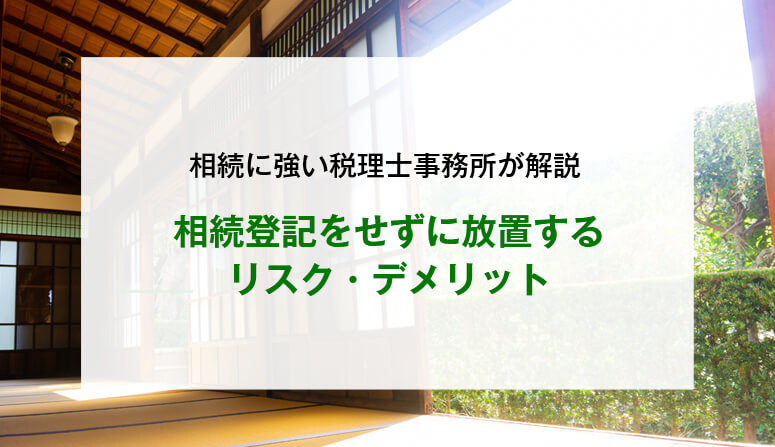
相続登記をしないまま不動産を放置することは、法律上の義務違反となるだけでなく、以下のようなデメリットもあるのでご注意ください。
- 新たな相続が発生し権利関係が複雑になる
- 相続不動産を活用・売却できない
- 他の相続人によって共有持分を売却される恐れがある
このように、相続登記を済ませずにいると、過料が科せられる以外にも問題が発生する恐れがあります。
仕事や家事などで忙しく自分で登記申請することが難しい場合には、司法書士に登記申請を依頼することも検討しましょう。
相続登記の流れ・必要書類
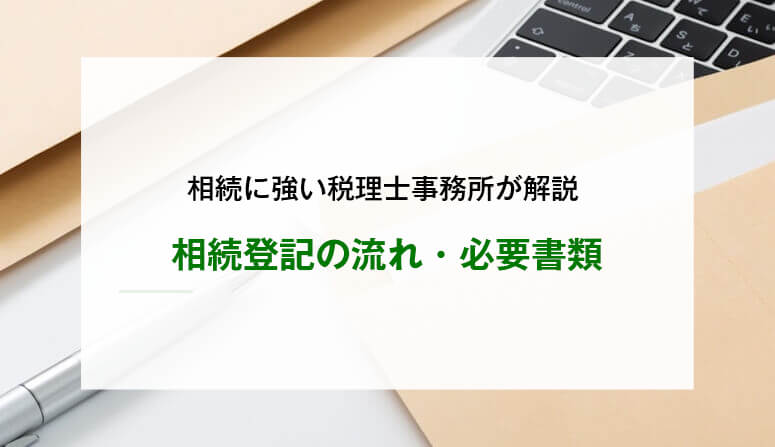
相続登記では、法務局に登記申請書や必要書類を収集する必要があります。具体的には、以下の流れで手続きを進めていきましょう。
- 不動産の所在地の法務局を確認する
- 必要書類の収集と申請書の作成をする
- 登録免許税の計算をする
- 法務局に必要書類を提出し相続登記識別通知を受け取る
それぞれ詳しく見ていきましょう。
不動産の所在地の法務局を確認する
まずは、相続不動産の住所地を管轄する法務局を確認しましょう。相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に対して申請を行うからです。
関連サイト法務局「法務局・地方法務局所在地一覧」
必要書類の収集と申請書の作成をする
続いて、必要書類の収集や登記申請書の作成を行いましょう。相続登記の際には、以下のような書類が必要となります。
- 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本類
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺言書(ある場合)
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合、相続人全員の署名・押印が必要)
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
上記の書類をもとに、法務局所定の様式に従って登記申請書を作成します。
関連サイト法務局「不動産登記の申請書様式について 」
登録免許税の計算をする
相続登記には、登録免許税という税金がかかります。登録免許税は、「不動産の固定資産評価額 × 0.4%」で計算され、例えば、相続不動産の評価額が1,000万円の土地であれば、登録免許税は4万円となります。
評価額は、市区町村が発行する「固定資産評価証明書」で確認可能です。
法務局に必要書類を提出し相続登記識別通知を受け取る
すべての書類と収入印紙を準備できたら、法務局に提出します。提出方法は窓口での対面提出のほか、郵送、オンライン提出も可能です。
申請書類に不備がなければ、通常は1週間から10日前後で登記が完了します。
登記が完了すると、法務局から「相続登記識別通知(登記識別情報)」が交付されるので、内容に誤りがないことを確認し、大切に保管しておきましょう。
関連サイト法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」
相続登記にかかる費用
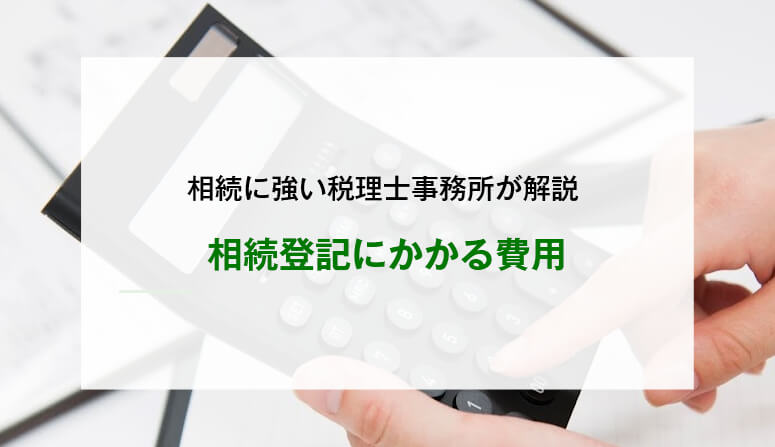
相続登記をする際には、以下の費用がかかります。
- 登録免許税
- 書類収集費用
- 司法書士報酬
それぞれ詳しく見ていきましょう。
書類収集費用
相続登記には、被相続人の戸籍謄本類などいくつか書類を収集しなければなりません。その書類収集費用として数千円程度かかることが一般的です。
ただし、先祖代々土地の名義変更がされていない場合などでは、必要書類の数が増えるのでご注意ください。
関連サイト杉並区「戸籍に関する証明書申請書等 」
司法書士報酬
相続登記は自分で行うだけでなく、司法書士への依頼も可能です。司法書士に依頼した場合には、5万円〜10万円程度の報酬が発生します。
相続手続きは相続登記以外にも様々なものがあり、他の手続きも併せて依頼した場合、費用がその分高額になります。
期限までに
相続登記が完了しない場合の対処法
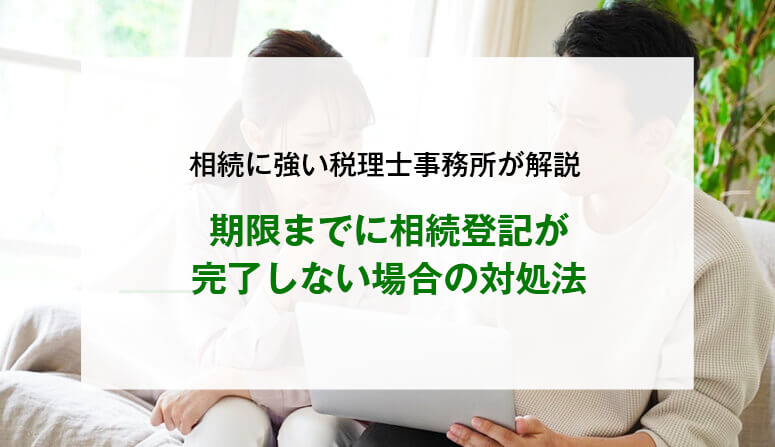
2024年4月からは、相続発生から3年以内に登記申請しないと、10万円以下の過料が科せられる恐れがあります。
とはいえ、すぐに遺産分割協議がまとまらない場合など、相続登記の期限に間に合わないこともあるかもしれません。何らかの理由で相続登記の期限に間に合わない場合には、相続人申告登記を行いましょう。
相続人申告登記とは
相続人申告登記とは、「自分が相続人であること」を登記官に申告できる制度であり、登記義務を一時的に果たすことができます。
関連サイト「相続人申告登記について 」
相続人申告登記をしておけば、期限までに相続登記が完了しなくても過料が科せられることはありません。相続人申告登記の方法や必要書類は、以下の通りです。
相続人申告登記の方法や必要書類
| 手続きする人 |
|
|---|---|
| 手続き先 | 相続不動産の住所地を管轄する法務局 |
| 必要書類 |
|
| 費用 | 無料 |
相続手続きは
杉並・中野相続サポートセンターへ

相続登記が義務化されたことにより、被相続人が不動産を所有していた場合には、相続から3年以内に登記申請を済ませなければならなくなりました。
相続登記を行う際には、相続不動産に関する調査や相続人調査を行う必要があり、書類の収集も必要です。
自分で相続登記や相続手続きをすることが難しい場合には、司法書士などの専門家に相談することも検討しましょう。
相続税手続きは、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
被相続人が不動産を所有していた場合には、被相続人から相続人へ不動産の名義変更をしなければなりません。2024年4月からは相続登記が義務化されたので、相続から3年以内に登記申請を行いましょう。
万が一、相続登記を期限内に済ませられない場合には、相続人申告登記を行いましょう。
また、自分で相続登記を行うことが難しい場合には、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ