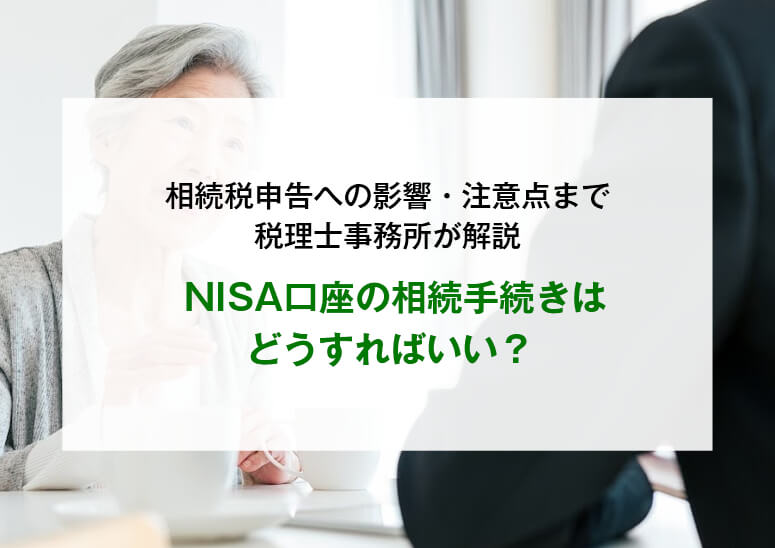
NISA口座の相続手続きはどうすればいい?相続税申告への影響・注意点まで解説
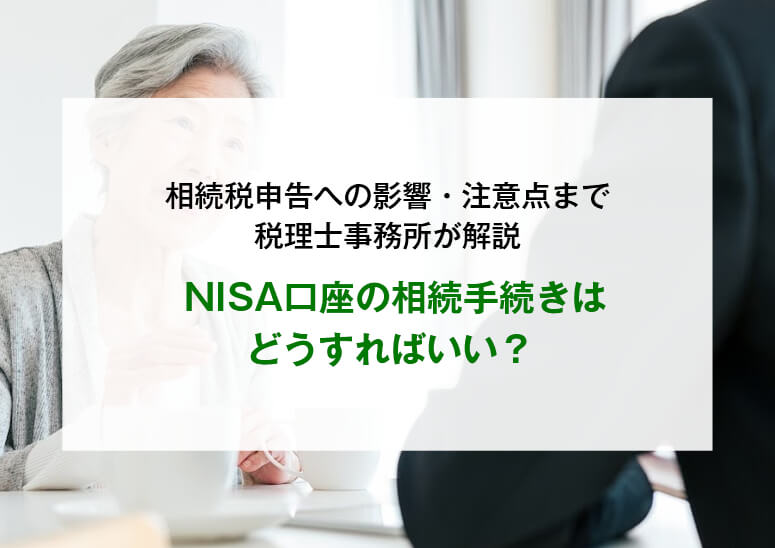
NISA口座は、運用益や配当金が非課税となる個人投資家向けの制度として広く利用されています。
しかし、口座名義人が死亡し相続が発生すると非課税措置はその時点で終了し、残された資産は相続財産として評価・移管されたうえで、通常の課税資産として取り扱われるようになります。このため、相続時の取扱には注意が必要です。
本記事では、NISA口座の相続における取扱いや相続手続きの流れについて注意点を解説します。
目次
NISA口座の相続における取り扱い
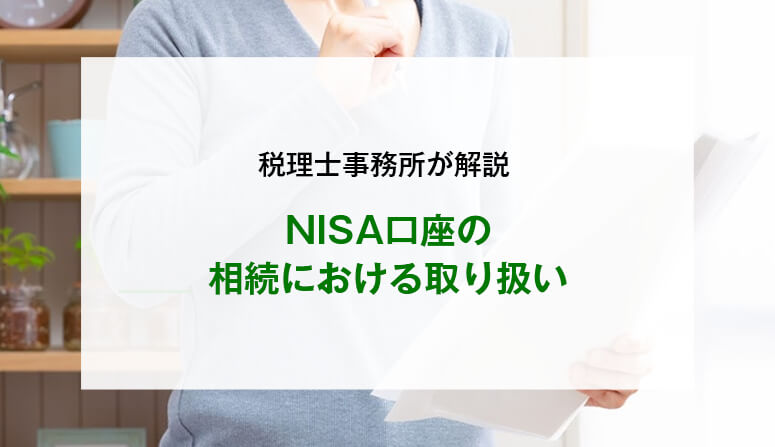
NISA(少額投資非課税制度)は、運用益や配当金が非課税となる個人投資家向けの制度です。しかし、NISA口座を保有している方が亡くなった場合、その非課税の恩恵がそのまま相続人に引き継がれるわけではありません。
相続が発生した時点でNISA口座の非課税措置は終了し、その後に発生した含み益については税金がかかることを理解しておきましょう。
本章では、相続発生時のNISA口座の取り扱いや課税関係について詳しく解説します。
相続開始日までの含み益は非課税となる
NISA口座では、売却益や配当金が非課税になるメリットがありますが、口座名義人が死亡した場合、非課税措置は「相続開始日(被相続人の死亡日)」までしか適用されません。
したがって、相続開始日時点までにNISA口座内で含み益が出ていたとしても、その含み益については非課税扱いになります。
一方で、相続開始後にその資産を売却した場合には、以後の値上がり益については通常の課税口座と同様に、譲渡所得税の対象となる点に注意が必要です。
相続開始時点のNISA口座の残高が相続税の課税対象となる
NISA口座の非課税措置は、あくまで所得税や住民税に関するものであり、相続税には影響しません。そのため、被相続人が保有していたNISA口座内の金融資産は、相続財産として評価され、相続税の課税対象となります。
評価額は、相続開始日時点の時価で算出されることにも注意が必要です。相続開始時点のNISA口座の時価によっては、相続税の負担が重くなることもあるでしょう。
NISA口座に高額な金融資産がある場合には、早い段階から専門家と連携するなどして評価額の把握や相続税の試算といった相続対策を事前に検討しておくことが重要です。
被相続人のNISA口座から相続人のNISA口座に移管することはできない
NISAは個人単位で開設される制度であり、その非課税枠はあくまでその年の本人のために設定されたものです。したがって、相続人が被相続人のNISA口座を「そのまま引き継ぐ」ことは制度上できません。
また、相続人が自分名義のNISA口座を保有している場合であっても、そこに相続財産として受け取った株式や投資信託を移すことはできません。
そのため、移管後に相続した株式を売却すれば、譲渡益に対して所得税および住民税が課されます。
関連サイト「No.1463株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
NISA口座の相続手続きの流れ
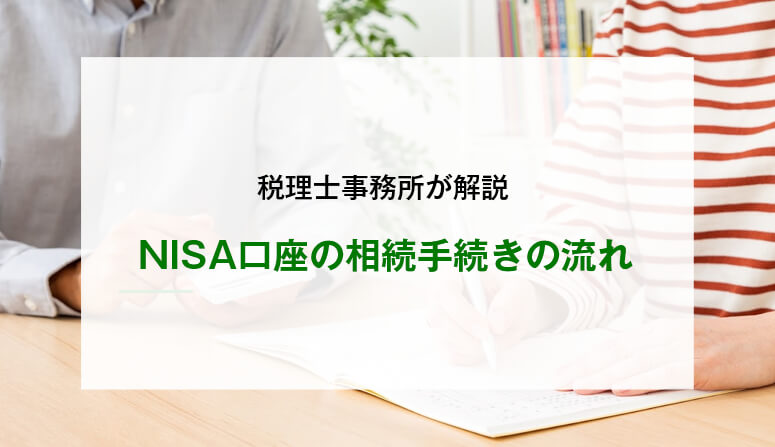
被相続人がNISA口座を所有していた場合、以下の流れで相続手続きを進めていきましょう。
- 被相続人がNISA口座を開設していた金融機関を特定する
- NISA口座の名義人が死亡したことを金融機関へ連絡する
- 必要書類を提出する
- 相続人名義の口座に被相続人のNISA口座の金融資産を移管する
それぞれ詳しく解説していきます。
被相続人がNISA口座を開設していた金融機関を特定する
まずは、被相続人がどの金融機関でNISA口座を開設していたかを確認することです。NISA口座は一人1口座の制度であり、同一年に複数の金融機関で開設することはできません。
しかし、年単位で金融機関を変更していた可能性もあるため、取引履歴や口座のある証券会社・銀行等の情報を整理することが重要です。被相続人の自宅を整理し、通帳、郵送物、メール通知などを確認してみましょう。
特に、被相続人が複数の金融機関にて証券口座を開設していた場合、NISA専用口座はどこにあるかを明確にしなければなりません。
NISA口座の名義人が死亡したことを金融機関へ連絡する
NISA口座を特定したら、次に行うのは金融機関に「口座名義人が死亡した」旨を連絡することです。連絡後、金融機関側でNISA口座は閉鎖処理され、非課税扱いも終了します。
必要書類を提出する
続いて、金融機関に必要書類を提出しましょう。NISA口座の相続手続きに必要な書類は、主に以下の通りです。
- 戸籍謄本(被相続人との続柄がわかるもの)
- 被相続人の除籍謄本または死亡診断書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺言書または遺産分割協議書(遺言がない場合)
- 相続人の本人確認書類(運転免許証等)
- 金融機関所定の相続手続き依頼書
上記を提出すると、金融資産の評価や移管の準備を行ってもらえます。
関連記事株の相続方法と必要書類について
相続人名義の口座に被相続人のNISA口座の金融資産を移管する
必要書類の提出後、金融機関での審査が完了すると、被相続人のNISA口座に保有されていた株式や投資信託等の資産が、相続人の名義の証券口座に移管されます。
ここで注意すべき点は、移管先の口座は「NISA口座ではない」ということです。移管後は相続人の課税口座(特定口座または一般口座)での管理となります。
被相続人が
NISA口座を開設していたときの注意点
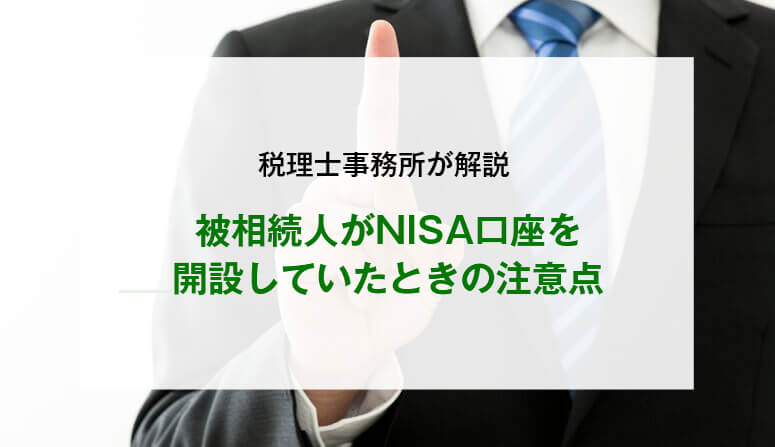
被相続人がNISA口座を所有していた場合、相続時には以下のような点に注意しなければなりません。
- 相続発生によりNISA口座の非課税措置はなくなる
- 新NISAも相続に取り扱いはほぼ同じである
- NISA口座の相続手続きでは相続人も証券口座を用意する必要がある
それぞれ詳しく解説していきます。
相続発生によりNISA口座の非課税措置はなくなる
NISA口座は、生存している本人のためにのみ認められる非課税制度です。そのため、NISA口座の保有者が死亡すると、非課税の扱いは即座に終了します。以降、その金融商品は課税口座に移され、通常の課税対象となります。
新NISAも相続に取り扱いはほぼ同じである
2024年から始まった新NISA制度では、年間の非課税投資枠が大幅に拡充され、生涯非課税投資枠も導入されました。これにより、多くの人が長期的な資産形成を目的として、新NISA口座を開設しています。
しかし、新NISAであっても相続が発生した場合の取扱いは基本的に旧制度と変わりません。非課税の恩恵は相続開始日までで終了し、その後は一般課税口座へ移行され含み益は課税対象となります。
また、移管された金融資産が相続税の課税対象であることも変わりません。つまり、たとえ新NISA口座で高額な資産を保有していたとしても、その非課税枠が相続人に引き継がれるわけではなく、あくまで一代限りの制度と理解しておきましょう。
NISA口座の相続手続きでは相続人も証券口座を用意する必要がある
被相続人がNISA口座で保有していた資産を相続する場合、相続人も証券口座を開設しておく必要があります。
相続された株式や投資信託は、原則として金融機関を通じて相続人の口座に移管されます。その際には、受け皿となる証券口座を開設しておく必要があるからです。
相続人が証券口座を開設していない場合には、相続手続きと併せて開設手続きを行っておかなければなりません。
NISA口座の相続手続き・相続税申告は
当サポートセンターにおまかせください

被相続人がNISA口座で保有していた資産も相続税の課税対象となるのでご注意ください。
被相続人が証券口座やNISA口座を開設していたことに気付かずに相続税の申告をすると、申告漏れとしてペナルティの対象となることもあります。
また、遺産の種類が多い場合や、評価が複雑な遺産がある場合、相続税申告に専門的な知識や経験が必要となるので、自分で相続税申告するのが難しいこともあるでしょう。
相続税の計算や申告は、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
NISA口座は生前の資産形成に有効な制度ですが、相続発生時には非課税の恩恵が終了し、通常の課税資産として扱われます。
相続手続きには、金融機関への連絡や必要書類の提出、相続人名義の証券口座の準備などを行う必要があります。
2024年から始まった新NISA制度でも、相続における取扱いは変わらないため、今後ますますNISA口座の相続対策が必要となってくるでしょう。
不安なことがある場合や疑問点がある場合には、相続に精通した税理士に相談してみることをおすすめします。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ