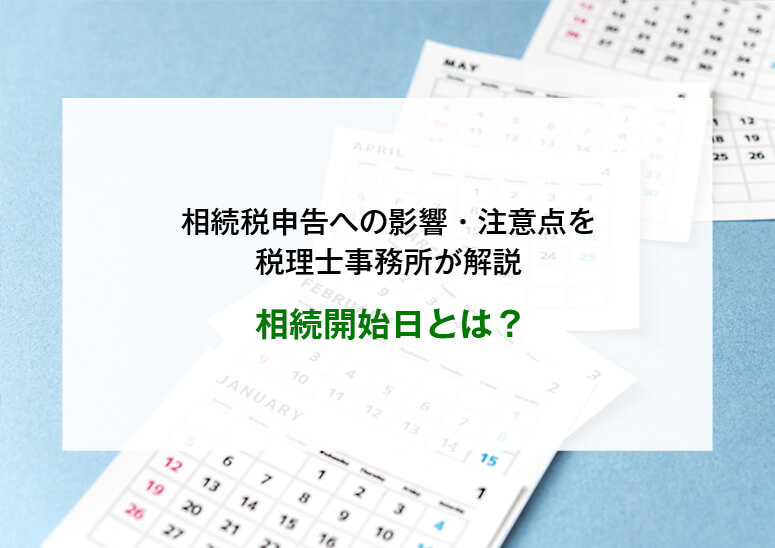
相続開始日とは?相続税申告への影響・注意点を税理士事務所が解説
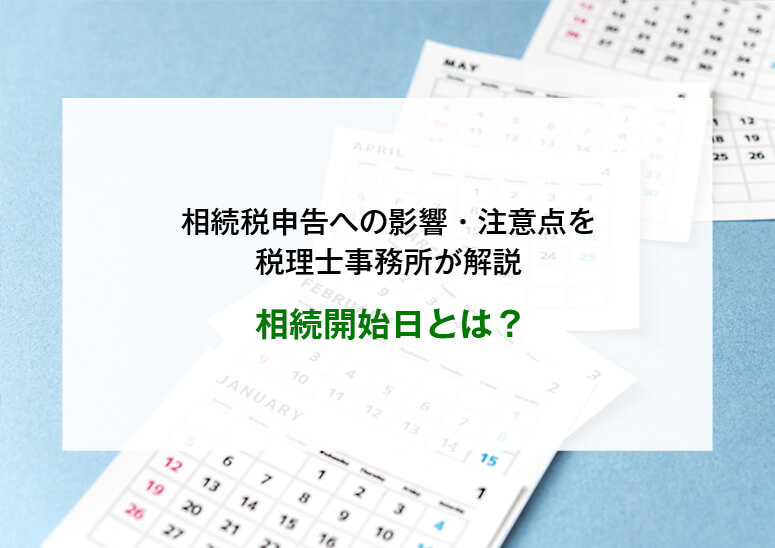
相続手続きは、被相続人の「死亡」によって始まりますが、その起点となるのが「相続開始日」です。相続手続きの中には期限が設定されているものもあるので、相続開始日を正しく理解しておくことは非常に重要です。
相続開始日は基本的に被相続人の死亡日となりますが、死亡時の状況によっては、相続開始日の判断が複雑となるのでご注意ください。
本記事では、死亡時の状況別に相続開始日はいつになるのか、代表的な相続手続きの期限を解説します。
目次
相続開始日はいつ?
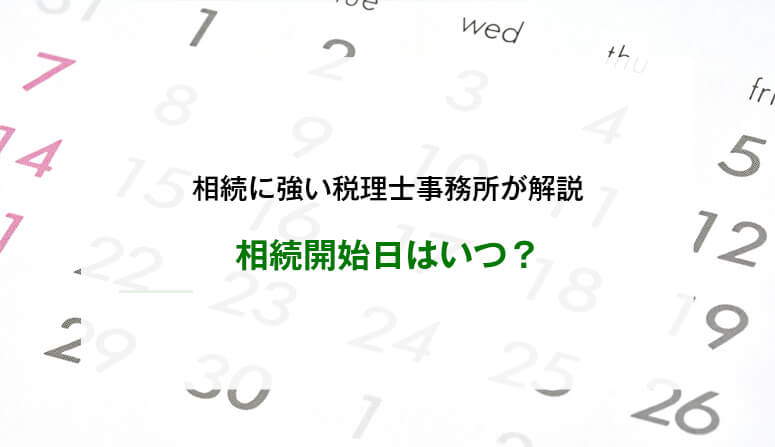
相続開始日とは、相続に関する手続きや申告期限の起点となる日付です。
相続開始日は、原則として被相続人が死亡した日を指しますが、死亡状況によって相続開始日が変わってくることもあるのでご注意ください。
本章では、代表的なケースにおける相続開始日について、詳しく解説します。
自然死亡の場合
被相続人が病気や老衰などにより自然に死亡した場合、死亡日が相続開始日となります。
認定死亡の場合
海難事故や災害、事故などで遺体が確認されないものの、死亡が推定される場合には、認定死亡という手続きが取られることがあります。
認定死亡の場合、死亡の事実が明確でなくとも、状況や証拠から裁判所が死亡を認定し、死亡の日時を定めます。
例えば、海難事故により死亡が推定される場合には、事故発生日が死亡日(相続開始日)となることが一般的です。
ただし、認定死亡の場合も、遺族が自分たちで事故発生日を死亡日とすることはできます。認定死亡であっても、裁判上の手続きを経て、死亡日が確定されると理解しておきましょう。
関連サイト国税庁「認定死亡と相続開始があったことを知った日」
失踪宣告の場合
失踪宣告とは、長期間生死不明である人物について、家庭裁判所の判断によって死亡したものとみなす制度です。
関連サイト裁判所「失踪宣告」
失踪宣告には、(1)普通失踪と(2)特別失踪の2種類があります。それぞれの制度の概要や相続開始日がいつになるのかを詳しく見ていきましょう。
普通失踪の場合
普通失踪とは、7年間以上生死が不明である場合に、利害関係者(相続人など)が家庭裁判所に申し立てることで、失踪宣告が認められることです。
普通失踪の場合には、法律上の死亡日は「生死不明となった期間の満了日」とされ、これが相続開始日となります。
例えば、2015年1月1日を最後に音信不通になった方が2022年に普通失踪として失踪宣告された場合、相続開始日は「2022年1月1日」となります。
特別失踪の場合
特別失踪とは、戦争や船舶の沈没、震災などの危難に遭遇して生死が不明になった場合に、1年の経過で失踪宣告が認められるものです。
特別失踪では、危難が去ったと認められるときに失踪者が死亡したとみなされます。つまり、相続開始日は災害などの危難が去ったとされる日になります。
相続開始日と相続開始を知った日の違い
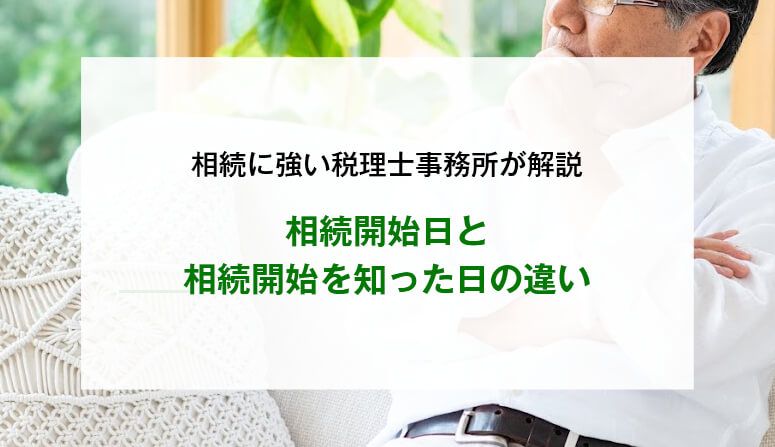
相続に関連する手続きの期限の起算点は、相続開始日だけでなく、相続開始を知った日となるものもあります。
相続開始日と相続開始を知った日は同じ日になることもありますが、相続の状況によっては別日となることもあるのでご注意ください。
相続開始日とは、被相続人が亡くなった日(または死亡が法律上認定された日)を指します。
一方で、相続開始を知った日とは、相続人が「被相続人が死亡したこと」と「自分が相続人であること」の双方を認識した日を意味し、相続放棄や限定承認の申立て期限の起算点となります。
相続開始日と相続開始を知った日の違いが異なるケース
相続開始日と相続開始を知った日が異なるケースとして、代表的なものは、被相続人と相続人が長年音信不通であった場合や、被相続人が遠方でひっそりと亡くなったような場合が挙げられます。
相続開始日と相続開始を知った日の違いが最も重要になるのが、相続放棄や限定承認の申立てをするときです。
これらの手続きは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。
相続手続きの主な期限
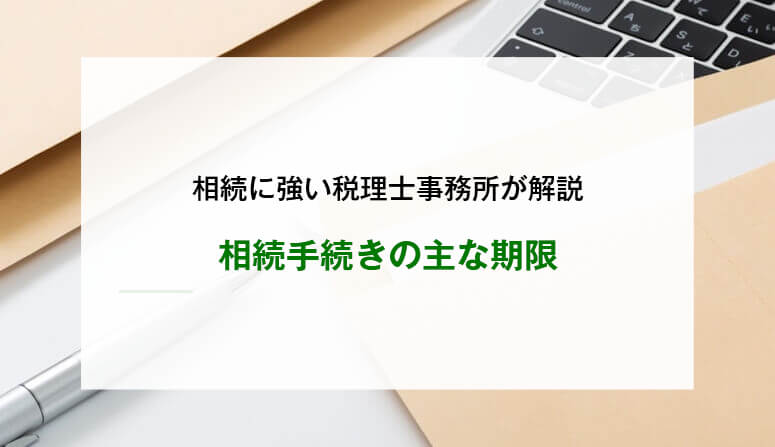
相続が発生すると、相続人は多岐にわたる手続きを限られた期間内に行わなければなりません。
中でも、相続放棄や相続税申告といった期限付きの手続きについては、ひとつでも失念すると取り返しがつかない事態になりかねません。本章では、代表的な相続手続きとその期限について解説します。
相続放棄・限定承認
被相続人が多額の借金を遺していた場合、相続人は相続放棄や限定承認を検討する必要があります。
| 相続放棄 | 被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も一切相続しない |
|---|---|
| 限定承認 | 被相続人のプラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を相続する |
相続放棄や限定承認をする際には、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
準確定申告
準確定申告とは、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに確定申告を行うことです。準確定申告の期限は、相続開始日の翌日から4ヶ月以内とされています。
相続税申告
被相続人の遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税の申告が必要です。相続税の申告期限は、相続開始日の翌日から10ヶ月以内とされています。
遺留分侵害額請求
被相続人が遺言書などで、特定の相続人や第三者に偏った遺贈・贈与を行っていた場合、被相続人の配偶者や子供、両親は、自らの最低限の取り分である遺留分を侵害されたとして、遺留分侵害額請求を行えます。
遺留分侵害額請求の期限は、相続開始および遺留分の侵害を知った日から1年以内または相続開始から10年以内とされています。
相続開始日についてよくある質問
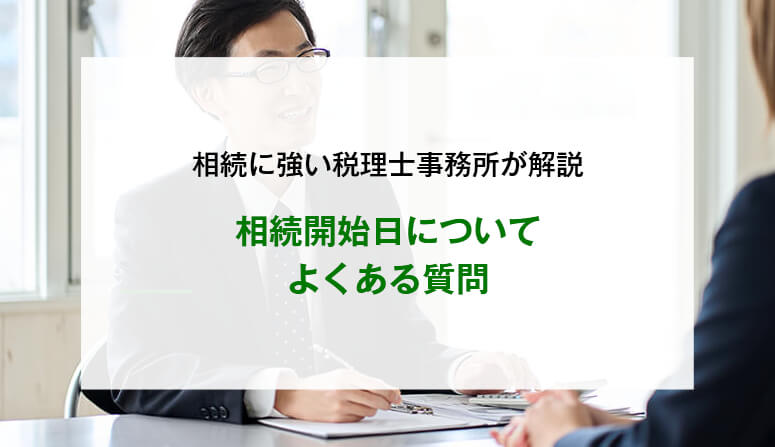
相続開始日は、相続手続きの期限の起算点と重要な日付ですが、実務上は様々なケースがあり、相続開始日の判断が難しい場合もあります。
本章では、相続開始日についてよくある質問を回答と共に紹介していきます。
脳死の場合、相続開始日はいつになりますか?
被相続人が脳死となった場合、相続開始日は心肺が停止し、医師によって「死亡診断書」が発行された日となります。
医学的には「脳死=死亡」と判断されることもありますが、日本の民法では、「心肺の機能が停止した日」が死亡日とされるからです。
相続放棄における「相続開始を知った日」はどのように証明できますか?
相続放棄や限定承認の期限は、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内と定められていますが、相続開始を知った日がいつかは、相続人の主張だけで認められるとは限りません。
家庭裁判所は、以下のような資料をもとに、相続開始を知った日を判断する場合もあります。
- 死亡通知書や死亡診断書を受け取った日付
- 親族や役所から連絡を受けた際の記録
- 除票(住民票の除票)を取得した日
- 死亡届の提出に関与した日
孤独死の場合、相続開始日はいつになりますか?
孤独死の場合、発見された日と死亡した日が異なるケースが多く、相続開始日の特定が難しくなります。
しかし、法律上の相続開始日は「死亡した日」であり、「発見された日」ではありません。このようなケースでは、医師や検察医が「死亡日は◯月◯日頃」と推定し、その日が戸籍に「死亡日」として記載され、相続開始日が確定します。
相続手続きは
当サポートセンターにお任せください

ほとんどの相続開始日は被相続人の死亡日となりわかりやすいですが、死亡時の状況によっては相続開始日や死亡日の推定が必要になるのでご注意ください。
被相続人と相続人が疎遠だった場合や、被相続人が長年行方不明だった場合には、相続手続きをするのが難しいこともあるでしょう。
相続手続きは、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
相続開始日は多くの相続手続きの起点となりますが、死亡の状況によって判断基準が異なるため、慎重に確認しなければなりません。
一方、相続放棄や限定承認の期限は、相続開始日ではなく相続開始を知った日なのでご注意ください。
相続手続きは期限が設定されているものも多く、自分たちだけで漏れなく進めることは難しい場合もあるでしょう。その場合には、相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ