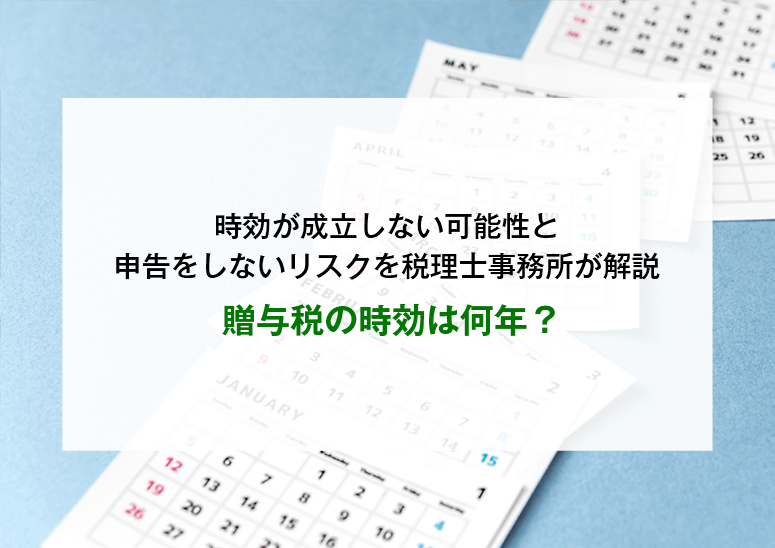
贈与税の時効は何年?時効が成立しない可能性・申告をしないリスクを解説
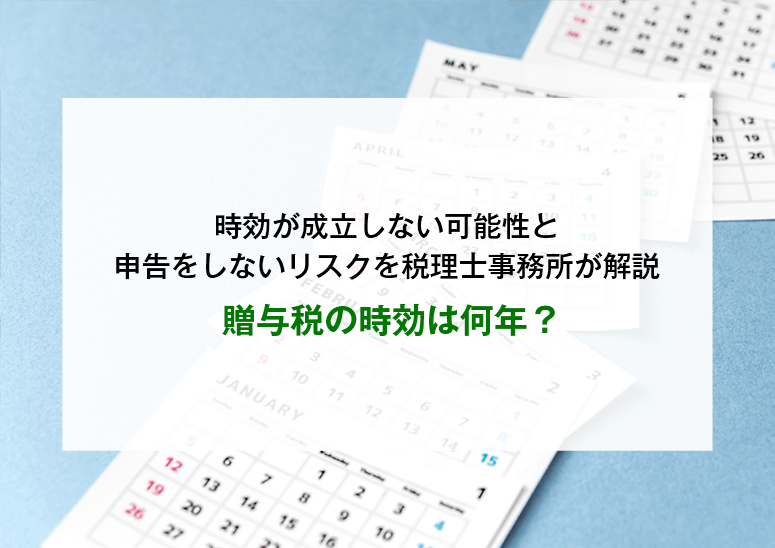
贈与税には原則6年、隠蔽等がある場合は7年という「時効(除斥期間)」が存在します。
しかし、実務ではこの贈与税の時効が成立するケースは決して多くありません。親子間の資金移動は税務署が把握しやすく、特に相続税の調査では過去の贈与が詳細に確認されるためです。
また、贈与契約書や使途の記録がない現金手渡しの贈与は、贈与が成立していないとみなされ、相続税の課税対象となる恐れもあるのでご注意ください。
本記事では、贈与税の時効は何年か、成立しにくい理由、申告しないリスクについて相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが詳しく解説します。
目次
贈与税の時効期間は原則6年
重加算税がある場合は7年
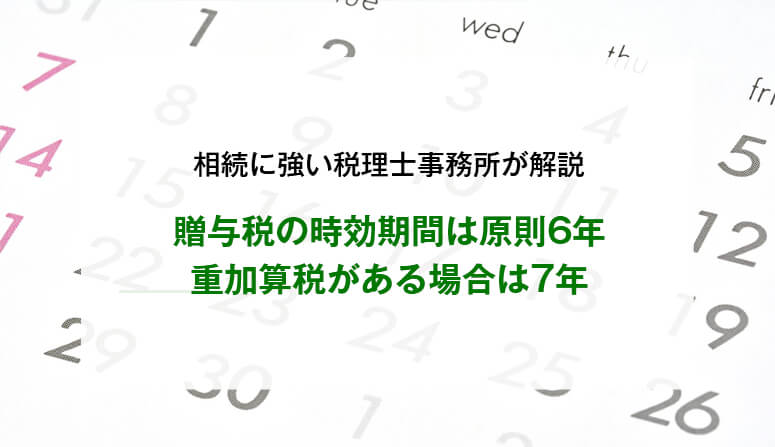
贈与税の時効(除斥期間)は原則として6年であり、偽りや不正が認められるような悪質なケースでは7年の除斥期間が適用されます。
本章では、贈与税の時効について詳しく解説していきます。
通常の時効期間は6年(贈与税の除斥期間)
贈与税は、原則として6年が時効期間とされています。
すなわち、贈与を受けた翌年の3月15日(贈与税の申告期限)から起算して6年が経過すると、その贈与に対して税務署は課税処分を行えなくなります。
関連サイト国税庁「No.4429贈与税の申告と納税」
意図的な無申告や隠蔽があると7年の除斥期間が適用される
納税者が贈与を「隠そうとした」と税務署に判断されると、時効に至るまでの除斥期間は7年が適用されます。贈与税の時効(除斥期間)7年が適用される主なケースは以下の通りです。
贈与税の時効(除斥期間)7年が適用される代表的な例
- 名義預金を故意に隠した
- 不正な名義変更で贈与を偽装した
- 贈与を受けた事実を意図的に申告しなかった
- 税務調査で虚偽の説明をした
通常の無申告は6年で時効が完成しますが、「隠蔽・仮装」があると判断されると、当初から7年の除斥期間が適用されます。
実務では、相続税の調査で過去の贈与が問題になるケースが多く、特に名義預金や不自然な預金移動がある場合は7年間の除斥期間が適用される例がよく見られます。
贈与税の時効の起算日はいつ?
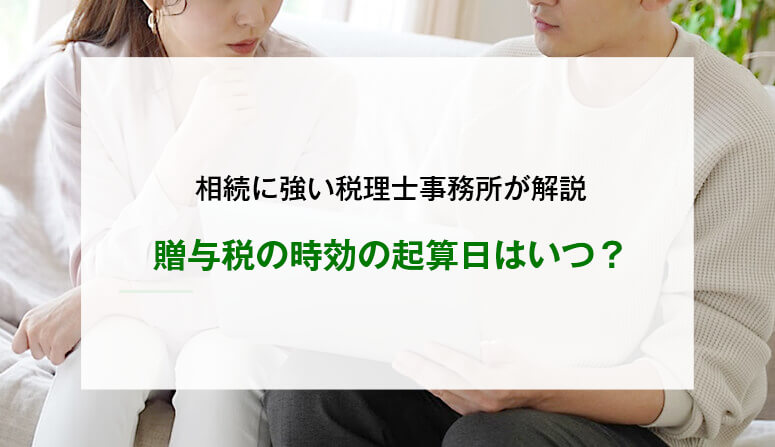
贈与税の時効の起算日は、贈与を受けた翌年の3月15日(申告期限日)です。例えば、2025年に贈与を受けた場合の時効は、以下の通りです。
2025年に贈与を受けた場合の時効
| 時効の起算日 | 2026年3月15日 |
|---|---|
| 通常の時効満了 | 2033年3月15日(6年) |
| 隠蔽がある場合の時効満了 | 2034年3月15日(7年) |
また、贈与が複数回に分かれている場合、それぞれの贈与について独立して時効が進行します。
例えば、毎年110万円を超える贈与が10年間続いていた場合、10件それぞれに別々の時効が存在するイメージです。
なぜ贈与税の時効は成立しにくい?
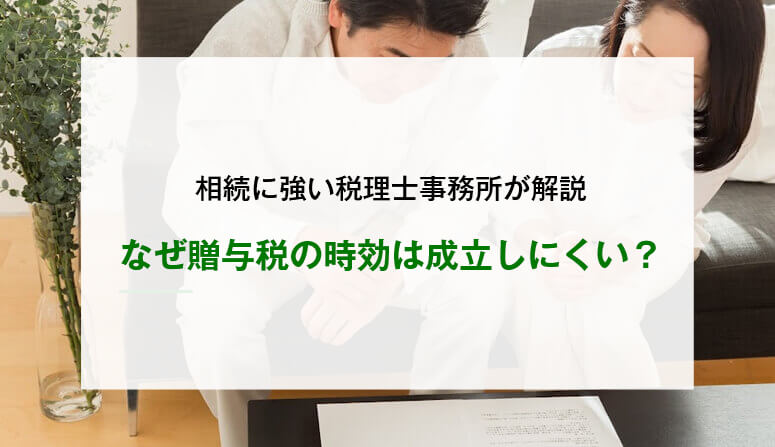
贈与税には時効が設定されているものの、実際には成立しにくいのでご注意ください。贈与税の時効が成立しにくい理由は、主に以下の通りです。
贈与税の時効が成立しにくい理由
- 贈与契約書や使途の記録がないと時効の成立が難しい
- 税務調査により隠蔽・仮装が認定されると7年の除斥期間が適用される場合がある
- 仮に贈与税の時効が成立しても相続税として課税される場合がある
それぞれ詳しく解説していきます。
贈与契約書や使途の記録がないと時効の成立が難しい
贈与税の時効を主張するには、「そもそも贈与がなかった」または「贈与があっても時効期間を経過している」ことを説明する必要があります。
しかし、贈与契約書や金銭の使途を示す資料がない場合、そもそも贈与の有無を巡って税務署と争うことになり、納税者の主張が認められないケースが少なくありません。
特に、名義預金や生活費の立替えなど、親子間で曖昧な金銭移動がある場合には、贈与と生活費負担の区別が曖昧になりがちです。
税務署は「通常の生活費か」「扶養の範囲内か」を厳格に判断するため、使途が不明な資金は贈与とみなされやすくなります。
調査可能期間が長期化して見える場合がある
贈与税の時効(除斥期間)は、法律上 原則6年と定められています。
しかし実務上は、税務署の調査や質問検査権の行使によって事実関係が明らかになり、結果として7年分さかのぼって課税されるケースが少なくありません。
例えば、以下のような対応では贈与の態様が確認されることがあります。
- 税務署からの「お尋ね」や照会文書が届く
- 税務調査が行われる
- 税務署から金融機関への資料開示請求が行われる
これらは、時効(除斥期間)を途中で延ばす行為ではありませんが、調査の結果、贈与が 意図的な隠蔽・仮装を伴うものと判断された場合には、もともと7年の除斥期間が適用されることになるため、調査可能期間が長期化しているように見えることがあります。
「あと数ヶ月で時効が完成する」と思っていても、税務署が調査を行い事実関係を把握すれば、7年の時効(除斥期間)を前提として課税関係が判断されるのでご注意ください。
このように、時効を期待して贈与税の申告をしない判断は極めて危険であり、実務では時効を盾にした節税はほぼ成立しないと言っても過言ではありません。
仮に贈与税の時効が成立しても相続税として課税される場合がある
たとえ贈与税が時効により課税されなかったとしても、相続時にその贈与が「相続税の課税対象」として扱われる場合があります。
例えば、過去に現金手渡しで贈与を行い、贈与税の申告をせずに時効を迎えたケースを考えてみましょう。
このようなケースでは、贈与者が亡くなったときに、以下のような主張をすることがあります。
- そもそも贈与の事実は存在していない
- 現金は被相続人(贈与者)の遺産に含まれる
上記のようなケースでは、贈与税は課税されなくても、過去の贈与財産が相続税の課税対象となってしまうケースがあります。
贈与税を申告しないリスク・ペナルティとは?
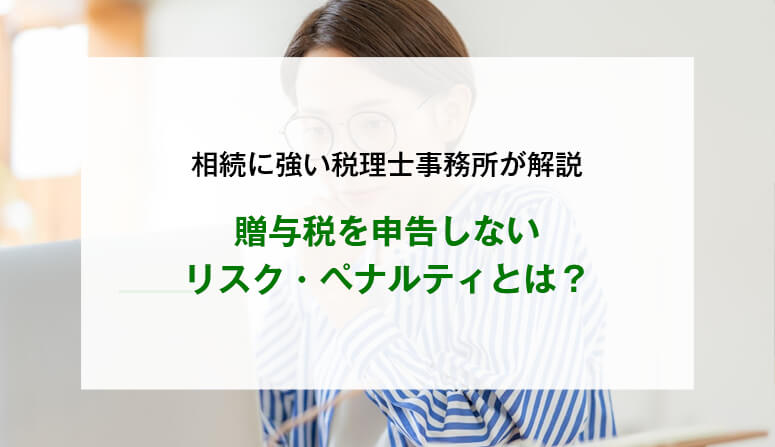
贈与を受けたにもかかわらず、贈与税を申告しないでいると、以下のような追徴課税が課せられる恐れがあります。
贈与税を申告しないことで課せられる可能性がある追徴課税
- 無申告加算税
- 重加算税
- 延滞税
ここからはそれぞれの追徴課税の詳細について、詳しく解説していきます。
無申告加算税
贈与税の申告が必要であったにもかかわらず申告しなかった場合、贈与税そのものに加えて無申告加算税が課されます。
無申告加算税が課されると、本来納めるべき税額(本税)に対して、一定割合を掛けた追加の税金が課されます。
税務署から指摘される前に自主的に申告すれば軽減される場合がありますが、通常は以下の税率で加算されます。
無申告加算税が課せられた場合の加算される税率
| 税務署からの事前通知より前に自主申告した場合 | 5% |
|---|---|
| 税務調査の事前通知後~調査着手前に申告した場合 | 10%(50万円を超える部分15%) |
| 税務調査後に申告した場合 | 15%(50万円を超える部分は20%) |
自主的な申告であればペナルティは最小限で済みますが、税務署から連絡や調査が来てからでは税率が上がり、支払う税額は大きくなります。
また、無申告額が高額である場合や、過去にも無申告があるなど悪質性が高いと判断された場合には、300万円を超える部分について税率が加重されることがあります。
さらに、隠蔽・仮装などの悪質性の高い行為が認められると重加算税の対象となり、無申告加算税よりも厳しい処分が下される可能性があります。
重加算税
重加算税は、納税者が故意に事実を隠したり、虚偽の説明を行ったりした場合に課される最も重いペナルティです。無申告加算税の場合と同様、本来納めるべき税額(本税)に対して、一定割合を掛けた追加の税金が課されます。
贈与税では、名義預金を意図的に隠したり、現金贈与を無申告のまま帳簿上処理したりするなど、「隠蔽・仮装」があったと税務署が判断した際に適用されます。その税率は非常に高く、無申告で、かつ隠蔽・仮装が認定された場合には40%の税率が課せられます。
さらに、重加算税の対象となる場合、当該贈与については当初から贈与税の時効(除斥期間)7年を前提として課税関係が判断されます。
延滞税
贈与税には延滞税と呼ばれる利息のようなペナルティも課せられます。これは、納期限までに税金を納めなかった場合に、納付が遅れた期間に応じて課せられるものです。
延滞税の税率は、その年の状況によって異なりますが、令和7年の税率は以下の通りです。
| 納期限後2ヶ月以内 | 2.4% |
|---|---|
| 納期限から2ヶ月経過後 | 8.7% |
延滞税の特徴は納期限の翌日から完納日まで日割りで計算され、発生した日から累積していく点にあります。
税務署から指摘されて数年遅れで納付することになれば、延滞税だけで数十万円に達することも珍しくありません。
関連サイト国税庁「No.9205延滞税について」
贈与税の申告は
杉並・中野相続サポートセンターに
ご相談ください

贈与税には時効が設定されているものの、時効成立は難しいと理解しておきましょう。贈与税を節税したいのであれば、控除や特例を利用するなど正しい方法で節税対策することが重要です。
贈与税の申告や節税対策に不安がある場合には、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
贈与税の時効(除斥期間)は、原則として6年であり、隠蔽がある場合には7年の除斥期間が適用されます。
時効が定められているとはいえ、税務署の調査能力や資料収集の仕組みを踏まえると、実際には「時効で逃げ切れる」可能性は極めて低いといえるでしょう。
また、時効(除斥期間)の進行は調査によって隠蔽・仮装が認定されると時効成立までに7年の除斥期間が適用されることもあり、申告しなかった場合には無申告加算税や延滞税といった追加負担も発生するリスクがあります。
さらに、贈与税の時効が成立しても相続時に課税されるケースもあるため、適切な申告と記録管理が最も安全な対策です。
贈与を行う際は、相続や生前贈与に精通した税理士へ相談し、正確な申告とリスク管理を行うことが重要です。











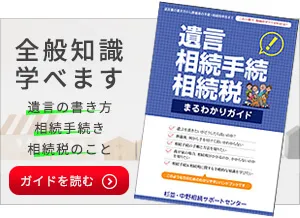
 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ