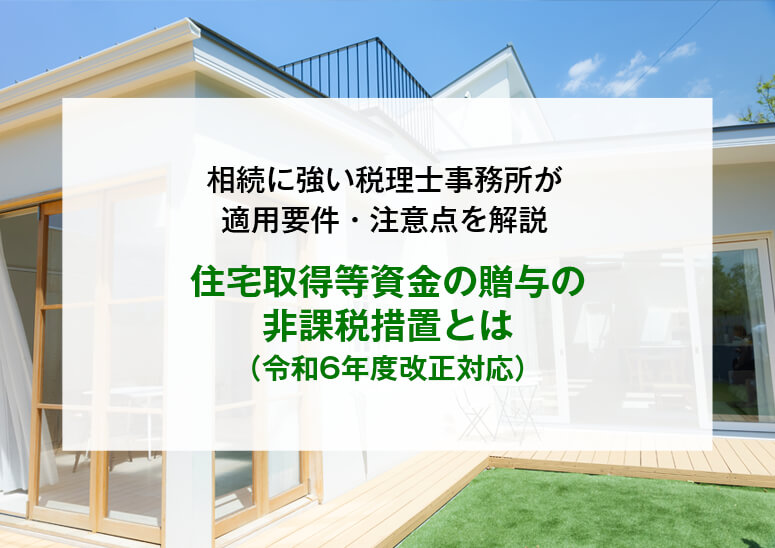
住宅取得等資金の贈与の非課税措置とは(令和6年度改正対応)適用要件・注意点を解説
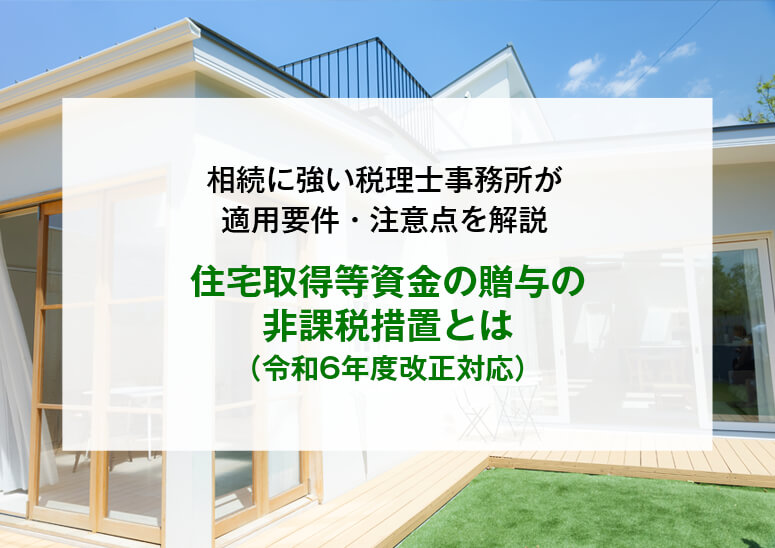
「住宅取得等資金の贈与の非課税措置」を活用すれば、両親や祖父母などの直系尊属からの生前贈与を最大1,000万円まで非課税で受け取ることができます。
生前贈与された資金の使い道は住宅の新築・購入・増改築・リフォームに限定されますが、人生の中でも大きな支出である住宅資金に充てられるのは大きな魅力です。
一方で、この制度を利用すると将来の相続における「小規模宅地等の特例」が使えなくなるなど、注意すべき点もあります。
本記事では、相続専門の税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが、令和6年度改正後の「住宅取得等資金の贈与の非課税措置」の内容や注意点をわかりやすく解説します。
目次
住宅取得等資金の贈与の非課税措置とは
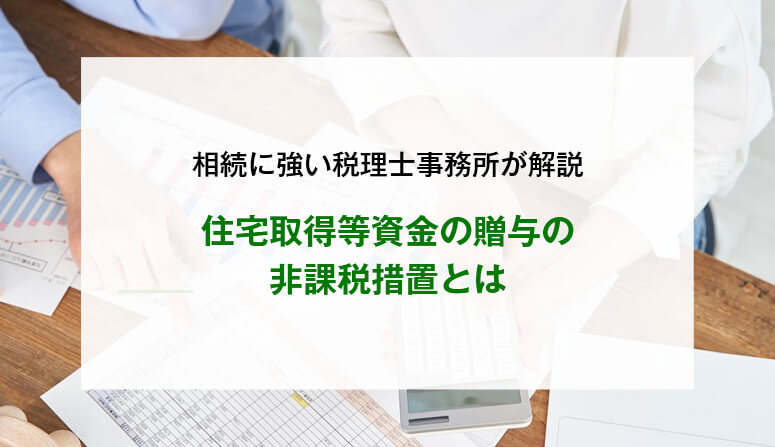
住宅取得等資金の贈与の非課税措置とは、住宅の購入やリフォームなどの目的で贈与を受けた資金について、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。
通常、贈与税には年間110万円までの基礎控除しかありませんが、この制度を利用すれば、より大きな金額を非課税で贈与できます。
関連サイト国税庁「No.4402贈与税がかかる場合」
この制度は、一定の要件を満たす新築住宅および既存住宅・増改築の際に活用できます。令和6年度税制改正により2026年(令和8年)12月31日まで延長されました。これから住宅購入・改修をしようとしている人や、子・孫に生前贈与をしたい人にとってはうれしい制度と言えます。
最新の非課税限度額(令和6年改正後)
| 住宅の種類 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 耐震・省エネまたはバリアフリー住宅 | 1,000万円 |
| 上記以外の住宅 | 500万円 |
関連サイト国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」
住宅取得等資金の贈与の非課税措置の
適用要件
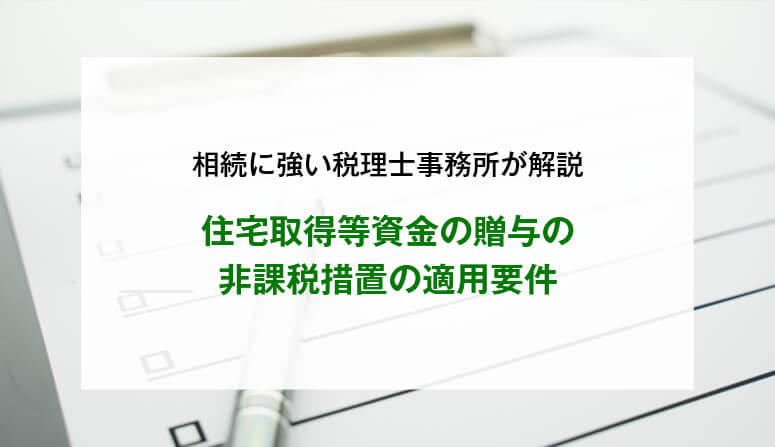
この制度を利用するには、受贈者(もらう側)・贈与者(あげる側)の要件に加え、取得・改修する住宅にも要件があります。
受贈者(もらう側)の要件
住宅取得等資金の贈与の非課税措置の受贈者(もらう側)の適用要件は以下の通りです。
- 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
- 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
- 平成21年分から令和5年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けたことがないこと
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金で住宅を取得し居住を開始すること
- 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
- 原則、贈与を受けた時点で日本国内に住所を有していること
贈与者(あげる側)の要件
贈与を行う側は受贈者の両親や祖父母など直系尊属でなければなりません。配偶者の子供や孫に贈与を行った場合、非課税措置の適用はできないのでご注意ください。
また、配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当せず、適用対象外となりますが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当し、非課税措置の対象となります。
住宅の要件
住宅を新築・購入した場合
住宅取得等資金の贈与の非課税措置には購入や改修を行う住宅の条件も設定されています。
- 登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
※合計所得金額が1000万円以下の受贈者(もらう側)に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用可能 - 工事後の床面積が40㎡以上240㎡以下になること
- 床面積の2分の1以上が受贈者の居住用であること
住宅を増改築・リフォームした場合
- 工事費用が100万円以上であること
- 自己所有・居住用の住宅であること
- 「増改築等工事証明書」等の証明書類があること
制度適用の可否は物件や工事内容によって異なります。ハウスメーカーや税理士に事前確認をしましょう。
住宅取得等資金の贈与の非課税措置の
利用がおすすめなケース
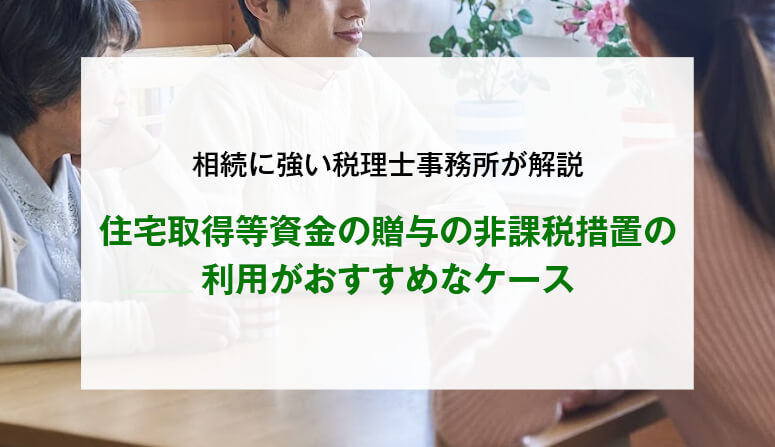
以下のような方には、住宅取得等資金の贈与の非課税措置の活用をおすすめします。
- 子や孫に向け住宅取得資金をすでに準備している人
- 今後、独立して住宅を取得・新築しようとしている家族がいる人
- 相続対策を行いつつ、子や孫の住宅取得を支援したい人
ただし、住宅取得等資金の贈与の非課税措置を利用すると、将来の相続で「小規模宅地等の特例」が使えなくなる場合があります。そのため、相続全体の見通しを含めて検討することが大切です。
住宅取得等資金の贈与の非課税措置の
注意点
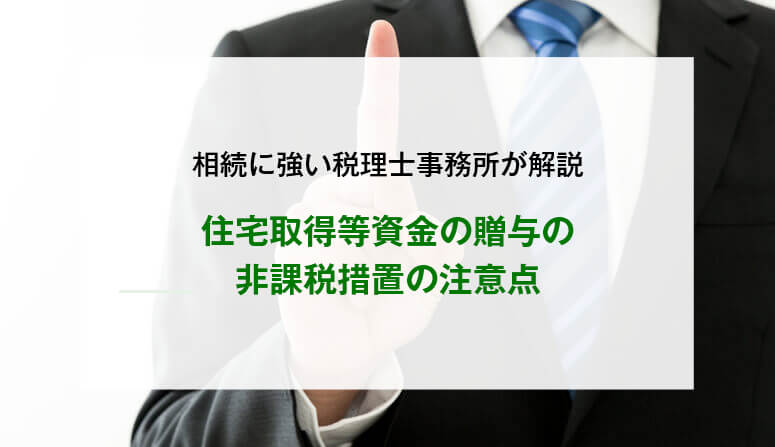
住宅取得等資金の贈与の非課税措置と小規模宅地等の特例と併用できない
小規模宅地等の特例とは相続時に被相続人が所有していた330㎡までの土地を最大80%評価減にできる制度です。
相続税は全ての相続財産の評価額の合計によって決まるので、土地の評価額を下げられればそれだけ相続税の金額も下げることが可能です。
しかし、小規模宅地等の特例の適用要件には、被相続人と同居していたこともしくは別居していた場合、自宅を受け継ぐ方が自分の住宅をまだ持っていないことが含まれています。
そのため、この住宅取得等資金の非課税措置を利用して住宅を取得してしまうと、「自分の家を所有している」とみなされ、非課税特例の適用対象から外れる可能性があります。
相続税額への影響が大きいため、どちらの制度を優先すべきかは専門家と相談しましょう。
住宅取得等資金の贈与の非課税措置を適用すると贈与税が0円でも申告が必要
非課税枠内で贈与税が0円となっても、贈与税申告書の提出は必須です。住宅取得等資金の贈与の非課税措置を活用した結果、贈与税が0円になったとしても贈与税の申告書の提出が必要です。
贈与税の申告書提出時には、申告書だけでなく受贈者と贈与者の関係を証明する書類や住宅購入を証明する書類などの添付も必要になります。申告期限(翌年3月15日)を過ぎると非課税が認められない場合があるため、早めの準備をおすすめします。
相続トラブルの火種になることも
相続人が複数いるにも関わらず、一人の子や孫だけが住宅取得資金を受け取ると、他の相続人に不公平感が生まれ、将来的な相続トラブルの原因になる場合もあります。
生前贈与を行う際は、他の相続人への説明や遺言書の準備も含めて慎重に進めましょう。
相続税対策・生前贈与は
当サポートセンターにお任せください

住宅取得等資金の贈与の非課税措置は節税効果が大きい一方で、他の相続税特例との兼ね合いも重要です。
- 住宅取得資金の贈与の非課税措置を使うべきか迷っている
- 小規模宅地等の特例と住宅取得資金の贈与の非課税措置の比較が難しい
- 生前贈与・相続税対策のタイミングを相談したい
このようなケースでは、相続を専門に扱う税理士に相談するのがおすすめです。相続専門の税理士に相談すれば、あなたに合った相続税対策や生前贈与のプランを立ててもらえます。
杉並・中野相続サポートセンターでも、相続税対策や生前贈与の計画から実行まで一括でサポートを行っています。相続や生前贈与に関する疑問やお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
住宅取得等資金の贈与の非課税措置を利用すれば、住宅取得のための生前贈与を最大1,000万円まで非課税にできます。 ただし、小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性があるため、相続全体を見据えた判断が必要です。どちらの制度を優先すべきか迷う場合は、ぜひ相続専門の税理士にご相談ください。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ