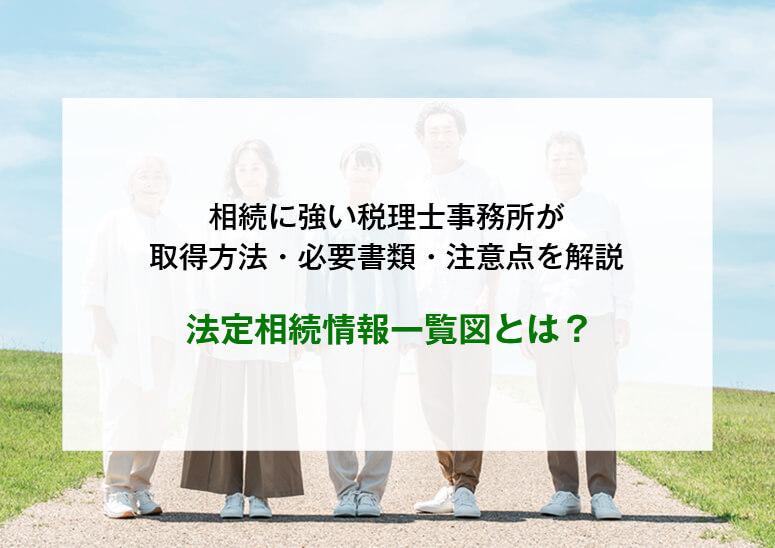
法定相続情報一覧図とは?取得方法・必要書類・注意点を解説
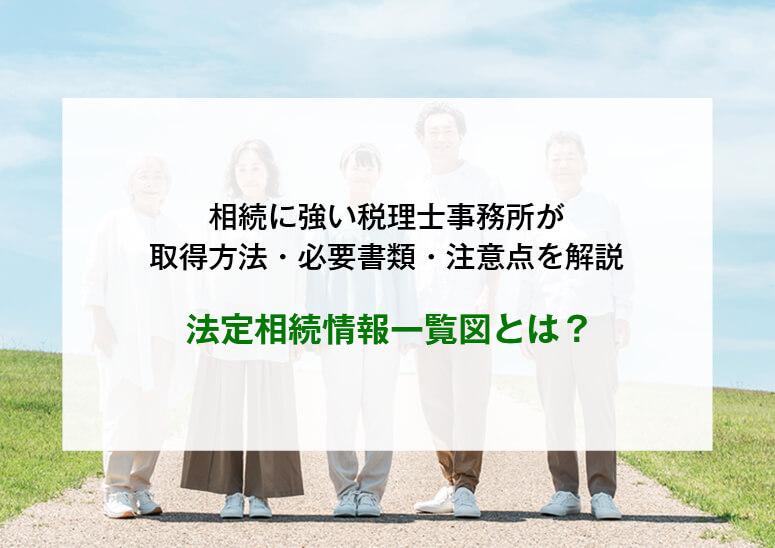
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍を揃える必要があり、その量や複雑さに戸惑う方も少なくありません。
そこで役立つのが「法定相続情報一覧図」です。
法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係をまとめた書類であり、写しを法務局が発行してくれます。
法定相続情報一覧図の写しは公的な書類として、相続手続きの際に活用できます。本記事では、法定相続情報一覧図とは何か、作成するメリット・デメリット、手続き方法を解説します。
目次
法定相続情報一覧図とは
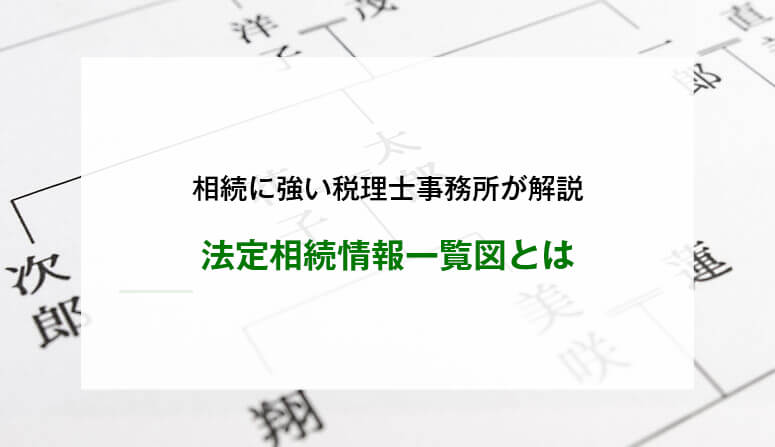
法定相続情報一覧図とは、被相続人の戸籍一式をもとに相続人の範囲や続柄を図式化し、登記官がその内容を証明した書類です。
手続き後は、法定相続情報一覧図の写しを取得し、相続手続きの際に必要書類として提出できます。
関連サイト法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」
従来であれば、相続手続きを行う際、各種金融機関や役所に戸籍謄本一式を提出する必要があり、必要書類の数も多く、書類や提出先によっては原本を用意する必要があり、相続人にとって大きな負担となっていました。
法定相続情報証明制度が新設されたことにより、一覧図の写しを利用し、相続手続きを効率よく行えるようになりました。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い
相続に関する書類として「相続関係説明図」というものも存在します。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図は似ていますが、以下のような違いがあります。
| 項目 | 法定相続情報一覧図 | 相続関係説明図 |
|---|---|---|
| 作成する人物 | 相続人が作成し、法務局が内容を確認する | 相続人や代理人(司法書士など)が任意に作成するもの |
| 効力 | 公的な証明力があり、相続手続きで戸籍謄本類の代わりに提出できる | 登記申請時に添付すれば戸籍の返却を受けられるメリットがあるが、公的な証明力はない |
| 利用範囲 | 様々な機関にて提出書類として認められている | 一部の機関では提出書類として認められない |
法定相続情報一覧図を利用できる手続き
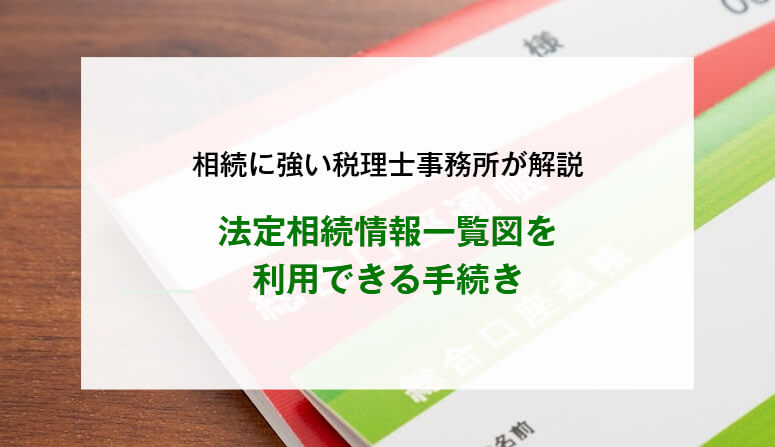
法定相続情報一覧図は、相続に関連する様々な手続きで活用できます。代表的な例は、以下の通りです。
- 不動産の相続登記
- 銀行や証券会社での相続手続き
- 生命保険金や年金の請求
- 相続税申告や準確定申告
このように、法定相続情報一覧図は、相続に関わるほとんどの手続きで戸籍謄本類の代替書類として活用できます。
法定相続情報一覧図を取得する
メリット・デメリット
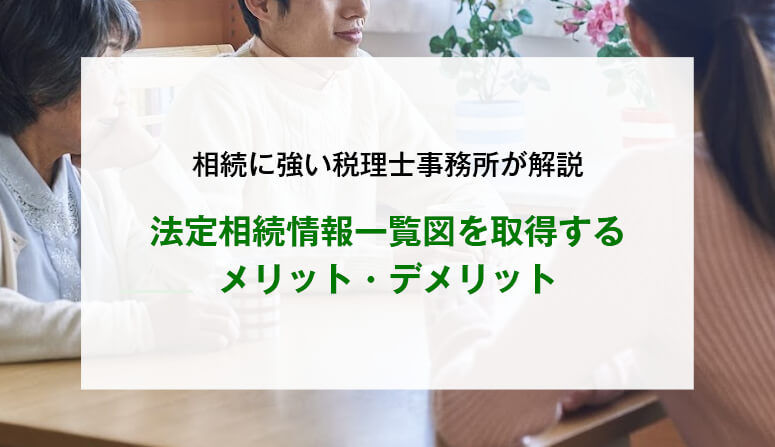
法定相続情報一覧図は相続手続きの効率化を目的に導入された制度であり、活用することで大きなメリットがあります。
本章では、法定相続情報一覧図を取得するメリットとデメリットを整理して解説します。
取得するメリット
法定相続情報一覧図を取得するメリットは、以下の通りです。
- 戸籍謄本一式の提出が不要になる
- 複数の相続手続きを同時進行できる
- 一覧図の写しの交付は無料であり、何通でも取得できる
相続人の人数が多い場合や、それぞれが遠方に住んでいる場合には、法定相続情報一覧図を取得することで、効率よく相続手続きを進められるでしょう。
取得するデメリット
法定相続情報一覧図はすべての相続で効果があるわけではなく、以下のようなデメリットがあります。
- 申請手続きに時間と労力がかかる
- 内容に誤りがあると再申請が必要となる
- 相続手続きによっては利用できない場面もある
- 相続人調査が未完了の場合は使えない
法定相続情報一覧図の申請をする際には、自分で戸籍謄本類を収集し相続人調査を行う必要があります。
相続人が1人の場合や相続手続きの数が少ない場合には、わざわざ申請するメリットが薄い場合もあるでしょう。
法定相続情報一覧図を
取得する方法・必要書類
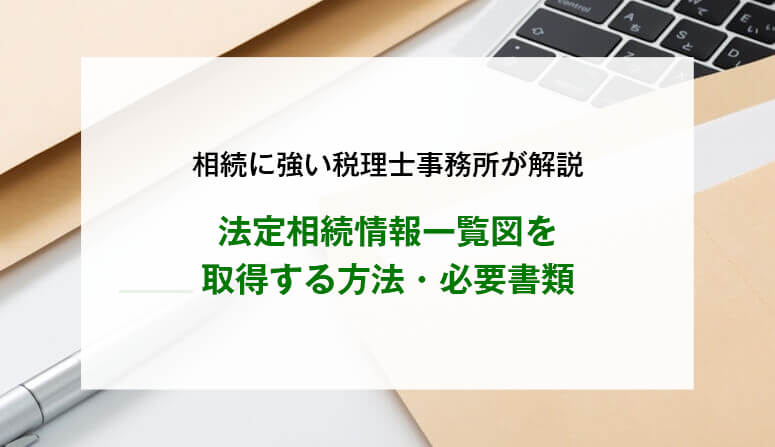
法定相続情報一覧図を取得するには、戸籍を収集し、一覧図の作成、申請を行う必要があります。手続きの流れは以下の通りです。
- 必要書類を収集・準備する
- 法定相続情報一覧図を作成する
- 申請書を記入して登記所へ提出する
それぞれ詳しく解説していきます。
必要書類を収集・準備する
法定相続情報一覧図の申請をする際には、相続人を確定する必要があり、以下のような書類を用意しなければなりません。
法定相続情報一覧図を作成する
法定相続情報一覧図は自分で作成しなければならず「被相続人」と「相続人」の関係を示す家系図のような形式で作成する必要があります。
申請書を記入して登記所へ提出する
そして、申請が受理されたら、法定相続情報一覧図の写しを発行できるようになります。発行手数料は無料なので、相続手続きで提出する分を発行しておくと良いでしょう。
法定相続情報一覧図の費用と有効期限
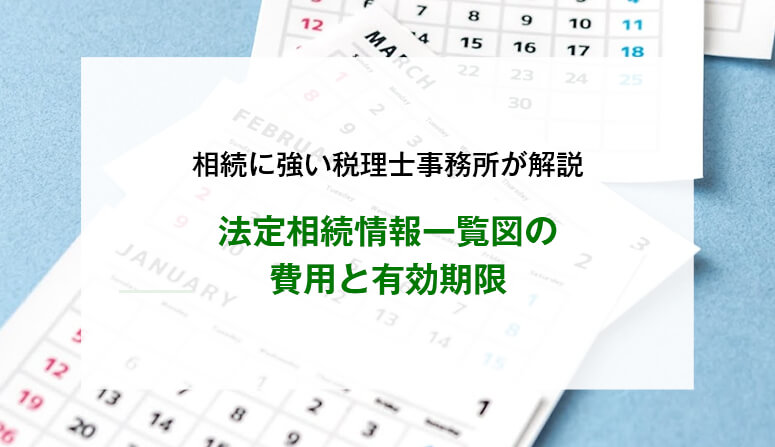
法定相続情報一覧図は、法務局に申請して交付を受けることができますが、申請時や写しを発行してもらう際に手数料は一切かかりません。
相続関係説明図や戸籍の束を何度も発行したりコピーしたりする手間や費用を考えると、法定相続情報一覧図を申請するメリットは非常に大きい効果といえるでしょう。
法定相続情報一覧図の有効期限は設定されていないものの、法務局による保管期間は5年間とされています。
申請から5年経過した後に写しが必要な場合には、再度、法定相続情報一覧図の申請をしなければなりません。
法定相続情報一覧図を
取得するときの注意点
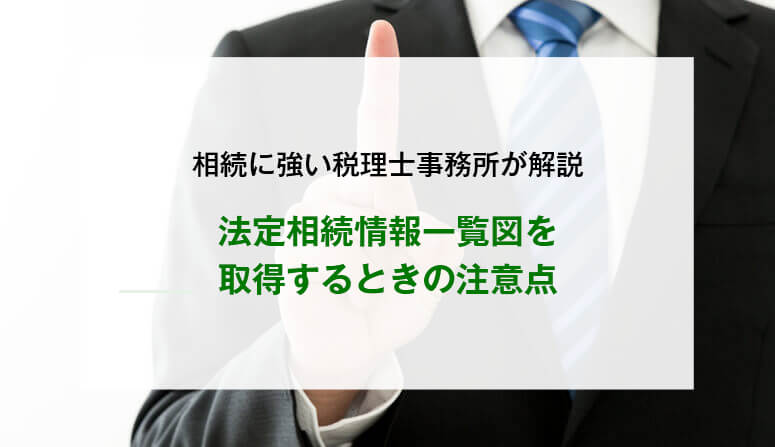
法定相続情報一覧図は便利な制度であるものの、利用時には以下のような点に注意しましょう。
- 外国籍の相続人がいると法定相続情報一覧図を作成できない
- 相続人以外の手続きには利用できない
- 相続放棄した相続人がいると追加書類が必要となる
それぞれ詳しく解説していきます。
外国籍の相続人がいると法定相続情報一覧図を作成できない
法定相続情報一覧図は、日本の戸籍制度に基づいて作成される書類です。そのため、外国籍の相続人が含まれる場合には、日本の戸籍制度の対象外であることから法定相続情報一覧図の作成はできず、交付も受けられません。
同様に、被相続人が外国籍で日本国籍を有しない場合も法定相続情報一覧図の作成はできません。
外国籍の相続人がいるケースで、相続に伴う銀行口座の解約手続き等を行う場合には従来どおり、戸籍謄本類や外国の公的書類(出生証明書や婚姻証明書など)を提出する必要があります。
相続人以外の手続きには利用できない
法定相続情報一覧図はあくまで「法定相続人を証明する」ための書類です。そのため、相続人以外が手続きを行う際に身分証明として使うことはできません。
例えば、遺言執行者や受遺者(遺言で財産を受け取る人)が相続手続きを行う場合には、別途、戸籍謄本や遺言書などが必要となります。
相続放棄した相続人がいると追加書類が必要となる
法定相続情報一覧図には相続放棄の事実は記載されません。また、相続放棄により次順位の相続人が現れたという情報も反映することができません。
法定相続情報一覧図はあくまでも、被相続人と相続人の法定相続における関係性を証明する書類だからです。
そのため、相続放棄をした相続人がいる場合、被相続人の銀行口座の解約等の手続きには法定相続情報一覧図だけでは足らず、相続放棄申述受理証明書等も併せて提出しなければなりません。
相続手続きは
当サポートセンターにお任せください

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本類の代わりに相続手続きの提出書類として使用できるものです。相続人の人数が多く、必要書類の数や手続きの数が多い場合には、作成を検討しても良いでしょう。
なお、相続手続きは自分たちで行うこともできますが、専門家に依頼することも可能です。
相続手続きは、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
法定相続情報一覧図を利用すれば、相続手続きを効率よく行えます。また、法定相続情報一覧図の写しは無料で何枚でも発行できるため、相続人の人数が多い場合にも適しています。
一方で、外国籍の相続人がいる場合や相続放棄がある場合には、制度自体が利用できなかったり、実際の手続き時には法定相続情報一覧図に加えて追加書類が必要になったりするので注意しましょう。
自分で相続手続きを進めることが難しい場合や不安な場合には、相続の専門家に相談することも検討すると良いでしょう。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ