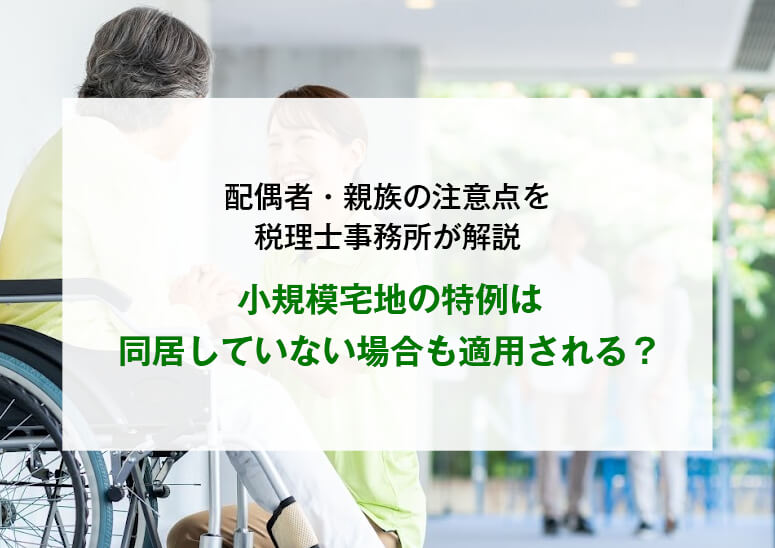
小規模宅地の特例は同居していない場合も適用される?配偶者・親族の注意点を解説
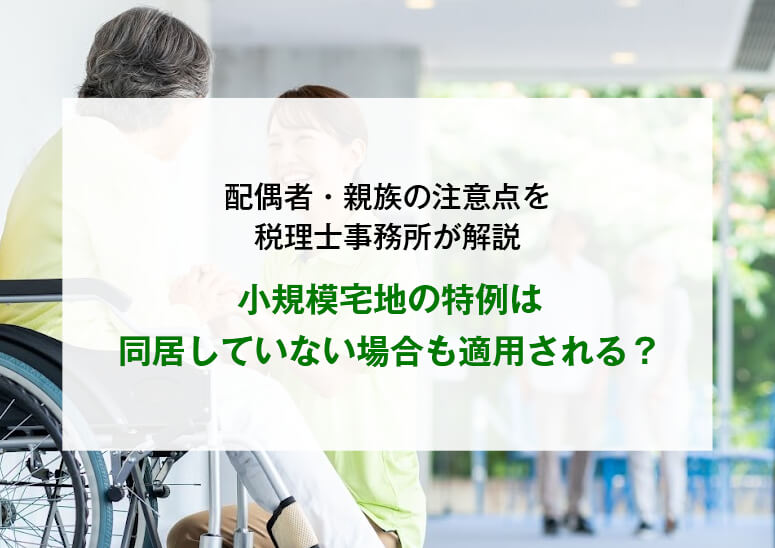
小規模宅地等の特例を適用すれば、相続税の負担を大きく減らせます。しかし、被相続人の自宅に対し、小規模宅地等の特例を適用するには、原則として同居要件を満たさなければなりません。
ただし、被相続人の配偶者や「家なき子特例」の要件を満たす相続人であれば、被相続人と同居していなくても小規模宅地等の特例を適用可能です。
本記事では、小規模宅地等の特例の同居要件や家なき子の特例の適用要件について解説していきます。
目次
小規模宅地等の特例とは
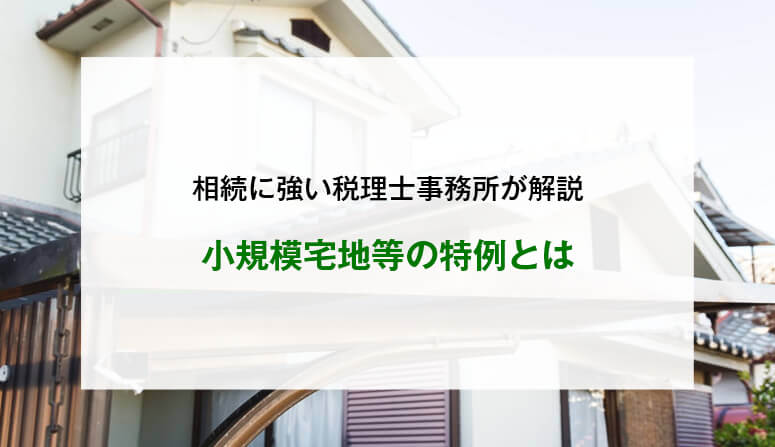
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす相続人が自宅や事業用の土地を相続した場合、土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
特に、被相続人が住んでいた自宅の土地(特定居住用宅地)は、面積330㎡まで80%の減額が可能であり、多くの家庭にとって相続税対策の中心的な制度となっています。
特定居住用宅地とは?
特定居住用宅地とは、相続税の小規模宅地等の特例において、被相続人が居住していた宅地のことです。配偶者や同居親族など一定の要件を満たす親族が相続し、原則としてそのまま住み続ける場合などに、330平方メートルまでの部分について土地の評価額を80%減額できる制度です。これにより相続税の負担が大幅に軽減され、自宅の相続がしやすくなります。
ただし、この小規模宅地等の特例を受けるには「被相続人と相続人の同居関係」や「相続人が相続後も住み続けるか」など、細かい要件が設けられています。
同居していない場合に
小規模宅地等の特例が使えるのはどんなとき?
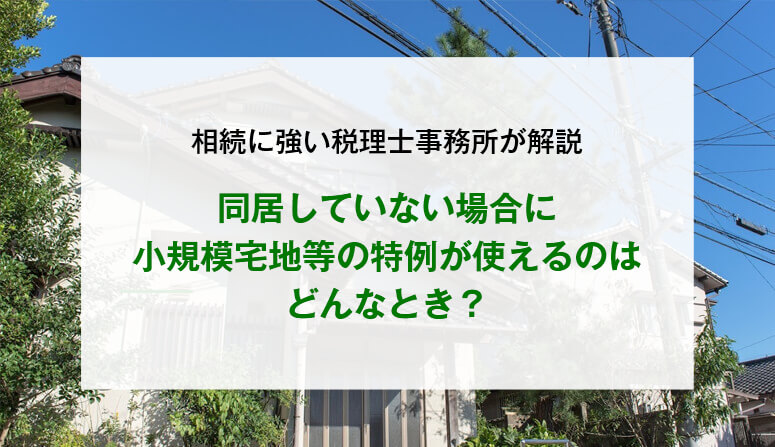
同居していない場合でも、小規模宅地等の特例がまったく使えないわけではありません。配偶者であれば同居の有無を問わず適用されますし、一定の条件を満たす「別居の親族」も利用できる可能性があります。
また、被相続人が老人ホームに入所していたケースも特例の対象になることがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
同居していない配偶者の場合
被相続人の配偶者が自宅を受け継いだ場合には、同居していなくても小規模宅地等の特例を適用可能です。
つまり、長年にわたり、被相続人と別居していた配偶者であっても、原則として小規模宅地等の特例を適用可能です。
別居している親族(子供・兄弟姉妹など)の場合(家なき子の特例)
被相続人と同居していなかった親族であっても、小規模宅地等の特例を適用できる場合があり、これを「家なき子の特例」と呼びます。
家なき子の特例とは、被相続人と同居していなかった子供などが、自分自身では持ち家を所有しておらず、かつ過去に配偶者や同居親族が所有する家に住んでいたこともない場合に限り、小規模宅地等の特例を利用できる制度です。
例えば、相続開始直前に相続人が賃貸住宅に住んでいた場合などでは家なき子の特例を適用できる可能性があります。
家なき子の特例の要件については、本記事の後半で解説します。
被相続人が老人ホーム入所中だった場合
被相続人自身が老人ホームに入所していたケースでも、小規模宅地等の特例を適用できる場合があります。
具体的には、被相続人が要介護認定または要支援認定を受けており、自宅を賃貸や事業用に供していない場合には、同居していなくても小規模宅地等の特例を適用可能です。
小規模宅地の特例が適用されるための
同居要件とは
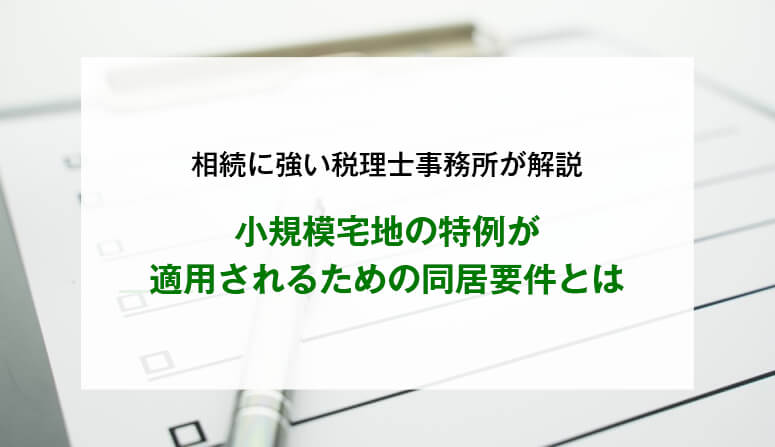
先ほど解説したように、小規模宅地等の特例を利用するためには、相続人が被相続人と同居していたかどうかが重要な判断要素となります。
特に、被相続人の自宅を引き継ぐ「特定居住用宅地等」の場合、相続人が同居していなければ原則として特例を受けられません。
本章では、小規模宅地等の特例における同居の定義や判断基準を解説していきます。
「同居親族」の定義と判断基準
税法や通達上の考え方における「同居親族」とは、被相続人と生計を一にして、かつ同じ家に住んでいた親族を指します。具体的には、被相続人と同じ建物に居住していた配偶者や子供などがこれにあたります。
ただし、同じ建物に住んでいたかが形式的に判断されるわけではなく、実際の生活の実態の有無が重要となるのでご注意ください。
例えば、二世帯住宅の場合、単独登記と共有登記であれば同居要件を満たしますが、区分登記された二世帯住宅では同居要件を満たしません。
同居の判断に使われる「住民票」と「実態」
小規模宅地等の特例の適用可否を判断するにあたり、まず住民票の記載が確認されます。
しかし、住民票だけで同居かどうか判断が確定するわけではなく、税務署は「生活実態」も確認します。例えば、仕事の都合で単身赴任しているが生活の本拠は被相続人宅にある、というケースでは、住民票が別でも同居と認められる可能性があります。
逆に、住民票上は同じ住所でも、実際には長期間別の場所で生活していた場合には同居とみなされないことがあります。
家なき子の特例の要件
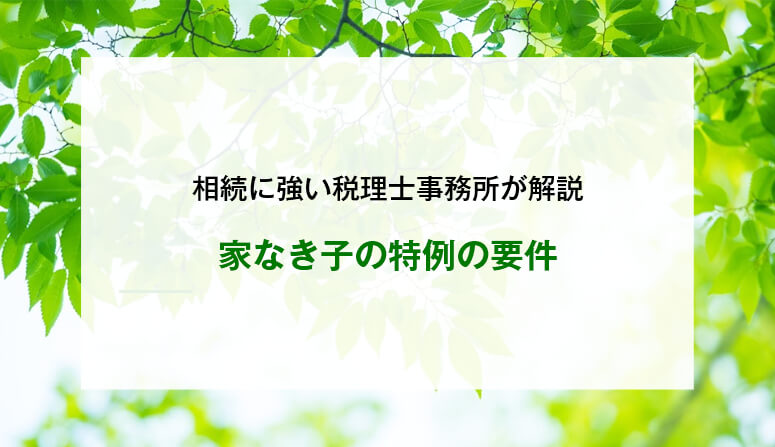
相続人が被相続人と同居していない場合でも、家なき子の特例の要件を満たせば小規模宅地等の特例を利用できる可能性があります。
家なき子の特例とは?
家なき子の特例とは、相続開始前3年以内に、自己・配偶者・三親等内の親族・関係する法人などが所有する家屋に居住していない親族が、被相続人の自宅敷地を相続した場合に適用される小規模宅地等の特例です。
被相続人に配偶者や同居親族がいない場合に限り、一定の要件を満たす別居親族(家なき子)でも330平方メートルまで80%の評価減を受けられます。
この家なき子の特例を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
家なき子の特例を受けるための要件
- 被相続人に配偶者や同居の相続人がいない
- 相続開始前の3年間、自己または配偶者・同居親族(3親等以内)が所有する宅地・家屋に住んでいない
- 相続した宅地を相続税申告期限(10か月以内)まで所有し続けている
- 相続開始時に居住している家屋をこれまで一度も所有したことがない
家なき子の特例は、税制改正により適用要件が厳しくなりました。
令和2年(2020年)4月1日以降に発生した相続では相続発生直前に相続人が持ち家を手放し賃貸住宅に住むなどといった節税対策は封じられたのでご注意ください。
小規模宅地等の特例の同居要件について
よくある質問
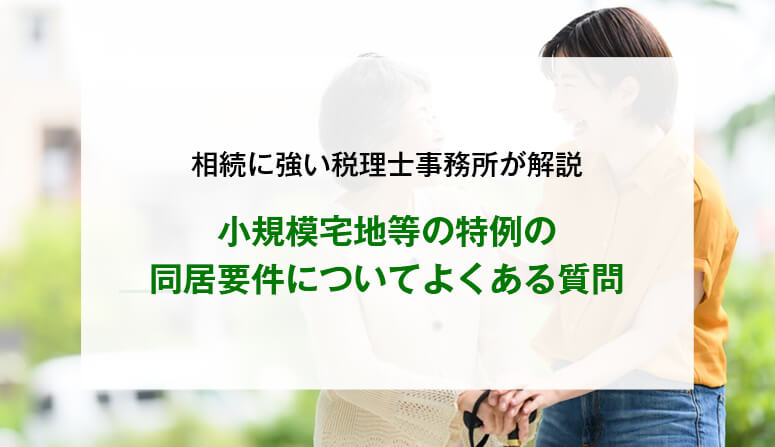
最後に、小規模宅地等の特例の同居要件についてよくある質問を回答と共に解説します。
一時的な別居(入院・介護施設など)は同居とみなされますか?
入院や介護施設への入所など、やむを得ない事情による一時的な別居は「同居」として取り扱われる可能性があります。
なお、被相続人が要介護認定を受けており、老人ホームに入所していた場合には同居要件を満たしていると判断されます。
同居の開始時期はいつから必要となりますか?
被相続人の自宅に対し、小規模宅地等の特例を適用する場合、相続開始時(=被相続人の死亡時)において同居している必要があります。つまり、死亡の直前から同居を始めても形式上は要件を満たすことになります。
しかし、税務署は被相続人と相続人が本当に同居していたか生活実態を調査するため、単に被相続人が死亡する直前に相続人が形式的に住民票を移しただけでは、税務署に否認される恐れがあります。
相続税対策・申告は
当サポートセンターにお任せください

小規模宅地等の特例や家なき子の特例は節税効果が大きいものの、要件が複雑であり適用できるかの判断が難しい場合もあります。
また、家なき子の特例の適用要件は過去に改正され厳格化したこともあり、今後もさらに要件が変更される可能性もゼロではありません。
自分で小規模宅地の特例や家なき子の特例の適用要件を満たしているか判断がつかない場合や、相続税申告や対策に不安がある場合には、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
小規模宅地等の特例は、要件を満たせば相続税の大幅な軽減が可能な制度ですが、同居の有無や生活実態、過去の居住状況によって適用可否が変わります。
形式的に住民票を移すだけでは、被相続人と同居していたと認められない一方で、単身赴任や老人ホーム入所などやむを得ない事情による別居は同居とみなされることもあります。
また、家なき子特例は税制改正により要件が厳しくなった点にも注意しなければなりません。
小規模宅地等の特例や家なき子の特例の要件を満たすか不安な場合には、相続税に精通した税理士に相談してみることをおすすめします。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ