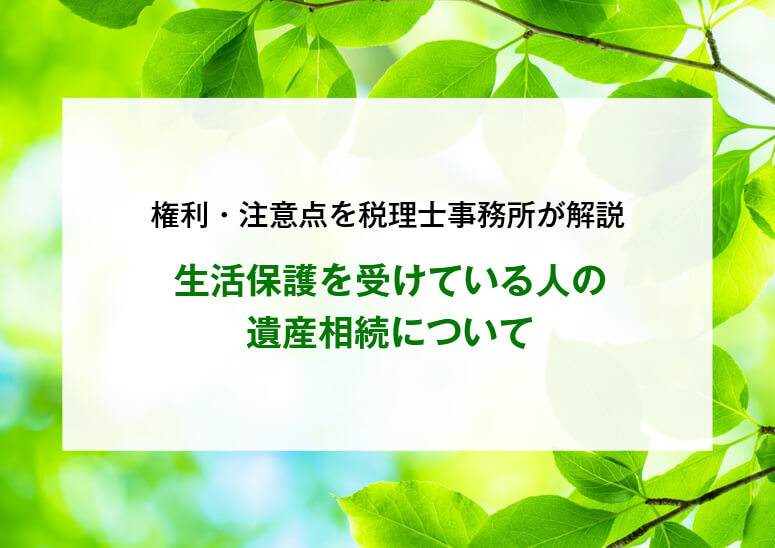
生活保護を受けている人の遺産相続について|権利・注意点を解説
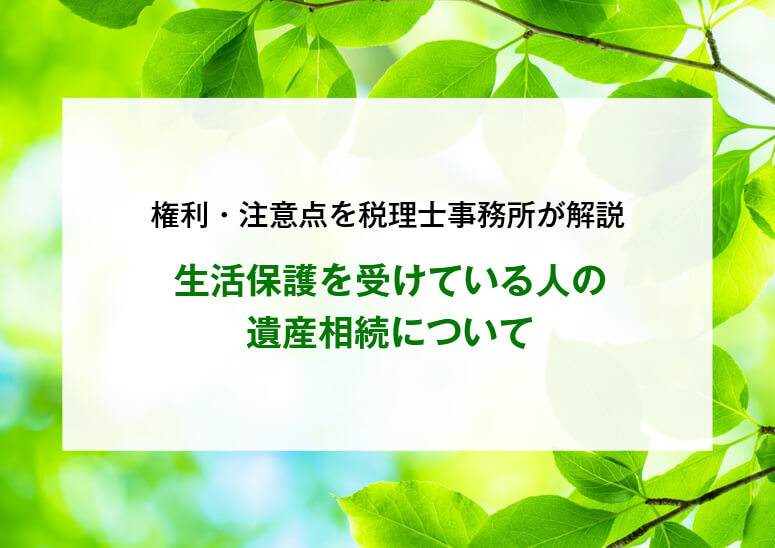
生活保護を受給中の人が相続人になった場合、遺産を受け取っても良いのか悩んでしまうかもしれません。生活保護を受給している場合、税金をはじめ住宅費や医療費など様々な免除を受けることもできます。
そのため、遺産を受け取ったことにより生活保護が受給停止となることを避けるために相続放棄を検討する方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、生活保護受給者も遺産を相続できますが、遺産の金額によっては生活保護が受給停止・廃止となる可能性があります。
加えて、受給停止・廃止を避けるための相続放棄は認められない可能性が高いので、ご注意ください。本記事では、生活保護を受けている人の遺産相続について、解説します。
目次
生活保護と相続に直接の関係はない
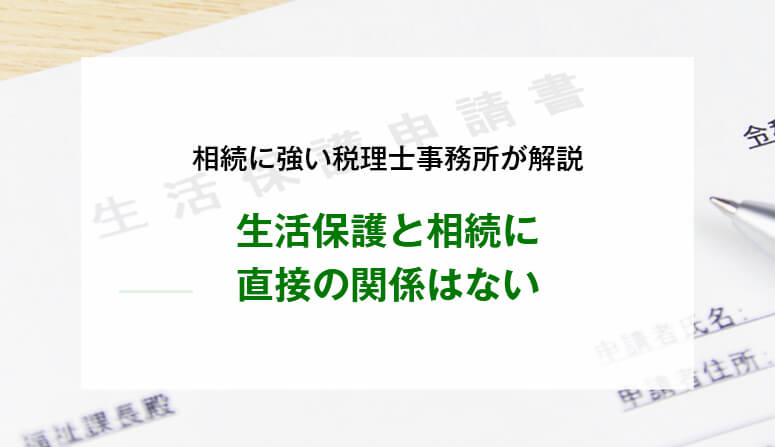
生活保護を受給しているからといって、相続人になれないということはありません。
相続権は民法上相続権がある全ての人に認められている権利であり、生活保護の受給の有無によって制限されることはないからです。
関連サイト杉並区「生活保護」
本章では、生活保護受給者が相続人になったときの取り扱いを詳しく紹介していきます。
生活保護受給者は遺産を相続できる
生活保護受給者も、他の相続人と同様に遺産を相続する権利があります。生活保護受給と相続権については、直接的な関係がないからです。
遺産の金額によって生活保護が受給停止・廃止となる場合がある
生活保護受給者も遺産を相続できるものの、遺産の金額によっては生活保護が受給停止・廃止となる場合があります。生活保護制度では、受給者の資産状況を定期的に確認しているからです。
生活保護受給者が遺産を相続し、その金額が生活保護の「資産基準」を超える場合、生活保護の受給は停止または廃止される可能性があります。
遺産相続によって生活保護受給者が一定の財産を得た場合、相続した遺産を生活費に充てることが可能になると判断されます。
なお、相続した遺産を生活費として使い切り、再び資産が一定以下になった場合は、生活保護の受給申請を改めて行うことは可能です。
遺産が少額であれば生活保護の受給を続けられる可能性もある
相続した遺産の金額が少額であり、生活保護の資産基準を超えない場合、引き続き生活保護を受給できる可能性があります。
また、遺産が居住用の不動産であり、居住のために必要と判断される場合には、一定の条件のもとで生活保護の受給が継続されるケースもあります。
例えば、受給者が住んでいる家が相続財産であり、その家を手放すことで生活に支障が出ると判断された場合、一定の条件のもとで生活保護を受け続けられる場合もあるでしょう。
ただし、資産の活用が可能であると認められた場合は、生活保護の受給が制限されることもあるのでご注意ください。
遺産を相続した後も生活保護を受給できるかは、ケースバイケースなので担当のケースワーカーにまずは相談してみましょう。
関連サイト職業情報提供サイトjob tag「福祉事務所ケースワーカー」
生活保護受給者も相続放棄できる
生活保護受給者であっても、他の相続人と同様に相続放棄をすることは可能です。
相続放棄とは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行うことで、被相続人の財産や負債を一切引き継がないようにする手続きです。
被相続人が多額の借金を抱えていた場合などは、生活保護受給者も相続放棄した方が良いでしょう。
関連サイト裁判所「相続の放棄の申述」
受給停止・廃止を避けるための相続放棄は認められない
生活保護受給者が相続による保護費の受給停止・廃止を避けるために、相続放棄をすることは、原則として認められません。
生活保護は「自助・共助・公助」の考え方に基づいているため、まずは自らの資産や権利を最大限活用しなければならないと決められているからです。
そのため、生活保護受給者が正当な理由なく相続放棄をして生活保護の受給を継続しようとする場合、不適切と判断され、受給停止・廃止になる恐れもあります。
そのため、被相続人が預貯金や不動産などプラスの資産を遺していた場合は、遺産を相続し、遺産を生活費として使い切ってから生活保護を再び申請する必要があります。
生活保護受給者の遺産も相続の対象となる
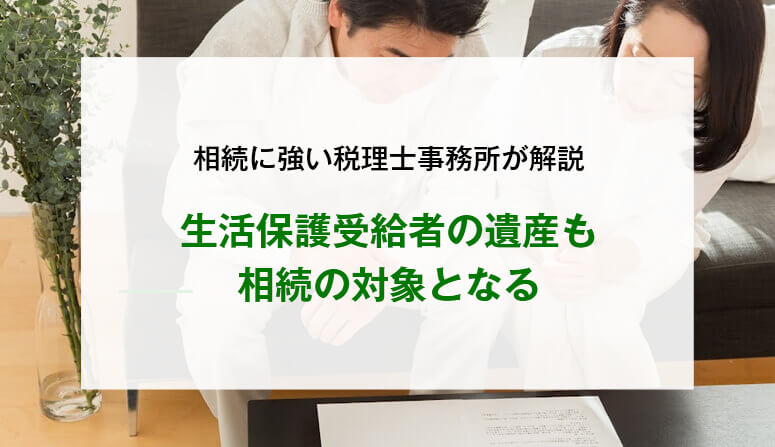
生活保護受給者が相続人となれるだけでなく、生活保護受給者が亡くなった場合も、通常の相続と同様に扱われます。
本章では、生活保護受給者が亡くなったときの相続について、詳しく解説していきます。
葬祭扶助を受ける場合は担当者・部署に連絡する
生活保護受給者が亡くなった場合、葬祭扶助を受けることができる場合があります。葬祭扶助とは、生活保護受給者などの葬儀費用を自治体が支給してくれる制度です。
葬儀費用の支援を受けるためには、自治体の福祉担当者に連絡し、必要な手続きを行いましょう。
生活保護受給権は相続することができない
生活保護の受給資格は個人に対する一身専属権であり、相続の対象にはなりません。
被相続人と同居していた家族が相続発生後も生活保護を受給したいのであれば、個別に申請をする必要があります。
相続人が生活保護費の返還義務を負う場合がある
亡くなった生活保護受給者が過去に保護費を不正受給していた場合などでは、相続人が生活保護の返還義務を負います。遺産を相続する場合は、保護費の返還義務がないかも確認しておきましょう。
また、生活保護受給者は、遺産の金額もわずかであることが考えられます。
保護費の返還義務や遺族も知らなかった借金問題などに巻き込まれたくない場合は、最初から相続放棄してしまうことも選択肢のひとつといえるでしょう。
相続手続きは
当サポートセンターにお任せください

生活保護の受給と相続には直接的な関係はなく、生活保護受給者であっても相続人となり遺産を相続可能です。
しかし、生活保護受給中の人が遺産を受け取ると、生活保護が受給停止・廃止となる可能性もあるので、事前に確認しておきましょう。
相続手続きには、相続財産調査や相続人調査、遺産の名義変更手続き、相続税申告など様々なものがあります。
期限内に相続税申告が終わるか不安な場合や、どのような書類を集めれば良いかわからない場合は、相続に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
当サポートセンター・対応エリア
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
まとめ
生活保護受給者であっても相続人になり、遺産を受け取ることは可能です。ただし、遺産の金額によっては、生活保護が受給停止・廃止となる可能性があることも理解しておきましょう。
また「生活保護の受給停止を避けたい」などの理由で、相続放棄をすることは認められません。
生活保護受給者の家族や親族が亡くなり相続が発生した場合は、担当のケースワーカーや相続の専門家に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。












 0120-317-080
0120-317-080 資料請求
資料請求 お問い合せ
お問い合せ